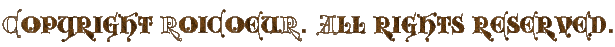第10章 光





1
嫌な臭いがする。暗く、湿っていて陰気だった。
ぽたん、と水滴が垂れる。それは塩水、海水だった。
ここはノートンディルの海底。パラ・オールの地下の奥深いところだった。窓はない。最初から地下室として建設されたものだった。柱、壁、床のすべてのあちこちが崩れ落ちている。
大きく、長い階段がある。それは地下の一番最下へ続くものだった。下り切った広い室には何もない。
昔は立派な建物だったに違いない。だが今はただの廃墟だった。階段を背にすると、奥には天井の見えないくすんだ壁が広がっている。そこだけがぼんやりと薄い光に照らされていた。
壁の表面は剥がれ、そこには焼き付けられたような黒い線で大きな魔法陣が描かれている。それは「彼」が作り出したものだった。その「彼」は魔法陣の前の椅子に深く座っている。
彼は魔薬王の異名を持つノーラ。魔法陣を見つめながらパイプをふかしている。その目は空ろで、異様な光を灯していた。
ふと背中で気配を感じる。ノーラが振り向くと、そこには二人の男が片膝をつき深く頭を下げていた。
一人はギメル。ネクロマンサーだ。小柄な体には古びた黒いマントを、目元だけ残して巻きつけている。
その横にいるのが黒魔術師ハゼゴ。全身を紫の衣で包み、その節々に金の刺繍が施されている。二人の見た目は対照的だった。だがその邪悪さは類稀でどちらも引けを取らず、人を呪い、殺し、苦しめることには何の抵抗も感じない者たちだった。
ギメルはその出生は明らかではなかった。一説では生まれたときから人の形をしておらず、それは惨めな命を持って生まれた者であり、人を呪い続ける内にそれだけが彼の生き甲斐となってしまった哀れな生き物だと言われている。
ハゼゴは魔法戦争後、初めて出現した邪悪な魔法使いだった。その後も彼を筆頭に道を外す魔法使いは何人かいた。だが今までに魔法審判会の網から逃れられた者はほとんどおらず、すべては闇の中に封じ込まれてきた。そんな中で唯一今に至るまで存在し続けてきたのが彼だった。
間違いなかったのは、二人には人の心がないということだった。
「来たか」
ノーラが低い声で呟いた。ギメルとハゼゴは動かない。
「クライセンを倒し、この私が神となれば人の形をした者が歩く大地など不要となる」
ノーラは再び魔法陣に向き合った。
「パライアスを潰せ」
既に二人の姿は消えていた。水滴の滴る音だけを残して。
*****
黒い船、シャルノロエスは静かに海を漂っていた。
甲板ではティシラとマルシオがトールに縄を渡して引き上げていた。船によじ登ってきたトールは甲板に仰向けになり、ずぶ濡れで咳き込んだ。
「大丈夫か?」
マルシオが心配そうに覗き込むと、トールはふて腐れたように目を逸らして体を横にする。
「君たちこそ、僕を助けたりしていいのか」
ティシラとマルシオは顔を見合わせる。その後ろでは海賊たちが様子を伺っていた。
「あいつはな」マルシオは隣に座りながら。「基本的にクライセンは人に興味を持たない。だが自分の気に入らないことにはしっかり仕返しをするんだ」
「……なんだそれは」
「あんたの場合、まず登場の仕方が悪い。しかも剣なんか突きつけて、海に放り投げられただけで済んだからマシだと思え」
「思えるか」トールは飛沫を飛ばして体を起こす。「泳いで帰れだと? 侮辱にもほどがある」
「落ち着けよ。あんた本気でクライセンに同行したいと思うならこれくらいでかっかするなよ。ついてきたとしても、これからそれ以上の屈辱を覚悟しないと無理だ。じゃなきゃ、本当に泳いで帰ればよかったと思うことになるぞ」
「どういうことだ」
「その内分かるよ。確かにあいつは世界一の魔法使いで、その存在感も迫力も普通じゃないし、叡智にも富んでいる。でもそれ以上に」マルシオは声を潜めて。「とにかく性格が悪い」
「なんてこと言うのよ」ティシラが横からマルシオの背中を叩く。「女の子には優しいじゃない」
「何の話だ」
「私には酷いこと言ったりしないわ」
「……いいからお前は黙ってろ。話がややこしくなる」
ティシラは口を尖らせる。そんな緊張感のない二人を見ているうちに、トールは意地を張ることを忘れてしまっていた。
「……どうすればいい」
「一番簡単なのは謝ることだ。あいつの前には暴力も権力も何も通用しない」
「ひけらかすつもりはなかったんだ……」
「分かってるよ。あの時本当のことを言わなかったら、少なくともロープが届かないところまで飛ばされていただろうな。あの程度で済んだってことは俺たちが助けても文句は言わないよ。それに、よく考えてみろ。あんたの剣──」
海に投げ出される寸前に手から離れたトールの剣が甲板に転がっている。質は決して悪くない。だがこうして見ると、高価な装飾が無駄に輝いて見えた。まるで持ち主がまだそれに相応しくないと語っているように感じる。
そんなことを思ったのは初めてだった。間をおいてマルシオは続けた。
「あれごと海に落ちてたら、あんたは溺れるか、大事な剣を手放さなければいけなかったかもしれないな」
トールは胸が痛み、唇を噛み締めた。クライセンは自分から剣を取り上げたわけでも何でもなかった。あの短い時間で、自分に合った低俗な罰を与えただけなのだ。悔しい。だが、それ以外の思いが心を巡った。
「でもよ」そこでワイゾンが会話に参加してくる。「王家の坊ちゃんよ、話を聞いていたなら分かってるんだろう。俺たちは今からあの毒ガスの遺跡に向かうんだ。なんでわざわざ死ににいく?」
「戦いにいくんだ」トールは眉を吊り上げる。「僕は死など怖くない。その覚悟もある」
「そんなことは子供でも言えるぞ」
「何だと」
「俺はこれでも──今はこの空っぽの船と二人の手下しか持たない貧相な海賊に見えるかもしれないが、今まで数え切れない死線を越えてきたんだ。たくさんの惨い死を目の当たりにしてきたし、俺自身も何度も死に掛けた。海の上は陸の人間が思うより苛酷だ。まあ、当然だよな。元々人間は陸で生きるように出来ているんだからな。敵は海賊だけじゃなかった。むしろ自然の災害の方が恐ろしいかもしれない。嵐や津波、飢餓、病気、遭難や難破に座礁。海の中に棲む怪物たちは未だに名前すら知らない奴らがウジャウジャしてる。俺たち海賊はその中で常に生存競争をしなければいけない」
「海賊は犯罪者の集まりだ。平和に暮らそうってのが間違いだろ」
「だが俺たちは陸では生活しない。この海で誰が俺たちを犯罪者だというだろう。大体何を基準に人を裁き、罪だと決める? パライアスが決めたことだろう。その権力は海の上まで支配しているのか? そもそも俺たちは法に守ってもらおうなんて思っていない。海賊と名乗るだけで重罪だ。上等だよ。戦後、貧しさに耐えられずに財宝を欲して海に流れ込んだ死に損ないが未だたむろしているとでも思っているのか。もう時代は違う。俺たちは海賊というひとつの人種だ。海の上でしか生きられない生き物なんだ」
話に耳を傾けながらも敵意を向けるトールに、ワイゾンは冷たい視線を送りながら続ける。
「まあ、そんなことはどうでもいい。とにかく俺たちはそうやって生きてきた。人間のそれは汚い部分や恐ろしい所業を見てきた。少なくともあんたよりは経験がある。説教するガラじゃないが、忠告はできる……あんた、死相が出てるぞ」
トールの額に汗が流れる。海賊の言うことなど聞きたくないと思う反面、ワイゾンの言葉には重みがあることを感じていた。
「何をそんなに生き急いでいる? あんたは若いし、勇気もある。きっとその気になれば欲しいものは何でも揃う環境に恵まれているんだろうな。それに甘えろとは言わない。だが人にはそれぞれ生まれ持ったものがあり、その上で生きることから逃れられないようになっているんだ。受け入れようが放棄しようが本人の自由だが、必ずそれと向き合って、選択しなければいけない時間があるはずだ。絶対に無視することはできない。迷ってもいい。答えなんかないかもしれないんだからな。だが何を選んだとしても、信念を持って貫かないとあんたの周りには誰もいなくなってしまうぞ。豊かな環境に恵まれた者が幸せになれるとは限らない。俺たち海賊はそれをこの目で見てきたんだ」
トールの顔から鋭いものが消えていた。今まで見下してきた海賊の言葉は、彼の心に響いていた。
海賊も同じ人間。行き場を失い陸から逃げていった者の集まりではない。彼らも意思を持って生きている。乱暴な略奪者であることに変わりはないが、その一人一人の言葉や意志がすべて間違っているとは思えない。
トールは滴り、顔や体を伝う海水に構わなかった。ただ俯いて佇んでいる。すべてではないが、彼からいくつかの棘が落ちていたのが見て取れた。
「歩きやすい道が用意されているにも関わらず、わざわざそれを踏み外してきたんだ。俺はあんたを一概に愚かだとは思わない。だがそこには間違いなく犠牲が伴ったはずだ。それをどう償うかは、あんた次第だ。ここで王家というブランドをぶら下げて海賊を見下すくらいなら、最初から豪華なお城でふんぞり返ってた方がよっぽど楽しいんじゃないのか」
「……そ、それは」
「ついでに言っておくが、あんたは運がいい。今は魔法使いの旦那に従うと約束したから俺はこんな話をしているんだ。旦那の慈悲がなきゃ、俺はあんたと人間の言葉では会話してない。即刻、魚の餌だ」
ワイゾンは立ち上がり、黙って目を逸らすトールに剣を拾って差し出した。
「とにかく濡れたままじゃ体に悪い。少し休め。来いよ」
トールはワイゾンを見上げ、ゆっくり剣を受け取る。それは妙に重く感じた。今までずっと軽々と振っていたはずなのに、と思う。ワイゾンは背を伸ばし、マイとキジに声をかける。
「見張りは俺たちで順番にやろう」
マルシオが立ち上がりながら口を挟む。
「俺もやるよ」
「それは助かる。何せ人手が足りないんだ。だが居眠りをするくらいなら出しゃばらないでくれよ」
「ご心配なく。俺はあんたたちより頑丈にできてる……って、あんたも魔族だったな」
ワイゾンは「ああ、そうだった」と思い出したような顔をする。
「思ったより心強い面子が揃っているようだな」
「だといいが」
ワイゾンは口の端を上げた。そこにマイが声をかける。
「進路は?」
ワイゾンがマイを見る。無表情でしばらく黙っていたが、ふっと海に目線を移し、その忌まわしき名を口にした。
「パラ・オールだ」
マイは小さく頷いた。キジも真剣な顔になった。
パラ・オールの恐怖は誰よりも、海賊である彼らが一番身近に感じている。普通なら近づくだけで死に至る。敢えてそこへ赴くことの無謀さは百も承知だった。
きっと人は「狂気の沙汰」とでも言うだろう。だが海賊は騒ぐことが大好きだった。彼らは安泰など求めない人種だったのだ。笑いたい奴は笑えばいい。遊んで暮らしたいために海賊になったんじゃない。難を避けて平和を祈るために海に戻ってきたんじゃない。その気持ちは語らずして通じていた。
「ただの間抜けと思っていたけど」ティシラが呟く。「結構頼りになりそうね」
「そうだな」
マルシオも素直に同意する。
その頃、クライセンは一人、船内の一室で明かりも点けずに椅子に深く座っていた。薄く目を開き、人形のようにじっとしている。手の中には液体の入ったガラスの小瓶が握られていた。入れ物の形も中身も、グレンデルに渡したものとは別のものだった。
それを手の中で転がしながら、漏らすように呟いた。
「……ノーラ」
小瓶を握り締め、何かに語りかけるように。
「少々遠回りをしてしまった」その目には青い炎が灯っていた。「そろそろ終わりにしような……」
2
ティオ・メイの城では静かな夜を迎えていた。町にはぽつぽつと明かりが灯っている。それを見下ろすような城の一室では、またあの三人が神妙な顔をしていた。
グレンデルとオーリスとダラフィンだ。扉の前には数人の警備兵が並んでいる。三人の会話ははっきりとは聞き取れない距離で、黙って立っている。
ダラフィンはあれから一日もかけずにライザを連れて帰ってきた。オーリスは泣きそうな顔で娘を迎え入れた。
彼女がクライセンたちと何をしていたのかは追求されなかった。だが、しばらくは自分の部屋で謹慎するようにグレンデルから命ぜられた。ライザは大人しく従った。それを見送り、ダラフィンはグレンデルに今までのことを報告した。
まずはミングでの奇妙な出来事。それを話し終わった後、ダラフィンは人払いを要求した。グレンデルの命令で警備兵はすべて室を出ていった。
ダラフィンはそれを確認して、エンタナでクライセンに会ったことを話し出した。グレンデルは僅かに戸惑っていたが、なぜ彼を連行してこなかったのかは聞かなかった。ダラフィンもそれについては触れずに話を進めた。
グレンデルは話の中で出た、忌まわしい二つの名前にまた頭を痛めた。
「ギメルと、ハゼゴ……」
その名前は、一般的な教育を受けた者なら誰でも一度は聞いたことのあるものだった。
この二人に接点はなかった。それぞれに恐ろしい伝説を持ち、いまや邪悪の象徴として語り継がれている。
だがその存在はもう何十年も確認されておらず、それほど現実の恐怖としては思われなくなっていた。人知れずどこかで死んでしまったのだろうと言われていた。
特に人々は百年前に名の上がったノーラを恐れて、その二つの「化け物」への関心は薄れていっていた。
その三つの名前が一つに繋がった。グレンデルは悪寒を感じ、えもいわれぬ恐怖が彼を包んだ。
三人はしばらく黙った。敵の名前が分かったところで対策は思いつかない。事が少しずつ形になればなるほど、絶望へと近づいてきている。誰一人、気休めの言葉すら出てこなかった。
ふと、その重苦しい空気に異常を感じた。
三人は同時に顔を上げる。その目線は一点に集中していた。
室の片隅になにかがいる。息を潜めている。
室の戸口には警備兵がいるはずだ。どうやってここへ入った? だがそれはさほど問題ではない。黒い塊は声を出さずに体を揺らしていた。笑っている。それはゆっくりと顔を上げる。
小さな体にマントが巻きつけられていた。その隙間から覗いた目はギョロリと大きく、茶色い皺だらけの皮膚で縁取られている。それがモゾリと動くとぼろ布のようなマントが剥げ、顔が露になった。鼻は古い木の根が突き出たように下に垂れている。締まりのない口元には不揃いの歯が並んでいた。
一同はその化け物の目に捕らわれ、身震いをする。まるでこの世のものとは思えなかった。
それはひひひ、と笑った。
「鼻がむず痒いと思ったら」その声は枯れていた。「こんな高いところで儂の噂がされていたのか」
それは奇妙な笑い声を上げた。ダラフィンがゆっくりと剣に手をかける。それをオーリスが手で制した。
「無駄です」オーリスは微かに震えていた。「あれは土くれの傀儡(操り人形)。分身です」
「誰の分身だ?」
グレンデルが呟くと。オーリスは間を置いて答えた。
「……ギメル」
予想はしていたが、と息を飲む。
ギメルは頭をもたげてさらに笑い出す。その姿はぞっとするほど奇怪で卑しいものに見えた。
「そう、儂はギメル」ギメルは独り言のように喋りだした。「いつの日かそう呼ばれるようになった。儂は土の中から生まれた。奇病で死に、埋められた母親の中で育ったんだ。腐った腹を突き破り、儂は産声を上げた。這いずり回っている内にようやく人に出会った。だが人は儂を恐れた。そしてやっと分かったんだ。儂は化け物なんだと。死体だけが儂を拒まなかった。だから殺した。たくさん殺した。生きてる人間は嫌いだ。全部死んでしまえばいい。儂が殺してやる」
ギメルはまた笑い出す。彼がまともな人間でないことだけは間違いなかった。ギメルはさらに続ける。
「儂は一度土に還った。もう体が呪いに蝕まれ、肉は腐り骨は穴だらけになって動かなくなってしまったんだ。別にそのまま眠ってしまってよかった。しかし、ある男が儂を生き返らせた。そいつが儂に煙の出る水をかけた。そしたらみるみる体が再生した。男は儂を怖がらずにこう言った。この水があればお前は永遠に、気の済むまで人を殺し続けられる。人間がいなくなるまで呪い続けられると。男はいくらでもそれをくれると約束してくれた。儂はいつまでも人を呪い殺す。そのために生まれてきた」
ギメルは興奮したように大声で笑った。笑いすぎて呼吸困難を起こす。グレンデルはその姿に嫌悪を感じた。
ギメルの話の中の「ある男」とはノーラに間違いない。そして「煙の出る水」とは他ならぬ魔薬のことだ。
この知能の低い、呪われた化け物に永遠の命を与えたノーラを憎んだ。グレンデルは膝の上で拳を握る。
ギメルはまだ笑っている。そして乾いた目を動かして三人を睨み付けたかと思うと、喉を震わせて叫んだ。
「お前たちも殺す!」
ギメルは体を浮かし、歯をむき出して飛び掛ってきた。
「!」
瞬時にしてダラフィンが剣を抜き、ギメルの体を真っ二つに切り裂いた。するとそれはパン、と砂になり、部屋中に広がった。グレンデルが体を屈め、オーリスが彼に覆いかぶさるようにマントを広げた。
砂は粉になり散っていく。外から警備兵が戸を叩いている。何事かと声を上げているが、誰も入室を許可しない。ダラフィンが慌てずに「騒ぐな」と大声を出すと、戸の向こうは静かになった。
ギメルの気配は完全に消えた。それを確認して三人は姿勢を正す。
「陛下、ご無事ですか」
オーリスが気にかけると、グレンデルは頷き、言葉にはしなかった。
「今のが、ギメル……」ダラフィンは剣を鞘に収めながら。「なんて邪悪さだ」
「あんなのが他に二人もいるとは……」
グレンデルが青ざめている。
「ノーラはそれの支配者。さらに強い力を持っているでしょう」
オーリスも椅子に座りなおして、頭を抱えた。
「だが」ダラフィンも座りながら。「敵は確認しました。後は戦うのみです」
「ギメルはネクロマンサーです」オーリスが顔を上げる。「死体を操り人間を襲い、殺した死体はさらに奴の手中に落ちるのです。限がありません」
「それでもやるしかないだろう」
「そう……しかし奴が操る死体は民のもの。躊躇わず斬ることができますか」
「躊躇っている場合ではない。もちろん心は痛むが、やらなければさらなる犠牲が増え続ける」
「闇雲に剣を振り回していても殺戮は終わりませぬぞ」
「ならばどうしろと」
「ギメルを殺るしかありません」
「当然だ」
「奴はノーラに永遠の命を授かっている」
再び沈黙になる。一同は俯いた。ダラフィンは眉を寄せて口を噤んでしまった。
そこでグレンデルが呟いた。
「ひとつ」二人に注目されながら。「方法があるとしたら……」
「それは……」
グレンデルは懐から小瓶を取り出した。クライセンから受け取ったものだ。
「これが国を救ってくれるかもしれない」
瓶を持つグレンデルの手は震えている。しかし、それに希望を託し、握り締めた。
次の日、朝から王室に衛兵が集合させられていた。
王座の前にずらりと国の精鋭たちが勢揃いしていた。王の左右にはオーリスとダラフィンが控えている。グレンデルから向かって右に緑のローブを纏った魔法兵。左に青銅の鎧に身を包んだ衛兵たちが整列している。
その中にはライザの姿もあった。優秀な魔法使いである彼女は早々と謹慎を解かれた。
ざっと室に入りきれるだけ、百名ほど詰め込まれている。外の中庭にも三百名は並んでいる。もちろんこれが戦える者のすべてではなかった。国中の砦に常勤している者も集めれば十五万以上の兵がいると思われる。長年大きな戦争に見舞われず、すべての兵を総動員することもなかったため正確な数は把握されていない。
ここにいない兵たちも通信を使い、王の言葉を聞き漏らさないように魔法の水晶の前に集まっていた。それぞれの国の王は、もちろんその国を治める権力者ではあったが、兵のほとんどはメイから委託された者ばかりだった。
兵を動かす勅令の権利は各国の王にあったのだが、軍事に関してはメイの指示を無視する者はいなかった。実質、軍事力を決して濫用しないグレンデルに逆らう理由もなく、メイがすべてを支配していると言っても過言ではなかった。
三十センチほどの水晶の中に仄かな光が灯っている。
国の民は騒がず、しかし警戒しながらその朝を迎えていた。いつもと同じ時間ではなかった。民間人もそれぞれの自宅や、近くの公共の場に集まり水晶を見つめている。
一体今から何が起こるのだろう。気が気ではなかった。もちろんミングでの奇怪な事件が発端であることは予想されていた。この数日の間でいろんな噂が飛び交っていた。だが決して取り乱す者はいなかった。
国中にグレンデルの、王の言葉が伝わった。
「恐怖が堕ちてくる」
その一言で口火が切られた。大陸中が静かに緊張した。
オーリスとダラフィンも交え、厳かに真実が語られた。ノーラを始めとする、ギメルとハゼゴの陰謀。この世界を滅ぼそうとする脅威。
そしてその鍵は、四代目魔法王クライセン・ウェンドーラに託されていること。
昨夜、あれからグレンデルの元にフィレスアンでの騒動が伝えられた。海賊と魔法使いの一行が船を強奪したと。海賊たちはミングでクライセンと一緒にいた者であることが確認され、魔法使いたちの人数や姿格好からそれが何者であるか、すぐ判断された。
グレンデルは彼らが海に出たと認識し、そのことも伝えられた。
それから、ノーラとハゼゴの全貌は明らかではないが、ギメルの分身が宣戦布告してきたこと、その恐ろしさと姿を説明した。彼を見つけ次第迅速に王に報告せよと命が下った。彼は不死の肉体を手に入れた。いくら剣や魔法で攻撃しても無駄なのだ。希望は王の手中にある小さなガラスの瓶の液体のみだった。
グレンデルはそれぞれの砦の幹部や国の王に指示を出し、すぐに戦闘の準備に取り掛からせた。
国の人々にも状況の説明が順次になされた。取り乱さずに、自分の身や家族をしっかり守るように言い聞かされた。この国のどこにも安全な場所はなかった。
一人ひとりの意志と精神力が要となった。人々は怯えながら身の回りの整理をした。
その一日は慌ただしく、決して長くは感じられなかった。
太陽が傾くにつれ、静寂が訪れる。ティオ・メイの城は特に厳重に守りが固められた。その核には王が座していた。オーリスとダラフィンも先陣は切らずにその隣で、国中の兵に指示を出すために居残っている。
三人の目の前には水晶があった。いつでも出陣できるように完全装備をしている。ライザは城門前に配置している。
人々の口数も減り始め、暗くなると共に静寂に包まれていった。
夜空には欠けた月と星がくっきりと象られている。国中がしんとしていた。まさに、嵐の前の静けさだった。
張り詰められた緊張の糸の中、ぼこりと土が盛り上がった。土の塊はぎょろ目を瞬かせ、ゆっくり左右に動いた。そして、呪いの言葉を呟く。
「みんな、死んでしまえ」
ギメルの笑い声が轟いた。それを合図に戦いが始まった。国中の土の中からゾンビが這い出してきた。
同時に、大陸に王の声が響き渡った。
「敵襲だ!」
一斉に兵が武器を構えた。
地獄と化した大地の上で、ギメルは夜空を仰ぎながら一人で笑い続けた。
3
シャルノロエスは二日目の夜を迎えていた。相変わらずのんびり進んでいる。
「もっと早く進まないの?」
ティシラがつまらなそうに呟く。
「風がないんです」ワイゾンは申し訳なさそうに。「こればっかりは」
辺りは靄がかっており、視界が悪い。今のところ特におかしなことは起こっていなかった。
マイとキジがワイゾンに近寄ってくる。
「こんな航海は初めてだわ」マイは不安そうだった。「行き先は当然だけど、武器も食料もろくにないなんて。慌てて出たとは言え、余りにも計画性がなさ過ぎる。一流の海賊のやることじゃないわよ」
「そうは言ってもな」ワイゾンが眉を寄せる。「俺たちは一度死んだも同然だ。今更一流なんて言える立場じゃないだろ。こうして海に出られただけでも奇跡に近い」
「だからってこの状況は酷すぎる。海に出たなら出たでそれなりの準備をしないと」
「そんな時間はないだろ」
「子供の水遊びじゃないのよ。敵に会ったらどうするの。シャルノロエスは海賊の間じゃ『黒い棺桶』と呼ばれて恐れられてきた。なのに、これじゃ文字通り私たちの棺桶になってしまうわ。もし敵に奪われでもしたとき、この空の船は末代まで笑い続けられるわ」
「末代が」ワイゾンの声が低くなる。「あればな」
「……どういうことよ」
「魔法使いの旦那が負ければこの世は終わる。俺たちは橋渡ししかできないかもしれないが、この船はそんな大事な使命を乗せているんだ。別に俺たちは英雄になりたいわけじゃないだろ。余計なものなんかいらない。今は身一つで敵陣に乗り込もうじゃないか」
そんなワイゾンを見ながら、キジが感動している。
「お頭、かっこいいです」
マイは俯いた。だがその顔は眉を顰めて歯をむき出している。
「バカじゃないの!」そしてワイゾンを蹴っ飛ばす。「食べるものがなくなったら人間は死ぬようになってんのよ。敵に襲われたらどうするのって聞いてるの。そうなったら使命もクソもないでしょ。これだから男は! 夢ばっか見てんじゃないわよ」
「てめえ!」ワイゾンは半泣きで。「本気で蹴ったな」
さらにマイはキジも殴る。
「あんたもよ! 長い間洞窟に閉じ込められて、脳にカビでも生えたんじゃないの。頭かち割って海で中身洗ってきなさい」
「マイさん」キジも涙目になる。「酷いです」
そこにマルシオが仲裁に入る。
「ま、まあまあ」少し怖がりながら。「ここにいる皆が戦えるし、食料なら俺とティシラはいらないからさ」
「それに」ティシラもフォローに入る。「ワイゾンもよ。魔族はしばらく食べなくても別に生きていけるし。クライセン様も必要ないみたい。一緒にいてほとんど食事してなかったみたいだし。だから食料は三人で分けて。それなら何とかなるでしょ」
「それならギリギリで一週間は持つわ」マイは震えるワイゾンに。「パラ・オールまでどれくらいかかりそうなの」
「よ、予定では四日だ」
「そう」マイは腕を組みながら。「それなら前後しても持ちそうね。でも病気や怪我にはろくな応急処置もできない。薬もなければ船医もいない」
「そういうのは事が起きてから考えよう」マルシオが引きつった笑顔で。「魔法使いが三人もいるんだ。洞窟での時みたいな大惨事じゃなければ、俺が治癒の魔法だって使えるからさ。まあ、あの一番頼りになる大旦那には何も期待しない方がいいけどな」
マイの肩から力が抜ける。しかしすぐに再びワイゾンを睨み付ける。ワイゾンはびくっと身構える。
「言っとくけど」マイは無表情だった。「この航海が普通じゃないのは分かってる。でもあんたの浮かれた態度が気に入らないのよ。陸の上じゃクズでも、海に出たからにはごめんなさいじゃ済まさないからね。今度腑抜けたマネしたら……大砲に突っ込んでぶっ飛ばしてやる」
「……はい」
ワイゾンが真っ青な顔で呟くと、マイは背を向けて船内に消えていった。それを見送って、マルシオがティシラに囁いた。
「お前より怖いな」
「なんで私と比較するのよ」
その頃、クライセンは船長室にいた。日誌や海図等の書類は押収されていたが、いくつかの本は机の引き出しや棚にごちゃごちゃと残されていた。
クライセンはワイゾンの許可も取らず、そこに引きこもって勝手にそれらを読んでいた。
クライセンの座る向かいの椅子にはトールが座っていた。トールは姿勢を正してクライセンを見据えている。クライセンの方は、まるで彼がいないかのように黙って本に目を通している。
「昨日は」トールは真面目な顔で。「すまなかった」
マルシオに言われた通り、とりあえず謝ってみようと思う。
「怒っているのか」
だが、クライセンは見向きもしなかった。
「返事をしてくれ」
トールは戸惑っていた。彼はクライセンのような者とは接したことがなかった。
今まで剣の腕には自信があったし、その名を利用したことはなかったが、どこかで王子と言う地位を誇示していたと、昨日のワイゾンとの話で気が付かされた。
だがクライセンには自分が何者であるかなど全く関係なかった。いや、彼だけではない。海賊という人種、そして同行している二人の魔法使いもまた普通ではないと感じていた。
何が普通でないのか、それは分からない。ただ、こうも何の隔たりもなく自分を一人の人間として、ただの浅い若者として扱われたのは初めてだったのだ。
トールはここにきて初めて一人になった気がした。ここには砦も王の名も何もない。あるのは剣とそれを振るう自分の体のみ。
クライセンには魔法王と言う名がある。だが自分のそれとは明らかに違う。彼は本物だ。虎の衣を借りる必要などない、虎そのものなのだから。
トールは言葉を捜した。下手したらまた怒らせてしまうかもしれない。重い空気がのしかかるが、クライセンは構わずに本を読んでいる。じっとしていても仕方がない。彼だって人間だ、とトールは思い切る。
「話がしたい」
すると、クライセンはちらりとトールに目線を移した。トールは驚いて肩を揺らすが、平静を装う。
「さっきから」クライセンは煙たそうに。「何の話?」
「何って……」トールは戸惑いながら。「昨日、あなたに剣を向けてしまった無礼を詫びたい」
「理由があったんだろ。剣士が安易に頭を下げるな」
トールは息を飲む、意外な言葉だった。どんな罵声を浴びせられるのかと覚悟してのだが、その一言で彼が人を尊重する礼儀正しい人格だと思った。話ができる、とトールは気を取り直す。
「いいえ。剣士はむやみに剣を抜いてはいけない。剣を脅しの道具に使うなんて、僕は最低なことをしてしまった」
「別に誰も脅されてないから問題ないんじゃない?」
クライセンの軽い返事にトールは再び戸惑う。
クライセンの言葉はつまり、自分の剣が脅しにすら値しなかったと取れた。もちろん、その通りだった。じわりと苛立ちが沸くが、ぐっと我慢する。
とにかく彼はそのことについては怒っていないようだ。もうこの話は進展しないだろうと判断し、終わりにすることにした。
4
「僕は、国を変えたいと思っている」
唐突なトールの言葉にクライセンは相槌すら打たない。黙って彼を見ている。興味なさそうに。
「確かに」トールは構わずに話を続ける。「パライアスは歴代の王により現在に至るまでに平和な国を造り、守られてきた。だが僕にはそれが罪滅ぼしのように見えるんだ。魔法戦争による傷は深く、それに伴った犠牲も簡単に償えるものではない。もちろん歴史の上に文明は造られるものだし、過去の過ちを糧にしていくことは大切だ。王たちは戒めのもと、道を踏み外すことなく立派な国を造り上げた。だが、もういいんじゃないだろうか……もう十分、ザインやイラバロスへの贖罪は終わったはずだ。彼らも納得してくれているんじゃないだろうか。もう自分たちの足で歩き始めてもいいんじゃないのかと、僕はそう思うんだ。僕は王家に生まれたというだけでその後を継ぎたくない。僕は僕の足で歩きたい。だから家を出て剣の修行をしながらいろんなことを考えているんだ。僕が王に相応しい男になるまで帰らないつもりだ。もしそれに及ばなければ、国は他の誰かに任せる」
「で」クライセンがやっと口を開く。「君は国をどうしたいわけ?」
「それはまだ分からない」トールは俯いた。「平和は尊い。それは守らなければいけない。だけど、それだけじゃないはずだ」
「戦争を起こすのは簡単だよ」
「戦争をしたいわけじゃない。平和ボケしてるなんて思っていない。国の軍事は決して怠られているわけじゃないし、今回の脅威は未知の力によるものだ。何もかもが初めてで戸惑っている。だけど何かがおかしい。最強だの軍神だの言われた国が、なぜこんなにも無力なのか。なぜ何一つ抵抗できる武器を持っていないんだ」
「いいじゃないか。それで進化するも滅びるも運命だ。太古に天使は地上を離れ、魔法大陸は海に沈んだ。確かに大きな損傷かもしれないが、それがなければ生きていけなかっただろうか。失ったものの中に何か新しいものは生まれなかっただろうか」
「それがティオ・メイだ」
「光があるところには必ず影がある。ティオ・メイの放つ光の生んだ影こそがノーラだ。世の中はこういった自然の法則には逆らえない」
「僕はいつかこんな日が来るんじゃないかと思っていた。光だけが強さを増していたんじゃない。影もまた光に比例して色濃く力をつけていた。だが、気になることがある。ノーラを生んだ光とは、本当にティオ・メイだろうか」トールは少し体を倒して。「確かに今発展途上の医学の裏に魔薬という影が生まれた。だがその発端は一体どこにあるだろう。僕たちは今、その悪を倒すためにどこに向かっている?」
クライセンは手元の本を閉じる。
「はっきり言ったらどうだ」
「ノートンディルだ。我らが戦争で失った大陸だ。しかし今になって顔を出し、我らを拒むように毒を放っている。いや、ノーラを歓迎しているのではないだろうか。潜む影はそこを舞台に選んだ。ティオ・メイを無視して。なぜだ。影が疎む光とはティオ・メイではないんじゃないか」
「つまり?」
「ノーラの狙いはあなた、リヴィオラを持つ魔法使いだ」
「私がノーラを生み出したと?」
「単純にそうだとは言えない。あなたもまた光の存在だ。しかし直接魔薬王を生み出したのはノートンディルの毒から育ったパライアスの医学でもある。答えがあるかどうかは分からないが、僕が考えたのはこうだ。戦後、パライアスは再建され新しい文化も生まれた。その文化の中で一番大きな変化となったのは魔法に希少価値を見出され、尊重されたことだ。代表的なのはリヴィオラの存在だ。それを持つ魔法使いは世界一と言われ、まるで神のように崇められている。それは今も変わらない。だが現実、あなたが受け継いでからはその存在はまるで幻のようになっていた。不思議なことに、人々はその現象で魔法王をさらに神聖視していった。その人々の理想や希望が光だとしたら、ノーラを生んだのはあなたではなく、平和の中で抱かれ続けた幻想がそれなのかもしれない」
「…………」
「いや、そうだとも一概には言えないだろう。魔法王はここに存在する。実際にリヴィオラを受け継ぎ、時を刻み生きている。やはりノーラを生み出した光は、他ならぬあなたなのだ」
「だったら何だ」クライセンはため息をつく。「まとめて話してくれ」
「そう思ったとき、僕はあなたを恨んだ。この時代、魔法王とは一体何なのだ、必要なのか。その疑問を抱いたのは僕だけじゃない。理由は様々だ。だが誰もそれを解決しようとはしなかった。なぜか。それはあなたの存在があやふやだったから。そして、あなたが怖かったからだ。どこにいるのか分からない。いないのかもしれない。持つ力も計り知れない。そんな簡単な理由で誰も触れようとはしなかった。だから僕は苛立ったんだ。どうして世界一という名前だけで皆が畏怖するのか。僕は真実を知りたくてあなたに会いたいと思った。僕はインバリンの名を隠しながらも国の情報機関を利用してあなたに関することを調べた。それでもどこにいけばあなたに会えるのか検討も付かなかった。しかしここ数日、国が動いた。あなたを追うために。機が訪れたのだと思った。フィレスアンで会えたのは偶然に等しいが、僕の勘が当たったんだ。奇跡だと思ったよ。そして今こうしてあなたと顔を合わせ、話をしている」
「それで、答えは出たのか」
「朧げだが、なんとなく」
「ふうん」
「聞いてくれよ」
「簡潔に頼むよ。眠くなってきた」
トールはクライセンの緩い受け答えを気にしないようにした。返事をしてくれるだけでもマシだと思う。
「正直に話すよ。最初は予想通り、自分勝手な奴だという印象を受けた。なぜ王があなたに執着し、その結果単独行動を許したのか理解できなかった。だけどその疑いはすぐに晴れた。あなたを取り囲む環境だよ。若い魔法使いと屈強な海賊たち。彼らはあなたの為に命をかけているようだ。それぞれ個性も強く不揃いだが、その信頼はあなたを中心に築かれている。僅かな会話とやり取りの中でもそれだけは垣間見えた。今まであなたたちがどんな関わりを持ってきたのかは分からないが、他人の為に簡単に命を懸けられる者などいない。それはあなたが魔法王だからではない」
「長い」そこでクライセンは初めて苛立ちを見せた。「もう終わりだ。出て行け」
トールは眉を寄せる。それでも話を止めない。
「彼らは君を世界一としてでなく、一人の人間として慕っているんだ。僕は君とは出会ったばかりだが、それを見て分かる。君は魔法や叡智だけの塊などではない。人を引き付ける何かがあるんだ。イラバロスに、リヴィオラに選ばれ、王に必要とされ、人々に尊敬されている。ただの幻にそんな力があるわけがない。あなたは光だ。例えだが、その言葉が相応しい」
「だから何だ」
クライセンは疎ましい目でトールを睨み付ける。トールはぞっとした。
「私は彼らを仲間だとか認めた覚えはない。頼んでもなければ必要ともしていない」
「だが彼らは君を必要としている。君に好意を抱き慕っている。それを踏み躙れるのか」
「押し売りも甚だしい。迷惑だ」
「違う。それが本音なら彼らは君についてきてはいない。そんなことくらい君には分かっているはずだろう」
クライセンは不快感を隠さずに、机に拳を叩きつけた。トールが体を揺らす。
「そんなに言うなら」青い目が細る。「今ここで彼らを全員殺してみせようか……君も一緒にね」
トールに背中に寒気が走る。その目には殺意があった。しかし、彼がなぜここまで感情的になってしまったのか、図星だからだとトールは確信した。息を飲んで、顎を引く。
「……できるものか」トールは恐れを隠して。「あなたは神ではない。人間だ」
その時、戦慄が走った。二人は同時に顔を上げる。すると船が大きく揺れ、体勢を崩す。そこにワイゾンが駆け込んできた。
「敵襲だ!」ワイゾンは剣を手にしていた。「あんたらも早く」
トールはすぐに気持ちを切り替え、剣を抜き立ち上がる。クライセンも冷静を取り戻してワイゾンに聞く。
「海賊か」
「違う。ゾンビだ」
「何だって」トールがワイゾンに近寄りながら。「ここは海だぞ」
「幽霊船だ。海で死んだ奴なんてゴマンといるんだ。まとめてきやがった。相当な数に囲まれてる」
トールは舌打ちする。走り出そうとしたとき、ティシラの怒鳴り声が響いてきた。
「ワイゾン! 何やってんの」
「ご、ご主人様、すみません」
ワイゾンがトールを押しのけて走り去っていった。トールはクライセンに振り向く。
「君も戦うんだろ」
クライセンは黙って、また椅子に座りなおしてしまった。
「クライセン!」
「うるさい」クライセンは目を閉じた。「皆が死んだら、自分でやる。精々働いてくれ」
トールは怒り震えたが、揺れる船体と甲板から聞こえてくる喧騒を放っておけずに出て行った。一人残ったクライセンは薄く目を開けて、静かに耳を澄ませていた。
トールが甲板に上がると、そこは地獄と化していた。シャルノロエスより大きな幽霊船にぐるりと囲まれていたのだ。
靄は緑がかっており、その不気味さは息苦しいほどだった。幽霊船には数え切れないほどのゾンビがうろついているのが分かる。次々とシャルノロエスに乗り込もうと、まるで列を成しているようだった。
一同がそれぞれに交戦しているが、その健闘も空しく限がない。トールも戸惑いを捨てて剣を振るった。そんな修羅場でも構わずにティシラはワイゾンを怒鳴りつけている。
「あんた、何やってたのよ!」
「ごめんなさい。旦那に知らせに……」
「余計なことしなくていいの。私たちの役目はクライセン様をパラ・オールへ送り届けて、それまでの間は私たちが彼の身を守る。そのためにここにいるんでしょ」
「は、はい」
「いい加減に状況を把握しなさいよ。本当に脳にカビでも生えてるんじゃないの」
「酷い……」
それを聞いていたトールが口を挟んでくる。
「ティシラ。君は本当にそう思っているのか」
「な、何よ。いきなり」
「もしも彼が、君たちが信頼するに値しない人だったら……どうする?」
その言葉を聞いてティシラの顔がみるみる赤くなってくる。トールは首を傾げた。
だが、思いも寄らずにティシラに頬を強くぶたれる。彼女に対して無防備だったトールはまともに受けて目を丸くする。
「そんなわけないでしょ!」ティシラは大声を出す。「このバカ、ダメ、クズ王子! 私はもうこの際クライセン様が世界一だろうが何だろうが関係ないのよ。私は彼を愛しているのよ」
「ティシラ」マルシオも大声を出す。「バカはお前だ! 下らないことを言ってないで働け」
「下らないとは何よ」ティシラは目を吊り上げている。「何なのよ、あんたたち。役に立たないくせにガタガタうるさいのよ」
クライセンは室の中で、人より鋭い感覚でその状況、会話のすべてを吸収していた。虚ろなまま、動かない。
ティシラは素早く船の舷檣に飛び乗った。目の前には海賊船が聳え、海面からぞろぞろとゾンビが顔を出している。
「敵の媒体は地面のようね」ティシラが呟く。「沈んだ死体が海底から蘇ってる。これじゃいつまで経っても終わらないわ」
「ティシラ、何やってるんだ」
マルシオが戦いながら、舷檣に立つティシラに近づいた。ティシラはそれを待たずに、飛び上がった。
「ティシラ!」
一同が注目した。ティシラは幽霊船に囲まれた海の中に飛び込んでいった。
5
クライセンがふっと目を開き、体を起こした。
ティシラはできるだけ早く海底に潜っていった。死体が上から下から追いかけてくる。それを振り払いながらどんどん進んでいく。
夜の海はさらに暗くなる。ほとんど視界は闇だった。
ティシラには闇の遮りや水圧など邪魔にはならなかった。海底が見えてきた。ティシラは手を伸ばし、底につける。死体がティシラの体に纏わり付いてくる。ティシラはその重みに耐えながら赤い目を見開く。
(来い、来い……魔界の炎よ)
強く念じた。ティシラの手元から微かに泡が立ち上がった。
(呪われし邪悪なものを焼き尽くす残酷な業火よ……ティシラ・アラモードの御名の元に……燃えろ。哀れな魂を地獄へ導け……)
ティシラの姿は死体に覆いつくされていた。だがその死体の塊の真ん中にいる彼女を中心に変化が起きた。感情のないゾンビたちが揺らいだ。
(来い、来い……)
海底に黒い炎が灯った。かと思うとそれは凄い勢いで海の中に広がっていく。
不思議な現象だった。水の中で炎が燃え上がったのだ。海水はただ騒ぐように揺れるだけで、その炎を消そうとはしなかった。魔界の黒い炎は海面まで昇っていった。
それに触れた死体は次々と消失していく。炎は辺り一面に広がっていった。その勢いは凄まじく、幽霊船に燃え移り炎上する。
海の中から燃え上がる黒い炎にマルシオたちは目を奪われ、立ち尽くしていた。熱くはなかった。その炎はこの世のものには触れなかった。シャルノロエスとその船員たちを避けて燃え盛る。幽霊船は音を立てて崩れ落ちていいった。甲板にいるゾンビたちも灰になって炎に巻き上げられていく。
「ティシラ……!」
マルシオが慌てて海を覗き込む。皆もそれに続き、海を見下ろすが、彼女の姿はない。
次第に幽霊船が燃えながら砂のような粉になり、渦巻きながら炎の中に溶けていく。だが炎の勢いは止まらない。
「ティシラ!」
マルシオが身を乗り出し、舷檣に登ろうと片足をかけた。
しかし彼は襟首を引っ掴まれて投げ出され、後ろに転倒する。驚いて顔を上げると、彼と入れ替わるようにクライセンが炎の海の中へ飛び込んでいった。一同は目を疑った。
その時、急にワイゾンが呻き出した。
「……うがぁっ!」
ワイゾンは白目を剥いて仰向けに倒れた。
「今度は何?」
マイとキジが慌てて駆け寄る。ワイゾンは気が狂ったようにのたうちまわっている。二人が止めようとするが、物凄い力で弾き飛ばされる。
「お頭、どうしたんですか!」
「離れろ」マルシオが怒鳴る。「ティシラが膨大な魔力を使って魔界の炎を召還してるんだ。あいつ、相当無茶してやがる……ワイゾンはその力に連動してるんだ」
「何よ、それ」
「それだけで死にはしない」マルシオは再び海に向かった。「ティシラが無事ならな……」
クライセンは暗い海の中で五感を研ぎ澄ましながら海の底に潜っていっていた。
炎は収まらないが、海水以外の感覚は感じなかった。
ティシラの姿を見つけた。炎に包まれながら海底に横たわっている。クライセンはティシラに手を伸ばし、掴もうとした。しかし、彼女はかっと目を開いてそれを振り払った。牙を剥き出して睨み付けている。
(魔力を制御できなくなっている……)
クライセンは再び近寄るが、ティシラは炎を身に纏い、威嚇する。
(このままだと彼女の魔力が尽きるまで止まりそうにないな)
炎はさらに威力を増した。
(……仕方ない)
クライセンはふっと片手を揺らし、額の前に拳を握った。しばらく目を閉じたあと、すぐに開く。
その青い目は朧げに揺れていた。クライセンは握った拳を伸ばし、ティシラに向けて開いた。手のひらには光る紫の小さな魔法陣が浮き上がっていた。
ティシラはそれを見て体を震わせ、怯えだした。追い詰められた猫のように背を丸め、唸っている。
だが吸い込まれるようにそれから目を離せず、体も動かない。クライセンが目を細めると、その陣の光が強くなる。すると同時にティシラの額にも紫の光が灯り、彼の手から移動するように魔法陣を描いていく。
ティシラは抵抗できずに目を見開いて震えていた。それが完成するとティシラはふっと虚ろになり、だらりと両手を垂らした。
額の魔法陣が彼女の中に溶け込んでいくと、その全身からも禍々しさが消えていく。ティシラは眠るように瞼を落とし、気を失う。
海中の炎が上に向かって昇っていく。船上ではティシラと同じくワイゾンも気を失っていた。一同は辺りを包んでいた炎が空に舞い上がっている光景に目を奪われていた。
それは不思議な現象で、絶景だった。炎の螺旋が空高くに吸い込まれて消えると、その後は今までの静かな海に戻っていた。
海面からティシラを抱えてクライセンが上がってきた。クライセンは黙ってティシラをマルシオに渡し、すぐ船内に消えていった。トールが後を追おうとしたが、彼の背中から「近寄るな」と言う無言の威圧を感じて留まった。
一同が気を失ったティシラとワイゾンを船内のベッドに寝かせて介抱すると、二人とも数十分で目を覚ました。ワイゾンは何が起こったのか覚えておらずに混乱していた。
ティシラは違った。体が重く、頭痛がする。そして自分が何をしたのか、自覚していた。心配する皆に一言謝って、それ以上は何も言わなかった。
「本当にお前は」マルシオが眉を寄せて。「大馬鹿だ」
ティシラは黙って俯いた。
「何のためにアカデミーで魔法使いの修行をしてきたんだ。理性を失い、力を制御できなくなるなんて……あれじゃ、それこそただの魔物じゃないか」
「マルシオ」トールが彼の肩を掴む。「今は休ませてやれ」
だがマルシオはそれを振り払う。
「こいつは言わなきゃ分からないんだ」再びティシラに向かい。「あのままだったら魔界の炎はこの世界に完全に具現化してしまい、すべてを焼き尽くしていたかもしれない。クライセンが止めてなかったら……俺がお前を殺していたぞ」
「マルシオ」
トールが大声を出す。マルシオはティシラと目が合って、顔を逸らす。
しんとなった。だがティシラはゆっくりと重い体を起こし、ベッドから降りて室を出ていこうとする。堪らず、マルシオが声をかける。
「……どこに行くんだ」
「見張り」ティシラは振り向かずに。「私の番だったよね」
「それはいいから」トールが止めようとする。「他に替れる者はいるんだ。君はまだ休んだ方がいい」
「ううん。これ以上みんなに迷惑かけたくない。私は平気だから」
しおらしいティシラの態度に、マルシオは戸惑った。言い過ぎたと反省する。するとティシラは肩越しに振り返る。
「マルシオ」ティシラは微笑んだ。「あんたに殺されるなら、そんなに悪くないかも」
ティシラはそれだけ言い残して室を後にした。
まだ空は暗かった。誰も甲板には上がってこなかった。
きっと気を遣っているんだろうと思う。ティシラもその方がよかった。
今は誰と話しても「ごめん」としか言うことがなかったからだ。ティシラは船橋の上部にある見張り台に腰を降ろしてぼんやり空を眺めていた。まだ調子は悪い。
本当はクライセンに謝って礼を言いたいと思っていた。しかし彼に会いにいくことが出来なかった。
彼女は一連の出来事を覚えていた。記憶を辿るとすべてが巻き戻して思い出されていく。ティシラは自分を恥じていた。マルシオの言う通り、まるで獣のように暴走してしまっていたのだ。仲間を危険に晒し、クライセンに牙を向けてしまったなんて。いっそこのまま消えてしまいたかった。
ティシラはそれと別に、頭の中に違和感があった。彼女の中に入り込んだクライセンの魔力がまだ残っていたのだ。それは守護の魔法だった。
──嬉しかった。
ティシラは不謹慎だと分かっていながら、クライセンが助けに来てくれたこと、そして彼の施した魔法が自分の体の中に感じられることを密かに喜んでいたのだ。緩む頬を隠そうと、膝を抱える。そして、そんな自分が許せなかった。
今ならマルシオにいくら罵られても文句は言えない。だからこそここで消えてしまってもいいと思っていたのだ。
どんな顔をしてクライセンに、そして他の皆にも接すればいいのだろう。そんなことを止めどなく考えていた。すると甲板に人の気配がした。誰かが出てきたんだと、ティシラは我に返り、下を覗いた。
クライセンだった。
何よりも今ティシラが一番焦る相手である。
目が合った。ひっくり返るように身を隠した。ティシラは深く息を吸い込んで自分を落ち着かせようとする。まずは謝らなければ。それから、と考えようとするが、頭が真っ白になる。混乱している彼女に穏やかな声が届く。
「ティシラ」
どきん、と胸が収縮した。目が回りそうだった。
しかしこのまま隠れて返事をしないわけにはいかない。ティシラは体を起こし、顔を出す。
「まだ頭が痛いだろ」クライセンは自分の額を指差して。「勝手なことをして悪かったね。でも魔力も魔法も使えるし、そのうち消えるから」
封印のことだ。ティシラは慌てて体を乗り出した。
「そ、そんな。謝らなくちゃいけないのは私です。でも、何て言ったらいいか分からなくて……」
「そう。でもまだ無理はしないほうがいいよ」
「あ、ありがとうございます……」
ティシラは顔を真っ赤にして俯いた。しばらく間があった。ティシラの心臓が激しく脈打ち、手が震える。これ以上その静寂には耐えられない。
「あの」ティシラは台から目だけを覗かせて。「……どうして助けてくれたんですか」
言った直後に後悔する。小声だった。彼が聞き取れていない事を祈る。だがそれは叶えられなかった。
「どうしてって、君が……」
ティシラの心臓が一瞬、止まる。
「暴れてたから」
有り得ない期待は、やはり有り得なかった。クライセンは微笑んで見上げている。確かにあの状況では誰かが止めるしかなかった。ティシラも無理して笑顔を作った。
「君の魔力は自分で思っているより強い。常に冷静な判断と、手加減をしたほうがいい。ここは魔界じゃないんだ。やり過ぎると周囲だけじゃなく、君にも危険が及んでしまうかもしれない」
クライセンの口調は優しかった。ティシラはその的を射た助言を聞いてるうちに、また目が回ってくる。あまり話の内容は聞いていなかった。
ただ、クライセンの声だけが彼女の脳を刺激していた。本来なら魔法使いとして、彼の言葉は有難く受け取るべきなのだろうが、それどころではなかった。
ティシラはいつも相手の都合も考えずに勝手な発言をしてきたが、いざクライセンから接してこられるとどうしらいいかわからずに錯乱してしまっている。
嬉しい、だけど恥ずかしい。言いたいことは一杯あるはずなのに言葉が出てこない。つまり、元々偏っている思考回路が壊れてしまっていたのだった。
何をどうしたらいいのか分からなかった。嫌われたくない、よく思われたいという気持ちが先立ち、言動や思考を空回りさせる。しかしこのまま黙っているわけにはいかない。彼の方から立ち去られるのも寂しい。
体を起こして、とにかく適当に話を纏めようとした。
「わ、私なら大丈夫です。こう見えても頑丈だし、それに」一瞬だけ、間をおき。「魔族だから……」
ティシラの体が揺れる。ぐらりとバランスを崩して見張り台から落下した。
クライセンが驚いてその体を受け止める。ティシラは気を失っていた。クライセンと話ができたことで張り詰めていた緊張の糸が切れてしまっていたのだ。
何よりもそれ以上に、本人は自覚していなかったが、体力も魔力も消耗し切っていた。顔色が悪く、体も少し冷たい。
クライセンは無防備な彼女をしばらく見つめていた。そして、ぽつりと呟く。
「……無茶なところは母親にそっくりだ」
その青い瞳は憂い、複雑な思いに満ちていた。