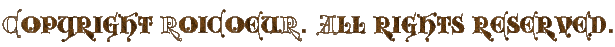第3章 追放





1
一年と言う時が過ぎた。
クルマリムの人々は、ウェンドーラの屋敷で魔法使いたちが騒いでいると噂した。
それも無理はなかった。魔法王の屋敷で、あの相性の悪い二人が毎日暴れまわっているのだから。だがクルマリムの住民は温厚な人が多く、街にまで被害が及ぶこともなかったため、たまに街に買い物に訪れる若い魔法使いを暖かく見守ってくれた。
クルマリムの街は安全な場所だった。なにせすぐ隣に魔法王の住処があるのだから。
実際はとくに影響はなかったのだが、世の悪党はわざわざここを襲おうなどとは考えなかった。世界もまた、クルマリムの街もウェンドーラの森もあまり重要視していない。確かに魔法王の屋敷はあるのだが、そこに大人しく本人が居た試しがなかったからだ。
街の人々はたまに森が光ったり、不気味にざわつくのを見かけたが、あまり珍しがる事もなかった。
ウェンドーラの森は、クルマリムができるより前からあった。クライセンは間違いなくそこで育ったと言われている。
彼が子供の頃には何度か街に訪れていたらしいが、それももう何千年も前の話で、クルマリムに彼の幼い姿を見た者はもうこの世にいないほど、遠い昔の事だった。
ウェンドーラの屋敷は不思議な造りになっていた。見た目も大きく立派なものだったが、中に入ると突き抜けそうなほど天井は高く遠く、限りがないようなその空間はどう考えても外観より広かったのだ。
ティシラは一年、マルシオはもう三年もここに住んでいるが、未だにすべての室を見た事がなかった。
入ってはいけないと言われている部屋はたくさんあったし、常に二人を召使としてしか扱わないジンは勝手に屋敷内をうろつくことを禁止していたのだ。
だが二人は、特にティシラは積極的に屋敷のあちこちを探索していた。時々ジンに見つかっては怒鳴られながら、決してめげる事はなかった。
そんな毎日が続いていたのだが、特に大した情報の収穫はなかった。ただただジンにこき使われてうんざりする時間を重ねていた。
指定された部屋の掃除、食事の買出しや仕度と片付け、庭の花の手入れや薬草の栽培、森の見回り……天気のいい今日も二人は広いエントランスの掃除をしていた。
「はあ……」ティシラはため息をついて。「何なのよ、この屋敷」
「仕方ないだろ」マルシオはホウキを持つ手を止める。「魔法王の屋敷だ。そう簡単に秘密がみつかるもんか」
「大体、毎日毎日大して汚れてもいない部屋の掃除ばっかり。どれだけ潔癖なのよ、あの猫」
「ただ俺たちをこき使いたいだけだろ」
「分かってるわよ、そんな事」
ぶつぶつ文句を言っている二人に、いつもの怒鳴り声が響いた。
「うるさいぞ、お前ら!」
ジンは怒鳴るだけではなく、いちいち声に魔力をのせて放ってくる。いつまでたっても慣れる事はできない二人は、その度に心臓を素手で掴まれるような衝撃を受ける。
「あんたの方がよっぽどうるさいわよ」
ティシラは決して毒づく事をやめなかった。
「何だと!」
勢いよく奥の扉が開き、そこから直径一メートルほどの黒い塊が飛んできた。
「ぎゃーっ!」
二人は叫び、反射的に床に伏せて頭を抱えた。すると塊は二人の頭上で破裂し、大量の墨が辺り一面に飛び散った。二人は墨に塗れ、真っ黒に染まる。が、痛くも痒くもない低級かつ悪質な魔法だった。開かれた扉の向こうにはジンが仁王立ちしている。
「掃除」ジンは墨に塗れた二人と室内を見回して。「夕方までには終わらせろよ」
ティシラが真っ黒な顔で立ち上がる。
「やり方が汚いわよ、この陰険魔法使い!」
「汚いのはお前の顔だ。私は礼儀知らずの魔法使いに正当な罰を与えたまでだ。早く掃除しろ。終わるまで休憩はなしだ」
そしてその扉はジンの意志に従い、ばたんと閉じた。
2
再びティシラとマルシオは掃除をしていた。まずは浴びた墨を洗い流し、服を着替えた。憂鬱な面持ちだが、黙々と作業していたので思ったより早く室内はきれいになっている。
それにしても、と思う。意地悪で墨を撒き散らすのは自由だが、ここは自分の家なのによくやると感心する。室内のあちこちには細かい細工のある彫刻や置物があるというのに、その細部にまで墨は張り付いている。しかしそこまできれいにしていないとまた怒られるに決まっている。染み付いて取れないところや手が届かないところと、仕上げには魔法を使うしかない。
最初からそうしたいところだがアカデミーでも横着な魔法は使ってはいけないと教えられたし、当然ジンにも怒られてさらに過酷な仕事を言いつけられる事になる。
むかつく、が、どうせ暇なんだしと二人は開き直っていた。
「大体」マルシオがティシラを睨む。「お前には学習能力はないのか。いちいち何の役にも立たない反抗なんかするな」
「私はあんたと違ってジンに頭を下げる義理なんかないのよ。そもそも巻き込んだのはあんたなんだから、私に指図しないでよね」
「もっと利口になれと言っているんだ」
「なんですって。そう言うあんたのどこが利口なのよ。あんたが一番バカじゃないの」
「うるさいな。済んだ事をごちゃごちゃ言うな」
そのとき、玄関の扉の横にある三メートルほどの鷹の彫刻から僅かに風が吹いた。二人がそれに気づいて見上げると、宙に何か白いものが浮いていた。
ティシラは舞い降りてくるそれを捕まえる。
「手紙だわ」
それは羊皮紙の封書だった。微かに白檀の薫りがする。鷹の彫刻の開かれた嘴から飛んできたらしい。しかし彫刻は外には繋がってはいない。おそらく特別な者が特別な魔法で送ってきたのだろう。
ティシラが表面をちらりと見ると、再びあの扉が開き、ジンが物凄い速さで彼女に体当たりしてきた。
「いったーい!」
ティシラは何メートルも吹っ飛ばされ、壁に体を打ち付ける。その拍子に手紙は彼女の手から落ち、ジンがそれを横取りする。マルシオはその一瞬の出来事に目を丸くして背を縮めていた。
「何なのよ、急に」
ティシラは体を起こしながらジンを睨む。ジンは冷静に封筒を胸元にしまった。
「許可のないものに勝手に触るな」
「目の前で手紙が届いたのよ。それを手に取るくらい自然な行動でしょ」
「黙れ。ここでは私が規律だ。不当な扱いを受けたくなかったら夜中にこそこそ屋敷を徘徊する妙な癖を戒める事だな」
ジンはそう言うと早足で奥に消えていった。ティシラは言い返さなかった。ぶつけた腰をさすりながら立ち上がり、奥の扉が閉まった事を確認して。
「ばれてた」
「当たり前だろ」マルシオがティシラに近づく。「ここはジンの腹の中も同然なんだから」
「でも、どこかに盲点はあるはずよ」
「そうかもしれないが……」
「ねえ今の」ティシラは声を潜めた。「よく考えてみて……あんなにムキになったジンを見た事ある?」
「…………?」
「予想外の出来事が起きたのよ」ティシラの目がきらりと光る。「手紙がきた事、それを私が手に取ってしまった事……その事態を塞ぎきれなかったんだわ」
「どういう事だ」
「あの手紙が彼にとって重要なものだったとしたら? そして私たちにとってもね。手紙がくる事を予想していたのなら……あれは特殊な魔法で送られたものだもの。ジンが知らないはずがないわ。問題は私が手に取ってしまった事よ」
「何か見たのか」マルシオも声を小さくする。「あの一瞬で何を?」
「あの手紙の宛名……『クライセン』だった」
嬉しそうに囁くティシラとは逆に、マルシオは眉を寄せて首を傾げた。
「やっぱりここにクライセン様がいるんだわ」
「ここはクライセンの家だから、彼宛の手紙がきてもおかしくないんじゃないのか」
「だったらなんでジンはあんなに必死になって手紙を隠したのよ」
「中身は重要だったかもしれないが……お前がいつもジンの身辺を嗅ぎまわっているから、中身をみられたくなかったんじゃないのか」
「もう」ティシラも眉を寄せる。「なんでそんなに思考が後ろ向きなのよ」
「思考の問題か。宛名を見ただけで一体何が分かる」
「あの手紙が重要だったって事よ」
「だがそれもジンに取られた。重要ならもう探し出せないところに隠される」
「クライセン様に手紙が届いたなら、彼がここにいるかもって思わないの?」
「そんな事、ここがクライセンの家だってだけで考えつくだろ。だが彼の姿はどこにもないのが現状だ。お前は手紙ごときで何を期待してるんだ」
その時、つい興奮してしまった二人の頭上にまたいつもの雷声が轟いた。
「うるさい!」
「ごめんなさい!」
二人は同時に縮こまった。
3
一週間、結局また同じ日が続いた。手紙は見つからなかったし、あれきり鷹の嘴から風が吹くこともなかった。
この日も玄関の掃除だった。今日は静かだ。二人は黙って掃除をしている。ふとティシラが呟いた。
「……はあ、退屈」
虚しく、さらに二時間ほどが流れたころ、外から玄関の扉を二回叩く音が聞こえた。
二人は顔を見合わせて、次に奥の扉に目を移す。ジンは出てこない。ノックの音に応えるべきか、また二人は顔を見合わせた。再びコンコンと戸が鳴らされる。
マルシオが緊張しながら戸をゆっくり開けた。来客など初めてだった。扉の向こうには一体誰がいるのか、まったく予想できない。
開いた扉の間から小柄な老人が顔を見せた。そしてのろりと中に入ってくる。二人は何も声をかけなかった。「いらっしゃい」とも「ようこそ」とも、言える立場ではなかったからだ。老人は長い髭と白髪で覆われた頭をゆっくり持ち上げて、皺で埋まってしまいそうな細い目でエントランスを眺めた。
「久しぶりだが、何も変わってないな」そして、きょとんとしている二人を順に見て。「若い魔法使いが二人いる事を除いては」
老人は深い緑色のマントを羽織っていた。その繊維には微量の金の糸が織り込まれており、老人が動く度にきらきらと光る。マントの中から覗く衣服には綺麗な刺繍が施されているのが見え隠れする。その身に纏ったものと、彼自身が放つ風格から身分の高いものである事が推測される。そこでやっとティシラがぽつりと尋ねた。
「あなたは?」
もっと早くしていい質問だった。
「ここの屋敷の住人じゃ」老人はにこりと微笑んで。「ここ数年、家を空けていたがな」
その言葉でまた沈黙になる。老人はその空気に首を傾げた。
ティシラの血がゆっくりと引いていく。目に見えるほど顔が青ざめていく。そして震える声で、再び質問する。
「……まさか」その声は途切れ途切れだった。「クライセン……様……?」
老人は皺の奥の瞳に意地悪な光を灯した。二人にそれは見えない。
「そうだとしたら?」
ティシラはさらに震え出し、みるみる顔が絶望に満ちていく。
「いや……そんな……」
マルシオは老人が中途半端に答えている事に気がついていた。彼がクライセンなのかどうかはこの時点では確信できない。マルシオにとって老人の正体より、ここまで落ち込んで身動きが取れなくなっている彼女を見るのは初めてで、そっちの方に気を取られていた。哀れだが、慰めの言葉はまだかけない。
「クライセンはもう五千年以上も生きてる。老人の姿であってもおかしくないだろ」
「そんな……」
先代のイラバロスはランドール人だったため、アンミールより遥かに長寿だった。少なくとも彼が旅に出るまでは若く美しい青年として描かれている。
人々の記憶に残っているのはそんな彼の凛々しい姿だったのでリヴィオラを受け継いだクライセンもまた、二千年前の青年の姿のままのイメージしか残っていなかった。
アンミールの寿命は様々だった。魔力が強ければその分長寿であり、若く強い肉体を維持できる。何千年も生きるアンミール人は今では珍しかったが、リヴィオラを持つ彼なら何年生きてても誰も不思議には思われなかった。少なくともほとんど人前に姿を見せない彼は尚更謎が多く、その素性も人格も容姿も皆の都合のいいように解釈されていた。
特に若い女性の間では「若く美しく、誰よりも勇敢で強い高潔なる男」であると、理想の男性像で描かれていたのだ。ティシラもその一人だった。
夢を打ち砕かれ──それはジンに「死んだ」と言われたときよりも強い衝撃で──蒼白するティシラは嘆きの声を上げた。
「……そんな! 私の未来の旦那様が……こんなお爺さんだったなんて」
そんな自分勝手で失礼極まりない彼女の反応を分かっていたかのように、老人はティシラに近づく。
「儂が君の旦那様? それはありがたい」軽く笑いながら。「ずっと昔に妻に先立たれて寂しい老後を不安に思っていたところだったのだ」
「嘘! しかも既婚者?」ティシラは老人から離れて、とうとう泣き崩れる。「私はこれから何を希望に生きていけばいいのよ」
老人は更に笑い声を上げた。明らかにからかっている。マルシオはとりあえずこの老人が何者なのかは後回しにし、目の前の下らないやり取りを渋い顔で見ていた。
しかしその平穏な時間も長くは続かなかった。奥の扉から鬼が、ジンが現れた。
「何をしている!」
ティシラとマルシオはびくっと体を揺らし、脅える。老人は一歩前に出てジンに軽く頭を下げる。ジンも会釈をしながら、丸くなって泣いているティシラを見て怒鳴りつけた。
「このバカ者が!」
するとティシラとマルシオが同時に吹き飛ばされ、壁に叩きつけられて悲鳴を上げる。そしてジンはすぐに老人に向き直り姿勢を正した。
「お久しぶりです」右手を左の胸にあて。「思ったより早い到着で……出迎えに不備と失礼があったことをお許しください」
「なに、楽しい出迎えではないか。儂は嫌いではないぞ。そう堅苦しくなるな」
ティシラとマルシオは壁に張り付いたままその光景に目を奪われた。あのジンが丁寧にもてなしている。ジンに頭を下げさせるこの老人は、やはりクライセンなのかと思わされた。
「まだ訪れられるまで」ジンは二人を無視して老人を奥へ促した。「時間がかかるものかと」
「急げと言うから急いで来たのに」
「そうでしたね……」
ジンと老人が奥へ行こうとした時、マルシオが体を乗り出してそれを止めた。
「ちょっと待てよ」
素早くジンに睨まれて一瞬怖気づくが、マルシオはぐっと踏みとどまる。
「その人は……本当にクライセンなのか」
ティシラは嗚咽しながらマルシオに縋るような目を向ける。
「黙れ!」
再び怒鳴られ、二人は体を揺らす。ジンは恐ろしい顔で二人に歩み寄る。
「この方はサンディル・ウェンドーラ様だ」脅えている二人の数歩前で足を止め。「クライセンの父親である偉大な賢者だ。お前たちが気軽に口をきいていい人ではない。これ以上失礼を働くようなら……鶏にして首を刎ねるぞ」
二人はその迫力に目を見開いて震えていた。すると老人、サンディルが宥めるように優しい声をかける。
「まあまあ、そんなに大きな声を出さんでも」
「あなたも」ジンはサンディルを肩越しに見ながら。「こんな役立たずの子供たちに悪ふざけなどやめてください」
さすがにティシラとマルシオはむっとした。怒りはゆっくりとこみ上げ、次第に奮えもとまる。そして改めて状況を整理する。とりあえずこの老人がクライセンでない事は間違いない。ティシラはそれだけで十分に立ち直れた。
「ちょっと」涙を拭きながら、立ち上がり。「何の説明もなしにそんな言い方はないでしょ」
「そうだ。散々こき使っておきながら役立たずはないだろ」
「それに、子供ですって? 私たちは一人前の魔法使いなのよ」
ジンは二人を睨み付けた。怒鳴らない。それが更に恐怖を募らせる。二人もその気迫に飲み込まれて言葉を失った。そしてジンは声に魔力を含め、怒鳴らずに言った。
「出て行け」
4
ティシラとマルシオの背中に寒気が走る。
「役立たずども」
ジンはそれだけ言うと、くるりと背を向ける。堪らず、マルシオが叫ぶ。
「何だよ、それ」
ジンは振り向かずに答える。
「出て行けと言った。意味くらい分かるだろう?」
「……どこに?」
「好きなところへ行け。そして二度とここへは戻ってくるな」
愕然とした。あまりにも突然な追放だった。さらにジンは続けた。
「マルシオ、もうお前の罪も許そう。自由にしてやる。ティシラ、お前はもともとただの居候だ。魔界へ帰って花嫁修業でもするがいい」
ティシラはその言葉にかっとなった。飛び出そうとする彼女をマルシオが掴んで止める。
「あんたには関係ないでしょ。ふざけんじゃないわよ! 私は好きでここにいるのよ。クライセン様に会えるまで出て行かないわよ」
「そうだ」マルシオも目を吊り上げて。「俺も、魔法王になると言う夢がある。ここにいるきっかけはともかく……あんたの事は魔法使いとして尊敬できるし、俺もクライセンに会いたいんだ」
「私には関係ない事だ。とにかくここにいられたら迷惑なんでな、よそでやってくれないか」
ジンは冷たかった。今までも優しくなんかはなかったが、それとは別のものが感じられた。
ジンが本気で言っているのが伝わり、二人は焦っていた。今まで扱いは悪いながらもちゃんと面倒は見てくれていた。喧嘩はしょっちゅうだったし、不満も山ほどあったが逃げ出したいなんて思わなかった。ここにいてその先に何があるか分からなかったが、嫌だ、と思った。
その光景をサンディルは黙って見ていた。その顔には悲しみの色が灯っていた。
「追い出してみなさいよ」
ティシラは両足に力を入れて、その目と声に魔力を乗せた。内心は、脅えていた。ここを出てどこにいけばいい?
自分たちが出ていったらこの猫はこれから誰と喧嘩するのだ。誰がこの屋敷の掃除をするのだ。
ここで別れる理由が見つからなかった。マルシオも同じく、この猫と屋敷に情が生まれていたのだ。
ジンは呆れたようにため息をついた。そしてふっと振り向いて二人に向き合う。その顔に表情はなかった。そしてジンは右手を挙げ、指を鳴らす。するとその指先に小さな光る星屑が散り、そこに手のひら大の銀の菱型の小箱が現れた。
ジンはそれを掴み、マルシオに投げつけた。
マルシオは戸惑いながら箱を両手で受け取る。二人は怪訝そうにジンに目を移すと、彼は「開けろ」と顎を突き上げた。
マルシオは慎重に蓋に手をかける。するとその中から青い光が溢れ出た。中には深く、透き通る空の色をした一つの石が入っていた。二人が初めて見るその宝石は今までみた事のない、いや、おそらくこれ以上の美しい宝石はこの地上のどこにもないと思えるほど輝かしかった。
自然とマルシオの口からその名が導かれた。
「……リヴィオラ?」
二人は息を飲んだ。こんなに早くそれを見る事ができるなんて思いも寄らなかった。しかしその美しさに見とれている場合ではなかった。ティシラがマルシオより先にその魅力から解放された。
「まさか」その目は震えていた。「本当にクライセン様は……」
それ以上は言えなかった。そんな彼女にジンは止めを刺すように。
「死体はないが……それで満足してくれるか?」
マルシオはゆっくりジンの言葉を待つ。箱を持つ手に力が入らない。今にも落としてしまいそうだった。
「欲しかったら」ジンは無表情のまま。「やるぞ。だから、出て行け」
マルシオは強く瞼を閉じた。歯を食いしばり、こみ上げる涙を堪えた。
「俺は……」かっと目を開き。「こんな形で欲しくなんかない!」
マルシオはリヴィオラを箱ごと床に叩きつけた。宝石は音を立ててジンの足元に転がった。それを見ていたサンディルが一瞬息を止めた。が、何も口出ししない。
「バカにするな!」マルシオの声は震えていた。「これは魔法使いに対する最大の侮辱だ」
彼のその銀の目は充血していた。怒りで固まる体に力を入れて振り返り、玄関の扉を魔法弾で破壊して飛び出していった。
「マルシオ!」
ティシラがそれを見送った後、再びジンを睨み付ける。
「……あんたって、最低」
ジンは相変わらず冷めた目をしていた。
「私は君たちの望むものを与えた。一体何が不満だ」ジンは眉を寄せ、足元の宝石を拾い上げた。「これを床に投げつける魔法使いなんて、前代未聞だな」
それだけ言うとジンは石を手の中に収めて、ティシラもサンディルも置いて早足で奥に消えていった。
遠ざかるジンの足音は、大股で感情的なのが伝わってくる。そして扉はいつものように一人でに閉じてしまった。玄関の方の扉は無残に大穴を開けられパラパラと破片が散り、埃が舞っている。
サンディルはずっと昔からそこにいる柳の木のように黙していた。
ティシラは立ち尽くした。ジンには追いかけて言いたい事が山ほどあるが、マルシオも放っておけない。今一番に何をすればいいのか、だがゆっくり考えている場合でもなくさらに混乱する。そんな彼女にサンディルが声をかけた。
「若い魔法使いよ」その声は風のようだった。「思うがままに行動しなさい。迷い、戸惑う時も必要だが、今ではない」
「……賢者、サンディル様」ティシラは深く息を吸い込んだ。「本当なら……今すぐあの猫をぶん殴ってやりたい。そしてあの暴言を取り消させてやりたい」
「暴言とは?」
「クライセン様が死んだなんて……それに、なんでここにあるのか知らないけど、リヴィオラをあんな未熟な魔法使いに簡単にくれてやろうとした事……許せない。魔法使いにあるまじき行為だわ」
「そうじゃな。奴は無碍に若い心を傷つけた。だが……」間をおいて。「理由があったのじゃ。恨むなとも許してやれとも言わん。それを君たちに説明し、納得させる時間がきっとないんじゃ。君たちに背を向けられるのを承知で取った行動なんじゃ……奴にも覚悟はあった。それだけは分かってやってくれ」
ティシラの悲しい顔から怒りが消えていた。
「教えてください……クライセン様は本当に……いないのですか?」
サンディルはすぐには答えなかった。再び一本の老木のように時を刻む。彼には彼女が微かに震えているのが分かった。答えを待っている。脅えながら。
サンディルの声には穏やかな魔力が篭っていた。
「リヴィオラが居所を見失い、彷徨っているのは君も目にしたじゃろう。それが事実じゃ」
ティシラの目から涙が零れた。
「だがリヴィオラは迷っているだけじゃ。いつか必ず在るべき所へ還るじゃろう。君も、君の友達も同じくして道に迷いかけている。そして、また見つける。道は必ずある。それが運命の力じゃ。さあ行きなさい、若き魔法使いよ。この世は間違いも多いが……過ごした時間に無駄は一切ないのじゃから」
ティシラは頬を涙で濡らし、ゆっくりと振り向く。重い足を引きずりながら、まだ埃が舞っている玄関の外に消えていった。サンディルはその悲しい背中を見えなくなるまで見送った。
サンディルが奥の室へ通じる扉の前に立つと、それは手を触れずとも開いた。彼がゆっくり潜るとまた閉じる。
さらに広い広間の正面の壁には三つの扉があった。サンディルは歩みを止めずに真ん中のそれに向かう。扉はまた一人でに開き、サンディルを迎え入れるとその口を閉じる。
そこは円形の大きな部屋だった。頭上には階段が螺旋状にどこまでも続き、天井は見えない。部屋の中心には一羽の大きな鷲がいた。彫刻ではない。鷲の首は二つに別れており、サンディルを四つの黄色い瞳で出迎えた。
サンディルは優しく微笑み、鷲に跨る。双頭の鷲は丁寧に、そして力強く翼を広げ、老賢者を螺旋の上方に連れていった。
鷲は螺旋の終わりまでは飛ばなかった。途中の階段で翼を収め、サンディルを降ろす。サンディルは再び地上へ舞い戻る鷲を見送って、目の前に構える黒い鉄で出来た扉の中へ入っていった。
そこはジンの、正確にはクライセンの書斎だった。壁はレンガ造りで奥には暖炉があり、火が灯っている。
本棚には古い本が詰まっており、入りきれずに床にいくつも積んであった。棚や机には何やらごちゃごちゃと物が散乱している。どうやらしばらくの間、掃除や整理はしてないようだ。中は特に変わったところはない。暖炉の前のソファで服を着た猫がパイプをふかしている以外は。
そして彼の前にある低いテーブルの上には、空のカップや職台などの隣に、青い宝石が転がっていた。
5
ジンはノックもせずに入ってきた老人をちらりと横目で見る。
「鷲が道に迷ったか?」顔の前には煙が漂っている。「だとしたら、あいつらもクビにしないとな」
ジンはあからさまに皮肉る。サンディルがここにくるのが遅かったのを、間接的に責めていたのだ。だがサンディルは気にしなかった。
「人に後始末を押し付けていっておいて意地の悪い事を言うな。ほっとけば今頃アラモードの娘が屋敷を破壊しているぞ」
サンディルは散乱した物を踏まないように気をつけながら歩み、ジンの向かいのソファに腰掛ける。
「余計な世話だ」
ジンは不機嫌そうだった。さっきとはまるで別人のように態度が違う。
「相変わらずじゃな」サンディルも胸元からパイプを取り出し、火をつける。「お茶の一つも出んのか?」
「ここはあんたの家だろ。自分でやれば?」
「それもそうだな」
サンディルは煙を吐く。続けてジンも吐き終えると、パイプを咥えたまま話出す。
「あれを持ってきたんだろ」
「……そうじゃ、そのために来たんじゃったな」
「見せてくれ」
サンディルはまた胸元から一冊のノートを取り出した。黒い表紙のそれはあちこちが擦り切れている。ジンが手を差し出すが、すぐには渡さなかった。
「これはとても危険なものじゃ」
「分かってる」
「できれば……見せたくない」
ジンはそれ以上は問答無用で、身を乗り出して乱暴にサンディルの手からノートをひったくる。サンディルはため息をついてソファに深く座り、背を縮める。
老人がじっと心配そうに見守る中、ジンはノートをしばらく読み耽った。その大きな瞳が左右にきょろきょろしている。一通り目を通した後、大体を理解したようにジンは頷く。
「なるほどね」ジンもソファに深く座り直し。「さすがだ、大賢者サンディル殿。しかし──」
サンディルはジンが何を言わんとしているか分かっており、代わって続きを口にした。
「『あいつ』も、同じものを持っている」
ジンは僅かに眉間に皺を寄せた。
「盗まれるとは、何たる間抜け」
ジンが気に入らないのはこのノートの存在ではなく、それをよからぬ者に奪われてしまったことだった。
「賢者たる者、こんな危険なものはさっさと処分し、あんたの記憶からも消し去るべきだった。もし私がこの存在を盗まれる前に知っていたら……私があんたを殺していたかもしれないな」
「儂は、どれだけ時間をかけても改良し、良い方向に使いたかった。それが適わなければ黙って墓に持っていくつもりじゃった。それは本当じゃよ」
サンディルは頭を垂れる。ジンはそんな彼に容赦なく続ける。
「力は使い方によって善にも悪にもなる。だがあんたが造り出したものは世界を滅ぼし兼ねない、この世のすべてへの挑戦状だ。その結果を予測できない以上、これは武器をも超越したただの『恐怖』に過ぎない。あんたは分かっていたはずだ。これは善悪、どちらにも属さないと。ならばなぜ廃棄しなかった?」
問うておきながら答えを待たず、ジンは続ける。
「しなかったんじゃない。できなかった、欲に負けたんだ。この誰も為しえない偉大な力を自分の胸にしまい、この世から消し去る勇気がなかった」
サンディルは汗を流し、頭を抱えた。
「……分かっている」
「賢者としては立派な功績かもしれない。が、人間としては最低だ。この愚かな欲で戦争さえ起こるだろう。魔法戦争も人間の強欲さが起こしたものだ。あんたはその戦をその目で見てきたはずだ。五千年も過ぎるとあの痛みを忘れてしまえるものなのか? あの戦争で世界は何を失い、何を学んだ? 再び戦争を起こし、残ったパライアスの大地までも砕こうと言うのか」
サンディルは黙った。そのジンの言葉はまるで台詞を読むかのように淡々としていた。顔を上げたサンディルの顔は、悲しんではいなかった。
「……そうではない。だからお前に……託すのだ」
ジンの表情がやっと動いた。
「儂の唯一の功績は、こんな恐ろしい兵器などではない。偉大な魔法使いをこの世に育てた事じゃと、自負している」
「そうかもな。じゃないと救えない」
「希望はあるか?」
「なくもない」
「儂にも協力させてくれ」
「それは何度も断った」
「まだそんな事を言っているのか。世界が滅んでしまうのかもしれんのじゃぞ」
ジンはふっと口の端を上げる。そして捨てるように言い放った。
「知った事か」
サンディルは困ったように眉を寄せる。顔の皺が余計に深くなった。
「ジン……」サンディルは表情を変えずに。「四代目魔法王は、クライセンは……蘇るか?」
ジンは答えない。しかしその目に灯るものでサンディルは答えを読み取った。
そして、深いため息をつく。
「まったく、寿命の尽きかけた老人をもう少し労わってくれてもバチは当たらんじゃないのか」
「クライセンは」ジンは皮肉に微笑む。「あんたを賢者として尊敬し、父として愛してるよ」
「……恨んでいるのだろう?」
「それはない」
サンディルはそれ以上聞かなかった。確かに彼が恨みなどと言う単純な言葉に捕らわれるとは思わない。恨みなどではない。他のもっと、複雑な思いがあるのだろうと思う。無神経な質問をしてしまったと、サンディルは後悔した。
「ならばせめて、孫の顔でも見せて欲しいものじゃな」
話の腰を折り、皮肉で返すがさらに切り返されてしまう。
「伝えておく。だが、相当時間がかかると思う。まだまだ長生きしないといけないぞ」
サンディルはふて腐れながら腰を上げた。今はここでこれ以上話をする事はないと判断する。お互い別れの挨拶さえ必要としない。
「ああ、そうだ」ジンは思い出したように。「もしラムウェンドに会ったら──アカデミーなんて無駄なものはさっさと畳んで引退しろと勧めてやってくれ」
何を突然言い出しているのかと、サンディルは肩を落とした。
「無駄ではなかろう」
「あの失敗作を」ティシラとマルシオの事らしい。「みれば分かるだろう」
なるほど、そのことか――サンディルは薄く微笑む。
「果たして、本当に失敗作かな?」
そしてのろのろと扉に向かい、戸を開ける前に、見送りもしないジンを振り返った。
「……この際、世界がどうなっても構わん」
その姿は賢者でも何でもない、ただの老人だった。
「儂より先には死なんでくれ」
ジンはサンディルを見向きもしないまま、微かに笑っていた。
「伝えておくよ」
そして黒い扉は老人を送り出し、静かに口を閉じる。ジンは一人、再び黒いノートを開いた。前方のテーブルの上では、暖炉の炎に照らされた青い宝石の光がゆらゆらと揺れていた。