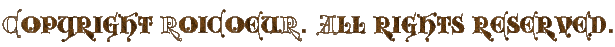第6章 軍神の砦





1
一行はミング山から半日ほど馬を走らせたところにある砦の地下牢に閉じ込められていた。明かりは立ち並ぶロウソクの光だけだった。通路を挟んで両側に牢がいくつも仕切られて並んでいる。閑散としていて他に誰も捕らえられてはいなかった。前日の毒ガス騒ぎで、常勤の兵も囚人も移動させられているのだろう。
一同は魔法使いと海賊、三人ずつに分けられて入れられていた。斜め前の海賊たちが嘆いていた。
「せっかく洞窟から出られたのに……もうお仕舞いだ」
ワイゾンが膝を抱えている。
「船も捕らえられているみたいね」マイはため息をつく。「見張りに残した奴らももう捕まったか、逃げてしまっているんでしょうね」
「ああ……」キジは半ベソだった。「拷問とかされてしまうんでしょうか」
「馬鹿」ワイゾンが顔を上げて。「死刑だよ」
「そんなあ」
マルシオが鉄格子ごしにそれを眺めていた。
その背後ではクライセンとティシラがそれぞれ角に背をもたれて黙っている。マルシオはこの魔法も何もかけられていない牢を脱走する気にはなれなかった。ティシラは相変わらず俯いて落ち込んでいるし、頼みのクライセンもやる気なさそうに物思いに耽っている。
海賊たちは無駄に騒いでいるし、何で無罪の自分たちがこんな牢に閉じ込められなければいけないのか分からないし、もう考えるのも疲れていた。
その時、衛兵たちが数人、地下に勢いよく傾れ込んできた。海賊たちが縮み上がる。が、彼らはその前を見向きもせずに通り過ぎていった。
そして魔法使い組の牢の前に立ち並ぶ。先頭にいた男は兜を取っていたが、その体格で先ほどの軍帥である事が人目で分かる。ダラフィンだった。
「その黒髪の男」ダラフィンは他の誰にも目をくれず。「名は?」
クライセンは自分の事だと分かり、その青い目線をダラフィンに送る。一同は黙ってそのやり取りを見守った。
「クライセン」
そう彼は名乗った。
「クライセン・ウェンドーラ。その青い目。四代目魔法王か」
「そう言われてる」
「本物か」
「質問の意味が分からない」
「死んだと言われているが」
「だから?」
「本物ならなぜ抵抗しない。この牢を破るくらい容易いだろう? それに、簡単にはその姿を捉える事すらできないと聞いている。本人だと言う証明を見せてみろ」
クライセンは彼をじっと見つめたまますぐには返事をしなかった。向けられた目線は好意的なものには見えず、ダラフィンは軽く首を傾げた。
「どうした」
「つまり、用件は?」
「何だと?」
周囲がどよめく。横柄なクライセンの態度に驚かされていたのだ。
「君たちは本当に面倒臭いな。証明と言うが、私がここで牢を破って逃げたら、せっかく捕まえたのに努力が無駄になるんじゃないのか」
クライセンは目を伏せ、物怖じもせずに白々しく続けた。
「オーリスからの手紙は読んだよ。よく働くね、彼は。私を探し回って心労しているそうじゃないか」
「分かっているなら、なぜすぐに彼を訪ねなかった」
「そのうち連絡するつもりではいたよ」
「そのうちだと?」
マルシオは、あの手紙は軍からのものだった事を悟る。オーリスの名前は聞いた事がある。当然だ。現在の魔法軍の頂点に立つ総監なのだから。アカデミーの教科書に何度かその名は載っていたし、ラムウェンドの口からも彼の勇姿や人格は話されていた。
ダラフィンは確かに、これ以上は時間の無駄かもしれないと思う。本来ならこの程度のふざけた問答から導かれる根拠など何もないはずだった。だが、彼を見ていると不思議と疑う余地を払拭される。
ダラフィンはあまり魔法界の事情には詳しくない。それでもこの男が普通でない事だけは分かる。
オーリスが「彼は普通の魔法使いではない」と言っていた。何が、と問われれば説明はできないが「なるほど」という言葉が頭を掠める。彼のこの偉そうな態度がそうさせているわけではない。雰囲気、とでもいうのだろうか。とにかく漠然としていた。
ダラフィンは頭で考えるより、まず体が動くタイプだった。話を先に進める。
「国王がクライセンをお探しだ。君が本物ならティオ・メイに連れていく」
「そう。じゃあ、早く連れていって」クライセンはあっさりと受け入れる。「ここは暗いし汚いし、不愉快だ。これ以上いたら病気になる」
それだけ言うとクライセンは目を逸らす。この大陸一の剣術使いと言われる大男を前にしても全く物怖じしない。何も知らない愚か者なのではない。だからと言って見下しているわけでもなかった。ダラフィンにはそれが分かる。さほど不快ではなかったのだ。むしろ、面白いと思った。個人的な感情に過ぎなかったが、こういうのは嫌いではない。彼も負けてはいられない。
「どうやら本物らしいな」ダラフィンはにやりと笑った。「歴史も時代もすべてを無視する、怖いもの知らずの不届き極まりない魔法使い──噂通りだ」
「そんなふうに言われているのか。傷ついた」
「嘘をつくな」ダラフィンは豪快に笑い出す。「おかしな奴だ。オーリスが手に負えないもの分かる。尋問は得意じゃない。もういい、出ろ」
そう言いながらダラフィンは部下に鍵を開けるように合図する。すると彼の背後にいた一人が牢の鍵に手をかける。その様子の中で、クライセンが立ち上がる前にマルシオが大声をあげた。
「ちょっと待ってくれ。俺たちはどうなるんだ」
「お前たちは」ダラフィンがぐっと見下ろしながら。「後で調べる。まだここで待ってろ」
「冗談じゃない。俺たちは何もしてない。無罪の者を牢に閉じ込めるなんて、軍のすることか」
「クライセンを送ったら部下の者を手配する。本当に無罪ならすぐに出られる。騒ぐな」
「送ったらって、彼をどこに連れていく」
「陛下の所だ」
「ティオ・メイか」
「そうだ」
「俺たちも一緒にいく」
「何だと?」
マルシオは勢いで口にしてしまった、一同が彼に注目した。
「馬鹿なことを。国王陛下との謁見が簡単に許されるか。君は一体何様なんだ」
マルシオは息を飲んだ。クライセンに助けを求めるが、相変わらず彼は目を合わさないように顔を背けている。ティシラも不安そうな目をしたまま発言する気配はない。マルシオは小さく舌打ちをしながら再びダラフィンに向き合う。
「俺は……」考える、が、時間はない。咄嗟に口をついて出てしまっていた。「クライセンの弟子だ」
何でこんなことを言ってしまったのか、少し後悔する。クライセンが事実を否定すれば嘘がばれて余計に立場が悪くなる。マルシオは脅えたが、もうやけくそになった。
「彼と常に行動を共にして魔法の修行をしているんだ」本当はさっき出会ったばかりなのだが。「師匠と引き離さないでくれ」
ティシラは目を丸くしていた。クライセンは迷惑そうにため息をつく。海賊たちも身を乗り出して格子から覗き込んでいた。
ダラフィンは当然疑っている。むしろ嘘だと見抜いていた。知る限りのクライセンの人物像から人とつるむなど考えられない。何よりも、少年の必死な態度がそれだけで嘘臭い。そう思いながらクライセンをちらりと見るが、彼は質問しないと答える様子はない。
ダラフィンは事実を必要としなかった。
「気の毒だが」少し身を屈めて。「そうだとしても一緒にとはいかない。オーリスに青い目の魔法使いの報告をしたら、そりゃもう大感激してな、奮発して依送の法を使う事になったんだ。もう準備に取り掛かっている。ただし、一人分だ。腰巾着の分は用意されていない」
「依送……」
マルシオは絶句する。その背後でクライセンが微かに目を動かした。
依送の法とは、その目標基点に魔法使いを設置し、人を瞬間で移動させる高等魔法だった。それに要する人手や魔力は膨大なものだった。よほどの事がなければ使われない。今まで報告された中でも、国家機関の大事以外で一件もないほどだった。
「後から俺もメイに馬を走らせる。取調べで問題がなく、俺の出発に間に合えば連れていってやるから。もう少し大人しくしているんだ」
ダラフィンはそう言うが、それじゃ駄目なんだとマルシオは焦る。置いていかれる以前になんとしても取り調べから逃れたかったのだ。
勝手に立ち入り禁止のアムジーに入り込んだ事、海賊との関わりを持っている事、そしてここで嘘をついてしまった事がばれればどんな汚名を着せられるか、どんな罰を受けるか分からない。魔法使いとしての立場は確実に悪くなる。
それに、やっとクライセンに出会えた。まだまだ知りたいことがある。そしてどうやら、既にとんでもない事件に足を突っ込んでいるようだ。こんな所で訳も分からないうちに戦線離脱するのだけは嫌だと思ったのだ。
「そんなの……」
マルシオが再び無理やり口を開こうとするが、思いもよらずそれをクライセンが止める。
「軍帥、頼むよ。私の弟子の分も用意してやってくれ」
2
マルシオは言葉を失った。そう言ってくれるのは有難いが、クライセンが何を考えているのか全く理解できない。ティシラも驚いて身を乗り出した。
「無茶を言うな」ダラフィンは眉を寄せて。「依送がどれだけ面倒か、俺でも分かる。とにかく今はあんただけでも……」
「そこを何とか」クライセンは意地悪な笑みを浮かべる。「メイには優秀な魔法使いが暇を持て余しているんだろ」
ダラフィンは厳しい顔をする。しばらくクライセンを睨み付けていたが、大きな体を反らして、また笑い出した。
「クライセン、あんたは本当に──いや、噂以上に性格が悪いようだな」
「さっきから酷い言われようだな」
「オーリスに恨みでもあるのか。だとしても年長者は大事にしないと碌な大人にはなれんぞ」
「それはオーリスにそのまま返そう。私は彼より長く生きてる」
「それは失礼」
そう言ってダラフィンは部下を連れて手配に向かう。話がついたところでクライセンはティシラに声をかける。
「君はどうする?」
「えっ!」
ティシラは面食らう。クライセンと目があった途端、それに縛られたかのように目を離せなくなる。焦る。と言うか、突然過ぎて照れを隠せない。
「君もついてくる? 退屈だと思うけど」
「えっ、あの……」ティシラは口籠るが、大きく何度も頭を縦に振る。「行くわ、行きます。当然、うん、もちろんです」
マルシオはそんな彼女を見て、あからさまに不愉快な顔になる。クライセンはにこりと笑って、どすどすと歩き去るダラフィンに背後から追加注文する。
「全部で三人だ」
ダラフィンは足を止め、肩越しに振り向いてため息をつく。オーリスの慌てる姿が目に浮かんでいるのだろう。そして返事はせずに、すぐに外に出て行った。クライセンがゆっくりと腰を上げて、鍵を解かれた牢から出る。その後にマルシオ、ティシラと続く。出ながら、マルシオは彼女にぼやく。
「まったく、いつまで落ち込んでいるんだ。これで貸し借りなしだぞ」
ティシラは恥ずかしそうに口を尖らせる。
「分かってるわよ」
「大体、よくこんな時にいじけていられるもんだな。いつもは事あるごとにギャーギャー暴れまわるくせに。未だにお前中心に世界が回ってるなんて思っているんじゃないのか。少しは成長しろ」
ティシラはブツブツ続けるマルシオにむっとする。だが今は仕方ないと我慢する。そう努力した。
「かと思ったら」だがマルシオは構わずに。「あの何もしないくせに、やたら偉そうなクライセンと目があっただけでデレデレしてやる気だしてるし。まったく、どこの乙女様だ。見てるこっちが恥ずかしい」
ティシラの努力はあっさりと無駄になった。ぷちんと何かが切れる音が聞こえた、ような気がした。言いたい放題のマルシオは後ろから殴られる。
「いい加減にしなさいよ!」ティシラは顔を真っ赤にして目を吊り上げていた。「偉そうなのはあんたでしょ! たかが場を繋いだだけでどれだけ立派なのよ」
「出たな、この暴力女! 悪魔、魔女! 本気でどこかの嫁に行きたいと思うなら一生猫被って生きていく修業でもするんだな」
「大きなお世話よ。例え世界が滅亡しても、あんたのところにだけは絶対いかないからご心配なく!」
怒鳴りあう二人を置いて、クライセンは先に行ってしまった。そんな二人に格子の中からワイゾンが声をかける。
「ちょっと、あんたたち」怖いが、思い切って。「け、喧嘩は後にして、俺たちも助けてくれないかな」
「うるさい!」
二人は同時にワイゾンを睨む。ワイゾンは脅えるが、必死で縋りつく。
「俺たち、殺されてしまうよ。頼む。もう悪い事はしないから」
「知らないわよ」ティシラの怒りの矛先が変わる。「海賊が軍に捕まって当たり前じゃない。拷問でも絞首でも、正当な罰を受けるがいいわ!」
「そ、そんな……」ワイゾンは脱力して頭を垂れた。「ご主人様、俺を見捨てないでください……」
「ご、ご主人様?」キジが首を傾げる。「何言っているんですか、お頭」
ティシラが我に返る。額に汗が伝った。彼が魔族であり、その術を施したのが自分だったのを思い出す。
「ほら」マルシオがからかうように。「お前のしもべが泣いてるぞ」
「う、うるさいわね」
ティシラはイラつくが、ワイゾンとの間には間違いなく主従関係が成り立っていた。もう彼は魔族としてしか生きられない。確かに、ここで見捨てるのは主人として薄情かもしれない。だがこの状況でティシラには彼を助ける手段がなかった。
「とにかく」ティシラは声をくぐもらせる。「今は大人しくしててよ。後でなんとかするから……」
「あ、後でって、なんとかって何ですか」ワイゾンが顔を上げる。「適当過ぎます」
「いいから、軍帥に酷いことしないように頼んであげるから。でもあんたたちは元々海賊なんだから、無罪は主張できないでしょ。身の安全は保障できないわ」
「そんな……ご無体です」
「仕方ないでしょ」
ワイゾンは情けなく声を上げて泣き出した。ティシラはその姿を哀れに思ったが、どうしようもなかった。それに、だんだん腹が立ってくる。
「泣かないで」
「だって……」
「努力はするから、大人しくしてなさい」次第に苛立ちが込み上げ、噛み付くように怒鳴りつけた。「命令よ!」
そう言ってティシラは早足で立ち去る。泣きっ面で呆然とするワイゾンに、マルシオが一言送った。
「とんでもないご主人様を持ったな。ご愁傷様」
それから二時間は時間を費やしていた。砦の外の平野では十人ほどの魔法使いが難しい顔をしている。地面に大きな魔法陣を必死で描いていたのだ。
黙々と呪文を唱えている者、ああだこうだと口論している者、尖った魔法石で地面に文字を刻んでいる者。大掛かりな依送の法は急遽追加を言いつけられ、そこにいた魔法使いが総動員で準備をしていた。
もちろん最初は「無理だ」と反発したが「王の命令だ」と言われてしまったらやるしかなかった。
その様子を監督していたダラフィンは、状況的にここに魔法王がいる事は、重労働させられている魔法使いたちには伏せておくことが賢明だろうと判断していた。時々クライセンはダラフィンの隣にやってきて、冷やかすようにその光景を眺めていた。
「時間がかかりすぎているよ」クライセンが呟く。「雑だし」
「文句いうな」ダラフィンにはその仕事の善し悪しは分からない。「無茶と分かって注文したのは君だろう」
「失敗したりして」
「メイの魔法兵はある程度のレベルに達した者で揃えられているとは言え、今回はあくまで即席だからな。まあでも、到着の基点にはもっと出来のいい魔法使いが用意されてるだろうし、何よりあのオーリスがいるんだ。大丈夫だろう」
「それは楽しみだ」
「しかし」ダラフィンは笑いながら。「いくら魔法王でも、さずがにこれを一人でこなすのは無理だろう?」
「できるよ」
「見栄を張るな」
「確かに」クライセンは肩を竦める。「もっと簡単な方法があるしね」
ティシラとマルシオも違うところからそれを眺めていた。大変そうなのは見て取れたが手伝おうとはしなかった。クライセンに「君たちも一応、王の客だ。騒いだりしないで大人しくしていてくれ」と念を押されていたのだ。マルシオはまた彼に聞きたい事が増えたのだが、その質問も拒否された。
「縁があれば出会えるように、必要があれば知る時がくる。そして役目があれば自ずと導かれる」
彼の謎めいた言葉に二人は黙らざるを得なかった。
「何なんだよ、あいつ」
マルシオがぼやく。隣でティシラはボーッとしている。それに気づいてマルシオは肘で小突いた。
「お前もだよ。何考えてんだ」
「えっ」
「ああ、そうか。憧れのクライセンがあんなんで、ショックを受けてるんだろ」
「そ、そんなんじゃないわよ」
「すっかり冷めて、魔界へ帰りたくなったか?」
「バカ言わないでよ。まだ何も分からないじゃない。だから考えてるのよ」
「あ、そう。でもお前はあんまりものを考えない方がいいぞ。どうせ見当違いの勘しか働かないんだから」
「あんたに言われたくないわよ」
ティシラはそう言ってマルシオから離れる。これ以上一緒にいたらまた喧嘩になる。なぜならティシラは「考えてる」と言っても、結局クライセンの事しか考えてなかったからだ。確かに、出会い頭に見られたくない姿を晒してしまった。それにマルシオの言う通り、彼の言動は不可解だった。だがこれだけは確実に言える。十分過ぎるほど、見た目だけは好みだったのだ。
とりあえず、と思う。まずはやる事がある。ダラフィンに近づいた。クライセンは既にその場から姿を消していた。背後に小さな気配を感じて、ダラフィンは振り向く。ティシラが困った顔をして自分を見上げていた。
「あの、軍帥様」
「なんだい、魔法使いのお譲さん」
「まだ牢にいる三人の事なんですが……」
「彼らは君たちの仲間か?」
「いえ、親しくはないんですが……」
ティシラにはどう説明すればいいのか分からなかった。下手に嘘をつくわけにはいかない。少なくとも今は、自分の立場はクライセンの手中にあり、彼の弟子だと勝手に主張していい加減な事をするのはよくないと思った。
「彼らは」仕方なさそうに。「海賊です。でも、私の知る限りでは悪いことはしてません。訳あって私に従ってます。私に軍の規律をどうこう言える資格がないのは分かっています。だけど、お願いする事くらいは許されると思います。どうか、私の知らないところで彼らに酷い事はしないでやってくれませんか?」
ダラフィンは黙った。ティシラは大きな男の迫力に押されていた。しかし、ふっと俯いて「駄目なら駄目で仕方ない。今はこれが私にできる精一杯だし。まあ、あいつらが殺されたとしてもそこで縁が切れるまでよ」と、結局は薄情な事を考えていた。しばらくして、ダラフィンは意外にも優しく微笑んだ。
「女性のお願いを無碍にはできないな。本来なら海賊を名乗るだけで重罪だが、いいだろう。刑が軽くなる保障はできないが、奴らの処分は君たちの謁見が終わるまで待っててやる。それに今、国は少々騒がしい。武器もろくに持たない少人数の海賊の取り締まりも、そう急ぐ必要はないだろうしな」
「はあ……」
ティシラはそれほど喜ばなかった。ダラフィンの外見からして想像外の取り計らいだったが、正直、また改めてあの海賊の面倒をみなくちゃいけないかもしれないと思うと嫌気が差したのだ。しかしワイゾンとは血の契約を交わしてしまった。これも因縁と思うしかなかった。ティシラは苦い笑顔を浮かべて、礼の一つも言わずに立ち去る。ダラフィンはそれを不思議そうな顔で見送った。
さらに一時間が経ち、ようやく準備が整った。クライセン一行は術師たちに呼ばれて魔法陣の真ん中に集まった。
大きく複雑なその輪の中には、疲れきった魔法使いたちが決められた位置に配置し、印を結んでいる。三人は落ちついて、魔法使いたちの集中力を乱させないように呼吸を顰める。
「では」ダラフィンが軽く頭を下げながら。「よい旅を」
それを合図に魔法使いたちは呪文を唱え始める。
最初は八方からいろんな言葉が聞こえていたが、次第にそれは合唱となり、いつの間にか一つになっていた。
火・土・水・風の魔力が外側、太陽・月・宵の明星・明けの明星の力がその内側、さらに三人を囲む一番近いところでは光と闇の魔力が司られていた。その点は線で繋がれ、いくつもの星を象る。
呪文がまるで目に見えるかのように辺りに響き渡る。そこには特別な自然の法則が生まれていた。三人の人間が一瞬にして、遠く離れた場所に移動できるように。決してそれを悪戯に行ってはいけなかった。
この世を守り、支えているそれぞれの象徴の許可を貰い、その力を借りるためにはここまでの労力と手間をかける必要があったのだ。
それが「魔法」だった。
三人は朧げに光に包まれる。その透明な色は濃さを増し、三人の姿を完全に隠していく。すると光は粒子に変わっていった。粒子は星屑のように一つ一つ光りながら宙に溶けていく。
ダラフィンや衛兵たちがその「奇跡」を惜しむように見つめていた。そのうちに光は、空高く舞い上がっていき、完全に姿を消した。
目線を地上に戻すと、そこに三人の姿はなかった。それを確認したあと、魔法使いたちは黙ったまま順に顔を見合わせていく。沈黙が流れる中、一人ずつ印を解き、ばたばたと倒れていった。
ダラフィンも一安心と言ったように、その場に腰を下ろした。
「お疲れさん」
3
ティオ・メイの城は慌ただしかった。城の一番高く、その中心にある王室の前は大きな広場になっていた。
こは王の許可のある者しか近寄れない場所のひとつだった。入り口には一つの区切りとして門が構えている。その外には数人の警備兵が立っていた。
中では石畳の上に所狭しと魔法陣が描かれている。その上に厳選された魔法兵が決められた場所に立ち、印を結んで目を閉じている。その中の一人にオーリスがいる。
「来たぞ」
オーリスが大きな声を上げる。印を結んでいた魔法使いたちに緊張が走る。
自然の理に従って送られてくるものを正確に受け取らなければいけない。ミスをすればそれらは元の形を失い、空間の狭間で彷徨うことになる。自然の法則に歪みが生じ、術師たちも力を失い、起こる災害は予測できない。集中する。
魔法陣の中心に光の粒子が集まる。それは螺旋を描きながら人の形を象っていった。そして閃光を放ったかと思うと弾け、消える。
術師たちが目を開けると、そこには三つの人の姿があった。異常はない。確認して、ほっと息をつく。
ティシラとマルシオがきょろきょろと辺りを見回していた。その横で突っ立っているクライセンにオーリスが早足で駆け寄ってくる。
「クライセン殿」魔力を消耗し、少々疲れた様子で。「ご無事で何より」
「久しぶり、オーリス」
懐かしい二人の再会は、それほど感動的なものにはならなかった。
「しかしあなたはどこまで底意地が悪い!」オーリスはいきなりクライセンに捲くし立て出した。「おとなしく言うことを聞くとは思ってはいませんでしたが……弟子ですと? あなたが弟子など取られるはずがない。どうせいい加減なことを言って私を困らせたかったんでしょう。そんな悪ふざけをしている場合じゃないと分かっておきながら。しかし条件を飲まなければ来るつもりがないと私には聞こえましたよ。サンディル殿に警告はされましたが、まさか、こんな……」
クライセンは何も答えず、ただ笑顔でオーリスを眺めている。そして、一言。
「元気そうでよかった」
オーリスは急に言葉を失う。その体が微かに震えだした。そして頭を垂れる。
「……お会いしとうございました」
ティシラとマルシオはその奇妙なやりとりを黙ってみていた。魔法王と魔道総監が対話しているその光景は、二人にとって本の中の出来事のように遠く感じられた。
その中でクライセンは軽く頷くと、オーリスの肩を叩いて勝手に王室に歩き出した。
「王様は?」
オーリスは急いで後に続きながら答えた。ティシラとマルシオも慌てて、取り敢えず着いていく。
「王室でお待ちです」
「余計な時間を費やしてしまった」
「あなたのせいでしょう」
「一時間。それ以上は遠慮したい」
「約束はできません」
「だったら私の気分を損ねないように」
「それより、陛下に無礼のないようにお願いします」
「王様の態度次第だ」
「陛下はあなたを、希望を必要としています。どうか……」
「オーリス」クライセンはその続きを遮った。「王様の心の支えはあんたの役目だ。それを辞退して私に押し付けたくてここに呼んだのか」
オーリスは歩きながら、再び黙った。心の中で否、違うと言い聞かせた。クライセンは「頼りの綱」ではあったが、決して彼だけがすべてではない。自分を見失ってはいけない。オーリスは彼に諌められたことを素早く悟り、心を引き締めた。
クライセンがやっとここに来てくれた。そして国王と合間見えることで、そこから扉が開く。新しい道が開けるのだ。その中に自分の役目がある。それを見据えなければいけない。今から、始まる。その言葉が胸を貫いた。オーリスの目に厳しさが灯る。
オーリスは改めて思った。クライセンは礼儀しらずの無頼者ではない。自分が絶対無二の存在であること、そしてこの世のすべてがそうであることを知っているのだ。まるで見てきたかのように。
この隙のない男が仲間と戯れず、どこにも属さない理由が、なんとなく理解できる。
オーリスはふっと、自分の背後でちょろちょろしている二人に気を向ける。振り向いて目が合うと、二人は固まるように止まる。
「君たちが」オーリスは向き合い。「クライセン殿の弟子とやらか。これ以上は無用だ。どのような者たちかは知らぬが、これでお引取り願おう」
ティシラとマルシオは何も言えなかった。ここで大人しく帰る気にはなれなかったが、一国の王がすぐそこにいる。いつもの調子で無理を通す勇気はでなかった。二人が困っていると、クライセンが振り返って口を挟んだ。
「それは私の弟子だと言っただろう」
「まだそんなことを……」オーリスがクライセンに向かって。「あなたはここをどこだと思っていらっしゃる」
「どこだろうと私は招かれてここに来たんだ。それが客に対する態度か。そいつらをどうするかは私が決める。勝手なことをしないでくれ」
クライセンは再び背を向けて歩き出した。オーリスは、勝手なことをしているのは自分だろうと思いながら苦い顔をする。しかし揉めている時間はない。仕方なくオーリスもその場を後にした。
ティシラとマルシオはお互いに顔を見合わせる。相変わらずクライセンが何を考えているのか分からない。どうするかは自分が決めると言いながら、何も指示しない。
どうしろと言うのだ。つまり、好きにしろと言うことなんだろうと勝手に解釈するしかない。無理しても王に会いたいわけじゃない。だがそれ以上に、帰りたくないと思う。と、なると答えは一つだった。お互いに一言も発さないまま、歩き出す。
クライセンの言動の裏には、実は何も、意味も理由もなかった。何も考えていなかったのだ。今は誰もそれを知らない。
クライセンは力強く王室の扉を開けた。広く、静寂に包まれている。
灰色の壁には赤や白の模様が刻まれていた。左右にくすんだ金と銀の柱が交互に立ち並んでいる。
その先には王座があり、そこに王冠を被った男が座っていた。彼はゆっくり立ち上がった。グレンデルは「希望」を迎え入れた。
グレンデル以外には他に誰も居なかった。王座の前にいくつかの椅子が並べられている。グレンデルは彼らをそこに促し、自分もその向かいに座る。
扉を潜ったところでオーリスが立ち止まって国王に一礼するが、クライセンは全く構わずに歩みを止めない。オーリスはそんな彼の態度に眉を寄せるが、すぐに後に続く。
ティシラとマルシオも少し離れながら、恐る恐るついていく。クライセンはグレンデルの前にある椅子に遠慮なく腰掛けて、グレンデルに微笑む。
「王様には」首を傾げながら。「専用の椅子がおありでしょう?」
オーリスは座らずにグレンデルの右隣に静かに立ちながら、クライセンの失礼な第一声に目を伏せる。ティシラとマルシオはなんで自分たちがここにいるのか理解できないまま、緊張して音を立てないようにクライセンの隣に並んで座る。自分たちには何も触れないでくれと心で呟きながら。
「クライセン殿」グレンデルの目は真剣だった。「今、この一時は何も包み隠さず、すべてを私に打ち明けてもらえるよう──お願いする」
そして重い手を王冠にかけようとする。すると、オーリスが咄嗟に声を上げる。
「王よ、それはなりませぬ」
ぴくっとグレンデルの手が止まる。ティシラとマルシオは体を縮める。グレンデルは手を引き、しばらく思案した。その手が震えている。
「なぜ王冠を脱ぎます?」クライセンは一人で落ち着いている。「お似合いですよ」
皮肉だとしか受け取れない。言葉を失う一同にクライセンは構わない。
「それに私はティオ・メイの国王陛下と話をしにきたのです」そういいながら、足を組む。「その目印がないと、私には王がどこにおられるか見当がつかない。まさか、ただのそこら辺の一般人と世間話をさせるためにここに呼んだわけではありますまい」
ティシラとマルシオは気が気ではない。何を言っているんだ、この男は、と隣で冷や汗を流す。
「今ここにいる私は『魔法王』と呼ばれる者。そしてあなたはこの世界の頂点に君臨される偉大な王だ」クライセンは物怖じせずに続ける。「この世の誰より高い位置におられる。そうあるべきです。時が来るまで何者にも屈してはなりません。そうでなければ、私は何も話はしません」
グレンデルが拳を握った。王であることを放棄してはならない。クライセンはそう言っているのだ。今自分が必要なのは力だった。その為に魔法王を呼んだのだ。この男と対話するのは王でなくてはならない。この頭を下げて力を請おうとした自分を愚かだったと思い知る。
「……その来る時とは」グレンデルはクライセンの目を見た。「すぐそこにあるのかもしれぬな。いや、今なのかもしれない」
挨拶も敬意も無用だった。グレンデルが本題の扉をこじ開けた。オーリスも気を引き締める。この時間が国の未来を決める、そう思った。
「ここのどこに」クライセンは微笑んでいる。「あなたより力在る者がいるでしょう」
「私はそなたの力を必要としている。それが今の私にできることなのだ。そのためには何も惜しむつもりはない」
「私はあなたに何も助力などできないし、するつもりもない」
「なんと……」
「私がここへ参りましたのはそれを伝えるためです。この国にはすべてが揃っています。私が代われることなど何もありません」
「確かにこの国には足らぬものなどないのかもしれない。だが今、滅亡の危機に迫られているのだ」
「何を根拠に滅亡の危機と? あなたが何をご存知か」
「何も分からぬ。しかしそなたは知っているのだろう? すべてを明かしてもらえないだろうか」
「一体何を知りたいのでしょうか」
「ノーラのことだ。そしてそなたのこと。私の知らぬところで一体何が起ころうとしているのだ」
「起ころうとしているのではありません。もう始まっています。私は私にしか出来ないことを為すまで」
「そなたにしか出来ぬこととは?」
「ノーラ討伐です。ただし、彼を悪として裁くのではありません。それは法律と道徳にお任せします。私は彼を唯一の宿敵として認め、私の生きる目的としてプライドを守るためにのみ戦うのです」
「……何を言っている」
「逆も然り。彼もまた私を倒すために命を懸けてくるでしょう。彼のただ一つの障害は、他ならぬ私という存在なのですから」
「魔法王と魔薬王は我らを、国を無視するのか」
「魔法王とは他人がつけた名前です。私は興味もないし、自ら名乗った覚えもありません。確かに私は世界を滅ぼす力も、そして救うそれも持っているのでしょう。命あるものすべての願いを叶えることも可能かもしれません。ですがそれは私が望んで手に入れた力ではありません。人々は私を好きなように呼んでいます。世界一の魔法使い、神に最も近い男、生きる伝説、世界の希望の光……なんとでもおっしゃって結構。だが押し付けられたときは拒絶するしかないでしょう。なぜか、簡単です。嫌だからです。特別な理由はありません。私は誰にも何の約束もしていないし、しません。私を拘束する権利など誰にもありません。残念ながら、王ならお解りのはず──」
クライセンは力強く、断言する。
「『神』は、いません」
4
「奇跡とは起こり得ない現実のこと。いくら欲しいと請うても手に入るものではありません」
「……我々はどうすればいい」
「戦うのです」
「何と?」
「時代と文明です。戦争が繰り返されます。人が何かを求める限りそれはなくりません。だが、同じではありません。これを──」クライセンは懐から小瓶を取り出してグレンデルに差し出した。「邪悪な呪いを滅ぼす必殺の魔薬です。私が調合しました。まだ実験をしていないのですが、生憎とその材料と時間が足りませんでした。しかし魔法や剣よりは即効性があります」
グレンデルはその虹色の液体の入った小瓶を受け取った。そして目を強く閉じる。
「アムジーは犠牲になった。これがあれば救えたか?」
「アムジーの毒は、間抜けな海賊が何も知らずにノーラの洞窟に火を放ち、そのとき燃えた薬草から発生して村に流れ込んだものです。その場の毒は私が抑えましたが、漏れた分は手に負えませんでした」
「見殺しにしたというのか」
「では、あなたならアムジーを救えましたか? 私が村を救わなかったことを罪だと罰しますか? 私はたまたまそこにいただけです。通りすがりが罪なら、私はこの地のどこも歩くことはできませんね」
「それは……」
「村の一つを救ったところでノーラは倒せません。アムジーは事故に遭ったのだとお考えください。戦争に犠牲は必ず伴います。何も失わずに戦うことは出来ません。妙な理想は捨ててください。盲目になっていては足を踏み外しますよ」
グレンデルはしばらく頭を抱えた。言いたい放題の彼の言葉は、間違っていない。なのに納得できない。やり切れない気持ちが渦巻いていた。そして、辛そうに口を開く。
「なぜこれを」渡された小瓶を握り締め。「私に?」
「殺すため、奪うための争いからは何も生まれません。国を守るのがあなたの役目。それは昔から変わらぬはずです。あなたは道標です。あなたが迷ったら誰が民を守るのです」
「…………」
「これは忠告、とでもお受け取りください。私たちは最終的にはお互い同じ目的を持つ者。敵ではないと──私は思っています」
「敵は」グレンデルは何かに気づく。「ノーラだけではないと言うのか」
「ご存知の通り、敵は未知の力を持っています。今ある力では足りないかもしれません。だが通用せぬとも言いません」
「……役に立てと、そう言っているのか」
「王様、あなたは一体何を恐れていらっしゃる。その冠と矜持を打ち砕かれることか。それとも剣と砦を奪われ居場所を失うことか。私にはその誇示されるもののどれも大した価値は感じられません」
「では、そなたにとって『王』とは何だと思う」
「『名前』ですよ。そのものを表す言葉に過ぎません。私が何者か問われたときに、それを表現する言葉がなければ説明するのに時間がかかってしまいます。私が『魔法使いだ』と答えればすべての人が理解する。分かりますか? 名前とは魂なのです。人が私を『クライセン』だと呼べばそうであるし、『魔法王』と呼べば誰もが認めます。しかしそのとき私が魔法王に値する行いを為さなければ人は私を批判します。では『魔法王』とは一体何なのでしょう。そして『王』とは? 人々は『王』という言葉に何を求めていると思いますか? あなたが王と自ら名乗り、受け入れ、守ろうとおっしゃるのなら『王』という名前に固着してはなりません。『王』そのものになるべきです」
「『王』そのもの……」
「今あなたに必要なのは整理することです。歴史を守ることと過去に執着することとは違います。あなたを王として非難する民がいますか? 否ならばあなたは間違ってはいないのです。今こうして、私のような者が『魔法王』と呼ばれ、王に無礼を働くのも、時代なのです。世は常に進化しています。それを受け入れられない者が淘汰されるのです」
グレンデルは彼の言葉のひとつひとつを重く受け取っていた。分かっている、と心の中で何度も繰り返していた。王の力を持ってしてもクライセンを支配することができないことを感じ取っていた。
彼が『魔法王』だからではない。彼の言う通り、それは名前に過ぎなかった。見た目はただの若い青年で、その身なりも質素で目立つものは何も身につけていない。
クライセンの声、言葉、目の光、その存在そのものに力があった。彼が何をしたというわけではない。成り行きも伝えられないままにリヴィオラを受け継ぎ、ただそれだけで伝説だ神だと噂された。きっと望んでそうなったわけではないのだと思う。しかし彼は為るべくしてそうなったのだと、グレンデルは確信していた。
クライセンは誰の敵でもなく、そして味方でもない。その常人離れした存在は決して神々しいものではない。『孤独』という言葉がグレンデルの頭を掠めた。
「君は……リヴィオラを受け継いだ四代目魔法王とは一体、何者だ」
グレンデルの唐突な質問に、クライセンは少し間を開けた。
「私は、リヴィオラを受け継いだつもりはありません。リヴィオラが私を選んだのです。私にとってあの石は魔力を宿したただの付属品に過ぎません」
「リヴィオラが君を選んだ?」
「私は純血のランドールの生き残りなのです」
一同が息を飲む。オーリスだけがその言葉を聞いてふっと目を伏せた。
「父、サンディルはランドール人で、戦争で死にましたが、母もそうです。父はノートンディルでも名のある賢者でした。彼は未来を、その戦争の結末を予見したのです。戦争のどさくさに、まだ幼かった私を連れてパライアスに身を潜め、その命を永らえました。そして世は彼の見たとおりに進化を遂げました。その内に私は成長し、なるべくして魔法使いになりました。そうなるまでに何の苦労もありませんでした。だが私は優れているのでありません。パライアスにとって『異種』であり『特別』なだけです。リヴィオラは元々ノートンディルの産物です。リヴィオラにとって故郷と同じ魔力の宿る私を受け入れるのは自然の成り行きなのです。あれは何かの称号などではありません。人の思念や魂の宿ったただの石。それだけです」
「イラバロスと会ったのか。彼と何を交わしたのか聞かせてくれ」
彼と対峙したのはもう遠い昔のことである。クライセンは忘れたことはなかった。しかし、できることなら忘れたいことだった。話せと言われれば話せないことはないが、誰も傷つかないでいられるわけではない。少し言葉を選んでから、語った。
「偶然に、旅に出たイラバロスと出会いました。イラバロスは父と私がパライアスにいることを知りませんでした。しかし予感があったらしく、本当にランドールの純血が生き残っていた事実を目にし、涙して喜んでいました。そして私にリヴィオラを渡そうとしました。しかし私は拒絶し、彼に勝負を挑みました。私はこの世界にある価値には興味はなく、ただ自分の力がどれほどのものなのかを知りたかったのです。私の魔力が、パライアスの造った『魔法王』に通じるものなのか、若しくは勝るものなのか。答えは簡単に出ました。あまりにも迅速でした。彼は私よりずっと年上で、経験も知識も豊富な偉大なオセラ(郷)の魔法使いでした。しかし、イラバロスは長い間、このパライアスの地で心を苛まれて傷ついていたのです。本心では休息を、眠りを求めていました。誰かにその重い石を譲りたいと切望していたのです。哀れでした。彼は荷を背負い過ぎていたのです。それが三代目魔法王の実態であり、魔法戦争の残した深い傷跡だったのです」
グレンデルはその事実に苦悩した。額に汗が伝う。いっそここで涙を流し、先代が犯していた過ちを責め立てられたらと思うほど、心に重くのしかかっていた。だがそうはいかなかった。今一度踏みとどまる。
クライセンはさらに続ける。
「イラバロスは心の弱い男でした。人々はそれを『優しい』などと言いますが、いずれにしても彼は人の上に立てるような器ではなかったのです。だからこそザインの影に身を潜める生き方を選んでいました。だが、戦争がイラバロスを追い詰めた。イラバロスの決断は間違ってはいなかったかもしれない。間違いがあったとすれば、裏切り者の彼を受け入れたアンミールにあるのではないでしょうか。これは私の個人的な意見ですが、アンミールはイラバロスに罪を被せ、それに相応しい罰を与えるべきでした。彼の功績を称えたいのなら──殺してやることが最善だったと、私は思います」
そこにいたすべての者が、クライセンの言葉を冷酷だと感じた。同じ血を持つ者、稀少な生き残り同士で「殺すべきだった」と断言する彼が理解できなかった。
「君なら、そうしたか?」
「はい。イラバロスをザインから引き離すべきではなかったのです」
「君が、イラバロスを……殺したのか」
「彼が望みました。彼を許し、休ませることができるのは私だけでした」
「許す……」
その言葉で、少しだけクライセンの情が垣間見えたような気がした。殺すといえば聞こえは悪いが、大事な人を裏切ってまで生き延びてきたイラバロスが間違っていたのだと言える資格は、彼によって故郷を滅ぼされた同胞だけにあるのかもしれない。
「君はそこで何を為し、何を手に入れた?」
「私は彼の残した宝石を一つ譲り受けただけです。同じランドール人として。そして心に誓いました。私は……イラバロスのようにはならないと」
「では、イラバロスの子孫が未だに続けている事、アカデミーの存在はどう思う?」
「それは私が決めることではありません。あなた方が、世の人々が知っているでしょう」
「……だが、君はアカデミーを通らずして魔法王の地位についた。世の若者たちはカラエル、ザイン、イラバロスを英雄と称え信じ、五千年経った今でも彼らの意思を受け継ぐために鍛錬しているのだ。世界一の称号を、君の後に続きたいと切望する者も少なくない。だが、事実は人々が思っているような美しいものではないではないか」
「違った事実とは、私がアカデミーを通らなかった魔法使いだということですか」
「そうだ」
5
「だけど」ふっと笑う。首を傾げて。「誰が四代目がアンミールだとか、アカデミーの卒業者だとか言ったのでしょうか。ラムウェンドはそんなことは言わないでしょうね。そうでないとも言わなかったでしょうが。四代目が型通りの人物だなんて、無知なる者の勝手な想像ではないですか。事実を知りたければ突き止めればよかっただけの事。それとも、私が世界中に『伝説に相違あり』と告知する義務でもありましたか」
クライセンは真面目に話していたかと思うと、所々に皮肉を挟んでくる。ペースを乱され、巻き込まれる。だがグレンデルも馬鹿ではない。いちいちこんなことで腹を立てるほど軽薄ではなかった。
「いや、そんなことを聞いているのではない、話をはぐらかさないでもらおう。君にとって、アカデミーとは何なのだ」
ティシラとマルシオも微かに頭を上げた。その答えによっては、自分たちのしてきた事が愚行だったと罵られてしまうかもしれない。アカデミーでも象徴される魔法王の言葉は無視できない。怖い、と思いながら彼の答えを待つ。クライセンはそんな緊張を放つ二人を見もしない。そして口を開いた。
「そのままでいいと思いますよ。ラムウェンドはすべてを知っています。それでも尚、変わらずアカデミーを守っています。彼の意志を否定するつもりはありません。アカデミーはアンミールが造ったものです。私には関係のないことです」
ティシラとマルシオは複雑な気持ちになった。
アカデミーを通り、ラムウェンドから魔法戦争にまつわる真実を聞いた。それでよかった。そのときから今このときまで、二人は魔法使いになれたことを心から誇りに思っていた。なのに、ここでもう一つの悲しく、残酷なイラバロスの末路を知ってしまった。
知るべきだったのか、知らないままの方がよかったのか、二人には判断できなかった。それでも自分たちが魔法使いであることには変わりは無い。それを恥だとも思わない。しかし自分たちが魔法使いとして、この時代に一体何をすべきなのか分からなくなってしまった。
二人がそんな事を考えながら俯いている間に、クライセンは初めてそこにちらりと目を移す。誰もそれに気づかない内に、すぐグレンデルに向き直る。
「さて」クライセンは足を組み替えながら。「これからどうなさいます?」
グレンデルはぴくりと反応するが、すぐには答えなかった。代わりにオーリスが発言した。
「それはこちらの質問ですぞ」
「私ですか。私はこれからパラ・オールに向かいます」
「パラ・オール!」オーリス始め、一同が驚く。「あそこは猛毒で包まれています。いかにあなたでもその肉体は人間と同じ。それとも毒を退ける技をお持ちですか」
「彼が歓迎してくれる」
「彼……」オーリスは眉間に皺を寄せる。「ノーラか」
しばらく沈黙になった。結局クライセンはこれから起こること、そしてそれにどう対応するのが最善なのかを具体的に説明してはくれなかった。
しかしグレンデルはこれ以上野暮な質問をする気になれなかった。彼は何も答えないだろう。そう思いながら、受け取った小瓶を手の中で転がした。
ティシラとマルシオもただ黙っている。未だになぜ自分がここにいるのかよく分からないし、目の前で交わされる会話の内容に一体自分がどれだけ関わっており、そして関わっていくのか、今はいくら考えても無駄だったからだ。
答えは出ない。いや、まだ無いのだ。これから起こることは誰も予想できない、未知の領域なのだ。ノーラというたった一人の人間を倒すと言う単純な目的を達するまでの道のりはこれから造られるのだろう。
だが他人事ではなかった。できる限り何かしらの形で貢献したいという気持ちはあったが、それは漠然として形になりそうにない。
その時、ティシラが呟いた。
「あの」肩を竦めながら。「もし、クライセン様がノーラに負けてしまったら……」
それ以上は言葉を濁す。ティシラは失礼な質問だとは分かっていた。だがその問いかけは一同を注目させ、そこに暗い影を落とした。ティシラの次にクライセンに視線が集まる。彼は顔色一つ変えずに、グレンデルにその答えを告げる。
「パライアスに心はなくなるでしょう。ノーラにとって唯一の脅威である私という存在がなくなれば彼の天下が始まります。裏が表になり、悪が王となる。魔薬によって人々はその心と形を奪われ、ただノーラの奴隷となり永遠の苦痛を強いられるのでしょう」
グレンデルの顔がゆっくりと青くなる。この世にある地面も人間も、空も緑も今まで築いてきたそのすべてが失われる。きっとその支配からは、逃げ道も隙もないのだろう。それは想像を絶するものなのだろうが、考えるだけでぞっとする。だがクライセンはそんな空気を無視して、勝手に席を立つ。
「つまり」その瞳に冷たい光を灯して。「これ以上私の邪魔をしないでください。それが王様の最善策です」
クライセンはそう断言して、マントを翻しながらその場を後にした。
呆然とする一同を背にして、静かに室を出て行く。オーリスが一歩前に出て呼び止めるが、クライセンは返事もしなかった。
ティシラとマルシオは、グレンデルとオーリスの気が自分たちに向いていないことを確認しながら、急いでクライセンの後を追っていった。