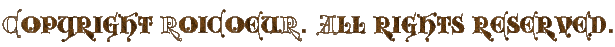第1章 伝説





1
「それは約五千年も前の話──」
ラムウェンドはゆっくり、そして思いを馳せて語った。
ここはマジックアカデミーの講堂。天井は高いが室内はそう広くない。教壇の背後には羽の生えた天使像が両手を広げ、天を仰いでいる。
その足元で、ありがたい話を説かれている生徒たちのための大きな机は半月の形をしている。それを囲むように二十名ほど座れる程度の椅子が設置してあるが、今日そこに座しているのは僅か七名だった。机の上には本もペンも置いてない。生徒たちの見た目は様々だが、一同は静かに姿勢を正しているだけだった。
アカデミーの総監督を務めるラムウェンドの短い茶色がかった黒髪は少し薄くなっている。だが肌の色は明るさを残しており、彼はいつも穏やかだった。すっきりした丸い顔立ちにはいくつかの皺があり、なで肩の体は赤いローブに包まれている。アカデミーを統べる証しのそれには、節々に複雑で繊細な刺繍が施されている。
近しい者は彼を「太陽の日差しのような人だ」とまで言う。本人はとんでもないと謙遜するが、その顔を逸らす姿にも暖かさを感じられる。ラムウェンドは心地よく響くその声で話を続けた。
「二つの大陸がぶつかり合い、大きな戦争が起きた」そう語るラムウェンドの表情は厳かだった。「一つはアンミール人の統治するパライアス大陸。もう一つは、今は海の底に沈んで消えてしまったランドール人の支配するノートンディル大陸。二つの大陸にはそれぞれ王がいた」
ここでラムウェンドは薄目をぱっと開き、静かに耳を傾けていた七人の若い生徒たちの一人を指差した。
「王の名前はもちろん知っているね、マルシオ」
マルシオと呼ばれた少年は頷いて、迷わずに答える。
「アンミールの王はガラエル、ランドールの王はザインです」
「よろしい」ラムウェンドは再び遠くを見つめた。「何度も聞いた話で退屈かもしれないが、もう一度順を追って話すよ」
ラムウェンドの口調から、これから語られる事は大切な話だと感じられる。ここで不謹慎に気を散らせたり、欠伸などをする者は一人もいなかった。
「そう、五千年前、この世界には二つの力があった。今は無きノートンディルは大地そのものに魔力を持ち、そこに生まれた生物はパライアスとは違う生態をもっていた」
人間の姿をする者のほとんどは、生まれついて優れた魔法使いだった。水や木々も魔力を帯びて不思議な力を宿しており、その頃はランドール人と共に、天上界の住民である聖なる天使もそこに住んでいた。
一方、パライアスも決してノートンディルに劣っていたわけではない。その大地は強く、気候もよく、たくさんの産物に恵まれていた。魔力もノートンディルほどではないが、確かにあり、努力をすればランドールに匹敵する魔法使いも育てられた。
時を経るにつれ、二つの人種はお互いの共存のために試行錯誤し、話し合いを続けた。時には意見がぶつかることもありながら、次第にそれぞれは進化し始め、ランドールは優れた魔法を、アンミールは強い軍事力を求めるようになっていった。その内に、いつの日か国を仕切る王が誕生した。それがガラエルとザインだ。二人はお互いの力を求めた。与え合っている内はそれは平和な世界だった。
しかし人間の欲とはことに恐ろしく、いつしか奪い合うようになってきた。最初は小さな争いだった。そこから暴力が生まれ、とうとう戦争が起きてしまったのだ。ガラエルとザインはどちらが優れた人種なのかを競い合った。忌まわしい戦いは長い時間をかけてお互いを傷付け合った。
その悲しい戦はザインの死で終わりを迎えた。ノートンディルにいた天使たちは人間の強欲さを哀れみ、嘆き、その地を去っていってしまった。ランドールは滅び、天使も地上から姿を消し、支えるものを失ったノートンディルの大陸は泣き崩れるように海底に沈んでいってしまった。勝利を手にしたガラエルはアンミールの頂点に立ち、パライアスを再建していった。その後、限りある魔力を扱う者として、魔法使いが重宝される時代が始まった。
そして今現在、パライアスで最も有名なノートンディルの宝石がある。ザインの王冠に輝いていた「リヴィオラ」だ。それはノートンディルでしか採れない、リヴサイトと言う希少な石だった。その中でも、特に等級の高い高価なものがザインの頭上に、王冠の中央に掲げられていた。リヴィオラはもともと神秘的な光を放っていた上、長年ザインと共にあったため、この世の何よりも美しく光輝く宝石になっていった。その石はザインの死後、ガラエルの手に渡った。
「天使の言葉で『イオル』は太陽、『リヴ』は夜を意味する。夜の中の太陽、つまり『リヴィオラ』とは『夜明け』の色と言う意味だ。本来天上界には太陽も夜と言う時間もないと言われている。天使は人間界を称えてその名をつけたのだろう」
ガラエルはその青いオーロラのような光を放つリヴィオラに心を奪われた。大きさこそ手のひらに収まるとは言え、その深さは計り知れず、ノートンディルやザインの偉大さを凝縮して物語っていた。これはノートンディルの遺産であり、賢人が持つに相応しいとガラエルは思った。これを手にした者はリヴィオラに選ばれし神聖なる者、世界を代表する偉大な魔法使いなのだと大きな声をあげた。そしてガラエルが軍人としてだけでなく、魔法にも長けていた万能かつ最強の勇者である事は誰もが認めていた。「ガラエルこそがリヴィオラに選ばれし者である」と称賛され、ガラエル本人もそれを快く受け取った。
その時、世界一の魔法使い「魔法王」が誕生した。
2
それと共にガラエルは一つの訂正を行った。「リヴィオラが世界一の称号ならば、私より先にそれを持っていた者がいる。他ならぬザインだ。彼こそが初代魔法王だ。私は二代目を受け継ぐ者としてこの地に名を馳せよう」と、敵であったザインの死を弔った。
しかしリヴィオラの名が世界に知れ渡った頃、結局ガラエルは魔法が、魔力が欲しかったのだと人々は囁いた。なのに結局それに恵まれた大地はガラエルの手によって滅ぼされてしまった。皮肉なものだと語られた。彼が大きな犠牲を払って得たものは、たった一つの宝石と、戦争の虚しさだけだったのだ。
それは「魔法戦争」と呼ばれた、と付け加え、ラムウェンドはそこで話を区切った。黙って聞いていた七人の若者は続きを待った。息の根以外、流れた沈黙を邪魔するものはなかった。
「ここから先が君たちだけに与えられる」ラムウェンドは再び口を開いた。「歴史と、このアカデミーの真実だ」
ラムウェンドの優しい目に悲しみが灯った。
「なぜザインが負けたのか……ザインには心から信頼できる親友がいた。その男の話をしよう」
男はザインの幼なじみで、魔法使いとしても戦士としても優れていた。男はすべてを持っていた。何一つ不自由なく王であるザインの傍に仕えていた。それだけ立派な青年でありながら、ザインと王の座を争おうともせず、身の程を弁え、王を純粋に尊敬し力になれる事を誇れるような高潔な男だった。もちろんザインは戦争でも彼の助言を頼り、必要としていた。
ザインは元々、争い事は好きではなかった。しかし民を守るためにその戦力を引くわけにはいかなかったのだ。ザインは戦争の間、苦悩していた。この戦いに意味はあるのか、終わった時、何が残るのか……その答えを見出せないまま血は流され続けた。
ザインはとうとう親友に問うた。「どうすればこの戦争は終わるのだろう」と。男は答えた。
「二つの勢力は互角です。どちらかが、若しくは両方が滅ぶまで終わる事はないでしょう」
ザインはその残酷な答えに胸を痛めた。気づいてはいたのだ。だが、認めたくなかった。言葉を失ったザインに男は続けた。
「もう一つ方法はあります。どちらかが敵に屈することです」
それも分かっていた。が、ザインはそれだけはできないと思った。大地の与えた聖なる魔力が人の造った武器にひれ伏し、それを濫用される事は神々や天使への冒涜だと思い、それだけは許せなかったのだ。
それに、今ここで白旗を揚げてもランドールの民の名に傷がつき、アンミールの民に蔑まれ卑しい名で呼ばれる日々が始まる。そう歴史に刻まれる事を恐れたのだ。
戦は終わってもランドールに平和は訪れない。ザインは男にそう伝えた。すると男は「では、滅ぶしかないでしょう」と言った。
ラムウェンドはそこで、胸元から一冊の古い本を取り出した。その古さは計り知れないほど年季の入ったものだった。ラムウェンドは本を顔の横に掲げた後、破れないように注意しながらページをめくり、それに目を通した。
「これは彼の、ザインの親友だった男の日記だ。その一部を読んで聞かせよう」
『歴史とは、文明とはこうして造られるものなのかもしれない。そこには必ず争いがある。友であり王であるザインはこれを甘受しなければいけない。なのに、彼は打ち臥せってしまっている。
ガラエルは勇敢だ。欲しいもののためには迷いを打ち払う強さがある。残酷だったとしても前に進む事を止めない。決して諦めない。
ザインは優しい男だ。しかし、優しすぎる。私はそんな完璧ではない彼が好きだし、だからこそ救いたい。
だが、もう遅すぎる。
この戦いは止められない。
今の私に何ができるだろう。私は王の友人でしかない。この恐ろしい殺し合いの前に、どんな魔法も知識も剣も正義も、何も無意味なのだ。増えすぎた、育ちすぎた何かをここで清算しなければいけない。
だが、どうすればいい?
この戦を止めるには大いなる犠牲が必要だ。その犠牲とは一体何なのだろう。
果たしてこの世の誰がその審判を下す権利を持っていると言うのだろう』
ラムウェンドはそこで本を閉じた。
「男もザインと共に苦悩していた。そして日々減り続ける二つの人種の命を前に……男は涙を流した。親友とは別の所で三日三晩泣き続け、その末にとうとう答えを出したのだ」
ラムウェンドは間を置き、静かに続けた。
「男は親友を、ザインを裏切った」
一同は一瞬、息をすることを忘れた。
「涙を流しながらザインの首を獲った」ラムウェンドは本を持つ手に力を入れた。「そしてザインは親友の愛と裏切りを、抵抗せずに受け入れたのだ。ザインのその安らかな表情は男の悲しみを煽った。そう、王は独りにはなれなかった。男は改めてそんな彼が好きだと思った。弱さを持つ優しい彼を守ってやろうと誓ったのに、と男は自ら手に掛けた友の首を抱きしめて更に泣き続けた。やがて力を振り絞り、王の首をガラエルに差し出した。そこで戦争は終わりを告げ、この真実は隠された。男は偉大なる裏切り者としてガラエルに称賛された。戦争を終わらせたその男の名は……イラバロス」
室内にどよめきが起こった。堪らず、生徒の一人が大きな声を出した。
3
「イラバロス! 三代目の魔法王だ」
それはそこにいる皆が、世界中の誰もが知っている事だった。
「イラバロスが裏切り者だなんて」
イラバロスがザインの親友だとも、ランドール人だとも世には公表されていなかった。ただ戦争で生き残った、優れた魔法使いだったとしか話されていなかった。王室の事はあまり綿密に伝えられる事はなく、時の流れと心の弱った人々の噂話の中で都合のいいように変えられていっていたのだ。
ラムウェンドが片手を挙げるとざわめきは収まった。だが、未だ戸惑いは残っている。
「イラバロスを恨むか。それもいい。彼の行為が許せぬ者は今、この室から出て行く事を許可しよう」
ラムウェンドの言葉は決して責めてはいなかった。しかし、誰も席を立つ者はいない。それを確認してラムウェンドは微笑んだ。
「いい子たちだ。最後まで話を聞いてくれるか」
誰かが小さい声で「続けてください」と呟いた。ラムウェンドは浅く頷き、ふっと辛そうな表情を浮かべた。
「イラバロスは、二代目魔法王ガラエルの弟子となり、パライアスの再建に力を貸した」
イラバロスはあまり表で目立った行動はしなかったが、時間が経ち魔力が貴重となるにつれ、彼は純粋な魔法使いとして尊敬され始めた。イラバロスもまた、本来はその才能、人格と共に民に信頼されるべき男だった。
だが彼は自分の犯した罪を償える方法を見出せず、ただ孤独と戦う事を心に決めるしかなかった。そんな複雑な心情を相談できる相手などいるはずもない。友も作らず、ガラエルにも惜しみなく助力はしたが、決して心は開こうとはしなかった。
ガラエルはそんな彼を心配した。世が安泰するにつれ、ガラエルに人を気遣う心が生まれ始めていたのだ。同時に、改めてイラバロスの残酷な行為に感謝の気持ちを持つようになった。彼のおかげでこの大地が守られたのだと。だがガラエルは彼に何を与えてやればいいのか分からなかった。
イラバロスは何も欲しがらなかった。ある時はランドールの血を残せと結婚を薦めた。ある時は純粋な魔法を蘇らせようと教えを請うた。
しかしイラバロスは首を縦には振らなかった。イラバロスは悲しみに捕らわれていたのだ。ガラエルはそんな彼の傍に長年いる内に、たくさんの事に気がついた。
戦争で一番大きな犠牲を伴い、その悲しみを一人で背負っているのは他ならぬイラバロスではないだろうか。ランドールは滅びたが、そのすべてを犠牲にしてアンミールの民を守ってくれたのは、この無欲な魔法使いではないか。彼こそが二大の王より強く、誰よりも穢れなき心を持った真の勇者ではないか。ガラエルは自分の愚かさを時間を掛けて思い知った。ガラエルは心からイラバロスに感謝し、密かに称え、涙を流した。
そうして時は流れ、ガラエルは年を取った。魔力の強いランドールであるイラバロスはアンミールより遥かに長寿だった。ガラエルは孤独なイラバロスを残してこの世を去ろうとしていた。
世は騒いだ。王の跡継ぎは? リヴィオラは誰の手に?
そんな混沌の中、ガラエルは自分の息子とイラバロスを床に呼んだ。王の子にはなるべくして王位を継がせた。そしてイラバロスにはリヴィオラを差し出した。イラバロスは驚き、拒絶した。裏切りで汚れたこの手に持っていい宝石ではないと。王は彼に言った。
「今この世にお前以外の誰が偉大なる魔法使いを名乗れる? 受け取ってくれ。お前は私よりも優れているのだ。もともとそれは私が持つべきものではなかった。気づくのに遅くなってしまった。許しておくれ。それとも、私の知らぬところにお前以上の魔法使いがいると言うのなら、若しくはお前の叡知でリヴィオラが必要ないと思うならば、私の死後、その称号は自由にするがいい。それが私からお前に与える最後の使命だ」
そしてガラエルは逝った。イラバロスは再び心からの涙を流した。その時初めて、ガラエルもまた大切な友だった事に気づいたのだ。
イラバロスはリヴィオラを受け継いだ。そして心に誓った。もう二度と友を裏切る事はしないと。ガラエルの死後、イラバロスは昔の心を取り戻し、結婚をして子孫を残した。その子にランドールの魔法と文明を大切に伝えた。子供は成長し、旅に出た。そして二度と戻ってはこなかった。
子供の消息は絶たれたまま数十年が過ぎ、ある日イラバロスの元に噂が届いた。いい話だった。立派な魔法使いが立派な魔法使いを育て、この世に送り出す唯一の養成所が設立されたと。そこから魔法使いの価値が変わった。
その頃、パライアスにはイラバロス以外の優秀な魔法使いがほとんどいなくなっていたのだ。それを増やす手段もなかった。下手に魔法を広めても悪用する者が必ず現れる。イラバロスは旅に出た子供に望みを託していた。それが現実になったのだ。
しかしそれから更に長い年月、その影響はあまり感じられなかった。イラバロスの不安は募り、落ち着かなかった。いつになったらリヴィオラを受け継ぐ者が現れるのかと。
そんな彼にまた吉報が届いた。世界のあちこちに優れた魔法使いが現れ、悪しきものと戦っているのだと。イラバロスは喜び、彼も旅に出た。友との絆を守るためにリヴィオラを受け継ぐに相応しい者を探しにいったのだ。この世に再び純粋な魔法が蘇ることを王に約束し、彼もまた二度と王の前にその姿を現さなかった。
ラムウェンドが語り終える頃には、室内に流れていた困惑はすっかりなくなっていた。落ち着いた様子で数人の生徒がそれぞれに声を出した。
「その養成所と言うのが、このアカデミーですね」
ラムウェンドは言葉少なく返事をしていった。
「そうだ」
「それじゃあ、ラムウェンド先生はイラバロスの子孫」
「もう純血ではないがな」
「アカデミーはとても重い使命を背負っているんですね」
「その通り。そしてここから送り出される優秀な魔法使いもまた、重い使命を持っている……いや」ラムウェンドは無邪気な微笑を見せた。「素晴らしい、使命だ」
ここでやっと若者たちも心から微笑んだ。このアカデミーで十年という過酷な修行を乗り越えてきた意味を初めて知ったのだ。ここに残った者はその伝説を──語られなかった部分を含め、軽々しく触れ回る愚か者はいなかった。
だからラムウェンドは決して口止めなどしなかったし、彼らに惜しみなくその秘密を打ち明けたのだ。
穏やかになった室内の空気を感じ取り、ラムウェンドは大きく両手を広げた。一同がそれに注目する。そして講堂内にアカデミーの総監督の低い声が響き渡った。
「これで、すべての講義を終了する」
若者たちはそこに流れた、短く尊い瞬間を心に刻んだ。
「ここから新しい人生が始まる。ここにいる君たちに魔法使いの称号を与える」
端にいた少年の頬に、静かに涙が伝った。
「卒業、おめでとう」
4
その日の夕刻からはアカデミーで盛大な卒業パーティが開かれた。そこにいた皆が新しい魔法使いを祝福した。きれいに手入れが行き届いた中庭は満月の光と、等間隔に並べられた松明で照らし出されていた。
新入生によって準備された会場は、既に騒がしく荒らされていた。その頭上にはめでたいパーティを見守るかのような大きな時計台が聳え立っている。その針はちょうど十一時を指したが、それを確認した者はいなかった。
アカデミーはレンガ造りの大きな城だった。いや、城と言うよりその面積は計り知れず、一つの街に匹敵するほどの広大さだった。それをすべて目にできる者は、責任者であるラムウェンドと教員たち、そしてすべての工程を成し遂げた九年生だけである。
最初の一年間に十回にも渡る筆記のみの入学試験は毎年五百名を超える。まずはそのための大きな試験会場が設けられている。それに合格した才能ある者が一年生として迎え入れられる。その時で上位百名に絞られ、彼らが生活するための寮も収容されている。
それからさらに八年、毎年だいたい十名ずつがいろんな理由で脱落していく。最後に卒業できるのはいつも一桁と僅かなものであり、最悪の場合、卒業者はいないときもあった。それも無理はなかった。
そのカリキュラムは残酷なものだった。まず入学試験はじっくり一年をかけて行われる。毎月一回、決まった日時にアカデミーに集合し、二回の休みを除いてその教養や知識を試される。
しかもそのテストの内容はあまり魔法には触れられていなかった。あるとしても「魔法とは何か」「魔法とはどんなときに使うべきか、あるいは使ってはいけないか」など、難解で漠然とした質問ばかりだった。
きっと魔法使いを「なんでも屋」と考える者にとっては「姿を消す呪文は?」とか「蘇生術に使われる道具は?」などの具体的な問題を期待し、予習してくるだろう。
もちろん途中で参加しなくなる者も珍しくなかった。だがこのアカデミーにそんな知識は前もって必要なかった。そしてそれをひけらかす人材も。
それをくぐり抜けて、めでたく一年生となる。
ここからはもっと意地悪な日々が始まる。一年目──まる一年、アカデミーの過ごし方、規則、罰則、方針をしつこいくらいに毎日教え込まれる。
二年目、まともな家庭に生まれた者なら誰でも知っている文字の読み書き、計算の仕方、国や社会のしくみや政治、世界の気候など、わざわざここで学ばなくても生活の中で自然と育まれるであろう、退屈が頂点を達するような授業の毎日が続く。魔法についてはほとんど語られないまま。
三年目、ここでやっと魔法の基本的な仕組みについて学ぶことができる。
四年目には魔法の基礎知識、五年目には魔法の種類や使われる道具などについての説明……しかしこれもまた魔法使いを目指す者なら、そしてそうでない者さえ、子供の頃聞かされる、物語の中にでてくるような話ばかりを毎日まじめに学ばなければいけなかった。
六年目、この年はブランクと呼ばれた。この一年は所謂「社会見学」だった。
生徒たちはアカデミーの外で過ごし、レポートを提出しなければいけない。どこで誰に何を学ぶかは自由だった。魔法に関する事でなくてもよかった。テーマは学ぶ「姿勢」とそれに伴う「行動」だった。虫の観察日記を提出する者もいた。それでよかった。
問題は何かに興味を持ち知ろうとする心、そこから何を感じ、受け取り、自分の中に吸収しようとするのか。個人個人の人格や人柄を純粋に見極めることができる、ラムウェンドにとってはとても大切な授業だったのだ。
生徒たちにとって何が一番辛いか、それはこの六年間(試験を含めると七年間)は一切魔法や魔力、魔術の使用を禁止されていることだった。
生徒である間は光の形を象った指輪が与えられる。それはアカデミーの生徒である証明であるとともに、六年目まで魔法の類を使えない封印の魔法が掛けられていたのだ。
六年目の工程を終了した時にその封印は解かれ、卒業の時にラムウェンドの手によって回収される。
自分で外すことは簡単だった。だが特例以外で外すと二度とアカデミーには戻れなくなり、今度試験を受ける権利までも剥奪されてしまう。
それは不思議な指輪で、事故で引っ掛けたりぶつけたりしても取れなかったが、故意に取ろうと手をかけるとするりと落ちていくのだ。そしてその光は粉になって消えていく。
ここまでは地獄そのものだと言われた。退屈過ぎる毎日は無駄な時間に感じられた。逃げ出す者、怒り罵り出て行く者、休みから二度と戻ってこなくなる者、悪を犯して追放される者、理由は様々だったが毎年目に見て取れるほどの人材が削除されていった。
七年目、ここでやっと魔法は解禁となり授業も実施に入る。ここからは決して退屈な時間などなかった。
なぜなら今までの幼稚な授業が信じられないようなハードな毎日が始まるのだ。魔力を扱い、保つには強い体力と精神を養わなければいけなかった。この一年は過酷なトレーニングと基本的な魔法を学ぶ。ついていけずに倒れる者もいた。
八年目からはもっと厳しくなると恐れ、辞退する者も少なくなかった。ここで生き残るのは自分が人々に貢献し、尊敬されるに値する魔法使いになるのだという自覚と目標を抱き、見失わない者だけだった。しかし現実、その数は少なかった。
九年目──最後の授業が始まる。この一年は穏やかなものだった。講義も大切で興味深いものばかりだったし、トレーニングにも自主性を求められるだけで強要される事はなかった。
ここで脱落する者は、自らが魔法使いに相応しくないと感じた者や、その称号を戴く自信を失った者だった。
こうしてパライアスには毎年立派な魔法使いが、少数ではあるが送り出される。今年はとりわけ豊富に実ったと、ラムウェンドは喜んでいた。
その七人の中には、試験のときから何かと目立つ二人がいた。このめでたいパーティで騒がないはずがない。
「俺は納得いかない! なぜこんな邪悪な魔女が魔法使いになんかなれるんだ」
見たところ、まだ大人になりきれてない生意気そうな少年がビールジョッキを片手に怒鳴っている。
「魔女じゃないって、何度言わせるの! あんたこそその性格の悪さでよくここまで来れたものね」
目の座った少年に真正面から立ち向かっているのは、同じ年頃に見える少女だった。
その少女は齢千年を超える、赤い目を持つ魔族の姫だった。
彼女の名はティシラ・アラモード。父にヴァンパイアであり、魔界都市ヴィゼルグの王であるブランケル、母に魔界一の美女と言われるサキュバス(淫魔)のアリエラを持つ純血の魔族だった。
大きく波打つ、長い黒髪は常に完璧にセットされている。身に着ける衣服も黒いものが多く、細部には凝ったレースが飾られている。一見気の強そうな雰囲気の彼女によく似合う甘さと辛さ、そして若さを含むバランスのいい組み合わせで拘りを感じさせていた。
魔族であるティシラは人間より強い魔力を持っていた。その力や風格は手に取るように感じられ、妬み、言いがかりをつける者もいた。
ティシラの深紅の瞳は魔族であり、その王であるヴァンパイアの血の色だった。それには一瞥されると飲み込まれるような迫力があった。そしてその容姿は母親譲りの美しさと危険なオーラがあった。まだ幼く、魔界一の美女の娘にしてはいくらか落ちるような気もするが、人間を惑わすには十分な魔力を帯びている。
生徒たちは彼女に心を奪われると血を吸われてしもべにされる、生気や理性を奪われ呪われると噂し、恐れた。
5
だが実際にはそんな事を心配する必要はなかった。
彼女は魔族の姫である事にコンプレックスを抱いていたのだから。魔王の娘と呼ばれ、それだけでちやほやされるのは苦痛で仕方なかった。ティシラと言う一固体として認められたいと思っていた。
しかし彼女の立場はあまりにも身分が高く、生まれ持ったそれから逃れることができないほどに確立されてしまっていたのだ。そこから抜け出す方法はなかった──魔界と言う絶対勢力の世界の中では。
つまらない生活の中、ティシラは一つの光を見出した。それは子供の頃に母から聞かされた御伽噺の中にあった。
ティシラは人間の魔法使いの話が大好きで執拗に憧れを抱いていた。そしていろんな情報を集める内にアカデミーの存在を知ることになる。そこを卒業すれば魔法使いになれる上、自分の存在が認められる。自分の願いが叶えられるのだと迷う事なくそこに赴いたのだ。ただ純粋に、真剣にアカデミーの試練に取り組み、高い壁を乗り越えた。もう彼女を魔族のサラブレッドだとか邪悪な魔物だとか言う者はいない。
ただ一人を除いては──。
「俺は認めない。いいか、俺が世界一の魔法使いになる前に、まずお前を叩き潰してやるからな」
その少年はティシラに絡んでいる。酔っているからではない。いつもの事。試験の時から、十年間、ずっと。
少年の名はマルシオ・ローレン。彼の風貌もティシラに劣らず目を惹かれるものがあった。
それは光の加減によって灰色に輝く銀の美しい長髪と、それと同じ色の透き通るような瞳だった。決して邪悪な色ではなかったが、冷たく近寄り難い雰囲気があった。
本人もティシラとの喧嘩以外で人との関わりを避けていたため、マルシオの出生は謎のままだった。
彼はただ、この時代に廃れてしまった純粋な魔力と神への信仰心を蘇らせたいと思っていた。ついでにその負けず嫌いな性格が誘って、どうせなるなら世界一、とリヴィオラを切望していたのだ。
そんな彼は試験の初日に出会ったティシラを魔族と言うだけで敵と見做した。ただでさえ魔族への敵意があったマルシオは、彼女がその性質を利用してアカデミーに志願したのだと思い、それが許せなかったのだ。
ティシラもまた気が強く、一番言われたくない事を無神経に投げつける彼に反発し続けた。
その日から二人の火花は散り続けた。飽きもせずにと周りは呆れていたが、いつしかそれは日常となり、一つのイベントとなり──下らない言い争いをしながらも、ずば抜けて常に首位を争っていた二人の喧騒は、本人たちの知らないところで周囲を良いほうへ刺激していた。
ラムウェンドはそれを良とした。また、この二人が時を同じくして魔法を学ぶ事に、何か特別なものを感じていた。それは期待と希望だった。歴史に関わる大いなる出来事がこの時代に訪れ、この特殊で風変わりな魔法使いが何かしでかしてくれるのではないかと、密かに楽しみにしていたのだ。それには何の根拠もなかった。だが、ラムウェンドはこの二人に夢を託した。まるでイラバロスが我が子にそうしたように。
二人の主賓の小競り合いを止めようとする者はいなかった。酒も入り、それは止めど無く続いている。
「世界一の魔法使い?」ティシラは目を細め、皮肉る。「点取り虫が厚かましい」
どちらも負けてはいない。そしてお互い、勝ちもせずに気の済むまで言い争うのだ。時には手も出る。そうなると周囲も巻き添えを食らう事になる上、少なくともこのアカデミー内には、ラムウェンド以外に二人を止められる者はいなかった。
その場には新人の生徒もいたのだが、尊敬すべき卒業生がこれでは品格が疑われないかなど、さほど気にかける者はいなかった。ここに偽りは一切ないのだから。
まだアカデミーの真意を知らない者が彼女らをどう受け取ろうと問題なかった。この二人がいくら下らない喧嘩をしようと過酷な試練を乗り越えた魔法使いであることに間違いなかったし、それだけが真実だったのだから。
「お前こそ」マルシオは散らかったテーブルに空になったジョッキを叩きつけながら。「邪悪そのものだ! 俺は騙されないからな」
「私がいつ誰を騙したって言うのよ」
「邪悪なんだよ。その姿形、そして何よりも、お前のふざけた志しが!」
「なんですって! 私の高く清らかな志しのどこが邪悪なのよ」
「何が『世界一の魔法使いの花嫁になる』だ!」
それを聞いてラムウェンドはふっと目を細めた──そう、これはラムウェンドの唯一の不安だった。
「立派な目標じゃない!」ティシラは本気である。「私はそれに相応しい、特別な存在なのよ。つまり、あんたなんかにリヴィオラは渡さないんだからね」
「勝手な事を。お前には近づく事もできない聖なる称号だぞ。口にするのも烏滸がましい」
現在リヴィオラは、イラバロスの死と共に四代目となったクライセン・ウェンドーラと言う青年に受け継がれていた。
それからもう二千年近く時は過ぎている。彼はあまり人前に姿を見せなかったし、国の行事に関わる事もしない変わり者だった。もう百年ほど前に行方不明になっている。
その名こそ世界中に知れ渡っているが彼の存在を確認した者は限られており、人々の間にはどれが本当か嘘かも分からない物語のような伝説が語り継がれていた。クライセンはドラゴンだ、いや本当は架空の人物で実在しないとも言われていた。
どこかでは悪の組織を殲滅したとか、不治の病を治したとか、どれも信憑性のない話ばかりが広がっていた。だが、あくまでリヴィオラを持つ者は神聖なる魔法使いであると信じられ、クライセンと言うその名は疑われる事なく崇められていた。
世の力ある者たちはクライセンの在り方に不満や不安を抱いていたが、現実では民は彼を希望の光とし、絶望の時には必ず救ってくれると信じながら地に足をつけて生活していた。
悪い傾向ではなかった。だがクライセンは本当に希望の光なのか、いざというときには現れてくれるのか。そうではなかったとき、民にそれが知れたら大変な事になる。
最悪、混乱と暴動が起きるかもしれないと、内心ヒヤヒヤしていた。ラムウェンドも数少ないその中の一人だった。
この時代、リヴィオラは本当に必要なのか。こんな疑問が権力者たちの間で時々会議の議題に挙げられる事もあった。答えは出なかった。なぜならクライセンそのものがどこで何をしているのか分からない時がほとんどだったし、実際彼を知る者は少なく、それらは彼についてあまり話そうとはしなかったのだ。ただ口を揃えて「クライセンはイラバロスを凌ぐ偉大なる魔法使いだ」とだけ。そのほとんどが嘘をつく者でない以上、信じるしかなかった。
ラムウェンドもクライセンとは何度か会ったことがある者だった。悪者でない事は確かだったが、ラムウェンドも彼を「偉大な魔法使いだ」としかコメントしようがなかった。
ティシラは毎日のように「魔法王クライセンと結婚する」のだと、人目も憚らずに目を輝かせて語っていた。彼女はクライセンの事以外に興味を示さなかった。それでも成績は優秀であり、学ぶ姿勢も真面目だった。
何よりも純粋だったのだ。ラムウェンドはそんな彼女をうまく諭し、躱すので必死だった。その夢が愚かだとは一概には思わない。が、余りにも現実味が無さ過ぎる。まるで小さな子供が絵本の主人公の真似をして空想しているのと同じレベルに感じられたのだ。
魔法使いの素質はあるのだが、その発想は幼いとしか言いようがなかった。
「ラムウェンド先生!」
思案していたラムウェンドはティシラの甲高い声に呼ばれ、我に返った。すると赤い顔をした彼女が下から覗き込んでいる。
「な、何だね、ティシラ」
「クライセン様は」ティシラは呂律が回っていない。「立派な魔法使いですよね」
「あ、ああ……彼はリヴィオラを正当に継承した偉大な魔法使いだよ」
「ですよね。クライセン様もこの狭き門を通って立派な魔法使いになられたんですよね」
ラムウェンドは困って、ふらつく彼女の肩に優しく手を置いた。
「ティシラ」ラムウェンドは微笑み。「彼は、クライセンはリヴィオラを持つただ一人の魔法使いだ。彼の事を知りたいならその正しい瞳で真実を確認しなさい。そして君が本当に愛すべき人なのか確かめに行きなさい。真実はそこにのみあるんだよ」
生徒たちにとってラムウェンドの言葉はありがたいものだった。ティシラの浮ついた発想すら根を下ろせるような気になる。
「大丈夫。君ならできる。決して希望を失わず、自分の正しいと思うことを貫きなさい。諦めなければ必ず夢は叶う。それはここを卒業するティシラ自身がよく分かっているだろう?」
ラムウェンドは黙って聞き入る生徒たちに穏やかな顔を見せた。
「そしてこのことはここにいる卒業生、これから学ぶ君たちすべてにも言える事だ。自分を信じなさい。君たちには力がある」
するとティシラはラムウェンドに抱きつき、ぼろぼろと泣き出した。
「ラムウェンド先生!」
それにつられてマルシオも嗚咽し始める。さらに次々ともらい泣きする一同がラムウェンドを囲んだ。下級生たちはそれを不思議そうな目で眺めている。
ラムウェンドはその光景に安堵した。とにかくこの困った魔法使いをなんとか十年間、うまく誤魔化せたと……。
次の日、空は快晴なのに門前で顔を合わせたティシラとマルシオはいつもの言い争いを始める。
「これで邪悪な魔女も見納めだ。せいせいする」
「チクリ魔のガリ勉がどれほどのものか、世界に出て思い知るがいいわ」
離れた所でその様子を見ていたラムウェンドとほかの教員たちが笑っていた。
「ほんとに、最後の最後まで」
「あの子達の成長は楽しみですね」
ラムウェンドは深く頷いた。
「赤目の魔法使いと銀の光の魔法使い……青い宝石はあの風変わりな魔法使いを必要とし、導くだろう」
ラムウェンドはそれだけ呟くと、門前でまだ喧嘩している二人に手を振った。すると二人はそれに気づき、慌てて遠くから深々と頭を下げた。かと思うと再び睨み合い、大股で門の外へ出ていった。そしてお互いフンと背を向けて違う方向へ姿を消していった。
「行ってしまったな」
ラムウェンドはしばらくその後を見つめていた。
「……また、会える」
その言葉を風に乗せた。