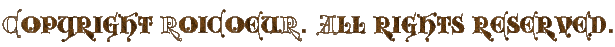第2章 再会





1
パライアスは数年に渡り、平和な日々が続いていた。これといって大きな変化も事件もなく、小さな悪や暴力、強奪などはなくならないものの、それらの被害が珍しくあるほど国の治安はいいものだった。
戦後、人々を恐れさせた海賊も今はすっかり数が減っている。なぜならパライアスは現在五十二の国に分かれ、その中で最大と言われる大国によって支配されているからだった。
その国の名はティオ・メイ。パライアスの東方にその門を構え、中央の王座にはガラエルの代から続くアンミールの王が座していた。時と共に王位は受け継がれ、今はインバリン王家のグレンデルがその椅子で大陸を守っている。
ティオ・メイは最強の軍事力を集結させ、大陸にある五十二の各国と国境のあちこちに兵や警備の砦を設けていた。その数や場所は民には正確には伝えられていない。いつでも迅速にその力を発揮できるようになっているため、時と場所、状況により移動する事があるからだ。
ティオ・メイは人々から「軍神の砦」と呼ばれている。その頂点に立つグレンデルもまた、神のように崇められ、アンミールの民に愛され尊ばれていた。逆に海賊始め、世の悪党は彼を恐れ、疎んじた。だがティオ・メイの軍に立ち向かえる者もその勇気のある者も、今の時代にはどこにも存在しなかった。
魔法戦争後、ノートンディルの大陸が海に沈んでから海賊が爆発的に増え、海賊の時代が来たとまで言われた時期があった。この世界を二分する大陸のひとつがなくなり海が開けてしまい、さらにその海の底にはランドールと天使の宝が眠っていると考えられた。
実際その噂は本当だった。パライアスの大地では造る事のできない貴重なものがいくつも発見されたのだ。その話は国中に広がり、財産や家族を失くした人々の心は荒れ、財宝を求めて次々と海賊行為に走ってしまった。
その上、パライアスの軍は戦争で大きな損傷を負って弱っていたため、その暴動を止める事ができなかった。
海賊たちはそんな軍を無視し、互いに宝を巡り争い、奪い合った。発見された財宝が誰の手に渡ってどこにいったのか分からなくなるにつれ、海賊の数は次第に減っていった。そして真に力のある者だけが生き残り、海賊は組織を成していった。
そこには秩序や掟が生まれ、強奪を司る彼らはパライアスの大地を捨て、神や軍に背を向けて海に生きる事を誓った。
ガラエルやイラバロスはその時代の流れを黙視した。ノートンディルの大地が海に沈んだ今、これも起こるべくして起こった変化なのだと受け入れ、海賊を滅ぼそうとはしなかった。その現実に暗黙のルールを見出し、最低限のそれをお互いが守っているうちは存在を認めることにした。
そうして海賊は今も海を根城にし、そこに暴力的な社会を作っている。
だが三百年ほど前、ノートンディルの眠る海に異常が起こった。
人が寄り付かないある場所に遺跡が顔を出したのだ。事前に大きな地震があった。その震源地の近くにいた海賊が遺跡の一角を発見した。
その話は海中に、そしてパライアスにも届いた。海賊は再び咆哮し、新たなる宝があると信じてそこに集合した。が、虚しくも遺跡に近づくことはできなかった。遺跡を中心としたその周辺には毒ガスが漂っていたのだ。未知の毒で解毒剤も存在しなかった。
海賊は酷く惜しんだ。そしてアンミールの民も同じ気持ちだった。ノートンディルが復活するのではと期待したからである。だがそうではなかった。そこに現れたのは、人を数秒で殺してしまう恐ろしい猛毒だったのだから。海賊を含め、世の人々はそれを離れた所から見守るしかできなかった。
しかし、そこから新たな発見があった。海賊から流れてくる情報をもとに遺跡の毒の研究が行われ、遺跡の毒は解明されなかったが、それによって薬や医学が進化し始めたのだ。人々は期待に満ちた。
魔法以外でも病気や傷を癒す手段が身近になったからだ。その内に遺跡の存在は人々の記憶から薄れていった。正確にはノートンディルへの憧れの気持ちが遠い昔のように感じられていっていたのだった。
光と共に必ず影が生まれる、と誰かが言った。
そうして医学が進化するにつれ、それを悪に利用する者が現れたのだ。新薬を使って人の体や心を操り、侵すそれは「魔薬」と呼ばれた。
国の取り締まりも虚しく、その取引は闇に潜んだ。いつの日か影の世界に「魔薬王」と呼ばれる者が誕生した。
彼の名はノーラ。それ以外を知る者は少なかった。
2
ティシラはアカデミーを卒業して五年間、これといって功績といえるものは残していなかった。実家にもほとんど戻らず、パライアスを放浪し続けて、あちこちの街や村をうろうろしていた。
そしてティシラはある街に足を踏み入れた。
「ここが、クルマリム」
平凡だがしっかりとした街だった。何でも一通りは揃うであろう店構え、道の舗装も立ち並ぶ民家も整えられており、安心して暮らせる町だった。公園や森林も豊かで子供ものびのびと成長できる。そこには平和を絵に描いたような光景が広がっていた。
だが、ティシラはそんな町並みには興味はなかった。
「今度こそ本当なんでしょうね」難しい顔をして眼球だけを左右に動かしている。「本当にここにウェンドーラの屋敷があるのかしら」
彼女はこの五年間、ただひたすらに魔法王クライセン・ウェンドーラを探し続けていた。彼に関する書物を読み漁り、飛び交う噂や情報をもとにその事実を突きとめようと片っ端から駆け回っていた。時間も労力も惜しまずに。
これまではほとんどがガセか空振りに終わってきた。そして一週間前に、クルマリムという街にクライセンの家があると耳にしたティシラは、迷わずにここに駆けつけたのだった。
「嘘だったら、あのジジイ」一週間前に話を聞いた老人の事だ。「とっ捕まえてカエルにしてやる」
不届きな独り言を呟きながらティシラは役所へ赴いた。街の情報を管理するところだ。ここに本当にウェンドーラ家があるなら役所に登録されているはずだとティシラは思った。だが彼女は、がっくりと肩を落とす結果を迎えた。役所の管理官は首を横に振った。また「はずれ」だったのだ。
ショックを受け、役所を後にしたティシラは老人をカエルにする気力も失う。また振り出しに戻ったと、途方に暮れた。
今度は図書館を探しにとぼとぼ歩いたが、途中でベンチに腰を降ろした。そこである日の事を思い出す。ティシラがアカデミーを卒業してすぐ、一度実家のヴィゼルグに戻ったときの事──。
一年振りの魔界だった。そこは空気が淀み、空が無かった。太陽も星もない空間に緑など育たない。あるのは朽ち果てて花も実もつけることのない呪われた木の死骸と、黒ずんで足場を悪くするだけの岩ばかりだった。だが魔界はそこに立派な国を創っていた。建物のほとんどは塔か城だった。身分の高い者しか住処を持てないのだ。それ以外の卑しい生き物は何かの影に身を潜めるしかなかった。
魔界は人間界とは別の空間にあり、そこは無限だと言われていた。誰も魔界の果てを見たことが無かったからだ。ここは大きく三つに区切られていた。
一つは貴族達が統治する魔界都市ヴィゼルグ。ここを支配し、魔王と呼ばれるのがティシラの父、ブランケルだった。もう一つはイン・クーラ。ヴィゼルグのさらに奥にあるもっと暗い土地には魔獣の類が生息している。彼らは人の姿をしておらず、言葉を話せる者は少なかった。
ヴィゼルグの住民より知能が劣り、凶暴だった。魔族は人間の世界にも行き来していた。人間には悪だと恐れられたが、必要がなければ無意味に襲うことはない。
もっともここの空気が居心地のいい彼らにとって、わざわざ用もないのに人間の地へ赴くことすら必要としなかったのだが。それに人間界には彼らが欲しいものはあまりなかった。
だが魔獣は少々違った。人間の涙を宝石のように欲しがり、恐怖や悲しみに捕らわれた魂が大好物だった彼らは、放っておけば気まぐれに人間を惨殺しかねなかった。獣としての本能でしかなかったのだが、人間たちはそれを邪悪と呼んだ。
もうずっと昔で、それがいつの事だか誰も知る術を持たないほど昔、魔族の中でも抜きん出で魔力の強かったブランケルがヴィゼルグを創った。
その目的は魔界の支配と、自らの力の誇示だった。力ある者が頂点に立つこの世界では、彼が王となる事に誰も逆らう事はできなかった。気に入らなければブランケルを殺すしかない。
だがそれをできる者は誰もいなかった。ブランケルは貴族に地位を与え、魔獣を魔界の奥へ追いやった。ブランケルは魔獣たちがいたずらに人間を脅かすのがあまり面白くなかったのだ。それ以来魔獣は特別な方法を持ってしか人間界へは行けなくなってしまった。特別な方法とは、邪悪な人間が黒魔術によって召還する事だった。
そうして魔界の秩序が生まれた。単純で分かり易いものだった。強い者が上に立つ。ただそれだけだった。
そしてもう一つの世界は、修羅界と呼ばれる空間だった。そこはブランケルでさえ、いや、この世界の誰も入れない場所だった。
修羅界とは何もない、無の空間だった
。魔界が無限と言われる所以はそこにあった。ブランケルは修羅界を、誰も入れないところなら仕方ないとあまり気に止めなかった。関わらなければ害もない。ただ時々、自分の言うことを聞かない困った魔族がいた時に「修羅界にほうり込むぞ」と言って脅しの道具に使うことはあった。実際これまでに何度か叩き込まれた者もいた。
修羅界はそうして「魔界の墓場」としてそこに黙って存在していたのだ。
3
ティシラはヴィゼルグで一番大きな城に駆け込み、魔界一の美女である母、アリエラの胸に飛び込んだ。
「ただいま。私、魔法使いになったのよ」
アリエラは優しく微笑んだ。
「お帰り、ティシラ」
その後すぐに、広いエントランスの中央に聳える大きな階段の上から父の声が響いた。
「ティシラ!」ブランケルは真っ黒なマントを翻す。「このバカ娘が! 何が魔法使いだ」
「パパ!」
ティシラはアリエラから離れ、ブランケルを睨んだ。素早く姿勢を整え、印を結ぶとそこから発生した魔法弾を投げつける。その赤い光の爆弾はブランケルに命中した。同時に彼の姿は無数の蝙蝠となって散り、ティシラに向かって飛んでくる。蝙蝠の集団はティシラを通り抜け、その背後に集まり再びブランケルが形を成す。
その姿は邪悪で凛々しく、高い背をピンと伸ばしている。意地悪な瞳は娘と同じ深紅の光を灯していた。だが左目だけは普通でなかった。深い赤であることには違いはないのだが、眼球がなかったのだった。義眼である。瞼は金の細工で縁取られ、その中には強い魔力の宿った希少な石が埋め込まれていたのだ。
本当の左目はどこかに保管してある。なぜ彼がそんなことをしているか理由は誰も知らなかったが、周囲は「派手好きな魔王のいつもの悪趣味だ」とあまり珍しがらなかった。
ブランケルはまるで生きているようなその瞳でティシラを見据え、口の端を上げる。そこから鋭い牙が覗いた。
「ティシラ!」
先ほどの剣幕は一瞬で消え、ブランケルは背を丸めて両手を広げる。するとティシラも満面の笑顔で、迷わずに父の胸に飛び込んだ。
「パパ!」
「おかえり、心配したんだぞ」
父子の派手な再会を無表情で見つめていたアリエラは、ゆっくり近づいて声を掛けた。
「さあ、二人とも」漆黒の髪を靡かせ、背を向けながら。「奥へ。お祝いをしましょう」
奥のリビングには豪華な食事が用意されていた。作ったのはアリエラではない。すべて召使であるピクシー(子鬼)によって整えられたものだ。
たった三人には広すぎる室、多すぎる料理だったが、その無駄な贅沢が彼らの当たり前の生活だった。
その空間で親子は色んな話をした。ティシラはその赤い目を輝かせてアカデミーでの思い出をとめどなく話して聞かせた。それは何時間も続いた。決して、飽きる事なく。
「ところで」話が途切れたところで、ブランケルが神妙な顔になった。「ティシラ、お前は未だにあの男の事を?」
「誰?」
「あれだよ、あの男……」
ブランケルが言葉を濁していると、アリエラが代わりに答えた。
「クライセンね」
その途端、ブランケルが拗ねた顔をする。唇を尖らせてアリエラを横目で睨むが彼女は既に顔を逸らしていた。そんな二人の心情も気に留めず、ティシラが再び元気を出す。
「当たり前じゃない。その為に魔法使いになったのよ」
「許さんぞ」
「パパに許してもらわなくても結構。私はクライセン様のお嫁さんになるんだからね」
「駄目だ!」ブランケルはテーブルを叩く。「あれだけはやめておけ。私の可愛い一人娘を。誰がやるものか」
「ちょっと、パパ」
「お前は自分の立場が分かっているのか。魔界を統べるアラモード家の大事な宝なんだぞ。あんな腑抜け魔法使いなんか……」
「パパ」ティシラはブランケルの剣幕を止める。「クライセン様を知ってるの?」
ブランケルは慌てて目を逸らした。
「し、知らん。魔法使いは皆、腑抜けだ」
気まずそうなブランケルの様子にティシラは噛み付かずにはいられない。
「嘘! 教えてよ」
室内の空気が変わった。邪魔にならないように周りをうろついていたピクシーたちがキィキィ声を上げて物陰に隠れていく。
二人の怒鳴り合いはいつもの事だった。アリエラは慣れた様子で黙ってワインを飲んでいるが、下っ端のピクシーたちには堪らない騒動だった。
魔界の王とその娘である二人は強い魔力を持っており、その感情や声にも力があったのだ。それに連動して空気が歪むと、弱い魔物は皮膚を刺されるような感覚に襲われる。それが長く続くと絶命する者もいる。
気を失い棚から落ちてくるピクシーたちを目で追いながら、アリエラが口を開いた。
「ティシラ」その声は滑らかだった。「どうしてクライセンのことを?」
二人はぴたりと動きを止め、眉を寄せながら椅子に座り直す。
「魔法使いは偉大よ。その頂点に立つ魔法使いは最高で、クライセン様は世界一なのよ。憧れて何が悪いの」
「悪いなんて」アリエラは微笑んだ。「私は反対してないわよ」
「アリエラ」
不満そうにブランケルが身を乗り出すが、アリエラに一瞥されて背を縮める。
「でも、あなたはクライセンがどんな人物なのか、今どこで何をしているのかも何も分からないんでしょ。そして彼の顔すら知らないのにどうやって結婚しようと言うの」
「それは」ティシラは真顔で言い切った。「私たちは赤い糸で結ばれているから」
ブランケルは頭を抱える。我が娘ながら、と思いながら呆れる。アリエラは驚きもせずに。
「で、なんで魔法使いになったの」
「クライセン様が魔法使いだから」
「関係あるの?」
「その方が近くなるじゃない」
沈黙が落ちてきた。あまりにも単純で何の根拠もないティシラの発言は今までも周囲を驚かせてきたが、今回もまた例外ではない。その度に肩を落とすブランケルの代わりに、真面目に諭すのがアリエラの役目だった。
「ティシラ、あなたはまだ幼いから分からないだろうけど」アリエラの微笑みは残酷なものになった。「結婚や恋愛はそんな単純ものじゃないのよ。お互いが愛し合い、必要としなければ成立しないの。顔も知らない人に想いを寄せるのは勝手だけど、その段階で結婚すると断言するのは妄想に過ぎないわ」
ティシラは反抗的な目をするが、反論はしない。
「片思いも立派な恋愛よ。でも、それから先に進むには縁と相性が噛み合わなければいけないの。何よりも相手を思いやる気持ちが無ければ、うまくいくものもいかなくなるのよ」
ティシラはアリエラが何を言わんとしているか、まだ分からない。
「今のあなたには運命とかそれ以前に、乗り越えなくちゃいけないもっと別の大事なことがあると思うの。それは、相手のことを知って受け入れていく、その人のためだけに養う思いやりの心」
「…………」
「つまり」遠慮なく。「相手にも選ぶ権利があるって事」
4
ティシラは深くため息をついた。その時のブランケルの不快な笑い声が耳に残っている。暗い顔をした彼女をよそに、クルマリムの街には平穏な時間が流れていた。
「会えないのかなぁ……」ティシラは呟いた後、頭を振る。「ううん、絶対諦めない。ラムウェンド先生は必ず夢は叶うって言ったもの」
だが彼女の不安は他にもあった。ティシラは悔しい勢いで、さっさと家を出て再び人間界へ旅立つとき、大事なことを思い出して出掛けにアリエラに声をかけた。
「ママ。クライセン様の事、何か知ってるの?」
アリエラは無表情で答える。
「今は知らない」
「今は……?」
そして遠くを見つめ、あっさりと言い切る。
「死んでるかもね」
信じない事にした。クライセンが死んだと言う証拠も、そんな話もないのだから。
その時、落ち込む彼女の闘志を蘇らせる懐かしい声が飛び込んできた。
「お前は、魔女!」
その忌々しい声、言葉に顔を上げずにはいられない。五年経った今でも鮮明に、あのときの苛立ちが内側から甦った。その声の主を確認するまでもない。
「マルシオ!」
一気にティシラのテンションが上がった。そこにはあの憎たらしい銀目の少年、マルシオが自分を睨みつけていたのだ。二人はあの頃と何も変わっていなかった。
「なんでお前がここに!」
「こっちの台詞よ!」
「なんでアカデミーを出てまでお前の顔を見なくちゃいけないんだ」
マルシオは眉を寄せ、通行人が足を止めて行くのも気に留めない。
「さては、お前もウェンドーラの屋敷に向かうつもりだな!」
ティシラは言葉を失った。いきなり目を丸くし、マルシオを凝視する。
「……な、何だよ」
マルシオは言い返してこない彼女を怪訝そうに見つめる。ティシラは口だけを動かして呟くように。
「今、何て?」
「だから……」
しばらくの間、二人は固まり見詰め合っていた。その内に見物人も散っていった。マルシオは考えがまとまって、いやらしい笑みを浮かべる。
「そうか……ティシラ、お前、知らないんだな」
「な、何を?」
戸惑い、口籠る彼女にマルシオは嫌な笑いを浴びせた。ティシラはむっとするが、罵声をぐっと飲み込む。そんな彼女の態度にマルシオはさらに反り返る。
「いい話を聞かせてやろうか。俺はな、魔法王の弟子入りをしたんだ」
「嘘!」
「さすがに」マルシオは自慢げに顎を突き上げた。「世界一の魔法使いは偉大だ。本人を見て俺にはまだ修行が必要だと言う事を思い知った。だから弟子にしてもらったんだ。つまり俺はこの世で一番リヴィオラに近い、才能ある魔法使いって事だ」
ティシラは驚きとショックで何も言えなかった。この宿敵である生意気なマルシオに先を越されたなんてと、今にも泣き出しそうなくらいの悔しさがこみ上げてくる。
だが、それと裏腹に希望も感じられた。魔法王はいる。この街に。自分のすぐ近くに、と。その思いは屈辱を跳ね除けた。煮え湯を飲み込む思いでティシラは震えを抑えた。とりあえず素直に聞いてみよう、と思う。当然まともな答えは返ってこないだろう。マルシオの返答次第で次のことは考える。よし、とティシラは呼吸を整える。
「マルシオ」ティシラは言いにくそうに、ぼそぼそと言葉を漏らした。「ウェンドーラの屋敷に……」
「案内してやろうか?」
「……えっ!」
ティシラの警戒をまったく無視して、マルシオはあっさりと彼女の要望を自分から受け入れた。あまりにも意外な展開だった。ティシラは糸が切れたように肩を落とす。マルシオは腕を組んで試すような目で彼女を見下ろしている。ティシラはその姿が決して、五年の時を経て彼が大人になったとわけでも何でもないと確信する。やっぱり腹立たしい。再び眉を寄せて大声を出す。
「何か企んでいるわね」
「嫌なら、結構」
余裕綽々のマルシオの態度にティシラは戸惑った。
絶対何か裏がある。この男が親切心だけで自分に助力するはずがない。
だが、その誘いを断る勇気もなかった。本当にクライセンに会えるならそのきっかけは何でもいいじゃないか。ティシラはできるだけ短く考えた。
ウェンドーラの屋敷がここにあると聞き、駆けつけた。しかし役所ではないと言われたが、マルシオはあると言っている。どれが真実か見分けるには情報がなさ過ぎた。
だがマルシオの言葉には僅かでも可能性がある。時間もたっぷりある。賭けてみてもいいかもしれない。もし何か罠や偽りがあった時は──ぶん殴ってやればいい。
少なくともマルシオも魔法使いだ。騙されたとしてもいたずら程度で、取り返しのつかないほどの窮地に追い込むような事まではしないだろう。思案の末、ティシラは心を決めた。
「お願い……」
「何?」
「案内して」
慎重な顔で警戒している彼女を見て、マルシオはニヤリと笑う。
「いいとも、だが」やはり、ただでは済まなそうだ。「人にモノを頼むなら、それなりの態度があるんじゃないのか?」
ティシラは牙をむき出した。その赤い目に睨み付けられれば大抵の人間は縮み上がるものだが、マルシオは当初からそれをものともしていなかった。殺気を放たれて、マルシオは更に彼女を煽る。
「何だ、その顔は」皮肉たっぷりに。「まるで『私は魔界のお姫様なのよ』とでも書いてあるかのようだな」
ティシラは胸が痛んだ。
「俺の知ってるお前は、魔界の姫と言われる事を嫌がっていたような気がするんだが……俺の勘違いだったか? それとも、お前は嘘をついていたのか?」
違う。ティシラは強く迷いを振り払った。姫だから人に請うのが嫌なんじゃない。
相手がこいつだからだ。そう思い直す。悔しい。心理戦だった。マルシオはいつもそうだ。ティシラに対し、嫌がる言葉をわざと選んで付け込んでくる。だが今は五年前と状況が違う。確実にマルシオの立場が上だった。ここで言い返してしまったら、あるかもしれないチャンスを逃してしまうかもしれないのだ。
激しく葛藤する彼女をマルシオは楽しそうに見据えている。そして「さあ」とティシラを急がせ、考える時間を与えようとしなかった。
くそ、とティシラは汚い言葉を飲み込む。今日は厄日だ。そう思いながら拳を握り絞める。そして何度も今だけ今だけ、と自分に言い聞かせる。
マルシオの言う事が本当ならそれだけの価値はあるはずだ。嘘なら──それなりではない、それ以上の報復を与えてやる。そう心に誓って、ティシラは一気に頭を下げる。
「お願いします! 案内してください!」
マルシオの歓喜の顔を見たくなくて、ティシラはすぐには顔を上げ切れなかった。彼の高らかな笑い声を後頭部に浴びながら、いずれにしてもこの仕返しは必ず、と腹を据えた。
「さあ、早く」ティシラは真っ赤な顔を上げ。「なめた真似したら許さないからね!」
マルシオは満足そうに「ついてこい」とティシラに背を向け、街中へ歩き出した。不愉快そうな顔でティシラは渋々その後をついていく。
マルシオはそのままクルマリムの街を通り抜け、すぐ傍らにあった森に入っていった。
「この先だ」
もうマルシオの顔に緩みはなかった。それどころか緊張しているようにも感じる。
「この森の奥に彼の屋敷があるんだ」
「でも、役所ではウェンドーラはないって言われたのよ」
「この森はウェンドーラ所有地で、クルマリムとは別の領地になるんだ。だから役所には登録されていない。街のすぐ隣だからな、よその奴は『ウェンドーラの屋敷はクルマリムにある』と言う。それにお前はどうやら『はずれ』を引いたようだな」
「な、何が」
「親切な街の人間ならウェンドーラの屋敷はすぐ隣だと教えてくれる」
ティシラはまたむっとした。役所で適当な返答をされても構わずに住民に聞き込みをしていれば、こんな奴に頭を下げてまで世話になる必要はなかったんじゃないか。まったく、どいつもこいつもと唇を曲げる。それを背中で感じながら、マルシオは話を続けた。
「この森は特別な魔法がかけられている。危険は一切ないが木々に意識が宿っていて、興味本位で近づく一般人や敵と見做された者は迷わされて屋敷へ辿りつくことはできないんだ」
「その魔法はクライセン様がかけたの?」
「さあ。森も屋敷も古い。意図して宿った魔力なのか分からないほど定着してしまっているからな」
「じゃあ、あんたは最初、どうやって屋敷へ?」
「それは」マルシオは少し言葉を選んで。「徳が高いからだろ」
「……よく言う」
ティシラは罵倒を飲み込む。今はまだ我慢しよう、そう思った。マルシオは彼女の心情を読み取れていたが、これ以上煽る事はしなかった。
「まあ、ここで俺と会えたお前は『あたり』って事だ。森に迷わされずに済むんだからな」
その内に森が開けた。葉の茂った木々が丸い壁を作り、彩られた花が絵画のように咲き誇っていた。
緑をベースに赤や白、黄色、青などのこの世の鮮やかな色のすべてがここに揃っているようだった。これだけの色が揃っていながらも決して騒がしくなかった。気まぐれでも無造作でもなく、そこには深みがあったのだ。
その情緒に吸い込まれていく内に、自然がメッセージを含んでいるように感じる。それは自分にではなく、誰か、遠いどこかに宛てられたものであり、それが何なのかはきっといくら考えても答えは出ないのだろう。それでも考えたくなる。足を止めて引き込まれていく。
そんな不思議な空間の真ん中に、大きく立派な館があった。その姿はまるで貫禄のある賢者が物静かに、そして堂々と座っているようだった。
ずっと、ずっと、まだ自分が生まれるずっと前からそこで物思いに耽って、そのまま眠ってしまったんじゃないだろうか。そうだとしたら安らかで、意味のある眠りに違いない。
きっとこの森はその眠りを邪魔させない為に人を寄せたがらないのだろう。そんな事を思わせるほどその屋敷は憂いに満ちていた。何かを、いくら待っても来ない誰かを待ち続けているように。
木や花たちはそれを祝福し、称え、永遠を誓っているのだろう。すべてを見届ける為に、ここでずっと花を咲かせ続けるのだろう。どこか物悲しいと思えば思うほど美しく見えた。
5
ティシラは心を奪われた。ここなら世界一の魔法使いがいてもおかしくないと思えた。
「……本当だったんだ」
そして本人の姿を確認しない内に、そう呟いていた。そんな彼女に気遣う事もなくマルシオは黙って屋敷に足を運んだ。ティシラは我に返り後をついていく。
その時、マルシオの変化に気がついた。彼は微かに震えていたのだ。
「マルシオ?」
声をかけても返事も振り向きもしない。やっぱり何かあるのでは、ティシラが勘繰りながら歩いているうちに、マルシオは腕に力を込めて玄関の扉を開いた。
しかしティシラの警戒は散り去った。その室内も立派なものだった。造りや装飾は一見そう珍しいものではなかった。穏やかな絵画やドラゴンの彫刻、派手過ぎないシャンデリア、屋敷を支える柱一本一本にさえ歴史や威厳を感じられるものばかりで揃えられえていた。
ここにどんな罠があると言うのだろう。邪悪なものなど何も在るとは思えない。ティシラはまたその光景と、漂う魔力に興味を示さずにはいられなかった。
が、それも束の間。いきなり屋敷の奥から恐ろしい怒鳴り声が放たれた。
「マルシオーッ!」
ティシラは心臓が破裂しそうだった。その声には強い魔力があり、音量だけでない威圧の力が空気ごと震え上がらせたのだ。マルシオの顔が真っ青になり、がくんと膝をつく。
「……ご、ごめんなさい!」
ティシラの目が丸くなる。エントランスの奥にある細工の施された大きな扉が激しく、一人でに開いた。そこには誰もいなかったが、中からまた先ほどの恐ろしい声が轟く。
「たかだか買出しにどれだけの時間を食っている! そんなにのんびりしたいなら亀の甲羅でも背負わせてやろうか」
「お許しください!」
マルシオは姿のないそれに反射的に土下座した。ティシラは呆気に取られる。
そして、まさかと思う。この傲慢で乱暴な声の持ち主がクライセンなのか。
声の主が魔法使いであることには間違いない。しかも相当な魔力がある。ティシラが一歩後ずさった時、扉から声の主が姿を現した。開け放たれた扉から意外と普通に、ゆっくりと歩いてくる。
「……マルシオ、お前が無駄にした時間はどうやって償う?」
「今日は眠らずに森の手入れをします。どうか、亀の甲羅だけは勘弁してください」
ティシラはさらに呆然とする。目を疑う余裕もない。その偉そうな魔法使いは……なんと、二足歩行で洋服を身に纏った背の高い「猫」だったのだ。
ここまでくると、もう「まさか」なんていう領域ではなかった。猫の魔法使いなんて聞いた事がないし、その踏ん反り返った猫にあのマルシオが必死になって謝罪している。これは、一体なんだろう。ティシラは状況が把握できずに、開いた口の端から少し牙が出ているのも気づかない。
「いいだろう」猫はマルシオを見下ろして。「もし居眠りでもしたら、よく眠れるようにその瞼を縫い付けてやる」
「は、はい」
「で」猫はその釣り目をティシラに向けた「こいつは何だ」
ティシラは猫と目が合い、反射的に口を結ぶ。が、言葉は出なかった。するとマルシオが慌てて顔を上げた。
「ジン様」猫はそう呼ばれた。「この者はアカデミーで私と同期だった者です。前に話した事があるティシラです。街で偶然会いました。急いでいる所を引き止められ、それで時間に遅れてしまったのですが」
そこでティシラは眉を寄せた。マルシオは早口で続ける。
「この者もここで働きたいと、どうしてもお願いされてしまったので、私の一存では決められず、連れてまいりました」
「ちょっと」ティシラはさすがに黙っていられない。「マルシオ! あんた、何を……」
「うるさい!」ジンの声にまた二人は抑えられた。「私の許可なく勝手に喋るな」
理不尽に黙らされたティシラにジンは近寄った。そして目をきょろきょろさせて彼女の顔を眺めた。マルシオは床に座ったままビクビクしている。
「ふん」ジンは意味深な笑みを浮かべた。「魔族か」
ティシラはジンを睨んだ。
「だったら何だって言うのよ」
マルシオはティシラを止めようとしたが、二人の間に入っていく勇気が出ない。
「魔族が魔法使いになって悪い? あんただって猫じゃない」
「よせ、ティシラ」とうとうマルシオは立ち上がった。「この方は魔法王の飼い猫だったジン様だ。長い間彼の傍にいて魔力を帯びたため、人語を扱い長寿を得てこの屋敷を守っておられる方だ。姿は猫でも俺たちよりずっと強い魔力の持ち主なんだ。逆らうんじゃない。お前なんか指一本で捻り潰されるぞ」
「だから何なのよ」ティシラは素早くマルシオの胸倉を掴む。「マルシオ、あんたやっぱり騙したわね。クライセン様はどこよ。私はこんな猫になんか興味ないし、むしろこんな毛の塊、嫌いなのよね。なんであんたなんかに頭下げてまでここまで不愉快な思いをしなきゃいけないわけ? これ以上私の気分を害したら亀の甲羅なんかじゃ済まさないわよ」
「そ、それは……」
「とんだお姫様だな」隣でジンが皮肉る。「お前も世界一の魔法使いを見物にきたお気楽な観光客か」
ティシラはマルシオを突き飛ばし、ジンに向き合う。
「私は──」
マルシオは尻餅をつきながら、慌てて「バカな事を言うな」と叫ぶが、間に合わない。
「クライセン様の花嫁になる女よ!」
マルシオは頭を抱え、その場に蹲る。ジンは目を丸くした。当然の反応だった。しばらくその場に重い空気が流れたが、我慢できずにジンが吹き出した。
「何がおかしいのよ!」
「笑うところだろ?」
ティシラの顔が赤くなる。かっと口を開こうとするが、ジンに止められる。
「それは無理だ」ジンの顔からすっと笑いが消えた。「彼はいない」
「……なんですって」
「クライセンは死んだ」
ティシラは頭の中が真っ白になった。
「ちょっと待てよ」マルシオも驚いて顔を上げる。「な、何だよそれ。お前、俺にはずっと知らないって言ってたじゃないか」
「いちいち説明するのが面倒臭かっただけだ」
「じゃあ」マルシオがゆっくり立ち上がる。「……リヴィオラは?」
「知らん。興味がないのでな」
二人の魔法使いは立ち尽くした。何よりも最悪の言葉だった。ジンはそれを眺めて、無情に声をかけた。まずはティシラに。
「用が済んだなら帰れ。魔界にな。さて、マルシオ」次はマルシオに向き。「お前はまだ済んでないよな」
マルシオはジンを睨んだ。
「いいや」怯えを隠し切れていないが。「俺はここに魔法王の称号があると信じていたからいたんだ。だけど、今の話が本当ならもういる意味はない」
ジンは呆れて、ため息をつく。
「そんな勝手が許されるか。お前は自分が何をしたか分かっているのか。魔法使いのくせに勝手に他人の家に侵入し、さらに価値のある水晶を盗んだ」
「盗んでなんか」マルシオは声を荒げた。「強い魔力を持った水晶だったから、つい覗いてしまって……そしたら、あんたに怒鳴られて、びっくりして……」
「落として、壊した。盗んだも同然だし、それ以前に家宅侵入は立派な犯罪だ。弁償しようにもあれは金で買えるものじゃない。魔法王の水晶なんだからな。だからそれを償うまでここで召使として働くと約束したよな。魔法使いが誓いを破るか?」
マルシオは黙ってしまった。どうやら逃げられそうにない。
ジンの目的は分かる。ここにいても大した仕事を与えられるわけでもない。ただこき使いだけだろう。
当初は、きっかけは間抜けなものでも、クライセンの家に仕えていれば彼に会えるかもしれないし、魔力が向上するかもしれないと前向きに考えて覚悟を決めていた。マルシオが思う以上にジンのこき使い方は乱暴だったが、悪人でない事は確かだった。
ときには一緒に森を散歩をしながら歴史や魔法について語り合ったり、その時々ジンは高等な魔法使いしか知らないような貴重な話も聞かせてくれた。その魔力と厳しい性格は恐ろしかったが、嫌いにはなれなかった。
少なくとも信頼はできる。マルシオはそう思い、ジンに頭を垂れた。
それを見てジンは頷き、目を伏せる。
そこで、今まで黙って沈んでいたティシラが顔を上げた。
「私もここにいるわ」
ジンとマルシオは同時に彼女を見た。
「猫の召使でもなんでも」ティシラはマルシオを睨み付けて。「あんたの策略に乗ってあげる」
「な、何を言って……」
「どうせ一人じゃ心細かったから私を巻き込もうとしたんでしょ」ティシラは図星のマルシオからジンに向き直り。「帰らないわよ。ジン、私を追い出したかったらクライセン様の死体でも持ってくることね」
ジンは目を細めた。
「無理だと言ったろう」
「嘘よ。信じない」
「死体を持ってくれば、お前はそれと式でも挙げるか?」
「本当に持ってくれば考えるわ」
「なんて不躾な姫様だ。親の顔が見たいね」
「こっちの台詞よ。一体何の股から生まれてきたの?」
「……品のない娘だな」
空気が重くなる。マルシオは気が気でなかった。ジンとティシラと間の火花が目に見えそうだった。その激しい間はティシラの低い声で仕切られる。
「あんたは、嘘をついてる」
ティシラはジンの意地悪な皮肉など聞く耳持たなかった。
あまりの険悪さに、堪らずマルシオが「よせよ」と止めに入るが、ティシラはそれを振り払う。ジンとティシラはその目に魔力を宿してぶつけ合う。その力は凄まじかった。空気が震え、僅かに柱や壁が振動する。それは屋敷の外にまで広がり始め、風もないのに森中の木や花がざわめくほどだった。マルシオはその迫力に息を飲んだ。
先にそれを解いたのは、ジンだった。魔力を解放し、口の端を上げる。
「いいだろう。ただし、ここでは私が主人だ。常に私に従ってもらう。生意気な口をきく事も逆らう事も一切禁止する。もしこの私を怒らせたら──ネズミにして油で揚げてやるからな。心しておけ」
「……努力はするわ」
「いい度胸だ」
そしてジンはつんと背中を向け、早足で立ち去った。
「まったく、ラムウェンドはどんな教育をしているんだか」
と、ぼやきながら。開いたままだった奥へ続く扉は、ジンが潜ると後を追うように閉じた。
マルシオはジンの姿が見えなくなると、大きなため息をついた。そして未だにジンの消えた扉を睨み付けているティシラの肩を掴む。
「ティシラ。どういうつもりだ」
「あんたこそ」ティシラはまたマルシオの胸倉を掴む。「何やってんのよ」
「い、いや……同期のよしみじゃないか。ジンからだって学べる事はたくさんあるんだ。だから……」
「私はあんな猫から何も学ぶつもりなんてないわよ」
「じゃあ、どうして」
「言ったでしょ。私は信じないって」
「クライセンの事か」
「そうよ。死んだなんて嘘よ。彼は世界一の魔法使いなのよ。この世の誰が彼を脅かすと言うの」
「さあ……俺には……」
「あんたは勝手に猫のトイレ掃除の極意でも極めればいいわ。私はここでクライセン様の事を探る。必ず何か情報を知る事ができるはずよ。絶対に諦めない」
「お前は……」マルシオは一度強く目を閉じ、ティシラの手を振り払う。「いや、クライセンの消息は俺にとっても重要な事だ。お前と争っている余裕はない。手を組もう」
「調子のいい奴」
「ガタガタ言うな。確かにお前を騙そうとしたが、価値のある状況を得ただろう」
マルシオは調子悪そうに、しかしあくまで意地を通し続ける。ティシラはそんな彼を冷めた目で見つめるが、もう怒りはなかった。天敵はマルシオではなくなったのだ。だが仲良くする気にもなれない。
「まあ、いいわ。許してあげる」つまり、マルシオの事はどうでもよくなったのだ。「休戦しましょう」
この日から、二人の共同生活が始まった。