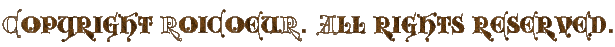第11章 魔女





1
夜が明けても空は明るくならなかった。厚く灰色の雲が空を覆っている。激しくはないが風があり、いつもより船の進みは速かった。雨が降りそうな気配はないが陰気な空気が漂っている。
だが、それに反して船にはやたら陽気な者がいた。意外にもそれはティシラだった。すっかり元気で、昨夜のことがなかったような笑顔だ。
あれから彼女はクライセンに抱えられて寝室へ運ばれた。クライセンはマルシオを呼んで看病を頼み、なぜ自分がティシラと一緒にいて、何を話したのかなどは一切言わずに室を出ていった。
マルシオは自分がきつく言い過ぎたことを気にして、付きっ切りで治癒の魔法を続けていた。
その甲斐あって数時間後にはティシラの呼吸が通常に戻った。マルシオの魔法に伴って、ティシラの驚くほどの回復力も手伝い、彼女は安らかな眠りについていた。
それを確認してマルシオは室を出ていった。目を覚ましても一人になりたいだろうし、自分には彼女に何を言ってあげればいいのか分からなかったからだ。
マルシオは、きっと彼女なら大丈夫だと自分に言い聞かせていた。こんなことでダメになる奴じゃない、必ず立ち直ると信じた。
それにしても──と、マルシオは思う。
「いくら何でもそれはないだろ」
クライセンを除いた一同は船内の居間に集まっていた。隣は台所になっており、居間には大きなテーブルとそれを囲むいくつかの椅子が並んでいる。
その一角で、ティシラがヘラヘラと笑っていた。
「何が?」
マルシオのぼやきにティシラは軽く頭を傾げる。マルシオはその姿に苛立ちを覚えた。
「人が心配してるのに、少しくらい申し訳なさそうにしてもバチは当たらないんじゃないのか」
すると、ティシラはキッと真面目な顔になり、カクンと頭を下げた。
「みんな、昨日はごめんなさい」
だが顔を上げると、またそれは緩んでいた。
「お前なぁ……」
マルシオが怒りで体を震わせる。そこにトールが口を挟む。
「とにかく元気になったんだし。いいじゃないか」
「そうそう」ワイゾンも困っていたが、取り敢えずフォローに回る。「一時はどうなるかと思ったが、ご主人様も他の皆も怪我一つないんだし」
「そうそう」ティシラは調子に乗って。「あんたって本当に後ろ向きなんだから。仲間が元気なのが何で不満なのよ」
マルシオは呆れてものが言えなかった。言いたくもなかった。一同はティシラよりマルシオへの同情が募った。そこでマルシオがティシラを睨む。
「分かった」マルシオは目を細める。「クライセンと何かあったな」
するとティシラは顔を真っ赤にしてマルシオを突き飛ばす。
「やだ。何かあったなんて。変なこと言わないでよ」
マルシオは椅子ごと倒れるが、すぐに座りなおして。
「お前のことだ。どうせそれしかない。しかもまたつまらないことで浮かれているだけだろ。いい加減にしろ。この単細胞」
「マルシオ」ティシラはニヤリと笑う。「さてはあんた、妬いてるわね。私に先を越されて面白くないんでしょ。あんた相当捻くれてるからね。アカデミーでは友達もいなかったし、全然もてそうにないものね」
「俺は敢えて関わりを避けてたんだよ」マルシオはむっとする。「お前だって人のことが言えるかよ。勘違いも大概にしろ。お前みたいな魔女、誰が本気で相手にするかよ。魔術で呪いをかけるのが精一杯だろ」
「何て事言うのよ。私のママは絶世の美女なのよ。ママは魔力なんか使わなくても誰でも虜にできるんだから」
「何の自慢だよ」
「みんな私のこと、ママにそっくりだって言うのよ」
「お世辞に決まってるだろ。そんなことは親戚か近所のおばさんなら誰だって言うんだよ。大体、俺はお前の母親なんか見たことないからな、お前と似てるなら母親も大したことないってことになるんだぞ。お前だけでも痛々しいのに、わざわざ身内の恥まで晒すな」
「ママの悪口は許さないわよ」
「お前を貶しているんだよ」
一同は白けた目で二人のやり取りを見ている。二人とも若くてきれいな容姿をしているのに、と思う。これがなければ……とある意味哀れにも感じる。天は二物を与えないとはこのことだろうか。そうだとしても、この二人の言動はせっかくのいいところを隠してしまい過ぎている。ちょっと残酷ではないだろうか、と神に物申したい気分にさえなる。
そこに、ふと人の気配がした。一斉にそこに注目が集まった。もちろん、他の誰でもない、クライセンだった。いつの間にか戸口に立っている。
「確かに……」言いながら、ゆっくりと中に入ってくる。「彼女は女神にも劣らないほど、美しい女性だった」
妙な空気が流れた。クライセンはそれを読まずに適当に空いた席に腰掛ける。今まで彼が自分から輪の中に入ってきたことはなかった。別におかしな行動ではないのだが、クライセンがそれをすると何かあるんじゃないのかと勘繰ってしまう。だが特別に何かがあるような雰囲気ではない。余りにも退屈で世間話でもしにきたのか、そう思おうとしても、なんだかしっくりこない。
そんな中で、ティシラだけが彼を違う目で見ていた。
「あの」と、戸惑いながら。「ママを知っているんですか」
「うん」
「そうだわ。ママも、パパも知ってるふうだった。いつどこで会ったんですか。どうして……」
クライセンは薄く微笑んでティシラを見つめた。その横でマルシオが一人、嫌な予感を察知する。ここにきて今更何のつもりだ、と刺々しい視線を送る。しかしクライセンは彼には見向きもせずにワイゾンに声をかける。
「船長。目的地までまだかかるか?」
「あ、ああ」ワイゾンは戸惑いながら。「早くても明日にはなる」
「そうか」クライセンはテーブルに肘をついて。「じゃあ、少し昔の話をしようか。暇つぶしにもならないだろうけど」
そうは言っても、誰も席を立とうとはしなかった。彼が自ら自分の過去を語ろうなんて、全員が興味を示さずにはいられなかった。クライセンはその様子を気にするでもしないでもなく、穏やかな声で語り始めた。
「もう千年以上も前の話だ……ある魔法使いが小さな町に滞在していた」
2
その魔法使いとは、他ならぬクライセン本人のことだった。
今と姿は変わらない。彼はパライアスの片隅にある小さな町に滞在していた。。特に用があったわけでもなかったのだが、そこである噂を耳にした。町の近くの森に魔女がいると。
魔女は夜になると町の若い男を森に誘い込み、魔術で虜にして生気を吸い取り、呪い殺してしまうと恐れられていた。
それはまだ最近の話だった。一ヶ月ほど前に、森から逃げ帰ってきた女性が「夫が魔女に呪われた」と泣きながら話した。彼女は夫を失い、数日間泣き続けて衰弱した挙句に自殺した。
町の人々は恐怖に怯えた。森には決して近づかないように注意をした。しかし、その魔女が絶世の美女だと言われているうちに、町の男たちは一度拝んでみたいものだと見えない欲望を募らせていっていた。いくら女たちがきつく言っても聞かずに、夜な夜な家を抜け出す男が後を絶たなかった。
そうした男たちは二度と帰ってこなかった。それでも男たちは、まるで病気のように森へ入っていった。
このままでは町から若い男がいなくなってしまう。誰かに助けを求めようと何度も話が持ち上がったが、それを拒否したのは町の女たちだった。
彼女たちの言い分はこうだった。たとえどんな美女だろうと所詮は邪悪な魔物。そんな得体の知れないものに男たちが次々と誘惑されて殺されているなんて、外部の人間に知れることを恥だと思ったのだ。
被害が増えるにつれ、最初に夫を奪われて悲しみに暮れた女がなぜ自殺したのか、女たちは本当の理由を察した。彼女はその魔女を見たに違いない。
そして夫が自分の言うことも聞かずに魔女の言いなりになってしまったことが、何よりも彼女の心に深く傷をつけたのだろう。同士が増えた今なら、その気持ちを共感できる。
そしてその屈辱を何も知らない外の人間に晒し、魔女に伴侶を奪われた女として見られるのは耐えられないと強く主張したのだ。
町長は、命には代えられないと反論したが、家族や恋人を奪われた女たちの目は尋常ではなかった。これも呪いの一環だとしか思えなかった。このままでは町は滅ぶ。日に日に町人の不安は大きくなっていた。
そんなとき、気まぐれに町に宿泊していたクライセンが魔法使いだと知って、町長が森を調べてくれないかと話を持ちかけた。
もちろん彼が四代目の、とは知らずに。
クライセンは町長の意図が分かっていた。この町には優秀な魔法使いも腕に自信のある力自慢もいたのだが、そんな有望な若者をむざむざ魔女の餌食にするわけにもいかない。かと言って危険な場所に女性を送り込むのも不安だったのだ。
クライセンはどうせよそ者、帰ってこなかったとしても彼の素性も何も知らないし、事故で済ませればいい。今更被害者が一人増えたところで、町にとってはさほど問題はない。もちろん解決すれば謝礼は弾むつもりだった。
クライセンは意外にも快く依頼を引き受けた。どうせ退屈していたし、彼もまた絶世の美女とやらがどれだけ美しいものか見てみたかったのだ。それ以上も以下も興味はなかった。こっちもこの町がどうなろうと関係ない。それはお互い様だと、名も名乗らずに軽い気持ちで森へ向かっていった。
夜は深く、森の中は静かだった。大きな木々が茂り、月の光を遮っている。まるで絵画のような風景だった。確かにそこには神秘的な雰囲気が漂い、奥へ奥へと誘い込まれてその限りがないように感じられる。
クライセンは、魔女がいるからではないと思った。どうやら魔界との境がどこかで薄れているようだ。そこから魔界の空気が微かに流れ込んできている。何かがいる。クライセンは迷わずに奥へ進んでいくうちに、それが美女でも怪物でも、この際なんでもよくなってきていた。
一時間も歩いていると空が白み始めていた。ふと、足を止める。何かが転がっていた。男性の死体だった。木の根や草で埋まった道のない地面に無造作に投げ捨てられている。それほど古いものではなかったが、腐敗したそれには落ち葉が積もっていた。
クライセンはそれには近づかずに、辺りに気を集中する。どうやらあちこちに同じような死体があるようだ。魔女を求めて迷い込んだ男たちだろう。再び死体に目線を落とす。
(……淫魔、夢魔の類の仕業ではない)
もしそうならば、快楽に悶えながら事切れた救いようのない姿であるはずだ。死体の表情は、苦痛と恐怖で歪んでいた。その胸元には乾いた血がこびりついている。
(生きたまま心臓を抉られたか、致死量の血液を吸い取られている)
人間にできることではないのだけは分かる。
(哀れだな。魔性の女を求めて、命を顧みず勇気を出してきたのに……)そう思うと、口の端が上がる。(何やらとんでもない化け物に襲われて、気が狂うほどの恐怖の中で惨殺されるとはね)
クライセンは先に進む。この場でその正体を探る必要はなかった。すぐ、そこにいる。
何かに近づいてきた。その時、木々の向こうから声が聞こえてきた。クライセンは少し離れた木の影からその様子を伺った。
そこには一人の男がいた。ブランケルだった。
クライセンにはその風貌と身に纏う魔力で彼が魔界でも格の高い魔族だと分かった。その時はまだ、まさかこんなところに魔界の王がいるとまでは思わなかったが。
その向かいの岩場に女性が腰を降ろしていた。クライセンはまた、彼女が例の魔女だと一目で分かった。思いがけず、彼も一瞬でその美しさに目を奪われてしまったからだった。
予想以上だった。その容姿も宛ら、目の動きや指先の仕草、髪の毛一本までが完璧だった。これでは何の力もない人間の男なら抵抗する間もなく堕ちてしまうだろう。
本音では、自分なら例え淫魔に襲われても打ち払える自信があった。しかしこれほどとは、と思う。危険なほど「極上」だ。クライセンは平静を保ちながらそんなことを考えた。
魔女、アリエラは俯いていた。その前でブランケルが必死に彼女に語りかけていた。
「魔界へ戻ろう。こんなところにいつまでもいたら本当に死んでしまう」
どうやら彼女は酷く傷心しているようだった。魔族が人間界にいるだけで死に至ることはない。だが、憂い、悲しみに捕らわれ続けていると石になってしまうと言う。それは天使も同じだった。だからこそこの世界に絶望した天使たちは天上界へ帰っていったのだ。
「私は」彼女のその声にもまた、男を惑わす色があった。「ここを死に場所に選びます」
「そんなことを言わないでおくれ」
「私の心も体もエルフィア様のもの。そう永遠に誓いました。人間界で石になってしまえば私のこの忠義心と悲しみはずっと形に残るのです。それが私のできる彼への忠誠です」
アリエラには恋人がいた。相手は魔界の貴族、エルフィアだった。
「あいつは君を騙していたんだ」
「死者を侮辱しないでください。例え魔界の王であっても許されません」
「どうして私を信じてくれないんだ」
「愛する人を殺した男の言うことなど……」
「殺してなんかいない。あいつは私を陥れるために自殺したんだ」
「同じこと。あなたはいずれ彼を殺していた」
「ほら、君はそうやって頑なにエルフィアを庇うんだ。あいつの思い通りに操られている。エルフィアは王の座を狙い、君を利用して私を引き摺り下ろそうと企んでいたんだ」
「彼は確かに野心家でした。でも王の座を狙うことに私は関係ありません。私に何の価値がありましょう」
「私が君を愛しているからだ」ブランケルはきっぱりと言い切った。「私にはそれがすべてなんだ」
アリエラは無表情でブランケルを見つめる。その目は空ろだった。ブランケルにはその視線は痛いものだった。呪いで正気を失っているその目そのものだったのだから。
「私に色目を使う男はみんなそう言いました。だけど真実などどこにもありませんでした。私は淫魔。それでいいのです。男に快楽を、夢を与える。持って生まれる色はそのためだけのもの。愛など無縁な生き物なのです」
「違う」
ブランケルが素早く否定するが、アリエラはそれに被せてくる。
「エルフィア様は、そんな私を必要としてくれました。それは陰謀だったかもしれない。それでも私は彼の役に立てるならそれでもいいと思ったのです」
「それは君が奴の呪いにかけられているからじゃないか。あいつは君を盾にして私を潰そうとしていただけだ。だから私はエルフィアを殺せなかったんだ。本当は殺しても足りないくらい憎くて仕方がない。だけど、私はそれ以上に君を愛している。君を奴の薄汚い罠から救ってやりたいんだ」
「……どうしてこのまま死なせてくれないのですか」
「君はこんなところで、あんな男に騙されて死んでいい女性じゃない」
「では、王はどうすべきと?」
「私と結婚してくれ」ブランケルは迷わずに告げる。「そして魔界の女王となってずっと私の傍にいてくれ」
「…………」
「確かにエルフィアはもうあの狡賢い口を持たない。だが私は君をおいてどこにもいかないと約束する。何があっても君を悲しませない。絶対に幸せにする。だから、一緒に魔界へ帰ろう」
アリエラは真剣なブランケルを見つめた。そして目を伏せて、ふっと笑う。
「ほら」ブランケルはそれを見逃さなかった。「笑った。エルフィアは君を苦しませるが、私は笑わせることができる」
「……魔界の王ともあろうお方が、どうして私なんかにご執心されるのでしょうか。私はただの淫魔。望まなくても男は私の虜となる。本気で私を愛したと錯覚して、結局私の中で乾き死んだものもたくさんいました」
「私がそうだと? 私が他の男と同じく淫魔の魔力で正気を失っていると思うのか」
「そんな、恐れ多い。もしそこに本当の心がなければ、腕の中で死んでしまうのは私の方なのです。私はあなたの魔力に侵食されて灰になってしまうでしょう」
「それは、君が私に対する心がないということか」
「どうか……私たち淫魔を哀れんでください」アリエラは寂しく、微笑んだ。「あなたが愛したのは幻なのです」
「……何を言っているのか分かっているのか」
「どうぞ、偉大な王よ」アリエラは手を差し出した。「最期に、この幻を抱いてください。私は王にひと時の夢を与えた淫魔として喜んで灰になりましょう。きっと、石になるよりも光栄なことでしょう。あなたに感謝します」
アリエラは目を伏せる。ブランケルはその手を見つめて動かない。微かに震えている。怒りと悲しみが内で湧き上がっていた。しかし、それを飲み込み、絞り出すように声を出す。
「……私は、君に心がない限り、指一本触れる気はない……殺すなら、ひと思いにその首を落としている。本当なら今君のしていることは八つ裂きに値する行為だ……だが、なぜだろうな。どうしても君の笑った顔が見たいという思いが私をここに留まらせるんだ」
アリエラは顔をあげ、手を引く。
「悔しいんだ。君が正気なら私も、ここまで言われてしまっては身を引くしかない。だが、君はまだエルフィアの呪縛から解放されていない。私には何もできないのか。私の心は届かないまま、君が石になってしまうのを見ていることしかできないのか」
アリエラの表情が動いた。迷いが生じた。
「ここに……」訊かずにはいられない。「あなたにとって一体何があるのでしょう」
ブランケルの深紅の鋭い瞳がアリエラの心を貫いた。アリエラは圧し込まれるように息を吸い込んだ。
「私が唯一、永遠に愛するに相応しい者がいる。私は魔界の王だ。幻想を見抜く眼くらい持っている。美女を隣に座らせる優越感も、欲求を満たしてくれるものも何もかも、そんなものは余るほど持ち合わせている。だけどここには、そんな私が欲しい唯一つのものがある。愛しくて仕方ない一人の女性だ」
「……なぜ、私なのでしょう」
「理由などない。ただ、こんな気持ちは初めてだ。そしてもう二度とない」
切実なブランケルをアリエラは見つめ返した。その深い闇の色の瞳にはいろんな想いが宿っていた。次第に彼女が捕らわれていた、見えない鎖が解かれ始めていた。そして真実を受け入れることで、アリエラの中に後悔が押し寄せてきた。それは、ここで死のうなどと考えた自分の愚かさへのものだった。
ブランケルはもう少しだと気づいていた。もう少しで彼女の呪縛が解けそうなのを感じ取っていた。だが、これ以上どうすればいいのか分からなかった。殺すことは簡単なのに、と思う。救うことの大変さとそれに必要な力が、どれだけ繊細で、そこに強さなどは無意味であることを初めて知ることになった。
淫魔は男性をインキュバス、女性がサキュバスと言う二つの名前で呼ばれていた。
異性を惑わし性交によって相手の生気を吸い取り支配する魔物だった。
性の虜となり奴隷になる者、廃人になる者、正気を失い死に至る者もいた。人間の間では夢魔、悪夢とも言われている。性を象徴とする淫魔が魅惑的な姿をしているのは当然のことだった。その中でもアリエラとエルフィアは特に美しい容姿を生まれ持っていた。
エルフィアは紫がかった長い黒髪と、血のように毒々しい赤い二つの角を持っていた。まばらにかかる前髪の間からは、異性の心を捕らえて離さない、アリエラと同じ漆黒の瞳が見え隠れしていた。それに見つめられて逃れられる女性はいないと言われていた。逆に魔界の男性のほとんどからは疎ましく思われる存在だった。ブランケルもエルフィアに嫌悪を抱く者の一人だった。
ブランケルとアリエラが初めて出会ったのは、魔界の貴族たちが集まるパーティだった。そこにエルフィアが彼女を連れてきたのがきっかけで、ブランケルはアリエラに一目ぼれしてしまったのだ。その時はまだエルフィアとアリエラは恋人でも何でもなく、ただの同族のつれあいにしか過ぎなかった。
アリエラはエルフィアがなぜここに自分を連れてきたのか、その時はまだ分からなかった。しかし、魔界の王であるブランケルに熱心に口説かれて悪い気はしなかった。
その頃からブランケルとエルフィアの、アリエラの奪い合いが始まった。アリエラからすればどちらも自分より遥かに強い魔力の持ち主であり、身分も名もない一介の魔族である彼女としては名誉な争いだった。
それから周囲の魔族たちは彼女に一目置くことになった。これほどの美しさなら納得がいくと騒がれ、女たちには羨ましがられた。
アリエラはそんな羨望の眼差しに気取られることはなかった。魔界では「持つ者」が上に立つ世界。アリエラの美しさと、それを包む魔力なら当然の扱いであった。
誰もがヴァンパイアとインキュバスの対決に興味を示した。早いもの勝ちか、力ずくかと二人の出方は傍観された。的となったアリエラはブランケルのしもべとなるか、エルフィアの奴隷となるか、二つに一つだと思われた。どちらにしても、力を持つ者に選ばれて永遠に仕えることは魔族にとって光栄なことだった。アリエラもそのつもりでいた。
だがブランケルは決して彼女を魔力や権力で支配しようとはしなかった。それがアリエラ始め、周囲の者を戸惑わせた。
ただアリエラを城に呼んではただ食事をしたり面白い話を聞かせたりするだけだった。それ以上、何も求めようとはしなかった。アリエラも彼とのそんな時間を素直に楽しむようになっていた。それだけでなく、人の上に立つ器と共に子供っぽい笑顔を持っているブランケルに純粋に惹かれていった。
周囲にはそんな二人の気持ちが全く理解できなかったが、このまま二人が結婚するものだろうと誰もが思い始めていた。魔界中が注目していたブランケルとエルフィアの争いは、盛り上がることなく終わろうとしていた。
しかしエルフィアはただそれを傍観していたわけではなかった。彼はブランケルが淫魔の魔力に毒される男ではないと悟っていた。
二人がお互いに心を開き、愛し合うその時を待っていたのだ。エルフィアはアリエラと同じ淫魔。誰も知らない生態を自覚していた。それは、本当に愛し合う者同士なら淫魔の呪いが無効化されることだった。
アリエラは自分がブランケルを愛し、そして彼もまた自分を守ってくれると確信した。
その時を待っていたかのように、今まで黙っていたエルフィアは彼女を襲った。アリエラの抵抗空しく、彼女の心はエルフィアの魔力で打ち砕かれてしまった。
その日からアリエラは二度とブランケルの元を訪れることなく、エルフィアの支配下に堕ちた。
それを知ったブランケルは怒りを抑え、今度は自分から彼女の元へ通った。だがそこに今までのアリエラはいなかった。それでも虚ろで自分の話など聞きもしない彼女を変わらず口説き続けた。
どんなに冷たくあしらわれても、決して彼女の首筋に牙を立てようとせずに。すべてがエルフィアのシナリオ通りだった。彼はアリエラを利用してブランケルを討つつもりでいたのだ。
ブランケルは分かっていた。淫魔如きの陰謀など。そんなことはどうでもよかった。ただアリエラに真実を知って欲しいと、それだけを願っていた。
エルフィアを殺すことは簡単だった。だが彼を殺したところで心を支配されているアリエラが救われるわけではない。
ブランケルは苦悩していた。そんな彼の姿を嘲る者もいた。王は力を失ったと、ここぞとばかりに闇討ちする魔族もいた。しかしそのすべてが返り討ちにされるうちに、ブランケルが正気であることだけは認識された。
王の不甲斐ない態度に苛立ちを感じた眷属や近しい貴族たちに「なぜエルフィアを殺さないのだ」と責め立てられることもあった。
ブランケルはそんな声も無視して、ただアリエラの身だけを案じて止まなかった。
エルフィアは機が熟したと確信した。アリエラを盾にすればブランケルを討てる、そう思った。彼の計画はすべて思い通りに進んでいた。
ただ一つの誤算を除いては──。
3
それは実に初歩的で、すべての基本となる単純なことだった。
ブランケルがエルフィアより強い魔力を持っていたことである。
エルフィアもそれは十分承知していた。だからこそアリエラを利用していたのだから。だが、その差はエルフィアが思うよりも遥かに上回っていたのだった。ブランケルが身動きひとつ取れない状態でも、エルフィアほどの魔族さえまったく及ばなかったのだ。勝てない。これが魔界の王、魔族の支配者の力だと、思い知らざるを得なかった。
自らの無力さと考えの浅はかさに打ち砕かれ、エルフィアは敗北を認めた。だがブランケルはそれでもエルフィアを殺そうとはしなかった。アリエラを解放しろと、それだけを要求した。そうすれば生かしてやる、二度と自分とアリエラに近づきさえしなければ今までの地位も奪わないと約束した。
エルフィアはその条件を飲まなかった。ただで死ぬつもりはない──エルフィアは先を見越し、ブランケルをさらに苦しめるために自らの命を絶ったのだ。
エルフィアの思い通り、主人を失ったアリエラは絶望し、ブランケルを恨んだ。
彼の話も説得も聞こうとはせずに、それどころか仇への復讐のように人間界へ逃げ込み、自分の屍を晒そうとしていたのだ。
ブランケルはそれを追って彼女を救おうとしていた。彼女の意志で魔界へ帰ってきてくれること、そしてできることなら自分の傍にいてくれることを願っていた。
そのためなら何を犠牲にしても構わないと思った。王という立場も、命のすべても。
アリエラはそんな彼の気持ちを理解していた。だが心が簡単には受け入れようとはしなかったのだ。それはエルフィアの呪縛がそうさせているのだと、次第に気づき始めていた。だが自分ではどうすることもできなかった。
そんな葛藤を時間と共に少しずつ溶かしたのは、他ならぬ魔界にはない太陽の光だった。魔力を中和し、浄化する太陽の光がエルフィアの鎖を緩めていた。
二人はそれに気づいていなかったが、僅かではあるが確実に、ブランケルとアリエラの間にある壁や距離が薄らぎ始めていた。
だからブランケルは諦め切れなかった。あまり時間はなかった。アリエラが石になってしまってからでは意味がないのだ。呪縛とは解けばいいものではない。その先に何があるかが重要だ。だからこそ、ブランケルは彼女を無理やり力でねじ伏せようとはしなかったのだ。
慣れない二人には太陽の光は眩しく、体を焼くような刺激があった。日に当たっている時間が続けば続くほど魔力が低下しているのを感じていた。
だが消失しているわけではない。魔界に帰れば元に戻る。ブランケルはそう思いながら耐えていた。その光が邪悪な呪いを解くものとは知らずに。
アリエラはふと太陽を見上げた。無意識に、木々の間から漏れる恵みの光を自ら求めた。
目を閉じても視界は白かった。その先には出口があった、そう感じた。
疎ましかった光に身を委ねた。体が軽くなった。目を開き、その目でブランケルを見つめた。
そこに映った彼は、今までとはまるで別人のように見えた。錯覚、ではなかった。二人の間にあった、あと少しだった壁が、まるで霧が晴れるように消えていった瞬間だった。
それは深く長い眠りから覚めたような感覚だった。虚ろだった目に光が戻った。
ブランケルにもそれがはっきりと見えた。自然と表情が緩んでいた。アリエラは優しい顔で何度か瞬きをした。愛する人の顔をその目で確認するように。
アリエラはまるで花が咲くように、純粋な笑顔を浮かべた。ブランケルはその意味をすぐに理解した。
「あなたの言葉はこの心に届きました」だが、その微笑みには悲しみが交差していた。「……でも、もう手遅れなのです」
ブランケルは途端に青ざめ、背筋を凍らせた。
「私の体は既に石になりかけています。もうあなたの元へ寄るための足が動かないのです……」
ブランケルは驚いて彼女に近づき、自分の目を疑った。
信じたくなかった。アリエラの黒いドレスから覗く美しい足が白く固まっていたのだ。
ブランケルは愕然とした。体の力が抜けていく。なぜもっと早く気が付かなかったんだろう。今この時まで、彼女は自分が思っている以上に苦しんでいたのだ。眉を寄せ、震えている。
「……私が抱えて連れて帰るよ」
「いいえ。もうこれは止められません。石化した女を妻になど、あなたにこれ以上恥をかかせるわけにはいきません」
「愛する女を妻にして、何が恥か」
「いいえ」その声は弱々しかった。「いいえ……」
アリエラの頬に涙が伝った。
「泣かないでくれ。私の前で悲しまないでくれ」
「いいえ、私は喜んでいるのです。最期にあなたの愛を受け取れたことを。この幸せはあの世でエルフィアに伝えます」
「だめだ。君が動かないなら私もここに留まる。君の隣で石になり、永遠に一緒にいよう」
ブランケルは必死になった。アリエラはふふっと笑った。相変わらず子供のようなことを、とでも言っているように。涙が溢れ出し、顔を両手で覆った。
「嬉しい……ありがとう」
「アリエラ……」
ブランケルは彼女の本当の笑顔を取り戻せたことで、本当にここで石になっても構わないと思った。それをアリエラが望んでいないこともどこかで感じながら。
ひとつ区切りが付いたその時、隠れていたクライセンが二人の背後から姿を現した。二人は同時に顔をあげ、彼に注目する。今までの空間は壊れた。
「誰だ!」ブランケルの形相が一変する。「また彼女の魔力に誘われてきた愚かな人間か」
「なるほどね」クライセンもその魔力を青い瞳に灯した。「誘い込まれた人間を殺していたのはあんただったか」
「魔法使いか」ブランケルはクライセンに向き合い。「何しに来た」
「ここは人間の世界だ。人間がいて悪いか」
二人は出会い頭で一触即発だった。お互い魔力をぶつけ合い、その強さを確認していた。気を抜いたほうが負ける。アリエラは涙を拭って不安に染まった。そこから逃げようとするが、足が動かず肩を揺らす。
「ちょっとした散歩のつもりだったんだけど」クライセンは歯を見せて。「まさか魔界の王に会えるとはね。光栄至極」
「人間如きが」ブランケル目が柘榴色に染まっていく。「この私を愚弄するか」
その顔は、先ほどまでの優しいそれとは別人だった。瞳を赤々と燃やし、尖った牙が更に鋭くなっている。だが、内心では怯えていた。
クライセンから感じる魔力は人間のものとは思えないほど強大だったからだ。それだけならブランケルも劣りはしない。だが今は太陽の光で魔力が低下している。そして、今まで誰にも隠していたが、エルフィアに切り刻まれた傷がまだ衣服の下で疼いていたのだ。
何よりも背後に守るべき、身動きの取れないアリエラがいる。それでもブランケルは既に戦うことを考えていた。果たして魔界の王の力を持ってしても、彼女を守りながらこの男を倒すことができるだろうかと、僅かな迷いを抱きながら。。
クライセンは彼のそんな心配を読み取ったかのように、不適な笑みを浮かべた。
「助けてやろうか」
「……何だと」
「彼女の」クライセンはアリエラを目線で指しながら。「石の呪い。私なら解ける」
ブランケルは戸惑った。なぜ、と思う。クライセンはそう言いながらも容赦なくブランケルに敵意を放ってくる。
何を考えている? それに、本当だろうか。本当にこの石の呪いを解けるのだろうか。
そもそも彼は一体何者なのだ。何から問うべきか、それとも問うべきではないのか。迷っている時間はあまりなかった。
焦りを隠すブランケルに、クライセンから切り出す。
「ただし、私と戦え」
「!」
そう言ってクライセンは胸元からリヴィオラを取り出して、ちらりと見せた。ブランケルは息を飲む。
「そうか」そして、笑い。「ジェナスラジェル(太陽の石を持つ者)。それなら納得がいく。私の相手にとっても不足はない」
「話が早いね」
「本気で相手をしてやろう。だが、その前に彼女の呪いを解くんだ」
クライセンは少し間をおき、ふっと笑う。
「……それじゃ面白くないだろう?」
「何?」
ブランケルの顔から笑みが消えた。しばらく考え、眉を寄せる。
「貴様……そうか」再びその目に怒りを灯す。「所詮はただの人間。彼女に心を奪われたな。私を倒して彼女をものにするつもりか」
「下種な言い方をしないでくれ。これはどちらかが死ぬ戦いだ。私は純粋に君と戦いたいんだ。魔族と人間の力比べだ」
クライセンは次第に声が大きくなってくる。
「それに伴う犠牲と、栄光。彼女はそれに相応しい。完璧だ。完璧な戦いの舞台だ。私はとても高揚している。野暮な話はこれ以上不要だ。さあ、始めよう」
クライセンの放つ殺気にブランケルは一瞬飲まれた。これが本当に人間かとまで思った。
クライセンは酷く渇望していた。ここに彼の欲しいものが揃っていたのだ。
ブランケルはクライセンが普通ではないと感じた。弱く、寿命の短いはずの人間がなぜこんなにも「欲望に餓えて」いるのか、理解し難かった。
欲望を満たそうとする人間ならではの渇きではなかった。彼は欲望そのものを求めていたのだ。こんな人間がいるのかと戸惑った。
負ければ殺される。受けなければアリエラは石になってしまう。いくらクライセンが彼女に惹かれていたとしても、それはこの条件の中での魅力に過ぎなかった。仮にただ受け渡されてしまっても、彼はきっとアリエラを平気で見殺しにするのだろう。
「なんという闘争心」ブランケルは迷いを振り切った。「だが魔族が人間になど屈するものか。受けてたつ」
*****
クライセンはそこまでを簡潔に話した。その時の情景を思い出しながら。
「ブランケルとの戦いは互角だった。私は宇宙の法則から錬成した『アスラ』を、彼は魔界から召還したヴァンパイアの宝刀『グレゲートの牙』と言う、お互い最強の剣を持って戦った」
それは一瞬のようで、何年も続いたような気がした。実際は数日だった。
気が付くと森は半壊し、原型を留めていなかった。真ん中に、ただ佇んだアリエラだけがそこにいた。
「そうだ」トールが呟く。「聞いたことがある。失われた魔女の森。邪悪な魔女を倒すために魔法使いが戦い、争いに巻き込まれて形を失ってしまった森があると。しかし人が中に入ったときはもうそこには誰もいず、証言もあやふやで真実は確証されなかった。それにもう古い話で、古書の文献に小さく載せられているだけでその事実さえあまり知る者はいない話だ」
その真実が今ここで明かされる。
クライセンは続けた。
4
二人の魔力は尽きかけていた。もうすぐ決着がつく。
二人の脳裏に新たな未来のひとつが過ぎった。相打ち──それも悪くない、とクライセンは思った。だがブランケルは違う。彼女をここにおいて逝くわけにはいかない。アリエラをこれ以上悲しませるわけにはいかないと強く思った。
やっと手に入れた、目前にあった幸せが今度こそ完全に闇に落ちる。それだけは、と剣を大きく振り上げた。
だが皮肉なことに、その迷いと恐れが一瞬の隙を作った。
グレゲートの牙が持ち主の手を離れ、宙を舞う。ブランケルの喉元にアスラが突きつけられた。
赤い瞳にはクライセンの微笑が映った。ぞっとした。その背後に、体を縮めて怯えたアリエラがいた。そんな彼女をブランケルの視界から遮るように、グレゲートの牙が回転しながら降ってきて、クライセンの背後の地面に突き刺さる。
「こんなものか」クライセンは目を細めた。「意外とあっけないな」
「つまらないか」ブランケルは力を振り絞り、睨み付ける。「その手に力を入れさえすればお前は魔界の王を殺し、魔界一の美女を手に入れることができる。何が不満だ」
「そうだな。確かにこの上ない功績だ。だが、君は私を失望させた」
「何だと」
「君の心はここになかった」
ブランケルは隙に付け込まれ、目じりを揺らす。
「色ボケした吸血鬼を殺すことに価値はあるんだろうか」
「貴様……どこまで私を侮辱する」
「そう怒るなよ」クライセンはいやらしい笑みを浮かべて。「私は今ここで剣を下ろし、君を見逃してあげることもできるんだよ」
「さっさと殺せ」
「怖いか?」
「黙れ!」
クライセンは笑った。ブランケルは歯を剥き出すが、彼の異常な狂気に寒気を感じた。
人間じゃない、そう思った。目的をはっきりさせて襲ってくる魔物の方がよっぽど分かり易い。この男からは心が感じられなかった。口ではからかって見逃すなどと言うが、そんなつもりは一切ないと分かる。
自分を殺した後、どうするつもりなのだろう。敵の死を弔うのか、それともヴァンパイアの血を浴びて歓喜に満ちるのか。そのどれも当てはまらない。想像もできなかった。
クライセンは剣を持つ手に力を入れる、入れようとした。
その時、アリエラが呟いた。
「やめて……」
二人はその声に意識を奪われた。
「やめて。その人を殺さないで」
ギシッ、と渇いた音が聞こえた。彼女は固まった足を必死で動かそうとしていた。
「や、やめろ。アリエラ」ブランケルが思わず叫んだ。「そんなことをしたら、折れて元には戻らなくなる」
クライセンは剣を突きつけたまま、肩越しに彼女を見つめた。アリエラは体を揺らし、倒れ、膝をつく。その衝撃で足にはヒビが入り、欠片が散った。
「アリエラ、やめるんだ」
アリエラは両手を付いて這い出す。手足が泥に塗れようと、黒いドレスが肌蹴ようと、崩れかける足に構わず進むことを止めなかった。
自ら望んで石になった者は神経が残ると言う。その苦痛は並大抵のものではないはずだ。彼女は呻きながらもその手を止めなかった。
「お願い。もう私のために、こんな歩くこともままならず地を這うことしかできない私のために血を流さないで」
アリエラの体の石化が速度を増し始めた。目の前で起こる争いは彼女にとって悲しく、空しいものだった。
男の戦いに口出しはしたくなかった。だが、もう限界だった。
止める方法があるとすれば、自分がいなくなってしまえばいいと、アリエラは死を覚悟していたのだ。いや、これは死などの安らぎなどではない。石になってしまえばその悲しみから永遠に解放されることはないだろう。生きながら身動きも取れず、体をバラバラに壊されても、ただその痛みを噛み締めることしか出来ないのだ。
それは永遠に生きられるはずの者に与えられた、命を粗末にした者への残酷な罰だった。アリエラは自分が何をしようとしていたのか、やっと気が付いた。だが、もう手遅れだった。すべてを受け入れる。
彼女の石化が腰まで進んだ。どんどん体は重くなる。
それでも這うことをやめなかった。もう這うことしかできなかったから、やめたくなかった。最期に少しでも彼の傍に近寄りたかった。涙が流れ出す。
「アリエラ!」
ブランケルはクライセンの剣を振り払って彼女に駆け寄った。膝を折り、アリエラの手を握る。
「……やっと」アリエラはその手を握り返し。「私に触れてくださいましたね」
アリエラはその手に、涙で濡れた唇を当てた。
「暖かい……」
そう呟く彼女の体は冷たくなっていく。
「もう、戦いを止めてくれますか?」
ブランケルは深く頷く。
「ああ」
「私が起こした争いは、私が死ぬことで終わるのですね」
「死ぬなんて言うんじゃない。聞きたくない。これは君が起こした争いなんかではない。君は何も悪くない。証しに、私が望みは何でも叶えるから」
「では、生きてください」アリエラは必死で微笑んだ。「あなたは死を望んだり、石になどならないでください。生きてください」
アリエラは胸の辺りまで石に包まれた。次第に声が小さくなる。
「私はここにいます。だから、悲しまないでください。私はとても幸せです。永遠に、ずっとここで……」
風が通り抜けるように、その姿は動かなくなった。
ブランケルを見つめた瞳は瞬きすらしない。深く美しかった漆黒の彼女のすべてが、白く硬い石になってしまった。
ブランケルは冷たくなったアリエラの手を握ったまま、現実を受け入れられないでいた。体の力が抜け、座り込む。そこには闘志の欠片もなかった。
クライセンが背後で剣を地面に突き刺しながら、ため息をつく。
「これで戦う理由がなくなったな」
ブランケルは項垂れたまま呟く。
「……滑稽か……笑えばいい。魔界の王は大切な女一人守れず、人間に剣を突きつけられた腑抜けだと」
変わり果てたブランケルの背中に、呆れたようにクライセンはため息を漏らした。
「その腑抜けは、これからどうする?」
「……ここにいる。彼女の隣で石になる」
「それじゃ、彼女との約束を破るだろう」
「私の約束はアリエラの傍にいることだ。彼女を一人にしないことなんだ。ここで石になってしまえば永遠に一緒にいられる」
「本気でそう思うのか。一緒にいられるなど、見た目はそうかもしれないが、実際はそんな単純なものではないと思うぞ」
「そんなことは百も承知だ。貴様の言葉など聞く耳持たぬ。去れ。まだ殺したいと思うなら殺せばいい。私はもう戦わない。抵抗もしない」
クライセンはブランケルの背中を見つめたまま。
「いや、私ももう気が失せた」クライセンはその場に腰を降ろした。「疲れたから、少し休んでいく」
「勝手にしろ」
ブランケルは二度と言葉を発さなかった。そしてクライセンも動かず、悲しみに包まれた恋人たちを見つめていた。本当は完全に石になったアリエラを元に戻すことはできた。だがブランケルはそれを請わなかった。だからクライセンも何もしなかった。
何時間が経ったのだろう。クライセンもまた、石のようにじっとしていた。
彼の青い瞳には手を取り見つめ合い、石と化した二人が写っていた。クライセンはその不思議な光景をいつまでも見つめていた。
二人はここで永遠に悲しみ、苦しみ続けるのだろう。いつか人に見つかってしまえば引き離され、身動きの取れない体は傷つけられて癒えない痛みに耐え続けなければいけないのかもしれない。
だが二人はそれを承知で自ら望んだ。その気持ちが理解できなかった。
何より、そんな哀れな二人が幸せそうに見えて仕方なかったのだ。
なせだ。クライセンは納得がいかずにイラついた。この内側からくる、ぶつけようのない怒りに似た感情は何だろう。
いっそこの手で二人を砕いてやりたい衝動さえあった。だがそんなことをしてもこの心の靄は消えやしないんだろうし、むしろそんな自分が惨めではないかと思った。
これは「嫉妬」──クライセンはやっと気が付いた。大切な人と出会い、守るために命をかける二人が羨ましかったのだ。
クライセンは目を閉じた。これ以上その姿を見せ付けられるのに耐えられなくなったように。生き残ったのは自分だと言うのに、何だろう、この敗北感は。
いや、これは空虚だ。もしかしたらブランケルより先にアリエラと出会っていたら、ここで石になっていたのは自分だったかもしれない。そんなことを考えた。だがそれもすぐに否定する。
自分は人間。石になどなれやしない。そうだ、ここにいていくら待っていても自分は石になどなれないんだ。
だからと言って、どこにも行くところはなかった。
クライセンはその時、改めて自分の孤独を噛み締めた。今まで人を求めたり、愛したことなどなかった。
彼にとって愛情などは人の生態の、子孫を残し育てるための本能が誘導するものだとしか思えなかった。クライセンには自分の子孫を残したいなどという欲求さえない。むしろ自分は滅ぶべきであり、戦争から生き延びてパライアスという大地に存在する意味すらないと思っていたのだ。
クライセンは今、この地上で誰よりも強い魔力を持っていた。どんな形でも人と関わりあったとき、そのすべてが脆弱に見えて仕方がなかった。彼の心を奪うものは何もなかった。欲しいものはすべて思い通りになり、難なく手に入る。
それが、どれだけ寂しいものなのかここで思い知ることとなった。
(……なぜだ。なぜこの男は、私に彼女を助けて欲しいと言わなかったのだろう)
それがブランケルの一番の望みだったのではないのか。
目の前に救いがあるのに、それに背を向けて永遠の苦しみに身を投じた。なぜだ。クライセンは繰り返した。彼のプライドが許さなかったのか。
いや、違う。手段を選ばなければプライドなどはいくらでも守れたはず。クライセンとブランケルは同等の戦いの末、例えどちらかが死んだとしても納得のいく結果が得られただろう。一体何が邪魔したのか、愚問だった。アリエラの存在だ。ブランケルのアリエラへの気持ちが男の戦いを邪魔したのだ。クライセンはそう思った。
(私なら……殺していただろうな)
どうせアリエラは死に掛けていたのだ。それでなくてもそもそも淫魔の一人くらい、魔王の力を持ってすればいくらでも思い通りにできるではないか。
ブランケルが命もプライドも捨ててまで守りたかったのは、手に入れたかったものは一体何なのだろう。
クライセンはふと、淫魔にまつわる逸話を思い出した。彼はこの世界のほとんどの本を読んでいた。すべてを常に覚えているわけではないが、記憶の引き出しを開ければ大体を思い出すことができる。その話は単なる小説だった。確か、そう。
(レスト・エティアラ)
本のタイトルだ。おそらくその言葉の意味を知る者は少ないだろう。魔界の言葉だったのだから。
退屈な小説だった。ある人間の男が淫魔に恋をした。その男のサキュバスに対する切な思いが長々と書き綴られていた。自分は決して淫魔の魔力に惑わされているわけではないことを強調するように。その物語の結末は、最後まで読み手を白けさせるものだった。
『二人は結ばれた。
男の純粋な気持ちは淫魔の呪いを跳ね除けた。
男は彼女の支配下には堕ちず、彼女もまた灰になり散ることもなかった。
二人は人知れず、いつまでも幸せに暮らした』
馬鹿馬鹿しい。そう思った。もしかするとそれはどこかであった本当の話なのかもしれない。だとしても何だと言うのだ。淫魔は淫魔らしく異性を食い漁っていればいいじゃないか。食われた者も、一夜とは言え悦い思いを味わっているのだ。その代償に廃人になるのなら本望だろう。なぜその流れに逆らおうとするのだ。
その時はそう思った。だが、男がなぜそれを書き残そうと思ったのか、今なら分かるような気がした。
(純粋で一途な真実の愛、か)
胸焼けがした。それがやり切れない「愛」とやらに対してなのか、それとも理解できない自分に対してなのか分からなかった。いや、理解できないのではない。理解しようとしていないのだ。なぜならそれを一度も近くに感じたことがなかったからだ。欲しいものは手に入れてきた。すべてが思い通りになってきた。だが、なぜそれだけがここにないのだろう。もしかして。
(私には、必要のないものなのだろうか)
それとも、どれだけの力を持ってしても、唯一自分が支配できないものなのか。
知りたくなかった。気づきたくなかった。それでもこの怒りや苛立ちをぶつける的はどこにもない。それはいくら探しても見つからないだろうし、自分が脆弱だと見下していた人間の誰もが持っているものなのかもしれない。
きっとアンミール人はこういった解決できないものを抱え、それと戦いながら短い人生を送っているのだろう。なんて遠い。そう思った。自分は今、一体どこにいるのだろう。どこに行けばいいのだろう。
その時、クライセンの耳の奥に何かが聞こえた。優しい女性の声だった。それに神経を集中すると、言葉を聞き取れる。
(……可哀想な人)
何が起こったのか分からなかった。その声は、アリエラのものだった。クライセンは少し顔を上げる。やはり二人は石のままだった。錯覚だとしか思えなかった。それでも自然と耳を澄ます。
(哀れだとは思うけど、私にはあなたは愛せない)
──何を言っている。
(あなたにとって私は飾りでしかない。力で手に入れたものはいずれ壊れます。それは本当の愛ではないのです)
──聞きたくない。
(そして愛とは許すこと、必要とすることでもありません)
──私には分からない。
(出会うこと、選ぶことです。この星の数ほどの流れゆく命と、止まることのない時間の中で、宇宙から見ればほんの僅か、たった二人が心を通わせること。他愛ないことでもそれは限りなく奇跡に近いのです)
──もういい。やめてくれ。
(あなたにもその僅かは必ずあります。知る権利はすべての命に平等なのです。そう、私のような淫魔にすら訪れるのですから。奇跡は起きます。あなたが求める限り……だから、あなたにも生きて欲しいと心から思っています)
声はそこで途切れた。自らが遮ったのか、彼女が沈黙したのかは区別できない。クライセンにはその幻聴の意味を理解できなかった。今は、まだ。
クライセンは呪縛を解き放って、立ち上がった。ゆっくりと両手を空に向けた。目を閉じ、呪文を唱える。
半壊した森がピクリと動いた、ような気がした。木々は無残に傷ついて倒れていた。炎上したもの、根元から折れてしまっているもの、真っ二つに割れているもの、様々だった。だが森は憂いてはいなかった。偉大なる魔法使いを称えていた。
「……私はお前たちが思うような人間ではないよ」
クライセンは森の祝福を受けながら、そう呟いた。
「これは救いではない。哀れみでもない……孤独に捕らわれ、行き場も見出せない私の復讐だ」
ブランケルとアリエラがぼんやり光に包まれた。
二人を中心に、銀の粉が蛍のように舞い踊った。クライセンは目を薄く開け、力が抜けたように手を下ろす。
森全体に飛び交う光の粉は次第に数が増えて、後から後から空に吸い込まれていく。視界がぼやけて見えた。
クライセンは最後まで見届けず、二人に背を向けて森から立ち去っていった。
5
「私は二度とその森には近づかなかった」クライセンは低く呟く。「一年後に二人が魔界で結婚して一人の娘を授かったと、噂好きの父から聞いた。私はもう二人への興味はなくなっていたし、二度と会うこともないだろうと心の中で祝福しておいた。だが、運命とは妙なものだ。こうして二人の間に生まれた娘と共に、同じ時間を過ごしているとはね……」
クライセンはその時のことを思い出し、つい零れそうになる本音を抑えながら起きた事実だけを順を追って語っていった。締め括るように口を結ぶ。
室内は静まり返った。話に対する感想よりも気になることがある。他ならぬティシラのことだった。ティシラは呆然として、瞬きもせずに固まっている。まだ内容を理解できないでいる様子だ。誰も口を開かない。誰かと目が合っては無言で助けを求め、逸らすを何度か繰り返す。
マルシオはその間に耐えられなくなった。
「……なんで」その声は震えていた。「そんな話をするんだ」
クライセンは目だけを動かし、素知らぬ顔をする。
「退屈だった?」
「ふざけるな」マルシオはテーブルを殴りつけて。「ティシラの気持ちを知ってて、無神経だろ」
「本当のことだ。隠す必要もないだろう」
「確かに、ティシラはバカだし勘違いだし、あんたはぜんぜん相手にするつもりもないのかもしれないけど……こいつは本気だった。あんたのためにここまで来たんじゃないか」
「いつか結果は出るものだ。それがいつだろうと、どんな状況だろうと」
「もっと、違う形とか言葉とかなかったのかよ。しかもこんな人前で、何の脈絡もなく……いくら何でも酷すぎるだろ」
「彼女が本気だったなら尚更だ。生憎と私は、こういうのはどうも不器用でね。傷つけたなら謝るよ」
「だからって、今じゃなくてもいいだろ」
「死んでからじゃ気の毒だ」
「そんなこと……」
マルシオは言葉を飲んだ。死──そうか、この船がパラ・オールに着いたら……いろんな可能性でそれが待っている。だけど、と思いながらマルシオはティシラを見る。
まだ固まったままだった。頭を抱える。かける言葉が何も思いつかない。彼女にとって恋愛は生き甲斐だった。それを踏みにじられてしまったら、もし自分なら耐えられないと思う。
きっとティシラはもうここには居られない。自分もそんな彼女を置いて、何もなかったようにクライセンについていける自信はなかった。友の心を傷つけた彼を憎み、蔑むだろう。トールは分からないが、そうなると彼女を主人とするワイゾンも離れ、その手下もマイとキジも降りることになる。
ここで終わってしまうのか。いざこの時が来てしまうとたかが恋愛だとは言えなかった。それぞれに様々な思いを抱いて彼の元に集っている。命を懸ける覚悟でここまで来たのに。もうすぐ一つの終焉に近づいているのに……他の者も同じ気持ちで不安に染まっていた。
トールがその中で眉を寄せていた。まさか、自分のせいなのかと後悔していた。先日、クライセンを焚きつけ、感情を煽った。それが行動を起こさせてしまったのなら謝らなければいけないのは、自分だ。
(……これでいい)クライセンは目線を落とす。(遅すぎたくらいだ)
ティシラの言葉を待つ。微かに空気が揺れ、一同が注目する。
「それって」ティシラは無表情だった。「クライセン様は、ママが好きだったって事ですか?」
クライセンはティシラの目を見て、迷わずに答える。
「そうだよ」
決してからかってなどいなかった。真正面から向き合っている。ティシラもその目を逸らさない。
「パパを殺そうとした?」
「そうだよ」
「でも、助けてくれた?」
クライセンの顔色が変わった。
「だから私が生まれた」ティシラの表情がふっと緩んだ。「……だから、あなたに会えたんですね」
ティシラは優しく微笑んだ。決して恨んでなどいなかった。すべてが許せるほど彼のことが好きだったのだ。代わりに一同の胸が痛んだ。切ない、と思った。緊張から不安の空気に変化していった。後はティシラがどうするか、それによって皆の進路が決まる。ただ、今まで通りとはいかないだろう。元々は無理やり付いてきていたのだし、クライセンが仲間などを必要としているわけでもなかった。
絆は切れた。皆がそう思った。
再びしんとなる。この思い空気をどうにかする役目をそれぞれが放棄していた。誰かが席を立てばそれについていくのが精一杯だった。
最初に立ち上がったのは、ティシラだった。彼女は俯き、肩を揺らしている。こみ上げる何かを我慢しているのが伝わる。その小さな体を、同情でも抱きしめてあげたくなる。
しかし、その必要はなかった。こみ上げる何かとは、涙でも悲しみでもなかったのだ。
この中でティシラ一人だけが皆とは全く違う方向を向いていたことに、今の今まで誰も気が付かなかった。
「……凄い」
ティシラは漏らすように呟く。
「凄い!」そう繰り返し、顔を上げた彼女はなぜか笑顔だった。「これって、運命だわ」
ティシラは胸の前で手を組み、目を輝かせていた。一同は何が起きたのかすぐには理解できずに目が点になっている。ティシラはそれに見向きもせずに一人でテンションを上げていく。
「あの魔界最強のパパを追い詰めるなんて、やっぱりクライセン様ってかっこいい。そんな二人を争わせるなんてママも凄い。さすが魔界一の美女、さすが私のママ。それにパパも凄い。愛を貫いて、命を懸けてママをやっと手に入れたのね。かっこいい。素敵だわ」
強がりでも何でもなく、ティシラは本気で心底感動していた。空気を読む気は皆無だった。
「でもパパもママも酷いわ。こんないい話を黙ってるなんて。きっとパパが妬きもちを妬いてるのね。道理でクライセン様のことを悪く言うはずだわ。男のくせに嫉妬深いんだから。まあ、ママがあれだけいい女だといろいろ大変なのかしら。今でもママに見とれる男がいるだけで目玉を抉ろうとするんだから。だけどそんな素敵なエピソードがあるならパパの気持ちが分かるわ。できればもっとドンと構えててくれた方がかっこいいんだけどな」
さすがのクライセンも困っていた。そんな彼にティシラは満面の笑みを向ける。
「これって運命ですよね。私、生まれる前からあなたを好きになるって決まってたんですよ。確信しました。もう、早く言ってくれればよかったのに!」
クライセンは絶句している。マルシオにはティシラの能天気ぶりより、彼のその表情の方が貴重に見えた。
ティシラは一向に構わず、うっとりとした顔で妄想に浸っている。どうやら目測誤りだったようだ。
魔族と言うだけで感覚が違う。それだけでなく、ティシラはその中でも抜きん出て「変り種」であることを思い知る。
アリエラを自分の目標、憧れとしているティシラは、母親である彼女がライバルであることにまったく抵抗はなかった。それどころか名誉にさえ感じ、その思いはさらに良い方に向かってしまったらしい。
唖然とする一同の中で、トールがいきなり笑い出した。それに釣られてワイゾンやマイ、キジも顔を見合わせて笑った。マルシオも肩を落として、乾いた笑顔を浮かべる。
ティシラは逆にとぼけた顔になった。みんながなぜ笑っているのか分からない。
クライセンは目を細めて、分が悪そうに立ち上がり、さっさと室を出て行った。
「クライセン様」
ティシラが呼ぶが、無視して行ってしまった。その背中を見送って、まだ笑っている周囲を見回した。
「何で笑ってるの?」
「安心したんだよ」トールが答える。「魔法王をあんなに困らせるなんて、確かに君は凄いよ」
結論は、裏切られる形で簡単に出た。何も変わらない。何があっても。
*****
その日の夜、クライセンは甲板の隅で海を眺めていた。海には不吉な気配が漂っていた。クライセンはパラ・オールが近づいてきているのを体で感じ取っていた。
トールも甲板に出てくる。クライセンの姿を見つけて近寄ってきた。
「ここにいたのか」
「また君か」クライセンは振り向かずに。「王子様談義はもう聞かないよ」
「それはもういいよ」トールもクライセンの隣で海を眺めた。「今は考えても無駄なようだ」
「こんなところにいていいのか」
「こんなところ?」
「おそらく国は戦場になっているだろう。王子ともあろうお方がお気楽にヘラヘラ笑ってるなんて、滅ぶのも時間の問題だな」
「それはそれで、出来の悪い王子を授かったと諦めてもらうしかない。もっとも、僕一人で揺れる国だとは思わないが」
「それは頼もしいことで」
トールは間をおき、クライセンに顔を向ける。
「彼女を悲しませようと思ったんだろ」
図星、だったが、クライセンが頷くわけがなかった。
「普通なら君の思い通りになっていただろうな。だが、普通ではなかった」
「……そうだな」
「もう手遅れだぞ」
「…………」
「彼女は当然、他の皆も、僕も引き返さない。本気で邪魔だと思うなら殺すしか方法はないのかもな」
「……考えとくよ」
それだけ言うと、クライセンはすっとその場を離れ、立ち去る。一人にしてくれ、と背中に書いてあった。
トールは海に向き直ってため息をついた。国のことを思い出す。もちろん気にならないはずがなかった。クライセンの言ったように戦が始まっているかもしれないし、きっと皆心配してる。
トールは何よりもある人物を気にかけた。トールの婚約者、ライザだった。
彼女も戦っている。無事だろうか。無茶をしなければいいが……本当は今すぐ帰りたかった。大切な人の傍にいて守りたかった。クライセンの語ったブランケルとアリエラの話を聞きながら、トールの脳裏には彼女の顔がちらついて仕方がなかった。
だが今の自分がそこにいたところで場凌ぎの慰めにしかならないと思っていた。人間として、男として、本当の意味で彼女を守れる力が欲しかった。その切実な思いは、彼に戦う勇気を与えていた。