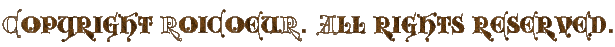第12章 茨の鎖





1
空は曇っていた。まるでこの先にある不吉な未来へ導くかのような暗さだった。シャルノロエスの甲板にはマイとキジ、船橋の上方の見張り台ではワイゾンが頬杖をついている。一同に会話はなかった。それと言うのもマイが今までにないほど機嫌が悪かったからだ。どうやらまだこの無茶な航海に対して不安があるようだ。ワイゾンとキジは用がない限り声を出さない。落ち着かない様子で常に体勢を変えるマイを横目で確認しながらビクついていた。
ワイゾンは霧でぼやけた水平線に目を移してため息をつく。マイの気持ちも分からないではなかったが、今はどうすることもできない。何も起こらないでくれと思う反面、いっそ海賊にでも出くわしたい気持ちもあった。それはそれで、この状況でも何とかなると証明してやりたかったのだ。なんとかなると言う根拠はなかった。が、なんとかなるような気がしたのだ。
おそらく自分のこんな行き当たりばったりな所が気に入らないんだろうなとも思う。今までも散々言われてきた。それでも何とかなってきたとは言え、マイに助けられたことも何度もあった。
ここにいる三人は生まれついての海賊だった。ワイゾンが独立したとき、弟分だったキジも彼についてきた。大飯食らいで怠け者ではあったがその大きな体には類稀なる怪力を秘めており、決して役に立たないわけではなかった。ドジを踏んでもそこに悪意はまったくなく、怒られれば半べそをかいて謝り倒す。一度は自分のミスで仲間を死なせてしまったときがあった。彼はけじめをつけたいと一週間の断食をした。だが加減を知らないキジは瀕死に至り、さらに周りの手を煩わせて余計に迷惑をかける始末だった。
今まで被られた損害は利益より大きいかもしれない。それでもワイゾンは彼を見捨てる気はまったくなかった。他の海賊頭ならさっさと捨てていたかもしれない。しかしワイゾンの考え方は利益一番ではなかった。この船の中に何かしら情のある者は快く受け入れてきた。それがいいか悪いかはそれぞれだった。無常過ぎて仲間に裏切られる海賊もいるが、出来の悪い船員に足を引っ張られて恥を晒す者もいる。結局は運だと思われた。海の上も社会であり、組織の固まりだったのだ。同じ人間である限りそのルールは陸と同じものだった。
ワイゾンに出会えたキジは運がいいとよく言われていた。ワイゾンは世話好きではないのだが、目を離すと何をしでかし、どこでどんな目に遭うか分からない彼を傍に置くことにした。その方が安心できた。キジはそんな彼の気も知らないまま、何も疑うことなくワイゾンに懐いてここに居着いていた。
一方マイは、ワイゾンがシャルノロエスを手に入れて数年後、立派な組織を作り上げてその名が海賊界に広がり始めた頃、海で漂っているところを拾われたのが出会いだった。
海の上での女のほとんどは「海姫」と呼ばれる海賊専門の慰安婦だった。海姫は船で産み落とされた者が多かったが、陸から浚われてきた者もいる。女たちは船の上には必要不可欠な存在であり、船員の一部として扱われていた。
だが口減らしのときには一番に捨てられ、物品との物々交換として敵に受け渡されることも珍しくはなかった。海姫は生き残っていくためにできるだけ強い男に気に入られる努力が必要だった。
そこには争いもあった。ただ男に媚を売っていればいいわけでもない。女同士の男の奪い合いもあれば、男女の関係の縺れや巧みな駆け引き、深く拗れてしまえば驚くほど簡単に心は鬼と化してしまう。そうなった女は、時に男よりも残酷になり醜く恐ろしい争いを起こす。それが海の女の戦いであり、生き方だった。
海姫は組織の「所有物」の印として刺青や焼印を入れられる。船の紋章であったりただの文字や数字であったり、それは様々だった。当然、いろんな理由であちこちに移動した女は印の数が多い。その数で海姫の価値が決まることはなかったが、それを見れば彼女がどこにいたのかが判断される。
死に掛けていたマイは露出の高い赤いドレスを身に纏っていた。波に揉まれて乱れていたが、長い髪を装飾品で高く結わえ、化粧の後が微かに残っていた。そして胸元には死を祝福する黒い薔薇の紋章がくっきりと焼き付けられていた。印はそのひとつだけだった。
ワイゾンはそれを見て寒気を感じた。まだ遭遇したことはなかったが、この紋章を掲げる海賊の噂は何度も耳にしたことがあったのだ。船の名はエンドローズ。総統の名はシャグラ。彼は情けのない残忍な男だと誰もが恐れていた。
マイがどんな扱いを受けてこんな目にあったのかはまだ分からない。相当水を飲んでおり、生きているのが不思議なほど衰弱していた。数日間の看病の末に彼女は目を覚ました。だがマイは奇跡の生還を喜びはしなかった。それどころか青ざめて震え出し、また海に身を投げ出そうとしたのだ。慌ててワイゾンが止めたものの、マイは「殺せ、死なせろ」と病み上がりの体で動けなくなるまで暴れていた。
ワイゾンは仕方なく彼女の腕を縛って、とにかく話を聞くことにした。マイは素直に会話をしようとしなかった。汚い言葉でワイゾンを罵り、自分を殺せと煽り続けていた。その様子に我慢できなくなった手下たちが剣を抜くこともあったが、ワイゾンは馬鹿を装いながら必死で仲裁した。
そんな時間が長く続くうちにマイは次第に大人しくなっていった。何を言っても怒らないし決して手を出そうともしない彼に疑問を抱き始めた。なぜ殺さないのかと聞いても殺す理由がないとしか答えない。ならば死なせてくれと言っても、自殺は裏切り行為だと許してくれなかった。そして、やっとマイは自分の素性とここまでの成り行きを話し始めた。
マイは物心ついたときからエンドローズで育てられてきた。美しい容姿を持って生まれてきた彼女は当然のようにシャグラの、「頭の女」の位置についた。
しかしマイにとっては地獄のような毎日だった。シャグラはマイを愛してると言うが、彼はどうしようもないサディストだったのだ。マイを「神経と感情のある人形」と称して心身を傷め続けた。周囲にはそれも運命だと言われた。きっとそのまま年を取っていくか、彼のいき過ぎの行為によって命を落とすまでそうしているしかないと思われていた。生まれながら苦痛を強いられた彼女にも、ある救いがあった。それは自分自身の中に生まれた憧れと夢だった。それは子供の頃から心の中に芽生えていた。
「海賊になりたい」
マイは強さを欲していた。おそらく目の前で罪のない人が惨殺されていくのを見ながら育った彼女は、恐怖や悲しみに打ち勝てる何かを手に入れたいと思ったのだろう。
そんなことを口にする彼女を周りは笑った。海姫も海賊の一種だった。だがマイはそうじゃないと、自分も剣を持って戦いたいのだと主張した。子供の戯言だとまったく相手にされなかった。正式に海姫として認められてから、その屈辱は日に日に増していった。それでも、どれだけ心を踏み躙られても、マイの中でその欲求だけは消えてなくなることはなかった。
彼女は海姫として教育されてきたにも拘わらず、男に頼ることをしようとしなかった。盾ではなく剣を欲しがった。恥を承知で何度もシャグラに剣を持たせて欲しいと言った。無駄なのは分かっていた。その度にシャグラに笑われ、皆の前で晒されることもあった。それでも諦められなかった。そしてこのまま人形として嬲られて生きていくくらいなら、とその身を海に投げたのだった。
マイは嵐の夜を選んだ。確実に死にたかった。だが、目を覚ましてしまった。せめて陸にでも打ち上げられればまだやり直すことができたかもしれない。なのに、その視界に映ったのはやはり海賊だった。気が狂いそうだった。場所が変わっただけで結局また違う男に同じ仕打ちを受けるしかないのだ。そう思ったことをマイはワイゾンに打ち明け、改めて死ぬことの許可をくれと申し出た。どんな死に方でもいい。
「生きていても仕方がない。これ以上は時間の無駄なのよ。さっさと死んで別のものに生まれ変わりたい。私は場所も時代も、性別さえも、すべてを間違えて生まれてきたの」
もうこの地獄から解放して欲しいと、マイは切実に頭を下げた。
そんな思いを他所に、ワイゾンは笑いながら彼女の縄を解いた。
「どうしてもと言うなら勝手に死んでくれ。だが、他に言いたいことがあるんじゃないのか」
マイはその言葉の意味をしばらく考えた。
「どうせ駄目元だと思ってるんだろ。死ぬほどの覚悟があるなら最後にやりたいことをやってみろ」
ワイゾンはマイの体に海姫の印を増やすことはしなかった。
それからマイが今の立場を確立するまでには幾多の問題と困難があった。当然、仲間に打ち解けるだけでも時間がかかった。それでもワイゾン始め、たくさんの仲間に支えられてマイは立ち直っていった。
しかし海姫と呼ばれることがなくなった今でも薔薇の紋章だけは消そうとしなかった。そこにどんな思いがあるのかは誰も知らない。マイはそれを抱えながら、誰もが認める立派な海賊になっていった。
そんなマイは、この状況がどうしても納得いかなかった。彼女にとってはロマンだの冒険だの、そんなものはどうでもよかったのだ。組織自体がなんとなくお気楽な雰囲気があった中、彼女だけが常に冷静だった。ワイゾンのやり方に逆らうつもりはない。だが、どこか間の抜けたこの男は定期的に喝を入れないととんでもないことをしでかす。アムジーでの出来事もそうだった。つい何も考えずについていってしまった自分のミスでもあると思う。後戻りできないなら頭であるワイゾンに従うしかなく、それで死ぬなら仕方ないと、自分が選んだ道だと腹は括っていた。
そしてほとんど奇跡に近かったが、僅か三人とは言え生き残ることができた。海へ帰ってきた。
一度は預けた命。生きている限り何度でもやり直せばいい。やり直すことができると、それを知ることができたのはワイゾンと出会えたからだということをマイは忘れたことがない。そして海賊らしい死に方ができればそれでいいと思っていた。それは物心ついたときから、今も変わらない。
2
緊迫した空気が数時間流れた。
ふっとワイゾンが体を起こす。目を細めて霧の中を見つめた。そして慌ただしく梯子に手を掛けながら大声を出す。
「海賊船だ!」
マイとキジも顔を上げる。素早く辺りを見回し、その視界に敵の船を捕らえた。ワイゾンは剣を抜きながら甲板に降り立った。改めて敵船を確認する。どうやら向こうもシャルノロエスを捉えているようだ。まっすぐこっちに向かってきている。逃げる気は一切なかった。同行者たちには迷惑をかけてしまうかもしれないが海の上では海賊の法則に従ってもらうしかない。
今までなら敵との遭遇は楽しいイベントだった。だが今回はそうはいかない。この船には海賊らしいものは何も残っていないのだから。せめて雑魚なら倒して食料でも奪ってやりたいところだが、敵船は何も期待させてくれなかった。皮肉なほど立派な船だったのだ。
敵船が近づいてくるにつれ、帆に描かれた紋章がはっきりと見えてきた。三人は息を飲み、その名を口に出すのを躊躇った。そこには、初めての遭遇だとは思えないほど見慣れた印があったのだ。マイの胸元に描かれた黒い薔薇と同じものだった。マイの表情は静かだった。
最悪だった。これで悪運も尽きたとしか思えなかった。ワイゾンは、敵でも出て来いなどとちらりとでも思ったことを、心の中で撤回する。
エンドローズはギリギリまで近づいたところでやっと止まる。これがこの船のやり方だった。エンドローズは大きさこそシャルノロエスと同じくらいではあったが、その中に詰め込まれたものは雲泥の差だろうと誰もが悟れた。
突き付けた船首には血の色のドレスと羽を纏った女神の木像が背を伸ばし、相手を威嚇するように見下ろしている。美しい、とは言えない。なぜならその女神は全身が骸骨だったからだ。その背後に人影が見えた。胸を張り、楽しそうにシャルノロエスを見据えている。更にその周囲には戦闘準備が済んだ大勢の海賊が立ち並んでいた。力の差は歴然だった。ワイゾンたちは圧倒される。だがワイゾンは毅然として前に出た。
「エンドローズ海賊頭」ワイゾンは歯を剥きだした。「何か用か」
シャグラは長い髪を靡かせ、ワイゾンを見て笑い出した。整えた髭の下から白い歯が覗く。光沢のある派手な青いコートを肩にかけ、全身のあちこちには自慢げに宝石や貴金属を散りばめている。悪趣味だとは聞いていたが、想像以上だと驚かされる。
シャグラは海賊界で死神と呼ばれていた。彼の悪趣味は見た目だけではなく、その趣向にもあった。シャグラは死体が大好きだったのだ。船を見つけると何の機も伺わずにまっすぐ襲い掛かる。目的は殺戮以外に何もなかったからだ。シャグラは死んだばかりの人間の体やその表情が最高の芸術だと言う。理解、共感できる者はいなかったが、その強さと残酷さは人を恐れさせ、屈服させてきた。
ワイゾンとは初対面だったがお互いに存在は認識していた。シャグラはこの黒い船に興味を示していた。珍しく速攻ではなく、話をする距離を置いている。
「君がワイゾンか」あからさまに見下した顔だった。「人間らしく陸の上で土に還ってしまったのかと思っていた。会えて嬉しいよ」
どうやらシャルノロエスが一度メイに捕らえられたことは知られているようだ。ワイゾンはむっとするが、事実だ。言い訳や否定するだけ余計に恥を上塗りすることになる。開き直るしかない。
「俺の名前はよほど有名なようだな」ワイゾンは目を細める。「光栄だが、生憎と今は忙しいんだ」
「忙しい?」シャグラはわざとらしく船を眺めた。「そのようだな。どれだけ焦ってきたのか、その貧相な船を見れば想像できる」
「確かに、一目瞭然ってとこだろうな。そういう事なんでな、ちょっとそこをどいてくれないか。邪魔だ」
シャグラの顔から笑みが消えた。
「どうしても遊んでほしいと言うなら予約をいれといてやるから。用が終わるまで待っててくれ」
「いや」シャグラは腕を組みながら。「その必要はない」
今ここで殺すから──当然の展開だった。ワイゾンは軽くため息をつく。そこに声を聞きつけてトールが甲板に出てきた。その後にティシラとマルシオも続いてくる。ティシラたちは立ち塞がる海賊船を仰いだ。
「ワイゾン」トールが駆け寄って。「誰だ、こいつら」
ワイゾンの代わりにキジが答えた。
「海賊ですよ」その顔は珍しく真面目だった。「エンドローズのシャグラ」
「海賊……」
トールは悪趣味なシャグラに目を奪われた。これが海賊か、などと悠長な感想を抱く。その背後でティシラとマルシオも海賊らしい海賊を見て感心していた。クライセンは相変わらず出てこない。興味もないのだろうが、今は特に機嫌が悪いらしくあれから誰とも会っていなかった。こういうときは放っておくのが一番だった。
張り詰めた空気の中、少し離れたところでマルシオがティシラに耳打ちする。
「なあ、あの薔薇の絵……」
「何?」
言われて、ティシラは帆に目を移す。あっと声が出そうになった。マイの刺青と同じものだと気づく。それが何を意味するのかは分からないが、どうやら何かの因縁がありそうだということだけは感じられる。それでもティシラは「面倒臭そう」としか思わなかったが。
ワイゾンは緊張感のないティシラたちを見向きもせずにシャグラに話を続ける。
「どうしても戦いたいなら相手になる。だがこの船には手を出すな」
シャグラは口の端をあげる。
「そんな船などどうでもいい」
そして黙ってシャグラを見つめていたマイをちらりと見た。マイは目が合った瞬間、寒気が走った。ワイゾンが眉を寄せた。やはり、シャグラの目的は彼女だ。
「マイ」シャグラはマイに向き合った。「久しぶりだな」
マイは答えない。冷たく鋭い視線でシャグラを睨み付けている。
「君が生きていると聞いてずっと探していたんだよ。そんなに薄汚い格好をさせられて、可哀相に……だが、着飾らない君もまた美しい」
マイはシャグラの笑みで体を震わせる。過去の悍しい思いが蘇る。表情はなかったが彼女の目に灯る憎悪の念は凄まじいものだった。隣でキジも怒りを増幅させている。キジもまたシャグラを憎んでいた。キジはマイを姉のように慕い、尊敬していたのだ。マイの方が年も下だったし海賊としても後輩に当たるのだが、キジは自分が及ばない彼女の実力を認めていた。
そして、そのことを煽るような真似はしなかったが、長い間ワイゾンが密かにマイに想いを寄せていることを知っていたのだ。キジですら勘付くのだ。今まで一緒に過ごしてきた仲間たちももちろん知っていたし、ティシラたちもそれぞれに、当然のように気づいていた。だが誰も口にはしなかった。わざわざ話題にするまでもないほど分かり易かったからだ。
そんな想いがあったからこそワイゾンは下手に彼女を口説こうともせずに、一人の海賊としてここに置いているのだと思う。男らしいかと聞かれれば首を傾げるが、キジはすっと二人が一緒にいられればいいと、それを見守っていたいと願っていた。
なのにこの時、この場所でこの男と出会ってしまうなんて。キジは自分たちを引き裂こうとするシャグラに殺意を抱いていた。
マイは人一倍勘が鋭い。ワイゾンの気持ちなどとうの昔に気づいている。しかしマイはそれに対して反応したことはなかった。根本的にワイゾンに男としての興味がないのか、それとも自分の立場を守るために感情を切り離しているのかは分からなかった。今までずっとそうだった。だからそれでいいと思っていた。
3
マイは動かない。ワイゾンとキジは不安に包まれた。戦うことになれば、正直この圧倒的な力の差の前に勝てる自信はなかった。殺されるだけではない。マイを奪われてしまう。そんなことになるくらいならいっそ洞窟で全滅していた方がマシだったのかもしれないとまで思う。絶望的だった。
マイがゆっくりと口を開く。
「シャグラ」その声は落ち着いていた。「あんた、まだ私に未練があるの?」
一同がマイに注目した。
「私はあんたの悪趣味には今でも吐き気がする。その声も顔も、腐った性根も全部嫌いよ」
シャグラはいやらしい笑みを消さない。彼は嫌がる女を無理やりねじ伏せて泣き叫ばせるのが好きなのだ。彼女に罵られても一向に構いはしなかった。
「それでも……うちの頭が負けちゃったら、逆らえないんでしょうね」
マイは目線をワイゾンに移した。
「それが、海賊の世界だもんね」
ワイゾンは息を飲んだ。今までくだらないことを考えていた自分が恥ずかしくなる。マイは「戦え」と言っていたのだ。迷う必要なんかなかった。自分は根っからの海賊ではないか。死ぬまで戦うしか道はないのだ。恐れた方の負けだ。
ワイゾンは自分の弱点が情け深すぎることだと自覚していた。それを支えていたのがキジで、戒めていたのがマイだったのではないか。この二人がいなければ、きっと自分はもっと早いうちに死んでいただろう。
それでも無情にはなれなかった。だが自分が無情であったならこの二人はここにいなかった。理由のない殺戮は好きになれない。ならば理由を作ればいい。仲間を、友を守る。そのためなら何でもできる。ワイゾンは剣を握る手に力を入れた。再びシャグラを睨み付ける。
「シャグラ」ワイゾンは剣先を突き付け。「マイが欲しかったら、俺を倒せ」
シャグラは眉を寄せた。
「俺が負けたら、後は好きにしろ」そして、笑う。「それが海賊だろ?」
シャグラは肩を揺らしてワイゾンを嘲る。
「よくこの状況でそんなことが言えるものだ。勇敢を通り越してただの馬鹿だとしか思えない。おとなしくマイを差し出せば見逃してやるかもしれないのに」
「馬鹿はお前だ。仲間を犠牲にして生き残った海賊がどこにいる」
「海賊はかっこつけていても生き残れないぞ。まあ、それが君の陳腐なプライドを守る唯一の手段だと言うのなら、いいだろう。受けて立ってやる」
「サシで勝負だ」
「承知」
「お互い、惚れた女を懸けて正々堂々と勝負だ」
それを聞いてシャグラは更に不気味な笑いを浮かべた。
緊迫した空気が流れる中でティシラとマルシオは目を合わせて肩を竦めた。真剣なワイゾンの背中を見守りながらティシラが呟く。
「あの人」呆れたように。「自分が魔族になったこと、すぐ忘れるわね」
マルシオも確かに、と思うが何とかフォローしてやろうと思いつつ、いまいち関係ないコメントを述べる。
「根が真面目なんだろ」
そんなことは露知らず、シャグラも剣を抜いた。
「いいだろう」シャグラはコートを脱ぎ捨てて。「エンドローズへ歓迎する。上がってこい」
「卑怯だぞ!」キジが慌てて大声を出した。「そんなの、お頭が不利過ぎる。お前がこっちに……っ」
最後まで言わせないうちにマイがキジを力一杯ひっぱたく。
一同が目を丸くした。頬を押さえながらキジが涙目になる。
「マ、マイさん……なんで」
マイの目は冷たかった。
「いいじゃない、どっちでも。頭同士がサシで勝負するって言うのよ。不利もクソもないでしょ」
その迫力に押されてキジは言葉を失う。マイはワイゾンに向き合う。
「……マイ」
ワイゾンは彼女に少々怯えながらマイを見つめた。
「ワイゾン」マイは目を細めた。「怖いの?」
ワイゾンは一瞬、息をするのを忘れた。そして絞り出すように怒鳴りつけた。
「怖いだと? 誰に向かって言ってる」
「怖いか怖くないか聞いてるの。はっきり答えなさい」
「怖いわけないだろ!」
マイは確かめるようにワイゾンの顔をじっと見つめた。心を見透かされているようだった。ワイゾンは邪念を必死で振り払っていた。額に汗が流れる。
「たまにはいいとこ見せなさいよ」
「た、たまにはとは何だ」ワイゾンはかっとなって。「ああ、やってやるさ。最初からそのつもりだ。大体お前はな、女のくせに態度がでかいんだよ。いちいち指図するんじゃねえ!」
ふっとマイの表情が変わった。ワイゾンはしまった、と口を結ぶ。「女のくせに」なんて、彼女には禁句だった言葉を使ってしまった。本当は今すぐ取り消して謝りたかった。しかし、もう後には引けない。マイから目を逸らして今度はシャグラに怒鳴る。
「今そっちに行く」
シャグラはそのやり取りをニヤついた顔で眺めていた。背後で整列している手下に合図し、橋代わりの細長い板を持ってこさせる。
キジが頬を張らしたままワイゾンに駆け寄った。
「……お頭」
「心配すんな」ワイゾンは彼の情けない顔を見ていると虚勢を張る癖がついていた。「だが万が一のことがあったらこの船はお前に任せるからな」
「そんな」
「万が一だよ」
俯くキジの肩を叩いて、ワイゾンはふっとティシラに声をかけた。
「ご主人様」
ティシラは条件反射で固まった。
「これは海賊の戦いです。あなたたちには迷惑はかけません。俺たちに何かあったらこの船は差し上げます。これで目的を果たしてください」
「え、ええ」
ティシラの笑みは引きつっていた。
「手出しは無用です」
「言われなくても」ティシラは軽く手を振った。「そのつもりだから」
船に乱暴に橋がかけられた。ワイゾンはやけくそでそれに飛び乗る。足を進めようとしたその時、マイが口を開いた。
「……私ね」
ワイゾンは振り返った。目が合うとマイは意地悪な笑みを浮かべる。
「殺しても死なない男が好きなの」
じわりとワイゾンに闘志が湧き上がってきた。自分のことを指しているかどうかは分からないが、少なくともここで生き残れば彼女の好みに近づけると思い込んだ。ワイゾンが完全にマイに躍らされているのは誰もが見て取れた。ワイゾンは顔が緩むのを隠し切れていなかったのだ。白い目で見られていることにも気がつかない。
ワイゾンはすぐに気を引き締めて、勇ましく敵船に乗り込む。シャグラの手下たちは舷檣に沿って端に寄り、戦いの場所を空ける。殺意の篭ったすべての目はワイゾンに向けられていた。ほとんどが彼を惨めな海賊頭だと見下しているのがビンビン伝わる。戦意を削がれる環境だが「何とでも思え」と開き直ることにした。
ワイゾンは視界の端に、ある四人の姿を捉えた。エンドローズの守護神と言われるイルマ、ゴルノール、シャンテス、レイドだ。まるで針の筵だった。仮にシャグラに勝てたとしてもきっとこの四人が黙って帰してはくれないだろう。だが今は考えないことにした。頭同士の勝負の後は、海賊らしい無法の殺し合いになる。それはその時に考えよう。今はシャグラにだけ集中しようと、そう思った。
ワイゾンとシャグラは同時に剣を構える。シャグラは余裕で笑っていた。もしも自分が少しでも不利になれば手下がワイゾンを串刺しにするのだ。今までそうやってきた。正々堂々なんて彼の概念にはなかった。この男は勝ち目のない戦いに背を向けずに立ち向かった。立派な最期ではないか。シャグラは既にワイゾンの死を確信し、彼が斬り刻まれて血に塗れる姿を想像して興奮していた。
二人は居合いを測りながら剣を腕の一部に変えていく。緊張する。勝負はすぐに決まるだろう。先延ばしにしても意味はない。ワイゾンが機を待たずに先陣を切る。
二つの剣が交わった。それはまるで火花が目に見えるほど激しくぶつかり合う。細かく、ときに大きく剣は空気を切り裂く。二人を取り囲む観客たちが一斉に雄叫びを上げた。
その時、船長室で居眠りをしていたクライセン薄く目を開ける。凄まじい雑音が船ごと振動させたのだ。何事かと神経を集中させる。そして、目元を翳らせながら強く眉を寄せた。船上での出来事を読み取り、じわじわと苛立ちが頂点に達していった。ただでさえ彼にとってはくだらないことだった。その上、そのくだらないことで睡眠を邪魔されたこと、何よりも寝起きで頭がすっきりしない彼は今まで以上に機嫌を損ねてしまったのだ。だが動こうとはしない。眉を寄せたまま、再び目を閉じた。
4
ワイゾンとシャグラの戦いは盛り上がっていた。黙って見守るマイの隣で、キジは唇をかみ締めて唸っている。更にその隣ではトールが身を乗り出して二人の戦いに釘付けになっていた。
(……凄い)瞬きするのさえ惜しんでいた。(速い。互角だ。自己流で何の型もない、なんてめちゃくちゃな剣術なんだろう。いや、これは剣術なんて言えない。野生の世界での、野蛮で乱暴なただの殺し合いだ。あれは剣なんかじゃない。体の一部なんだ)
ワイゾンとシャグラは一度離れる。まだどちらも掠り傷ひとつついていない。そして体勢を整える間もなく再び攻防する。
(ここで僕の剣は通用するだろうか。いや、レベルが違う。ならばメイに伝わる伝統的な剣術はどうだろう。もし世の海賊が束になってかかってきたらそれも危ういのかもしれない。ワイゾンの言う通りだ。海賊もひとつの人種であり、歴史と掟のある社会だ。メイは陸では最強かもしれないが、この海ではただの異物に過ぎない)
世界は広い。トールは改めて自分の小ささを思い知った。ぞくりと背中に悪寒が走った。武者震いとでも言うのだろうか。自分も「命の取り合い」とやらを経験してみたいなどと軽々しく思った。軽率だとは分かっていた。一生に一度きりになってしまうかもしれないのだから。
その時、僅かな隙にワイゾンの剣先が滑り込んだ。シャグラの太ももが切り裂かれ血飛沫が散る。
「やった!」
キジが両手を挙げて大声を上げる。入れ替わるようにエンドローズの船員が声を飲み込んだ。シャグラが顔を歪めて片膝をつく。これでワイゾンの勝ちが決まったも同然だった。喜ぶ前に止めを。ワイゾンは素早く剣を握り直す。シャグラはそれより早く、準備していたかのように四人の守護神に目線を送った。
再び鮮血が宙を舞った。それはワイゾンがシャグラに剣を振り下ろす、その寸前だった。
ワイゾンの体を四方から剣が通り抜けていった。ワイゾンの胸と背中、腕、足の肉が裂ける。その足元では返り血を浴びたシャグラの歪んだ微笑があった。ワイゾンは薄れゆく意識の中で、その映像に怒りと悔しさを噛み締めた。
どさりとワイゾンが倒れる。体の周りが流れ出す血で縁取られていく。守護神がそれを取り囲み、無表情で見下ろしていた。ワイゾンはエンドローズを護る四人の男に切り刻まれてしまったのだ。
「……お、お、おか……」
キジは震えていた。隣ではマイが立ち竦んでいる。しばらくの間、呼吸できなかった。
エンドローズで歓声が上がった。海賊たちは無数の剣を掲げて勝利を祝った。
「卑怯だぞ!」キジが剣を抜いた。「殺してやる」
キジは正気を失ってエンドローズに駆け出しそうになった。が、マイに肩を掴まれて足を止める。
「……マイさん、止めないでください」
マイの目は虚ろだった。だが何も考えていないわけではなかった。キジとは目も合わせずに呟く。
「命を懸けるってのはね」キジの肩を掴んだ指先に力が入った。「ただ死ねばいいってことじゃないのよ」
この結果を予想できなかったわけではない。むしろ予想通りだったのかもしれない。
シャグラは息をしてないワイゾンを確認して立ち上がった。そしてマイに向き直り、にやりと笑う。
「マイ、お前の頭は死んだぞ」
トールも眉を寄せていた。口出しするつもりはないが、誰が見てもあれは卑怯だ。正直、心から観戦を楽しんでいた。なのにこんな結果だなんて、気に入らない。その胸中は穏やかではなかった。ティシラとマルシオも動かずに見ていたが、やっぱり面白くなさそうな顔をしている。
「どうする?」
シャグラは煽る。キジは黙って彼女の答えを待った。マイはゆっくり手を降ろし、表情を変えずに呟いた。
「……シャグラ」微かな震えを抑えながら。「迎えにきて」
キジが体を揺らした。絶望だった。いっそここでマイを殺して自分も死にたい衝動に駆られた。だが、踏み止まる。そんなことをしてもワイゾンは喜ばない。キジは感情を抑えてぐっと拳を握った。
シャグラは堪えられないといった感じで高らかに笑った。血のついたその顔には「これが真の海賊だ」とでも書いてあるようだった。斬られた片足を前に出す。マイが再び口を開いた。
「待って」
シャグラは足を止めた。
「彼の、ワイゾンの遺体も持ってきて。ワイゾンはシャルノロエスの海賊頭よ。せめてこの黒い船で眠らせてやって」
シャグラの顔から笑みが消えた。マイの心理を読もうとしている。
「お願い」マイの表情はまったく動かなかった。「彼は立派に戦った。最期くらいは海賊としてのプライドを守ってやりたいの。それが私の、ここでできる頭への最後の忠義なの」
シャグラはすぐには答えなかった。いつの間にか周囲もしんとしている。
船の端でマルシオがティシラに小声で囁いた。
「あいつ、本当に死んだのか」
「残念ながら」ティシラも声を潜めて。「死んだほうがマシなくらいシリアスな展開になってるわね」
「生きてるんだろ」
「人間が耐えられる衝撃を超えたから、体が驚いて死んだと思い込んでるだけよ」
「教えてやった方がいいんじゃないのか」
「関わりたくない」
「お前なぁ」
マルシオは肩を落とした。だが彼も行動するつもりはなかった。とりあえず事の流れを見守ることにする。
シャグラはやっと口を開いた。
「いいだろう」
そしてゆっくりとうつ伏せで血に浸っているワイゾンに近寄った。シャグラは体を屈める前に、また守護神の四人に目配せをする。イルマがそれを受け取った。シャグラは斬られた足を庇いながら乱暴にワイゾンの体を抱える。滴る血に構わなかった。シャグラは血が好きだった。むしろ快感だった。ワイゾンの流血は誰が見ても致死量だった。ただし、普通の人間ならの場合だったが。シャグラはその時既に、ワイゾンの傷が塞がっていることにはまったく気がつかなかった。
シャグラは悠々と橋を渡ってシャルノロエスに乗り込む。そして甲板に降り立ち、乱暴にワイゾンの体をマイの足元に投げ捨てる。また血が飛び散った。マイは一歩足を下げる。キジは俯いたまま怒りや悲しみを抑え込んでいた。今ここでどう行動するのが最善か判断できずにいたのだ。
シャグラはワイゾンの血を浴びた姿でマイに近づく。
「マイ」その顔は歓喜に満ちていた。「これで分かっただろう。お前は俺から逃れられない運命なんだよ……今度はどこにも行けないように、首輪でもつけておこうか」
シャグラはマイに手を伸ばした。その指を彼女の頬に近づける。触れる寸前にその手がぴたりと止まった。
空気が揺れたのを感じ、キジがはっと顔を上げた。そこには見つめ合ったまま微動だにしないマイとシャグラの姿があった。シャグラは目を見開いて固まっている。
速過ぎて誰の目にも見えなかった。マイの右手が横に伸びている。その腕の先には剣が握られていた。重い空気を揺らしたのは、それで弧を描いた剣先だったのだ。
「なぜだ」シャグラは口だけを動かした。「こんなことをしてどうなるか分かっているのか」
マイは微笑んだ。
「ねえ、シャグラ」マイは手を降ろしながら。「あんたって何も変わってないのね。私はね、もう昔の私じゃないのよ」
エンドローズから手下が身を乗り出した。
「あの頃は泣くことしかできなかったけど、今は違うの。もう泣かないって決めたのよ。私はあんたを悦ばせてあげることできないの。残念ね」マイはシャグラの肩に手をかける。「私を女だと思ってナメてかかった……あんたの負けよ」
マイはシャグラの体を指先で軽く押す。するとその僅かな振動で、ごろんとシャグラの首が落ちた。
シャグラの首から血が噴出す。残った体は痙攣しながら倒れる。
「……シャグラ様!」
守護神の四人が蒼白して大声を上げた。マイはそれ以上に大きく口を開け、天を仰ぎながら声を出して笑った。今までの落ち着いた雰囲気の彼女とは別人のような姿だった。狂気を帯びた顔でエンドローズに向けて剣を振り翳す。
「エンドローズ死の守護神」マイは胸を張って。「私はあんたたちを許さない! さあ、総統の弔い合戦だ。皆殺しにしてやる。かかってこい」
守護神の一人、シャンテスが歯を剥きだした。
「貴様……! よくもシャグラ様を! 死ぬのはお前だ」
ティシラたちが戸惑っている間に守護神たちがシャルノロエスに乗り込んできた。キジも少し遅れて剣を取った。もう考えている暇はなかった。ただマイがワイゾンの仇を討ち、見るからに不利な戦いを挑んだ。それだけ理解できれば十分だった。マイの言った「命を懸ける」意味がやっと分かった。後はできるだけ多くの敵を道連れに死ぬまで戦うだけ。役立たずだった自分にしてはなかなかかっこいい最期ではないだろうか。キジはもう遠慮せずに闘志を全身に漲らせた。
「お頭、見ててください」
叫ぶキジにマイは微笑んで頭を叩いた。そこにトールが駆け寄ってくる。
「僕も仲間に入れてくれないか」
「あら、王子様。これは飯事じゃないのよ」
「分かってる」トールは無邪気に笑った。「僕は海賊じゃないけど君たちの友達だ」
分かってると言うがそうは見えない。マイはため息をつく。しかしどうせ逃げるところはないのだ。
「好きにしなさい」
そう言って背を向けた。
マイはイルマに、キジはレイドに向き合う。トールが剣を抜くと同時にゴルノールが彼を標的にしてきた。トールは口の端を上げて剣を構えた。ふっと先日のことが脳裏に蘇る。やっぱり愛剣は今までより重く感じた。だが、否定するな、受け入れろと自分に言い聞かせる。雑念を振り払う。間を措かずにゴルノールが斬りかかってくる。トールは慌てて剣で流した。
「なんだよ。挨拶もなしか」
言い終わらないうちに、更に容赦なく振り下ろされる剣をトールは弾き返した。容赦ない攻撃に腕が痺れる。それもそうだと気を取り直す。剣は飾りではない。持って構えればそれだけで武器になる。剣は見せびらかすものでも身分を示すものでもない。「斬る」以外の用途としては造られていない。闇雲に振り回すだけなら棒切れでもいい。だが剣はそうではない。そしてそこにあるだけでも意味はないのだ。
人の手に担われ、心を通わせて初めて機能を発揮する。
全身の神経を集中させる。すると不思議と剣が軽く感じた。目が色を見るように、指がものを掴むように、剣も脳からの指示を受けて思い通りに動かせる、そんな気がした。
ゴルノールはトールの目の色が変わったのを感じ取った。最初はただの軟弱そうなやさ男だとしか思っていなかった。だが剣を交わせば交わすほど、その衝撃のひとつひとつを丁寧に吸収していく。そして使えないと思っていた剣がどんどん自分の懐に近づいてくるではないか。ゴルノールは驚かずにはいられなかった。
トールは死を望みも恐れもせずに楽しんでいた。この僅かな時間でゴルノールはトールをいっぱしの剣士として認めていった。認めるしかなかった。二人は一度離れ、間合いを取る。
「貴様」ゴルノールは殺気を放ちながら。「海賊か」
改めて相手が何者か確認する。名乗り合い、素性を明かすことではない。人間としての器を知りたかったのだ。トールはそんな掟は知らない。ただ素直に答える。
「違う。僕は海賊にはなれない」
それだけ言うと間をおく。もしかしたら剣を振れるのもこれで最期かもしれない。トールはどこかで感じ始めていることを、ほとんど無意識に口に出していた。
「いずれ王になる者だ」
ゴルノールはそれを笑わなかった。逆にそれなら納得がいくと思った。どこの、何の王かは分からない。だが子供が憧れる絵本や童話の幼稚なそれではないことは分かる。そして無謀な志しでもなく、自分が海賊としての生き方を選んだように、彼もまた生まれもって何かを背負っているのだろう。これ以上は野暮だと思った。残念だがここでどちらかが死ぬ。お互いにその結果を受け入れるだろう。後腐れなく。
トールはもしここで死んだとしても悔しいとは思わなかった。つい先日まで海賊など低俗な人種だとしか思っていなかったのに、彼はそれすらも忘れてしまっていた。
5
エンドローズの手下たちはシャルノロエスには乗り込まず、守護神恒例の「公開処刑」を観戦していた。全員が武器を手にして咆哮を上げている。いつでも襲撃できると敵を圧迫していたのだ。
エンドローズにはよくあることだった。しかしゴルノールはそれを初めて鬱陶しいと思っていた。この人間同士の命の取り合いには邪魔だった。野次の声を耳から遮断する。トールの剣だけに集中する。目の前の若者はゴルノールの高貴な闘志を受け取り、笑った。
二人の間に張り詰めていた見えない糸が僅かに揺れた。それを合図に同時に動いた。ゴルノールは彼を真っ二つにするつもりで剣で一文字を描く。トールはそれを屈んで躱し、踏み込んでくる──そうさせるつもりでゴルノールは誘導した。
しかし彼の思い通りにはいかなかった。トールは挑発には乗ってこなかった。冷静に、切っ先に触れるか触れないかの距離まで体を引いたのだ。
ゴルノールに隙ができたその一瞬でトールは手を捻って剣を持ち直した。無駄な動きは一切なかった。ゴルノールが剣を返してくるより早く、引いた反動を利用してその懐に飛び込んだ。
トールの剣は吸い込まれるように柄の近くまでゴルノールの胸に刺さっていった。肋骨の間をきれいに突き抜けたのだ。派手で残酷な野生の戦い方に対し、トールは小さく、確実に的を射抜く技を選んだ。それはダラフィンに習った「上品」な剣術だった。
ゴルノールは遠くを見つめてグラリと揺れた。
「……見事」
恨みも後悔もなかった。ゴルノールはその一言を残して崩れ落ちていった。
それを見ていたエンドローズの船員たちはぴたりと騒ぐのを止めた。そして再び声を上げるが今までのとはまったく違う、怒りと恐怖の雄叫びに変わっていた。
トールはそんなものには構わずに大きく息を吐いた。時間にして、僅か数分だった。だがトールには生涯忘れられない瞬間のひとつとなった。込み上げる喜びをどうしても我慢できない。
「やった!」
先ほどまでの真剣な表情は消え去り、まるで別人のように笑顔ではしゃいだ。すっかり集中力は散漫している。今は難しいことは考えられなかった。生き残ったというよりもただ勝ったという単純な歓喜だけに支配されていた。
エンドローズの海賊が狂ったように流れ込んできた。トールは浮かれたまま、蟻のように列を為す海賊の群れに向かっていった。
さらに騒がしくなる船上でキジが唸っていた。キジの頭の中にはワイゾンの敵討ちしかなかった。彼は一度にひとつのことしか考えられない。その知能の低さの裏には動物のような凶暴さが潜んでいた。こうなってしまうとワイゾンやマイにも止められないほど荒れ狂う。
レイドはその様子を見て、逆に冷静に考えた。少し頭を使えばこんな単純そうな男、殺すのは簡単だと思った。キジは古びた剣を両手で握り締め、吠えながらレイドの頭上に振り下ろした。レイドはあっさりとそれを顔の前で受け止める。だが、その衝撃は予想以上のものだった。
(……なんて力だ)レイドは眉を寄せた。(振り払えないだと?)
キジはさらに力を入れる。剣がレイドの顔の前に迫った。ぎしり、と何かが軋む音がする。レイドが息を飲みながら片膝をつく。キジはそれを上から押え付ける。
(だめだ、このままだと)レイドの腕が震え出した。(そ、そんな……馬鹿な!)
単純なのはレイドの方だった。キジの怪力の前には戦術も小細工も通用しない。キジを見た目だけで侮った時点で既に勝負はついていたのだった。
「お頭の仇──!」
キジは剣に全体重かけて恨みのすべてを打ち付けた。
パキンと、高い音を立ててレイドの剣が折れる。レイドが死を覚悟する間もなくキジの剣が真っ直ぐに振り下ろされた。レイドの脳天が割れ、目玉が飛び出る。縦に斬り裂かれたレイドの体からは血に塗れた内臓が流れ出した。それを目にした者のすべてが体を引いた。キジは振り子のように顔を上げて拳を突き上げた。
「お頭! やりました」
そしてトールに続き、そのままの勢いで敵の群れの中に飛び込んでいった。
船の傍らでティシラとマルシオが困っていた。
「グロい……」
そう呟くティシラよりもマルシオの顔色の方が悪かった。目を逸らしながら背を縮めている。
「最悪だわ。これっていつ終わるのよ」
「皆殺しとか言ってたけど、俺たちも出た方が早いんじゃないか」
「そうかもしれないけど、私は海賊じゃないし……どうなのかしらね」
そんな雑談をしている二人の前にシャンテスが立ち塞がった。
「丸腰の子供が二人か」シャンテスは無表情だった。「かわいそうだが、死んでもらう」
ティシラがむっとする。シャンテスは剣を抜いた後、ぴたりとその手を止める。何を思ったか、ティシラとマルシオを舐めるようにジロジロと眺めた。
「しかし」ふん、と鼻を鳴らして。「変わった姿をしているな。その目の色、海の上では似つかわしくない美しく艶のある髪や肌。そうか、お前たちは『商品』だな」
その言葉でマルシオも不快になる。構わずにシャンテスは続ける。
「これは上玉だな。どこで捕まったかは知らないが殺すのは惜しい。逃げられるとは思うな。残念ながらお前たちがどこぞの変態成金の玩具になることは変わりないのだ。いい金になりそうだな」
ティシラとマルシオは黙ったまま目を細めた。そこでやめておけばよかったものの、シャンテスはそれが怖がっているものだと勘違いしてしまった。
「怖いのか? 可哀相に。だがその感情もいずれは麻痺して何も感じなくなるだろう。泣くなら今のうちだぞ。そのうち涙さえ出ない体になってしまうかもしれないのだからな」
シャンテスは嫌な笑顔で二人を見下した。胸糞が悪い。マルシオでさえその下品な口を縫い付けて黙らせてやりたいと思う。だが自分がそんなことをしなくても隣の魔族がじっとはしていないだろう。予感は的中している。ティシラの目には凄まじい魔力が灯っていた。その憎悪は半端ではなかった。マルシオはゾクリとする。やばい。絶対に過剰な制裁を与えるに違いない。立腹は当然だが、ここは一度ティシラを宥めようと思った。が、間に合わなかった。
ティシラは爪を尖らせ、それを突き出す。
同時、シャンテスは顔を歪ませ、剣を落とした。そしてそれ以上、一言も発さないまま崩れ落ちる。一同が動きを止めてそれに注目した。
倒れたシャンテスの向こうには目の据わったティシラが立っている。よく見るとその手から血が滴り落ちている。何かを掴んでいる。それはピクピクと脈打ちながら血を吐き出していた。一同は目を疑った。
信じ難かったが、間違いない。人間の心臓だった。ティシラはシャンテスの胸を突き破って心臓を抉り出していたのだ。ティシラはそれを無情に、肩越しに海に投げ捨てた。横でマルシオの目が点になっている。
「ティシラ……それはないだろ」マルシオは吐き気がして口を押さえる。「せめて魔法を使え」
「つい」まったく反省の色はなかった。「勢いで」
マルシオは青い顔でティシラを睨んだ。この場にクライセンがいたら絶対にこんなことはしなかっただろう。化けの皮も大概にしろと心の中で罵った。
それを見ていたエンドローズの海賊たちは恐怖に染まった。さっきまで勢いよくシャルノロエスに乗り込もうと押し合っていた者も足を止める。イルマが声を振り絞った。
「何なんだ、お前たちは!」イルマは戸惑いの色を隠せない。「化け物か!」
またティシラが眉を寄せる。前に出ようとした彼女をマルシオが止めた。
「ほっとけ」マルシオはティシラの腕を引っ張る。「今のは言われて当然だろ。お前は早くその手を洗ってこい」
ティシラはマルシオを横目で睨みつけ、感じ悪く手を振り払う。マルシオは何もかもが面倒臭くなってきた。今ここに自分の気持ちを理解してくれる者は一人もいないと思うと、ため息が出た。
その時、船室の扉が開いた。ティシラとマルシオはすぐにそれに気づいて体を揺らす。船内には一人しかいない。彼が出てきた。クライセンが顔を下げたまま姿を現す。力なく船上の様子を一通り眺めた。いつもに増してだるそうだった。隅で小さくなっている二人の魔法使いに近づく。ティシラは慌てて血に塗れた手を背中に隠した。
「なんだこれは」
クライセンの目が異常に怖い。イラついているのが見て取れる。あれから寝直そうとしたが、いくら待っても静かになりそうにない船上にとうとう我慢できなくなったのだ。マルシオが彼の様子を伺う。
「ね、寝てたのか」
この状況でよく寝ていられるものだと感心する。しかし人として起きてきただけでもマシだと思った。クライセンは再び周囲を見回した。しばらく黙っていた後、乱闘の中で倒れているワイゾンを見つける。それをじっと見つめるクライセンの目が更に険しくなった。何を思ったか、仰向けで無防備に横たわっているワイゾンにゆっくり近づいた。クライセンは一度足を止めたかと思うと、いきなり彼の腹を思い切り踏んづけた。
「!」
するとワイゾンの目がかっと開き、奇声を上げながら跳ね起きた。
「うわあっ!」
一同が目を丸くし、船上の時間が止まった。ワイゾンは踏まれた腹を押さえながら息を荒くして辺りを見回した。
「な、なんだ……?」
沈黙が落ちた。しかし、誰かの「化け物だ!」と言う叫びで一瞬にして混乱に陥った。海賊たちは慌てふためいてエンドローズに戻っていく。その中でイルマが怒鳴り散らした。
「貴様ら! 逃げるな」
だがその声は喧騒に掻き消されていく。手下たちはイルマの命令よりも、目の前で起こった不気味な現象への恐怖に捕らわれてしまっていたのだ。
「……クソぉ──!」イルマは剣を振り回しながら。「貴様ら、それでも海賊か!」
手下たちはイルマを無視して船を動かし始めた。ゆっくりと離れていく。
逃げ惑う船を見送りながら、悔しさと惨めさで折れたイルマの心は容赦なく貫かれた。目線を落とすと、自分の胸から剣先が突き出ていた。それを伝って血が滴り落ちている。
背後にいたのは、冷酷で凛としたマイだった。イルマは誰に刺されたかなんて確認する気はなかった。ただ、完全なる敗北を噛み締めながらゆっくりと瞼を落としていく。マイが剣を引くと、イルマは抵抗することもないまま息を引き取った。
敵は失せた。一番に大声を上げたのはキジだった。
「お頭」喜びで涙を流す。「お頭ぁ、てっきり死んだかと」
キジは、未だに状況を把握できずに戸惑っているワイゾンに抱きついた。わあわあと声を上げて泣きじゃくる。
「キ、キジ」ワイゾンは何も思い出せない。「どうしたんだよ」
トールも笑顔で駆け寄ってきた。
だが、マイは違った。ワイゾンには目もくれずに逃げ惑うエンドローズを見つめて立ち尽くしていた。その目は深い悲しみの色で染まっていた。
マイのその目が微かに動いた。それに続いてワイゾンとキジ、トール、そしてティシラとマルシオも同じ方向に目を奪われた。
離れていくエンドローズの頭上に三つの紫の星が舞い降りてきた。
それは数メートル上で止まり、くるくる回りながら線を結んで三角形を描く。さらにまた三つの星が降りてきて同じ動きを繰り返した。二つの三角は回転しながら重なっていく。すると六つの星はきれいな六芒星になる。
重なった星からまた線が伸びた。すべてが繋がり、寸分の狂いもない円で囲まれる。内側に見たことのない文字が浮かび上がると見事な魔法陣が出来上がった。
エンドローズの船員たちは既に戦意を失っており、手を止めて頭上の星を眺めていた、いるしかなかった。
円がふわりと光った。その光は中心に集まる。美しさに目を奪われている、その一瞬の出来事だった。集まった光が稲妻のようにエンドローズに降り注いだ。空気が弾ける。
無音だった。船が爆発するより少し遅れて、ドォンと物凄い衝撃が起きる。波に大きな波紋が広がり、シャルノロエスも大きく揺れた。
マイの見開いた目には、粉々に砕け、燃えながら海に沈んでいくエンドローズの最期が焼き付けられた。
紫の星は炎に巻き込まれ、溶けるように消えていく。何が起きたのか、誰も口には出さなかった。クライセンだ。こんなことをするのは、こんな大袈裟な八つ当たりをするのは世界中探しても彼しかいない。
クライセンはワイゾンの隣でただ突っ立っているだけのように見えた。何も知らなければ、まさかこいつが、なんて誰も分からないだろう。一同は改めて、一番怖いのはやっぱりこの男だと思った。
(……いや)と、トールは思う。(違う。単なる八つ当たりなんかじゃない)
じっと立ち尽くしていたマイの足元に、一粒の雫が落ちたのに気づいた。マイは肩を微かに揺らし、剣を持っていない方の手で顔を覆った。
「……マイ」
ワイゾンもそれに気づいて彼女の背中を見つめた。彼女の顔は涙でぐしゃぐしゃになっていた。泣かないと決めていた。泣くことは苦しいとき、辛いときのものだと思っていたからだ。それだけではないことを初めて知った。内側から込み上げてくるものを我慢できなかった。
エンドローズは彼女にとって牢獄だった。自らの手でシャグラの首を討つという、途方もないと思っていた願いは適った。
だがそれでもマイの鎖は断ち切れなかった。彼女には黒い薔薇の紋章そのものが忌まわしくて仕方なかったのだ。頭を失ったところであれだけの海賊を、組織ごと潰すのは一人の女には到底無理なことだった。
だから逃げてきた。今までずっと逃げ続けていた。だけど心にまで刻み込まれた傷を忘れることができなかったのだ。だから胸の紋章を消すことができなかった。
傷を隠すのではなく、消してしまわなければ意味がなかった。胸に咲いた薔薇の根はエンドローズに繋がっている気がしたのだ。本体がある限り自分もその茨の枝のひとつであるような幻覚が切り離せなかった。
その強大で残酷な薔薇が散っていく。今、目の前で完全に消滅していく。胸の薔薇は紋章ではなく、ただの飾りでしかなくなった。シャグラによって蔑まれてきた傷がやっと思い出になっていくのを感じていた。
ずっと彼女の心を縛り付けていた鎖が解けた。すべてが海に沈んでいく。
クライセンが何のつもりでやったのかは分からない。マイの気持ちをどこかで察したのか、それとも、本当にただの八つ当たりなのか。きっと聞いても答えないだろう。決して誰かの為であったり、感謝されたいわけでないことだけは確かだった。彼は何事もなかったかのような顔で、足元で呆けているワイゾンに声をかける。
「船長」
ワイゾンは大きく体を揺らして、彼を見上げた。
「どうして君たちは静かにしていられないんだ」クライセンの声は低かった。「何をやっているのか知らないが、私を巻き込まないで欲しい」
一同は、言ってることがめちゃくちゃだと思った。寝てたくせに。最初から出てくればいいじゃないか。巻き込んでない、自分が勝手にやっただけだろ。など、言いたいことはそれぞれにあったが誰も口を開かない。ワイゾンも反論せずにおとなしく頷いた。クライセンはふらりと振り向いてそのまま船室に戻っていった。
その後、ワイゾンはティシラに説教された挙句、マイにも散々文句を言われた。しかも数発殴られた上に甲板に散乱した血痕や死体の片付けを一人でやらされる羽目になった。せっかく生きてたのに、とぶつぶつぼやいていると、キジがはしゃぎながら手伝いにきてくれた。