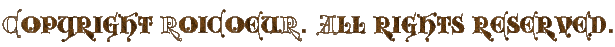第13章 白と黒





1
その日の夜、マルシオは夢を見ていた。いい夢ではなかった。
暗闇の中にいくつものロウソクが灯っている。風もないのに異様に膨れ上がったり、千切れたりして揺らいでいる。マルシオは凶兆を感じた。闇の中で銀の瞳を左右に動かす。体は動かない。いや、体は無いように感じた。ただ目に映ったものだけがその脳裏に映し出されている。苦痛はなかった。だが何かに拘束されているようで気分が悪い。
ふっと銀の目が大きく開いた。そこに映ったのは、闇の中に佇むあるものだった。髑髏に見えた。遺体ではない。血も肉もないはずのその体には魂が宿っていた。意識も感覚もある。見、聞き、話す。だが彼に心はなかった。その髑髏は邪悪なものの象徴だったのだ。
マルシオは目を細め、心の中に何かが渦巻いた。怒りとも憎しみとも言えない、それは嫌悪だった。
髑髏の意識がマルシオに向けられる。なぜだ、と思う。これは夢だ。自分を見ているはずがない。だがその二つの空洞はマルシオを捕らえて離さない。それは彼に重くのしかかってくる。マルシオも目を離せないでいた。きっと目を閉じてしまったらマルシオは闇に沈んでしまうだろう。そう感じた。瞬きすることも出来ずにその強烈な圧迫感と戦った。髑髏の邪悪さは彼に触手を伸ばしてきた。マルシオはそれを感じているうちに、内側から何かが沸々と湧き上がってきた。そして、言葉を発する。
「……ハゼゴ」
髑髏が笑った。骨だけの顔は動かないが、彼の表情は音のように振動で伝わってくる。髑髏は声に出さずに心の中に言葉を送った。
「この世は闇に堕ちる」
地の底から響いてくるそれにマルシオは心を奮わせた。
「光はもう、差さない」
髑髏、ハゼゴはマルシオを挑発した。ロウソクの炎がぼおっと音を立てて揺れる。
「……貴様!」
マルシオは目を見開く。彼の怒りが炎を揺らしていたのだ。
「この地は閉ざされ、希望はない」
ハゼゴが低い声で笑った。それはマルシオの意識の中に轟いた。マルシオはそれに包まれる。離れた場所からでもここまでの魔力を放ってくるのは並大抵の仕業ではない。勝てる相手ではなかった。
「お前の思い通りにはさせない」
だがマルシオはどうしても彼が許せず、冷静ではいられなかった。
「何が何でも、お前だけは俺が倒す」
自らその闇の中に飛び込む。マルシオは誰にも別れを告げることなく、船の上から姿を消した。
クライセンがふっと目を開いた。何かに感付き、意識を集中している。いつものように船長室にいた彼は立ち上がり、目を泳がせた。
クライセンは早足で室を飛び出した。狭い廊下を突き進み、突き当たりの部屋のドアを乱暴に叩き開けた。そこにはマルシオがいるはずだった。小さなデスクとベッドしかない殺風景な室内はしんとしていた。目に見えない邪気が漂っている。クライセンにざわりと寒気が走った。その青い目には「Н」の黒い文字が映っている。それはマルシオと入れ替わるように室の床に焼き付けられていた。人の手で描かれたものではない。クライセンにはそれが何を意味するのか、一目で分かった。物音を聞きつけて他の者も駆けつけてきた。最初に飛び込んできたのはティシラだった。
「マルシオ?」
ティシラは足を止めてクライセンの背後で室内を見渡す。
「……どこに行ったの?」
ティシラもそこの空気が異常なのを感じ取った。次にワイゾンが来て、クライセンの足元にある焼印に気が付いた。
「なんだこれは。誰がこんなものを」
続いてトールが来て、マイとキジは室に入りきれずに入り口から中を覗きこんだ。
クライセンはしばらく文字を見つめていた。
「……ハガル」低い声でワイゾンの質問に答える。「ハゼゴの司る破壊の意味の文字だ」
「ハゼゴ?」
ティシラとトールはその名を聞いて衝撃を受ける。
「邪導師だ」
クライセンはそれだけ言うと、一同を押しのけて室から出て行く。皆もその後に続いて追っていく。クライセンは甲板に出た。張り付くように舷檣に手をかけ、遠くをじっと見つめた。海は闇に包まれ、水平線もぼやけてよく見えない。彼の黒い髪がゆらりと逆立ったように見えた。風がクライセンのそれを煽り、靡かせていたのだ。後からついてきた一同は彼の背中を黙って見守った。
風がだんだん強くなる。まるで呼ばれているかのように舞い込んでくる。それを体で感じ、ワイゾンがマイとキジに指示を出す。
「急に風が強くなってきた。帆をもっと張れ」
ワイゾンも方向を確認しに走る。
クライセンは微動だにせず、ただ海を見つめている。その先にはまだ視界に届かないパラ・オールがあった。そこにマルシオがいる。クライセンはほとんど無意識に風を起こしていた。
ティシラは不安そうにクライセンの背中を見守っていた。彼女も感じていた。マルシオが邪悪なものに捕らわれてしまったことを。だが今はどうすることもできない。ただクライセンに望みを託すしかなかった。
トールがティシラの隣に立つ。
「凄いな」吹き荒れる風の中で空を仰ぎながら。「彼がやっているんだろ。これも魔法か?」
「魔法とは違うわ」ティシラはクライセンから目を離さないまま。「この世はすべて自然の上に成り立っている。そこに生きる私たちも自然の一部なの。蝶の羽ばたき一つが台風に影響を与えることもある。そんな自然の理を知る者はそれを操ることができるのよ。それは言葉や理屈ではなく、体で感じるもの。魔法で風を起こすこともできるけど、今のこの現象は違う。そもそも魔法は任意選択物。あなたの剣と同じ。使い方ひとつで善にも悪にもなるし、持たなくても生きていける。でも自然に逆らうことはできない。それを支配する者は賢者と呼ばれ、その数は少ない」
トールは間を置いて首を傾げた。
「彼は魔法使いじゃないのか?」
よく分かっていないトールにティシラはこれ以上説明しても無駄だと思い、口角を下げて適当に終わらせる。
「魔法使いよ」
あからさまに冷たくあしらわれてトールもその話はやめることにした。魔法に興味がないわけでなかったが、あまり知識は持たない。今それを学ぶ必要もないし、と気を取り直す。
風が巻き上がり、目を顰める。船はぐんぐん速度を上げていた。まるで何かに引き寄せられるように。とうとうあの太古の遺跡をこの目で見る時が近づいているのを感じる。戦争により沈没した大陸、ノートンディル。今そこには何があるのだろう。だが、それよりも友の身が心配だ。クライセンは未だに動かない。突風でマントが踊るようにはためいていた。
2
そこは少し寒かった。気温が低いせいか、避けられない恐怖のせいなのか、マルシオには区別できなかった。
両手両膝を地につき、肩を揺らしている。絶望が頭から切り離せない。額から流れた汗が地面に落ちた。無意識にそれを目で追っている。
パラ・オールの遺跡の中は邪悪な魔力に塗れていた。ハゼゴのそれだけではなかった。ギメルの呪い、そしてノーラの狂気がここで渦巻いていた。この禍々しい空気だけでも圧迫されてしまうというのに、マルシオはハゼゴに圧倒的な力の差を見せ付けられて生きたまま死んでいるような錯覚に惑わされていた。
マルシオには毒のことなど考えている余裕はなかった。遺跡の周りがどうなっているかは分からないが、この中ではそれは感じられなかった。
その空間は長い時間をかけて海水に侵食された岩で囲まれている。薄暗く、天井の高い穴蔵は一見ただの洞窟のようだが、よく見ると神殿だったことが分かる。適当に立っているだけのような柱もあちこちに装飾の後が残っており、その残骸は等間隔に並んでいる。だがマルシオにはそんな些細なものは目に入っていなかった。マルシオの見つめる地面には魔法陣が描かれていた。複雑なものではない。逆さになった五芒星の中に角を持ち、髭の生えた動物の絵が当てはめられている。辺り一面には無数のロウソクが所狭しと並べてある。普通なら息苦しくなってもおかしくない数で囲まれているのに、熱気はなかった。どうやらロウソクは人の脂で作られたもの、灯された炎はこの世のものではないようだ。
この空間を歪ませるものは邪悪な魔力だけではなかった。それ以上に、人間の最も深い部分にある怨恨、邪念、悲壮のような陰のものが寄り集まり、今にも形になりそうなほど色濃く蓄積されていたのだ。守る手段もなく、無防備に身を晒しているマルシオにはそれを痛いほど感じられた。ほとんど異空間だった。人間の世界だとは思い難い。
ハゼゴの紫のローブの中身は骸骨だった。ハゼゴも昔は人間であり、そして正当な魔法使いだった。だがある時、禁を犯してしまった。蘇生の魔術を使ってしまったのだ。人の生き死にや魂を操ることは自然の法則に反する。それに決して触れてはいけない。犯してしまえばその者も呪われ、人の形を失う。ハゼゴは分かっていた。決して幸せになんかなれないと。
しかし子供を事故で失い、悲しみで正気ではいられなくなった。なまじ力を持っていたからこそ、耐えることができなかった。そして、とうとう禁じ手を使ってしまったのだ。生き返った子供はただの血肉の破片の集まりだった。ハゼゴはそれを見て完全に自我が崩壊してしまい、完全に人の心を失った。まともでいられなくなった彼は、子供の肉を食い尽くした。しばらくするとそのことも忘れ去り、死んでしまったわが子を探しに彷徨い始めた。夜な夜な徘徊しては違う、違うと呟きながら子供を殺し続けていた。悲しみに取り憑かれた彼は、気がつくと魔界に迷い込んでいた。そして悪魔に唆されて魂を捧げた。それだけでなく悪魔は彼の肉体を食い漁った。だが魂だけは魔界に繋ぎ止められてしまい、死ぬことも許されなかった。ハゼゴはすべてを失い、骨だけで地を這い続けた。今もそれは続いている。
ハゼゴはこの苦しみから永遠に解放されることはないと気がついた。そんな時、ノーラと出会った。ノーラが彼に与えてやると言ったのは、完全なる死だった。ハゼゴは切望した。死ねる、やっと終わるとノーラに縋った。
「この時を最後に」ハゼゴはマルシオを見下ろして。「私の魂は解放される」
マルシオは顔を上げた。ハゼゴを睨み付け、のろりと立ち上がる。ふらつく足を踏ん張りながら。
「魔薬なんかで楽になんかなれるものか」
「清きものでないからこそ私を救えるのだ。神はいない。奇跡など起きない」
「俺がお前を救ってやる」マルシオは虚勢を張る。「お前に相応しい死を与えてやる」
ハゼゴは嗤った。彼にはマルシオがただの子供にしか見えない。
「君には他の役目がある。焦るな」
「俺はお前の思い通りになんかならない」
「その真っ直ぐで純粋な魂を生贄に、魔法王を呪い殺す」
「させるものか」マルシオは歯をむき出した。「俺はこの世にあって然るべき高貴な魔法を蘇らせるんだ。そして人々に神を敬い愛する心を取り戻させるためにここにきた」
「白魔術師か」ハゼゴは言い捨てるように。「高貴な魔術など、そんなものはとうに滅んでいる。戦争と共にな。天使が地上からいなくなってからというもの、人間は天に見捨てられたと落胆し、光の魔法は廃れていった。今魔法使いと呼ばれる者が操っているのは理想と憧れに捕らわれ、時を経て形を変えていった武力に過ぎない。もう本来の姿は忘れ去られた。取り戻すなど、不可能だ」
マルシオは体を揺らしながら背を伸ばす。確かに、と思う。ここに希望はなかった。
「……そうだな」マルシオの目は虚ろだった。「お前の言うとおりかもしれない。俺は天使が地上に戻ってくれば、また昔のような豊かな魔法が栄えるものだと信じた。ノートンディルの一角が浮上したと聞き、それは復活の前兆ではないだろうかと思ったときもあった。だけど、そうではないんだろうな。古きものを思い出にし、新しいものを生み出す方が在るべき人の形なのかもしれない。俺はそれでいいと思うようになった」
マルシオは表情を変えない。
「だけど、それでもお前だけは虫酸が走るんだ。お前はいつの世も、どこにいてもただの呪われた者でしかない。もういい加減に滅ぶべきじゃないのか」
「そうだ。やっと滅ぼしてくれる者が現れたのだ。そのためには犠牲が必要だ。何かを手に入れるためには何かを失わなければいけない。それがこの世の生業だ。なぜ邪悪な魔術がこうしてなくならないかと言うと、栄光の影にはかならず犠牲が伴っているからだ。いくら綺麗事を唱えても無駄だ。君も何か欲しいものがあるなら何かを犠牲にしなくてはならない。その覚悟がある者だけが栄光を手に入れることができるんだ」
そうかもしれない、と思った。「犠牲」という言葉が重く感じるだけで、実際、現実はそんなものなのかもしれない。特にこの人間界というものは時間の流れが異常に早い。マルシオがアストラル(幽体)を通してこの世を見通したとき、それは激しく目まぐるしく色を変えて見えた。この混沌の中で人間は同じことを繰り返す。だが全く同じではない。限りない螺旋を描いている。完璧を求めて止まないその姿は、愚かで脆弱のようでいて、猛々しく勇ましい。決して人は戦うことをやめないだろう。平和や幸せを求めながら、いつまでも殺し合うのだろう。
純粋、故に残酷。マルシオにはそれが羨ましいと思えた。マルシオは色を持たない。人間と関わるうちに、真っ白な自分が物足りなく感じることもあった。だがそれに気がついたとき、彼は微かに色づいていたのだ。マルシオはもっと欲しいと思った。ここから消えてしまわないように、どんな形でも成したいと思うようになっていた。それが何を意味するのか、マルシオは選択に迫られた。恐怖があった。何も失いたくない。できればこのまま、好きなものだけを見ていたい。真っ白なままでそこにいたかった。だけど膝を抱えてしまったら皆においていかれてしまう。一人ぼっちになってしまう。だったら走った方がマシだ。転んで怪我して、汚れてもいい。それでも、そんな自分を振り返るのが怖くて仕方が無かった。その理由が今なら分かる。選ぶことは何かを「犠牲」にしなければいけないからだ。後悔するかもしれない。だがその欲求は消えなかった。それどころか拒絶しようとすればするほど膨らみ、大きくなっていく。もう止めることは無理だと思った。何を捨てて傷つけても、守りたいものがある。
3
マルシオの心から、完全に恐怖は消えていた。
「ハゼゴ」マルシオは改めて彼に向き合う。「お前の邪悪さが俺の迷いを断ち切ってくれた。やっと答えが出たよ」
その声は穏やかだった。
「お前が俺を生贄にクライセンを殺すと言うなら、俺はこの命を犠牲に、彼を守る」
ハゼゴは彼の周囲の空気が清められていくのを感じていた。
「あいつに死なれたら困るんだ。泣く奴がいるんだ。たぶん、死ぬまで泣いてるだろうな。それに、俺も……嫌だ。あんな奴嫌いだけど、少しくらいは悲しいかもしれない。もう俺の目的とかどうでもいいや。あいつを死なせたくないんだ。そのために命を懸ける。なんでだろうな、そう思ったら全然怖くないんだよ」
ハゼゴはマルシオを取り巻く魔力が変わったのに気がついた。それはもうこの世にはない空気だった。白く、清く、高貴な力がそこにあった。ハゼゴはそれを直接見たことも触れたこともなかったが、すぐに感じた。それが遠い昔にこの地から失われたはずの、彼が最も疎むべき光の魔力だということを。
なぜ気がつかなかったのだろう。その少年の姿形、瞳に灯す白き光。間違いない。そして、笑う。
「……そうか、そうだったか」ハゼゴの心が昂ぶった。「クライセンを殺すに相応しい生贄に君が選ばれた理由が分かったよ。これはいい。私の最後の大魔術を飾る生贄が……天使とはな!」
ハゼゴの笑い声はまるで毒霧のようだった。きっと耳を塞いでも体の中に流れ込んでくるだろう。目に映るわけではないが耳に不快だった。気を失いそうなほどに。マルシオは耐えた。瞼が落ちそうだった。いっそ落としてしまえたらどんなに楽だろう。だがそれはできなかった。したくもなかった。
「聖帝天、左の光。ローレン第二天子」マルシオは片手を天に掲げた。銀の瞳に光が灯る。「そうだ、俺は天使だ。聖なる魔術を見せてやる」
ハゼゴは背を丸め、ゆっくりと印を結んだ。
「素晴らしい。白と黒の魔術対決だ。君の名を教えておくれ。我が名は破壊の象徴、魔術師ハゼゴ」
魔術師の間で敵に名を名乗ることは禁じられていた。名前には相手を支配する力があったのだ。その行為は敵に手の内を明かすことを意味する。それでもハゼゴは敢えて自ら名乗った。これは罠ではなかった。マルシオを高貴な力の持ち主として認めたのだ。
もう一つ、魔術師の間にはある暗黙の掟があった。それは敵同士名乗りあうことで、お互いの命とすべての力をぶつけ合う証しとするのだと言う。本来は魔術を個人的な理由で濫用することは禁止されていた。しかし自然を操る術を習得した者と言え、所詮は人間。自分の力を試したい、認められたいと思うのは誰もが持つ願望だった。それに好き嫌いもあれば喧嘩もする。敵対し、争いが起こることもあるのだ。それでも魔術師同士の力比べを公に行うことが認められることはなかった。そんな中で、いつの間にか術師同士の間では誰に許可を貰うでもなく、人知れず名を名乗り合って対決するという法則が生まれた。そこには必ずどちらかの敗北、即ち死が伴う。例えどれだけ力の差があったとしてもその結果を受け入れ、周囲はなかったように暗黙するのだ。ハゼゴは邪悪だが、誰もが認める大魔術師であることには間違いなかった。ここでマルシオが名乗ることを拒否してしまったら、礼儀を弁えないのは彼の方だと見做される。だがそれを口にしてしまえば間違いなく命を放棄しなければいけないのだ。そして勝ち目も、ない。それでもマルシオには拒否する理由はなかった。迷わずにハゼゴの挑戦に応える。
「スウォル(光)ガーディアン。マルシオ・ローレン」
勝てる要素は何一つなかった。力の差も歴然ながら、その場所、ある空気、取り巻く魔力のすべてがそれだけでマルシオを弱らせる。だがマルシオは、悪くないと思う。このまま抵抗空しく生贄にされ、クライセンの足を引っ張ってしまうかもしれない。友を悲しませ、苦しめてしまうかもしれない。
(悪いな……後は頼む)
マルシオは無責任に、そう心の中で呟いた。マルシオはこんな奴にクライセンが負けるはずがないと思っていたのだ。ハゼゴがどんなに力があっても、あの男には適いはしないと確信していた。だから自分のしたいようにできる。だからここで逃げたいという気にはならなかった。
室中を取り囲むように、無数のロウソクが一斉に炎を巻き上げた。その代わりに闇が落ちてきた。そこにはマルシオとハゼゴが対し、炎と魔法陣だけが浮かび上がった。
マルシオは既にハゼゴの術中にはまったと感じた。だが彼はまだ、どうすれば勝てるかを考えていた。
(ここに光はない。こいつに光は通用しない。慈悲も救いもない。無謀なのは分かっているが……ここまできたらやるしかない)
掲げた手に集中する。熱と共に光が集う。その小さな光はマルシオを照らし、彼の全身が白くぼやける。その美しさは神の為せる業だった。マルシオの背中からふわりと羽が生えてきた、ように見えた。白い光がそれを象っていた。羽はマルシオを称えるように彼を優しく包んだ。
マルシオは目を閉じ、呪文を呟いた。纏う光が粉となり、掌から天へ昇る。それは闇の中に溶けていく。
ハゼゴが両手を前に伸ばし交差させた。それだけでマルシオは顔を歪ませる。
「天使召還術か」ハゼゴの透いた口元から息が漏れる。「仲間に救いを求めるか。どうやら君は術師としては少々愚かなようだな。ここは闇に隔離された空間だ。天に君の声など届きはしない」
マルシオはじっと呪文を唱えている。手から出る光がいくら闇に掻き消されても止めようとしない。
「いや」ハゼゴはそんな彼の姿を眺めながら。「きっと分かっているんだろうな。私もそうだった。大切な者を救えると信じていた。切実な心を持ってすればきっと誰かが認めてくれると。人は私を邪悪と言うが、私にも信念はあった。それが裏切られたとき、人は呪いに捕らわれる。気の済むまでやるがいい。奇跡を信じて」
「黙れ」マルシオはハゼゴを睨んだ。「お前の体験談なんか参考にならないんだよ。お前は敗北者だ。俺は奇跡なんか信じてないし信念もない。ただやりたいことをやってるだけだ。何が起きても恨みはしない。すべてを懸ける。それだけだ」
闇が動いた。マルシオは目眩に襲われる。体制を崩し、無防備になったところに、空間を包んでいた闇が無数の刃となってマルシオの体に突き刺さる。
声すら出なかった。汗が額を伝いぽたりと落ちる。闇の刃はマルシオの体の中に入り込み、まるで高熱で溶けた鉛のように畝っている。息ができない。五感が鈍り意識が遠のく。マルシオはそれでも手を下げなかった。その光も失われない。
「まだだ」ハゼゴは笑っている。「まだ殺さない。苦痛こそが最上の快楽。味わえ。そして永遠に忘れられないようにその体に、記憶に刻むのだ」
マルシオは空を仰いだ。体が重い。潰れてしまいそうなくらい。闇はマルシオの中に流れこみ続けている。自分の体が石のようだった。考える力も失われていく。ただ呆然と、ハゼゴの放つ闇を許していた。抵抗できないし、する気力もない。吐き気がする。いっそ体の中のものを全部吐き出してしまいたかった。立っているのか倒れているのかも区別できなくなってくる。ただ掌の光だけが視界に映っていた。それもぼやけてくる。
マルシオは力を失い、吊られた人形のように仰け反る。白目を剥く。事切れた、わけではなかった。急に光が強くなる。掌から昇るそれも勢いを増す。
「なんだ! 何が起きた」
ハゼゴが戸惑った。彼も慌てて力を込めた。さらにマルシオへの侵食は強まった。なのに、ハゼゴの闇の力に比例するように白い光は激しく天に昇っていく。彼を包んでいた透明な羽もその光の流れに巻き込まれて、千切れながら乱舞している。周囲のロウソクが騒ぎ始めた。ハゼゴは辺りを見回す。
「バカな……ここは闇の牢獄。なぜ光などが……」
ハゼゴは集中した。この現象の原因を探る。その時間は短かった。
「そうか……」
ハゼゴは交差した腕をさらに絡ませ、呪いの杖を召還した。それを数回まわし、マルシオに向かって突きつける。マルシオはそれに気を取られるとこなく、ただ光を放っていた。いや、彼の意識はほとんどなかった。なるままに体を委ねていただけだった。
「もう力比べをしている時間はないようだ。残念だよ、聖者マルシオ」ハゼゴは杖を振り翳した。「……死ね」
杖を構え、マルシオの胸に狙いを定める。止めを、と顔を上げる。
4
だが、体が動かなかった。その一瞬でハゼゴの術は失敗に終わった。周囲の闇が渦巻きながらハゼゴの体の中に吸収されていく。再び神殿が姿を現す。ハゼゴは愕然とした。やっと自分の体の自由が奪われた理由がわかった。闇の中で四本の剣に、四方から貫かれていたのだ。肉体を持たない彼は痛みを感じないために、気づくのが遅れてしまったのだ。盲点だった。現実に引き戻されたハゼゴは完全に取り囲まれていた。トール、ワイゾン、マイ、キジの四人がそれぞれの剣で彼の動きを封じていたのだ。
「貴様ら……」誰だかを確認している余裕はなかった。「魔術師同士の戦いを邪魔するな!」
ハゼゴは頭上から強い光に照らされ、反射的に手を翳した。指の隙間から、大きな光の塊が形を成しているのが見えた。ハゼゴはそれに目を奪われた。それは天上界への扉だった。光は弾けるように空間を包んだ。その瞬間に四人は素早く剣を抜き、ハゼゴから飛び離れた。光は膨張し、かと思うとまるで生き物が呼吸しているかのように縮小する。再び現れたそこには、光の矢に胸を貫かれたハゼゴが震えていた。マルシオが放った矢ではない。そんな力など残っていなかった。彼は朦朧としたまま、手を垂らしてハゼゴを見つめている。
光の中に人の影が見えた。ゆっくりと姿を現す。そして優雅に、マルシオの前に背を向けて舞い降りた。
秀麗な青年だった。マルシオと同じ銀の髪と瞳を持っている。全身が上品で輝かしい装飾品で包まれている。高貴で威厳のあるその姿をさらに引き立てているのは背中に舞う、白く輝く大きな双翼だった。その羽ばたきでここにある重苦しい空気を薙ぎ払ってくれているようだった。彼の姿と存在だけで心が洗われていく。羽の動きに合わせて靡く長い髪、限りなく優しい細い瞳。動いているのが幻覚かと思わせるほど絵に描いたような神々しさだった。美しい、その言葉が何よりも相応しかった。「天使」は、音を立てずに指先からそっと地に足を降ろす。手には銀の弓弦を携えている。
マルシオはその名を口にした。
「……ネイジュ・ファクトラ様」
ネイジュは答えず、ハゼゴを見下ろした。ハゼゴはよろめきながら胸に突き刺さった光の矢を掴もうとするが、掴めない。矢が膨らみ始めた。ネイジュは黙ってそれを見据えていた。端々に散ったトールたちも剣を片手にそれを見守っている。ハゼゴの体の隙間から光が漏れ出した。
「天使よ、私を救ってくれるのか」
ハゼゴは奇妙な形に変形する。だがその声には歓喜を宿していた。
「私を滅ぼしてくれるのか……感謝する」
ネイジュは答えない。薄く開いた瞳で、哀れな空洞の彼に情けを与えた。
ハゼゴは光に包まれ、潰れるように消滅した。紫のローブが包むものを失い、はらりと落ちる。
ロウソクの炎がすべて消えた。そこは微かな煙の匂いと静寂に包まれる。
ネイジュが羽を収め、ゆっくりとマルシオに向き合う。未だ無表情で虚ろな彼を見つめた。マルシオは鈍った五感を取り戻しながら状況を把握した。重い唇を動かす。
「……ネイジュ様」敬意を払う余裕もない。「聖五大天使の一人が、なぜこんなところに」
頭上の光は収まっていた。ネイジュは幻や思念ではなく、本体としてここに降臨していた。発した声は低く、細かった。
「マルシオ・ローレン」その声は心地よい響きがした。「君に呼ばれたんじゃない」
「……そうだと思う」マルシオはふっと笑った。「こんなことができるのは、あいつしかいないよ」
離れた柱の隣にクライセンが立っていた。その後ろにティシラもいる。一同は黙って天使たちの再会を見守った。
「なぜこんなところに、とは私の質問だ」ネイジュはマルシオに哀れみの目を向けた。「こんなに暗く汚れた空間で、あのような呪われた者に命を晒すなど……」
「ネイジュ様」マルシオの意識がはっきりしてくる。「俺は間違っていますか」
「それは誰にも分からない。だがここにいることは間違っている。君は天上界で生まれた。天上界で生きるべきだ」
「なぜですか」
「ここに私たちの居場所はない。もう分かっているのだろう?」
「天使は人間を見捨てたのですか」
「私たちはもう必要ないのだ。人間は違う道を選んだ。私たちは幻でいる方がいい。私たちが人間にできることは希望を与えることなんだ」
「人間は」マルシオの声が震えた。「救いを求めています」
「救いはある。それが目に見えないからこそ人間は理想を追い、自らの手で作りあげようとするのだ。それは強さと安らぎを求める、人間の防衛本能の中に組み込まれているんだ」
「人間は弱い。このままでは人々は俺たちを忘れ去り、いつか闇に閉ざされてしまいます」
「彼らの本能と欲求は私たちの想像を遥かに超える力を持っている。弱いから、命に限りがあるからこそだ。人間は暗闇で炎を起こせば照らされることを知っている。私たちが差し出す必要はないのだ」
「でも」マルシオは眉を寄せる。「現状はご存知のはず。ノーラは、魔薬は未知の脅威です。このままでは人間は滅んでしまうかもしれない。それでも天使は何もしないのですか」
「ノートンディルは人間の過ちによって崩壊した。地上から我々の居場所を奪ったのは他ならぬ人間だ。私たちに忠実だったランドール人の血も絶えかけている。だが人間のすべてが滅んだわけではない。未だこの世に幸はある。何が足りないというのだ。増えすぎて余っているほどではないか。これはそこから生じた歪みが起こした災害なのだよ。むしろ我々が介入してしまう方が危険だ。その歪みはさらに増し、修正がきかず今度こそ完全にすべてが途絶えてしまうかもしれない。そう思わないか」
「それじゃあ……天使は何もしないんじゃなくて、何もできないということなんですか……?」
「そうだ」
そのたった一言は、マルシオの胸に突き刺さった。
「正直に言おう。天使は神ではないのだ。人間を作ったのも我々ではない。進化するも滅ぶも人間という命の選ぶ道だ。我々に救う力はない。天使は決して万能ではない。天使が地上から離れて行ったのではなく、追い出されたのだと、私はそう思っている。だが、恨みなどは一切ない。我々は流れを、時代を受け入れた。そして遠いところで今も尚、人間を守りたいという気持ちを持っている。その形にならないものが天使の心であり、力なのだ」
マルシオは俯いた。
「ここで君が天使としてできることは何もないんだ。君だけじゃない。私だって、正当な手段と祈りによってここに呼ばれたからこそ姿を現したが、きっとこうして召還されるのはこれが最後になるだろう。なぜなら、その必要がないからだ」
「ならばなぜ人間は天使に憧れて止まないのでしょうか」
「人間は恐ろしいものより優しいもの、醜いものより美しいものを欲しがる。この世に邪悪なものがなくならない限り私たちは見えなくても存在し続ける。私たちは光という輝きで人間に勇気を与え、闇に迷う者を導くのだ。それでは不満なのか」
「……天上界へ戻れば、俺にもその役目があるのですか」
「そうだ。それこそが君の役目だ。だがここにいてはそれも果たせない。帰ろう、マルシオ。皆、君のことを心配している。私は君を迎えにきたんだよ」
その言葉でマルシオが微かに揺れた。覚悟はしていた。が、実際この時がくると、思っていた以上に胸が痛んだ。自ら天使召還を行うと決意したときからその可能性は確実にあると、マルシオもそのつもりでいた。
「分かっているのだろう? さあ、一緒に帰ろう」
ネイジュはマルシオに手を差し出した。マルシオは顔を上げ、それを見つめる。
今まで黙っていたティシラが慌てて駆け出そうとした。だが、素早くクライセンに腕を引かれて止められる。ティシラは泣きそうな目をクライセンに向けたが、彼は表情を変えずに「行くな」と言葉にせずに伝えた。ティシラは留まって、唇をかみ締める。体の力を抜き、再びマルシオを見守った。
マルシオは虚ろなまま口を開いた。
「確かに、もうこの世界には天使は必要ないのかもしれない。あなたの言う通り、人間は違う道を歩んでいます。実際俺もこの目で見てきました。きっと今天使が戻ってきたとしても秩序が狂い、人々は混乱するだけなのかもしれない」
5
「それでも人間は未だに天使に憧れを抱いています。ないものを欲しがる強欲な生き物です。むしろ俺たちの手に負えないほど荒々しい生き物なのかもしれない」
ネイジュは黙って聞いていた。
「……いや、そんなことはどうでもいいんだ」
そう呟く彼の言葉に、少し目を動かした。マルシオは後悔したくないと、強く思った。
「父も、周りの皆も俺が魔法使いになるって、人間界に行くって言ったら凄く反対した。当然だと思った。でもそれは単なる体裁だとしか思ってなかった。俺だって天使が魔法使いになんて、おかしな話だと思った。でもきっと人間界に行くための口実なんて何でもよかったんだ」
アカデミーでも一目置かれる存在だった。そこまでは自信があった。魔法使いとしてじゃない。やっぱり天使は特別なものなんだと、単純に調子に乗っていただけだった。現実では自分の力なんてあまり役には立たなかった。ワイゾンが魔薬の薬草に襲われたときに……いや、クライセンの家で猫の姿をした魔法使いにまったく歯が立たずに、こき使われていた頃から自分の中での歯車が狂い始めていたのかもしれない。いつも隣には魔族がいた。魔族なんて邪悪な存在だとしか思っていなかった。そうじゃなかった。魔族は、そして人間は天使にない力を持っていた。認めるしかなかった。天使は何でもできると思っていた。だが、自分は何もできなかった。コルテのときもそうだった。たかが浮かばれないで大地に執着している母子の霊。彼らに光は届かなかった。彼らが受け取ったのは「心」だった。
自分はいつも一人だった。違う。一人じゃなかった。だから今もここにいる。必ず誰かが傍にいた。気が付くとそれが当たり前のように感じていた。
ハゼゴの挑発に乗って勝手なことをしてしまったことも、これが自分の力を、存在理由を確かめる好機だとどこかで思った。生き死になんてどうでもよかった。ただ、彼らが自分のために駆けつけてくれた。それが答えだと思った。
「嬉しかった。みんなの顔を見て安心した。いや、やっぱり、なんて思ってたかもしれない。ここにいていいんだと、初めて自分の足がこの人間界の地面に着いていることを確認した気がしたんだ」
マルシオに迷いはなかった。言葉を飾りも、選びもしない。
「天上界へは帰りません。いえ、俺はもう帰れません」
ネイジュは微かに眉を寄せた。
「……なぜだ」
「散り急ぐ命に毒されてしまいました。俺には天上界の永遠という時間は長すぎるのです」
「滅ぶ命を選ぶと言うのか」
「ここには俺の欲しいものが、欲しくても手に入りにくいものがたくさんあります。それを永遠に天上から眺めているなんて、とても耐えられそうにありません」
「何を言っているのか分かっているのか。人間は死んでも魂の循環で何度でもやり直せるが、君は、天使はそうはいかない。だからこそ永遠という時間を戴いているのだ。君は人間の変化についていけるようには出来ていない。君はまだ若い。目の前にあるものに慣れて、麻痺しているだけなんだ。この人間界に永遠はどこにもないのだぞ」
「……それでも」マルシオの決心は変わらない。「奪われてしまったこの心は、ここから動かないでしょう」
「…………」
「あなたがもし、俺を無理やり連れて帰ったとしても、その心はここに永遠に留まります。そう、人間界にも永遠はあります。心です。同じではなくても形を変えながらずっと、人から人へ受け継がれていくんです。俺は天使のように綺麗過ぎる整った直線を歩くより、いろんな色が絡み合っててそこから新たに生まれるものを探す方が性に合ってます。愚かとでも、異端とでも何と言われてもいいんです。お願いします。もう俺は死んだと思ってください。何なら、俺の言ってることがそれに値するなら殺してくれても構いません。俺にとっては同じことなんです」
マルシオはネイジュの目を真っ直ぐに見つめる。その目は震えていた。
「天使の名を……ローレンを捨てます」
ネイジュもマルシオを見つめ返した。ネイジュはその天の瞳ですべてを見通した。
ふっとマルシオの背後にいるクライセンに目線を移した。彼と目が合う。睨み付けているようにも見えた。過ちを犯すことは許さない、そんなことの為にここに呼んだのではないという言葉を感じた。賢明な判断を迫られていることに気がつく。マルシオの言う通り、ここには天使という肩書きは関係なかった。
マルシオを見る。なぜ彼がこんなふうになってしまったのか分からない。確かに、天上界にいたときからマルシオにはどこか変わったところがあった。当然のようにある天上界の秩序に、素直には従おうとはしなかった。理由を聞いても大した返事は返ってこない。何かに逆らっているわけでも、特に原因があるわけでもなかったのだ。それが彼の本質なだけだった。次第にマルシオは一人で過ごす時間が増え、家族ともほとんど会わなくなった。誰に迷惑をかけるわけでもなく、彼を気に止める者も少なくなってきた。しかし、ある日マルシオは突然人間界に行くと言い出して周囲を騒がせた。今更天使が人間と関わるなど、と最初は問題とされた。だが彼なら、マルシオなら勝手にさせればいいという、いい加減なことを誰かが呟いた途端、それに同意して関わりを避ける者が増えていった。それをマルシオがどう感じたかは知らない。数少ない上層の者だけが彼を説得し続けた。マルシオは反抗するのではなく、聞く耳を持たないといった様子で意志を曲げなかった。そして最終的に、誰の許可も貰わないまま姿を消してしまっていた。彼を追う者はいなかった。監視も含め、数人の者だけが彼をずっと気にかけていた。ネイジュもその一人だった。
ネイジュは、誰もマルシオを見捨てたわけではないことを伝えたいと思った。だがそこにある決意が揺るぎことを確認すると、言えなくなってしまう。マルシオは逃げているわけではない。自分と向き合って戦おうとしているのだ。その場所を見つけたのだと思う。奪う権利は自分にも、誰にもない。同時にネイジュに悲しみの色が灯った。マルシオはそれに気づいて唇を噛み締めた。こみ上げるものを抑える。ネイジュはふわりと羽を揺らし、差し出した手をそっと引いた。
「承知した」その声は優しかった。「……マルシオ・ローレン。君を天上界から追放する」
マルシオの目が熱くなった。今言葉を発してしまえば、一緒に別のものも流れ出てしまいそうで口を開けなかった。
ネイジュは目を逸らすマルシオを見つめた。そして、ふっと微笑む。
「マルシオ」ネイジュはマルシオの頭を撫でた。「強く生きろ。我々は君を恥だとは思わない。ずっと天上から見守っている。君が自分で自分の道を選んだことを、君の父上も誇りに思ってくれるだろう。ただし、決して力を誇示し驕ってはいけないよ。この世界は一人では生きられないようになっている。神はここをそういうふうに造られたのだから。だからこそ君はここを選んだのだろう」
マルシオはぐっと涙を飲み込んで顔を上げた。
「俺は、ここが好きなんです」
ネイジュは浅く頷き、マルシオの額にキスをする。そして一歩後退し、背中の羽を擡げた。ネイジュの体がふわりと浮く。
「さよなら」
マルシオは返さなかった。人間が一番嫌う言葉だった。今ならその意味がよく分かる。ネイジュはそれ以上何も言わず、再びクライセンに顔を向けた。もう彼から鋭いものは消えていた。クライセンはその目を伏せ、ネイジュに感謝の意を表す。
(まだ地上に正当な召還術を使える者がいたとはな)ネイジュはクライセンの意識の中に語りかけた。(スウォルの子、マルシオを頼む。彼は光の心を持ってして道に従っている。まだ眠っている力は計り知れない。覚醒すれば一人では抱えきれないほどの運命に見舞われてしまうかもしれない。そのときは力を貸してやって欲しい)
クライセンは薄く微笑み、同じく声にせず答える。
(私は彼の保護者じゃない。だが大天使様の直々の申し出を無碍にするのはさすがに気が引ける。もし彼が道を間違えたときは私が戒めよう。それでいいかな)
(十分だ。感謝する、ベルカナ(誕生)の守護者よ。いずれ地上からランドールの血は絶えるだろう。残る時間の中で君は何を守り、何を残す?)
(生まれたから生きてきた。この血に何の未練もないよ)
ネイジュは沈黙した。クライセンを見つめる目に悲しみ、哀れみのようなものが交差していた。それを閉じ、体は光に包まれる。
(マルシオの気持ちが、何となく理解できる)
ネイジュは昇りながらその言葉をクライセンに残した。
(周りが君を放っておかないようだな。その運命に光の加護を……)
光は完全に消え去った。マルシオを始め、そこにいた皆がその奇跡を静かに見送った。今更驚くこともなかった。逆に現実離れしたその出来事は夢か現かも判断し兼ねるほどだった。マルシオが今まで通りここにいる。それだけで十分だった。それ以上は必要なかった。
静寂と余韻を最初に破ったのはティシラだった。立ち尽くすマルシオに駆け寄る。マルシオは彼女の姿を見て、我に返ったような感覚に襲われた。そして今までのやり取りを見られていたかと思うと少し恥ずかしくなる。
ティシラは何も言わなかった。マルシオの前で複雑な表情をしていた。いつものように怒鳴りつけようか、それとも、無事でよかったと、ここに残ってくれた喜びを素直に伝えようか迷っていた。マルシオはそんな彼女の心理に気づいた。ティシラは俯いたまま目を揺らしていた。こんな彼女は初めて見た。いや、違う。ティシラは最初からこうだったんだ。そう思った。顔を合わせ、口を開けばいつも喧嘩ばかりだった。嫌いだからじゃない、と今更思う。きっとティシラはどこかで感じていたのだろう。天使の力を鼻にかけながらも、何かから必死で逃げようとしていた自分のことを。それが気に入らなかったに違いない。だから素直に、自然な感情をぶつけてきていたのだ。今、ここでマルシオは何かが変わった。大切なものをひとつ失い、ひとつ手に入れた。ティシラはそれを反映している。彼女は「鏡」のような存在だと、そう思った。
だからと言って、急に優しくはなれない。マルシオは照れを含む皮肉な笑みを浮かべた。
「……何だよ」
ティシラが顔を上げた。そして、それを見て考えるのをやめた。笑いも泣きもせずに、黙ったままマルシオに抱きついた。
マルシオは戸惑う。手のやり所に困った挙句、そっと彼女の肩に添える。暖かい、と思った。誰かの体温なんて意識したことなんかなかった。こんなにも暖かいものだったのかと、初めて気づく。魔族でも何でもいい。伝わる鼓動は自分と同じものだった。永遠ではない、だから愛しいと思える。だからこそこの一瞬を大切に感じるのだ。確かにここは自分の居難い所かもしれない。だが、そもそも居易い場所なんてどこにあるのだろう。そんな難しいことはこれから、時間が許す限りでゆっくり考えよう。マルシオは今指先から敏感に感じるものを心に刻んでいた。