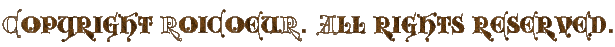第14章 二人の王





1
パライアスは暗雲に包まれていた。
希望の光はあるはずだった。人々はまだそれを失ってはいない。王を信じ、奇跡を信じてお互いに手を取り合いながら恐怖と戦い続けていた。
しかし未だ見出せてはいなかった。いつか終わる。だが、いつ終わるのだろう。そして結果は? それはきっと一瞬にして訪れるのだろう。その時、必ずこの闇から解放されると信じていた。
信じるしかなかった。それだけが人々を地上に留めるただ一つの手段でしかなかった。
空は厚い雲に覆われていた。どこが昼夜の境なのか分かりにくいほどに。太陽が昇っても光は差さない。いっそ一番高いところから一番長いものでその雲をかき払ってしまいたいなどと思わせるほど人々を圧迫していた。
最初は軍の優勢だと思われた。大量とはいえ、敵は愚鈍で知能も心もないただの死体なのだ。ましてや武器や戦う術も持たない。体力さえ保っていれば薙ぎ払うことなど容易かった。
だが、さらなる恐怖は夜明けを迎えたときに訪れた。ぼこぼこと大地が動いた。そこから出てきたのはゾンビではなかった。
それは土の塊だった。人の形をしている。目鼻口、耳も爪もある。そこに宿る表情は怒りに見えた。違う、そんな人間が共感できるような感情ではない。それは暴力と殺戮を求める渇望だった。土人形は乾いていた。きっとそれは満たされることはないのだろう。土人形はただ暴れるためだけに造られた凶暴の塊だったのだ。
その重量と怪力は人を簡単に押し潰した。痛みも感じない、疲れも知らない。周囲を取り巻くゾンビと人間の区別もなく、その三メートルほどの巨体は暴れ回った。
一度は落ち着いたはずの人々の心は、再び大きく揺れた。それでも逃げ場はどこにもなかった。土人形は「巨人」と呼ばれた。もちろん人間もただ逃げ惑うだけではない。攻撃を受けた巨人は斬られ、潰され、泥になって崩れ落ちる。それは地に吸収されて、再生する。巨人は次から次へと大地から生まれでてくる。
死人が数を重ねていく。その死体はしばらくすると、敵となって動き出す。人々はその光景が現実のものとは思えなかった。
これが現実なら、ここは人間のものではない。この大地は悪と呪いに塗れ、永遠に光が灯ることはないだろう。
戦うしかなかった。絶望に染まる人々を留まらせるために、兵士は恐怖を闘志に変えて巨人に立ち向かう。守りから脱し、攻めに入った。これからが本当の戦争だと、人々は心が折れないように虚勢の声を上げた。
「もう我慢できません」
ダラフィンが立ち上がって大声を上げた。その向かいでオーリスが呟く。
「またひとつ」水晶を見つめる目に悲しみが灯る。「通信が途絶えました」
二人の中心では苦悩するグレンデルが静かに座していた。
「私も出陣させてください」ダラフィンは苛立ちを露にしている。「さらなる敵はもう三つの国を滅ぼしました。ここでただガラス玉を眺めているだけなんて、これが大陸最強と言われた総軍長の最善策だとは思えません。誰が納得するでしょう」
「座れ、ダラフィン」
グレンデルは冷静に宥める。ダラフィンは今にも爆発しそうな感情を抑えるのに必死だった。
「私ならあの巨人を倒せます。確かに敵は多勢ですが、私が兵を導けば必ず犠牲を減らしてみせます。許可をください」
「ダラフィン殿」オーリスが説得する。「我々の目的は時間を稼ぐことではありません。敵は、ギメルは必ずここにくるでしょう。その時を待つのです」
「ならばギメルを探します。これ以上待っていられない。こちらから仕掛けるべきです」
「どこにいるのか分からないのだ。奴は土の中に身を潜めている。穴を掘れば見つかるものでもない。だがその時は近い。私には分かります。敵はゆっくりではありますが、近づいてきています。王を狙って。その時にはあなたの力が必要なのです。どうか冷静になってください。その心中は察しますし、王も私も同じ気持ちなのです。ただここで傍観しているわけではないのです」
オーリスは声を落として続けた。
「……私とて、今にも駆け出してしまいそうな衝動はあります。ですが私の役目はあくまでも王をお守りすること。倒した敵の数など何の功績にもなりませぬ」
ダラフィンは拳を握り、俯いた。まだ納得はいかない。オーリスの言葉が今まで間違っていたことはなかった。しかしこれからもそうだとは限らない。結果が出るまでそれは分からない。
「しかし」ダラフィンは乱暴に椅子に座り直しながら。「敵の手段のなんと卑劣なこと。反吐が出る」
オーリスは、王の前で下品な言葉を使うダラフィンを戒めはしなかった。
グレンデルはじっと水晶を見つめている。次々と消えていく兵や民の命をそこから感じながらどれほど心を痛めているか、二人は察した。だがそれも自分には及ばないほどのものだろうと感じながら。
その中で、グレンデルにはもう一つ気がかりなことがあった。父親として息子の身を案じていたのだ。
今は自分の言葉に耳を貸さずに家出した王子の消息を追う余裕はなかった。重々承知していた。一体彼はどこで何をしているのだろう。この国の状況の中で何を思い、どう動いているのか。
それにしても、と思う。なぜ連絡の一つもないのだろう。それがグレンデルの不安を募らせた。時に最悪の言葉が過ぎっては、それを振り払う。水晶から伝わる戦慄を感じ取る度にまさか、まさかと胸を痛める。まさか巨人に潰されてはいないか。まさか死体となって民を襲っているのではないだろうか。
いや、もしかしたら近くに居るのかもしれない……グレンデルは考えるのをやめる。やめたつもりでも、いつまでも息子の様子が気になって仕方がなかった。
トレシオールは決して悪人でも愚かでもなかった。ただ父であるグレンデルとしばしば意見を対立させ、常に違う道を主張していた。いつまでも子供だと思っていた彼は、気が付くと自分より背が高くなっていた。そろそろ自分の行動に責任を持たなくてはならないという話をしようとしたとき、黙って旅に出てしまった。
彼は王の後を継ぐとは約束しなかった。ただ、王がもし国の力を利用して自分を無理矢理拘束するようなことがあれば、インバリンの名を捨てるとだけ伝言を残して。
グレンデルはここにきて、つくづく思った。生きていようが死んでいようが──なんて親不孝な息子なんだと。それについて、前にオーリスに言われたことがあった。
「ご心配なされますな。トレシオール様には王家の正当な血が流れております。まだお若いながら彼の立ち振舞い、その端麗なお姿からは泥に塗れても陰らぬ風格がございます。それに頭もよく、剣の腕も見事なものです。それはダラフィン殿のお墨つきです。確かに、少々意固地な部分もございますが、何よりもそれは国の事をご子息なりに考えていらっしゃる故。王はこれを認め、喜ばれるべきです。王とその世継ぎが、お互いに国をより良いものにするために正直な言葉でぶつかり合うなど、今までにない事例です。私はトレシオール様が立派な王子であると微塵の疑いもありませぬ」
「絶賛だな」悪い気はしなかった。「だがあれの意志の強さは並大抵ではない。奴の中で王位を継ぐに満たぬ現状が続けば本当にそれを捨て、私は世継ぎを失う羽目になってしまうのかもしれぬ」
「それでも彼があなたの息子であることにも、唯一の王位継承者であることにも変わりはありません。トレシオール様が道を間違いさえしなければこの国は自然と守られるでしょう。国は、民は彼を求めます。彼はなるべくして王の地位を継ぐことになるでしょう。王、トレシオール様を信じてあげてください。王子は決して口にはしませんが、それが、父親の信頼と愛情こそが彼の誇りと自信なのですから」
グレンデルにとってオーリスの言葉は慰めやお世辞のようなものだとは思えなかった。彼の口からそう聞かせられるだけで安心した。それには根拠があった。
「それは」グレンデルは意地悪な目を向けた。「そなたの娘、ライザ殿の受け売りかな」
オーリスはその言葉で急に顔色を変えた。
「う、受け売りなどでは……」
はっと言葉を失った。誘導されてしまったと目を逸らす。
「どうやら」グレンデルは微笑んだ。「トレシオールはライザ殿には素直なようだな」
トールとライザは幼いときに初めて出会った。王室でパーティがあったときにオーリスが利口で可愛い一人娘を自慢したくて連れてきたのだ。
トールはその頃、まだ男とは呼べない可愛らしさを残す少年だったにも拘わらず、既に口達者で生意気な顔をしていた。周囲にはグレンデル始め、親族や権力者が並んでいた。その前でライザは簡単な魔法を披露して見せていた。無邪気なひけらかしに過ぎなかった。
オーリスが慌てて「はしたない、場を弁えなさい」と注意したが、一同の盛り上がりように悪い気はしなかった。
トールは彼女の魔法に目を奪われていた。グレンデルやオーリスの思いの他で、トールは席を立って自分から彼女に近づいていった。
「凄いな。僕より小さいのに、そんな術が使えるのか」
「年齢など関係ありません。魔法は心で使うものです」
「ならば、僕にもできるだろうか」
「すべての者に与えられた力ではありません。まずあなたに必要なのは知識です」
オーリスは慌ててライザを怒鳴った。
「ライザ! 王子に向かって何てことを」
ライザがしゅんとなった。オーリスが謝りなさいと彼女の頭を押さえつける。しかしトールがそれを止めた。
「オーリス」
オーリスは怯えた顔をトールに向けた。が、トールはきょとんと首を傾げている。
「彼女が言ったことは本当か」
「お、王子。それはどういう……」
「僕は無知だろうか」
「そ、そんなことは……!」
戸惑うオーリスを無視してトールはライザに向き合った。
「君はライザと言うのか」
「はい」
「君の知ってることを教えてくれ。もちろん謝礼は望むだけ与える」
それを聞いてオーリスが必死で口を挟む。
「王子、魔法のことなら私がお教えします。ライザは見ての通りまだ子供。あなた様に指南できるほどの知識も力も持っておりません。それに王子にこれ以上の無礼を働かせるわけには……」
「オーリス」トールは眉を寄せた。「僕は彼女と話をしているんだ」
「は。しかし……」
困り果てるオーリスにグレンデルが近づき「好きにさせろ」と促した。オーリスは黙ってしまった。するとライザはオーリスの心配を他所に、面白くなさそうな顔をトールに向ける。
「魔法はお金で買えるものではありません」ライザは怖気ず、はっきりと言った。「それに人にものを頼むときは命令ではなく、お願いするものです。私たち魔法使いは礼儀を知らない人とは友達にはなりません」
オーリスは頭を抱えた。
「友達?」トールはまた首を傾げる。「僕は友達になってくれとは言ってない」
「では」ライザはあからさまにむっとして。「あなたとはご縁がないのでしょう。失礼します」
そして、真っ青になったオーリスを置いてその場を立ち去ってしまった。トールは唖然としていた。オーリスが必死で頭を下げた。
「も、も、申し訳ありません! 私の躾不行き届きでございます。後でライザをきつく叱っておきます。もう二度とここへは連れてまいりません」
取り乱すオーリスを見ながら、グレンデルは笑っていた。トールは何やら思案しながら室を出ていった。それを見送って土下座しているオーリスの肩をグレンデルが軽く叩いた。
「子供のすることだ。気にするな」
「王よ……どうか娘の無礼にご慈悲を……」
「彼女は何も間違ってはいない。ライザの言う通り、無礼なのはトレシオールの方だ。しかしあれくらいで落ち込んだり傷付いたりするような子ではない。放っておけ」
次の日からトールはライザに付き纏い始めた。最初はライザは冷たくあしらっていたのだが、トールに質問攻めされているうちに根負けし始めた。毎日のように続いた子供の喧嘩は、次第に笑顔に変わっていった。その様子を心配そうに見ていたオーリスに、グレンデルは「子供とはああいうものだ。勝手に仲良くなる」と微笑んだ。
それから一年ほど経っても、トールの魔法は上達しなかった。素質がないとは思えなかったがその理由は見ているうちに、大人には理解できた。
トールが興味を示していたのは魔法ではなく、ライザだったからだ。
トールは魔法をそっちのけて剣を振り始めた。ダラフィンに直々に剣の修行を申し出たのだ。そしてその頃から国の在り方など、子供ながらに鋭く厳しい意見を発言するようになった。彼の中にある、まだ幼い「男」の本能が導いていたのだ。強くなりたい、かっこよく見られたいという単純な欲求がそうさせていた。
最初はそれでいいと、グレンデルは父親としてトールのしたいようにさせていた。
更に数年が経ち、トールが大人の剣を軽く振れるようになった頃、自分がライザに恋心を抱いていることにやっと気が付いた。拒否も否定もしなかった。ただ純粋に素直にその気持ちを告白した。
ライザはもっと早くからトールを異性として見ていた。だが今までそれを隠し、彼が自分の気持ちを伝えてくれたこの時でさえ、彼女はまだ答えを出そうとはしなかった。
トールには時期王位継承者と言う立場がある。もうお互いに子供だという言い訳は通じない。ただ好きだ嫌いだという感情だけでいつまでもこうしてはいられない。ライザは彼より早くそのことに気が付いていた。
トールは毅然とした態度でグレンデルに彼女と婚約したいと伝えた。反対されるつもりだったのだが、グレンデルはあっさりと許可した。ただ、もう少し大人になってからだとは言われたが。
オーリスも同じことを言った。むしろ彼は身に余る光栄だと、それは喜んでくれていた。それに何よりもトールの気持ちは揺ぎ無かった。反対する者もいない。何の障害もない、そう思った。
だがそれを受け入れなかったのはライザだった。
トールは毎日のように彼女を説得した。王妃としてだけではなく、彼女を一人の女性として幸せにすると堅く誓った。しかしライザは頭を縦には振らなかった。
「僕が嫌いなのか」
「いいえ。愛しています。あなたの申し出には感激しています」
「ならばどうして。父上も認めてくれている。みんな喜んでくれている。それに例え周りが何と言おうと、僕は君を浚ってでもずっと一緒にいたいとさえ思っている。君はそうじゃないのか。もし君が王妃という肩書きを重いと言うのなら、それを放棄してくれても構わない」
ライザは真剣なトールの目を見つめ返す。しばらく考えた後、ふっと微笑んだ。
「私があなたの妻に相応しい女になったと自信を持てるまで……まだ時間を戴けないでしょうか」
トールはその言葉の意味をずっと考えていた。ライザの言葉にはいつも意味があり、時々謎めいた発言をする。時にはこのような、一見普通に受け止めるべき言葉にも奥深い意味が含まれていることがあったのだ。
トールは今がそれだと感じ取っていた。だがすぐにはその答えが読めずに悩んでいた。
さらに五年が過ぎた。二人は婚約を先延ばしにしたまま成長していった。その間もトールは決して彼女の言葉を忘れはしなかった。同時にライザを急がせたり、答えを聞き正すようなこともしなかった。
間違いなく二人は愛し合っていた。周りも羨むほど仲睦まじく──時には喧嘩もするが、それも微笑ましいものとして──二人は結婚するものだと、誰も信じて疑わなかった。
その日は突然訪れた。ある夜、トールは自分の決意をライザに打ち明けた。
「やっと君の言葉の意味が分かった。僕はまだ未熟だったんだ。王子としても、男としても、そして人間としてもね。君はそれを伝えたかったんだね。僕はいつか父の後を継いで国王になるだろう。そして君を妻にする。それを当たり前のように甘受するつもりはなかった。しかしその覚悟や心構えがあるかと問われれば、僕は頷くことができないんだ。もっと強くなければ、もっといろんなことを知らなければいけない。それはここで修行し、学べるものではない。それ以上に困難で大切なものなんだ。それが何かは分からない。だけど僕にはそれが足りないんだ」
黙って聞き入れるライザを、トールは抱きしめた。
「僕は旅に出る。人を守るためには人を知らなければいけない。いろんなものを見て、触れ、学び、体験して、僕が背負うべき運命に相応しい人間になれたときに帰ってくる。いつになるか分からない。探すものがどこにあるのかも分からない。途中で辛くなるかもしれない。だけど、必ず手に入れてみせる。その時、もし君がまだ僕を待っていてくれたなら……僕を君の伴侶として迎え入れて欲しい」
ライザはすぐには答えなかった。泣いていた。トールは言わなかったが、そこには永遠の別れの覚悟もあった。ライザには伝わっていた。彼の決意が命を懸けるほどのものだと。
「……では」ライザは囁いた。「一つだけ約束してください。暁が訪れたときは、必ず私と結婚してくださると」
トールは力を抜き、彼女の顔を見つめた。
「それは」トールは小声で。「僕と婚約してくれるということなのか」
ライザは微笑んで頷いた。
「まだ結果は何も見えない。もしかすると……」
帰ってこられないかもしれない、という言葉をライザは遮った。
「私は今のあなたが好きです。そのあなたがどんな結果を導こうと、私の気持ちは変わらないでしょう。そして私もまた、あなたに相応しい女となってあなたの帰る場所になります。ずっと、この身が果てを迎えようとあなたを待ち続けます。ここで私は私の戦いを続けます。ただ、私の心が寂しさに負けてしまわないように、拠り所を与えてください」
一週間後に二人の婚約パーティが行われた。国中が若い二人を祝福した。
その日の夜、別れも告げずにトールは姿を消した。
2
グレンデルはため息をついた。なんでもいい、とにかく生きていてくれと心から祈った。
その時、隣でオーリスが呟いた。
「南シュリオル、通信が途絶えました」
グレンデルは我に返る。顔を上げるとダラフィンが唇を噛み締めて水晶を睨み付けていた。さらにオーリスが続ける。
「イオルデン、ティオ・ロウ……途絶えました」
グレンデルは頭を抱えた。通信が切れるということはそこの砦が陥落したことを意味する。
巨人が現れてからその速度は増していた。このままでは時間の問題だった。まさか、と思う。ギメルはこのまま出てこないつもりではないだろうか。それだけは回避しなければいけない。最悪にはダラフィンの言う通り、こちらから出向く必要に駆られるかもしれない。その時はほとんど望みがないと思うしかなかった。
土の中に身を潜め、大陸を自由に移動する彼をどうやって探し出すというのだ。
城の外でも戦いは続いていた。その衝撃が王室にまで伝わってくる。まだ少し遠い。周囲を守る兵たちが核には近づけさせないように体を張ってくれているのだ。
だがこれ以上待つことに意味はあるだろうか。グレンデルに迷いが過ぎった。
その時、王室に誰かが駆けてきた。乱暴に扉が叩き開けられる。それはライザだった。息を切らし、蒼白している。
「お父様!」
ライザはその場に立ち竦んだ。
「……ギメルです」
三人は一斉に立ち上がった。そして顔を見合わせる。その中でオーリスは娘の様子がおかしいことに気づく。
「ライザ、一体何があったのだ」
ライザは震えていた。目を見開き、今までにない恐怖の色を灯していた。喉を震わせ、必死で声を絞り出した。
「……ギメルは……ギメルは」言おうとすると涙がこみ上げてくる。「どこまで私たちの心を陵辱すれば……」
「!」
突如ライザは背後から肩を貫かれた。抵抗する間もなく血を流しながら倒れる。
一同は反射的に駆け寄ろうとしたが、体が固まる。
倒れたライザの背後に、男が剣を掲げて立っていた。その者は古い型の青銅の鎧を身に纏っていた。その姿は雄々しく、戦うために生まれてきたような凶暴さがあった。
三人は、いや、この国の誰もが彼の名前を知っていた。ライザが彼の足元で呻いていたが、オーリスはすぐには近寄ることができなかった。グレンデルは震えながら、剣の柄に手をかけた。
「……なぜ」グレンデルはするりと剣を抜きながら、呟く。「こんなところを彷徨っておられるのだ……初代国王、ガラエル殿」
間違いなかった。今に至る歴史を作った偉人が、邪悪な呪いを身に纏って蘇っていたのだ。
まるで肖像画から抜け出てきたような、ガラエルは五千年前のそのままの姿だった。
彼の鎧も剣も復元されている。後に「鮮血のマント」と言われ、自らの手で焼き払った赤いそれが彼の背ではためいている。死んだときの老人ではなかった。まさに、魔法戦争の最中でランドール人を圧倒させたときの勇姿のままだった。
空にギメルの卑しい笑い声が轟いた。ぞっとした。そして怒りがこみ上げる。それは決して許されることではなかった。この世の何を犠牲にしてもギメルを倒すと固く誓った。
その前にガラエルと戦わなくてはいけない。どうするか──しかし迷ってはいられなかった。確かにその体はガラエルのものかもしれないが、そこに心はなかった。彼はもう死んだのだ。すべてを未来に託して。
ギメルに死者を尊ぶ思念は愚か、歴史を重んじるような人として在るべき心はなかった。むしろそれを欺き、弄ぶことを快感とする、どこまでも救いようのない下種な生き物だと改めて思い知った。生かしておくわけにはいかない。相打ちでもいい。何が何でも奴だけは殺す。三人は心を決めた。
ガラエルは不適な笑みを浮かべると、ふわりと浮いた。身を翻し、城の外に出て行く。一同は後を追った。オーリスは足を止め、扉の傍らで蹲るライザに声をかけた。
「無事か、ライザ」
「……早く追ってください」
「……ライザ」
「私も後から行きます」
本当は気が気ではなかったのだが、オーリスはぐっと堪えてグレンデルの後に続いた。
ガラエルは城を舞い降り、さらに町を通過する。その向こうにある平原に降り立った。
そこにはギメルがいた。土の中から上半身を出してぽつんと佇んでいる。
ガラエルはまるでその卑しい生き物を称えるように赤いマントを躍らせた。その姿がさらに三人を憤慨させた。ガラエルは一歩前に出ると、剣を構えることで宣戦布告する。その姿は凛々しく、悲しかった。五千年も前に滅びたはずの最強かつ偉大な王が悪に従いこの時代に蘇り、その技のすべてを披露するのだ。彼の意志を受け継ぎ、守ってきた人々を滅ぼすために。
ギメルが再び笑った。それは楽しそうに、体を揺らして。するとその背後の大地が盛り上がった。ズズ、とそれは人の形を象っていく。一同は見上げた。
巨人だった。しかし、今までのそれより一回りも二回りも巨大だった。
「ゴレムよ!」ギメルは大声を上げる。「この大地をお前にすべてくれてやろう。好きなだけ暴れろ。土の上にある邪魔なものを壊してしまえ」
ゴレムは雄叫びを上げた。ズン、と足だけで人の身長を超えるそれを前に出した。そのひと踏みで大地が揺れる。
グレンデルはもう何も待たずに剣を振り上げた。その目標はガラエルだった。ガラエルは剣に魔力を灯す。刃が赤く光る。向かってくるグレンデルを一振りで弾き飛ばした。
「陛下!」
オーリスも飛び出した。素早く魔法弾をガラエルに放つ。ガラエルはそれも剣で弾いた。
その横でダラフィンが飛び上がる。彼の標的はゴレムだった。重量のある剣でゴレムの片腕を斬り落とした。どすんと地面に落ち、地面に溶け込んでいく。しかしゴレムの斬られた腕は生えるようにゆっくり元に戻っていく。ダラフィンは舌打ちをした。
「この土人形め」ダラフィンは体勢を整えながら。「その汚らわしい手で王には触れさせんぞ」
地平線では別の争いが続いている。時々戦火だけが目線の端にちかりと光る。
オーリスに肩を借りて立ち上がりながらグレンデルは再び剣を構えた。今の一撃でガラエルの力量を思い知らされた。グレンデルも最強と言われていた。しかしそれは彼自身とそれを取り囲む環境、国のすべてを含めての力だった。
ガラエルは違う。彼は個人そのものが力だったのだ。剣と魔法の両方を使いこなし、肉体だけでないその屈強な心が彼を強くし悲劇の勝利へ導いた。ガラエルは魔法戦争の象徴だった。
これほどか、とグレンデルは圧倒的な力の差を認めた。
3
当然だと思う。もう五千年も経っているのだ。ノートンディルはなくなり世の魔力は弱まっていた。そして小さな争いは絶えないものの、パライアスはもう宿敵となるランドール人と戦うこともなく、ただ平和と安泰を求めて国の在り方を模索し続けてきた。それを築き、淘汰していった人の体が弱くなって当たり前なのだ。
今の世にガラエルは、そのものが兵器に等しかった。
勝てるはずがない。例え国中の全軍を仕掛けても──だがグレンデルは闘志を失わなかった。
「オーリス、魔法で援護するんだ」
「御意に」
ここにきて恐れるものはなかった。ただ敵を倒すことだけを考える。それが何者であれ、国を脅かすものをこれ以上前に進ませるわけにはいかなった。
「パライアスの偉大なる創造神よ」グレンデルは剣を掲げる。「ご覧ください。あなたが守り残した大地の子は、五千年という時を経て立派に成長いたしました。我が名はグレンデル・インバリン。参ります」
グレンデルはオーリスの放つ魔力を受け、それを護身には使わずにすべて剣に送り込んだ。
守る必要はなかった。二人の王の対決はきっとすぐに決着が付くだろう。戦略も小細工もなしに、正面からぶつかり合うだけで十分だったのだ。
ガラエルはグレンデルの剣を剣で受け止めた。閃光が放たれた。その凄まじい力の衝撃を国中の人々が感じ取った。そこには希望や絶望を超越したものがあった。パライアスにある力のすべてが形を成していた。グレンデルは満足していた。この夜の最後を飾るに相応しい対決だと思っていた。
勝ち目などないのに、なぜか負ける気がしなかった。
隣ではダラフィンがゴレムと戦っている。ゴレムは怪力だが動きは鈍い。大振りな攻撃を避けながらダラフィンはゴレムの体に剣を突き立てる。ゴレムに痛みはなかった。しかし針を刺されたような感触はあるらしく、ダラフィンを払おうと腕を振り回している。
ダラフィンは重い鎧をものともせずにゴレムの体を飛び越える。深く刺した剣を振り抜く。重い。腕の筋を痛めながら剣だけは手放さなかった。後のことなど考えていなかった。この体がどうなろうと構わない。二度と剣が持てなくなっても、例え命を落としても。
少しでも自分の体を庇ってしまうような恐れや手抜きなど、ここであってはいけない。自分もまた戦うために生まれてきたと自負している。だがこの土人形とは違う。自分は壊すために戦うのではない。守るため。ダラフィンは何度も自分に言い聞かせていた。
片手を付いて着地し、顔を上げる。ゴレムは片足を失って体を崩していた。ダラフィンは今だ、と間をおかずにゴレムにかかる。
「痛みを感じなくとも」ダラフィンは剣を両手で持ち直した。「再生する暇もないほど切り刻めば動きは封じれる」
ダラフィンは剣で一文字を描いた。どすんとゴレムの上半身が落ちる。ゴレムは身動きが取れずに手足をじたばたさせている。体の土が崩れ始め、上と下が繋がろうとする。
「させるか!」
ダラフィンはさらにゴレムに斬りかかった。しかし勢いよく刺した剣が崩れた土に捕らわれてしまった。ダラフィンは不覚を取り、物凄い力で引きずりこまれる。
それはまるで生き物のように彼の体を包み始めた。ダラフィンの体を覆い、口や鼻の中に侵入しようとする。このままでは窒息する。ダラフィンは必死でもがくが体中に重い土がのしかかってくる。
「ダラフィン殿!」
咄嗟にオーリスがゴレムに魔法弾を放つ。命中し、土が飛び散る。その中からダラフィンが這い出た。だが安心している暇はなかった。グレンデルの援護が手透きになり、その一瞬の隙をガラエルは逃さない。
鮮血が散った。それと同時にグレンデルの右腕が剣を握ったまま宙を舞った。それは一同の目にスローモーションで映った。肩から下の腕が、音を立てて無残に地面に転げ落ちる。グレンデルは悲鳴を上げた。オーリスとダラフィンは目を見開き、声が出ない。二人は取り乱しながらグレンデルに駆け寄った。
「……案ずるな!」
グレンデルは大量に流れ出る汗を散らしながら怒鳴った。二人の体が固まる。グレンデルは必死で体を捩りながら左手で自分の剣を拾った。離れた自分の腕を剣から振り落とす。そして立ち上がり、胸を張った。
「ガラエル」グレンデルは歯をむき出す。「どうした。腕の一本や二本。首でも刎ねんと私は倒れぬぞ」
その堂々たる姿に照らされるようにオーリスとダラフィンは奮い立った。じわりと二人の表情が変わる。
ギメルは少し離れたところでじっとその様子を眺めていた。彼の目には絶望の中で足掻く者が映っていた。それを嘲るように、いやらしい顔で笑っている。
ダラフィンはそんなギメルの姿を横目で確認した。ガラエルとゴレムの盾を前にしては彼に近づくことは容易くなかった。仮に隙をつけたとしても、いくら剣で斬りつけても死には至らないのだろうし、土の中に潜り込まれてはそれすらも適わない。
こちらに有利なことがあるとすれば、彼が何も気づいていないことだった。たった一つ、彼を確実に滅ぼす手段を隠し持っていることを。
ギメルが魔力を放っている限り、ガラエルとゴレムを倒すのは不可能だった。ただ闇雲に攻撃することに意味はない。
三人は気を持ち直す。王を先頭に国の三大頭が立ち並んだ。それを見据えガラエルが笑った、ように見えた。
隣でゴレムが繋がった巨体を持ち上げた。ゴレムの鈍い動きを待たずに、ガラエルが三人に斬りかかる。
一同は跳ね退き、光りうねる剣を避けた。だが避けきれなかった。その剣の一振りはまるで矢の雨のように三人を同時に切り刻んだのだ。
血飛沫が散る。鎧は役に立たなかった。比較的体の弱いオーリスは顔を歪めた。肩、足、背中や片腹の肉が裂ける。避けるのが遅かったらバラバラになっていたかもしれない。寒気がした。さらにそこにゴレムが巨大な拳を振り下ろしてくる。
休む暇はなかった。ゴレムが叩いた地面は振動し、ヒビが入る。ゴレムは続けて腕を振り回した。そこには知能も理性も何もなかった。ガラエルさえも巻き込まれ、体を屈めて片手をつく。その反動で飛び上がる。ゴレムは敵も味方も関係なく、ただ欲望のままに暴れまわっていた。
ガラエルは無表情のままゴレムの頭上に着地する。
4
思わぬことが起こった。ガラエルは剣を大きく振り上げ、暴れるゴレムの脳天にそれを深く突き刺したのだ。
剣から魔力の光が溢れ出した。ゴレムは動きを止め、仰け反り、咆哮した。ガラエルの剣からさらに強い光が立ち上る。ゴレムは頭から下に向かって崩れていく。
ガラエルはひらりと身を翻し、ゴレムから飛び降りた。一同が目を奪われる中、ゴレムは地面に還っていき、最後はただの土山になってしまった。
ギメルも驚愕していた。目を見開き、ぎっと眉間に皺を寄せて怒鳴った。
「何をしている!」
ガラエルは見向きもしない。当然だ。彼に心はないのだから。決してグレンデルたちを庇ったわけではない。ただ無駄に大きな土人形が邪魔だっただけだ。再び三人に剣を向ける彼を見て、そう思う。ギメルは初めて苛立ちの表情を見せていた。
「おのれ……勝手なことを!」
ギメルを無視してガラエルは剣を振り、型を描く。
グレンデルたちはそれに目を奪われ、終わるまで待ってしまった。見事なものだった。これがパライアスの剣術の源かと、息を飲む。しかしいつまでも見とれてはいられない。一同も改めて構える。先ほどの剣術を見せ付けられては、まるで自分たちが子供のようだと思いながら。
グレンデルはガラエルに向き合った。その神に等しい完璧な姿は、彼にとって羨望そのものだった。
そして思う。自分は、今までの歴代の王たちは間違っていなかったと。
先代の残したものに甘えて、その上に胡坐をかいていたわけじゃない。退化し、弱くなってしまったんじゃない。
ガラエルは強すぎた。戦うことしかできなかった。だからこそ宿敵である友を、ノートンディルを滅ぼす道しか残らなかったのだ。
だが自分は違う。自分と共に戦う仲間がいる。自分は一人では生きていけないし、一人ではない。どちらが正しいのか、きっと答えはないのだろう。だが、ただ理想と思想だけに捕らわれてきたのではないと確信した。
ガラエルはこの迷走する国を嘆き、滅ぼすためにここに姿を現したのではない。
「あなたを」グレンデルはガラエルに語りかけた。「いつまでも地上に縛り付けていたのは、我々だったのですね」
ガラエルは何も言わない。
「あなたは為すべきことを為していたというのに、我々は失ったものへの責任をあなたに押し付けようとしていた。愚かでした。あなたも我々と同じ一人の人間。そしてイラバロスもそうでした。彼は彼の同胞の慈悲によって許されたそうです。友を救えるのは友なのです。だからこそここで、私があなたをお救いします」
グレンデルは腕の痛みに耐えながら、呼吸を整える。じっとしていても汗が吹き出る。だがその瞳は安らかだった。
「死してなお戦う必要はありません。我々はもう大丈夫です。この足で歩けます。だから、もうお休みください」
ガラエルは一瞬、優しい顔になった。グレンデルはそれを錯覚だと思った。そうでなければ剣に迷いが生じる。今はしばし傷の痛みを忘れて、片手で剣の切っ先をガラエルに向けた。
グレンデル、ダラフィンが同時にガラエルに斬りかかった。その背後からオーリスが魔法弾を放つ。
ガラエルを中心に爆発が起こる。ガラエルは一振りでそのすべてを弾き飛ばした。
空が揺れる。ガラエルは剣と舞い、その刃に光を走らせる。グレンデルとダラフィンの攻撃をすり抜けて、僅かな隙間から光の矢が走り抜けた。二人はしまった、と咄嗟に息を止めた。
遅かった。ガラエルの狙いはオーリスだったのだ。二人が振り向くより早く、尖った光の矢はオーリスの胸を貫いていた。
「オーリス!」
オーリスは崩れるように仰向けで倒れた。
矢はすぐに砕け散った。同時にオーリスの体から血が吹き出る。オーリスは逆流してくる自分の血で喉が詰まり、声も出せない。体が急激に冷えていくのを感じた。
グレンデルとダラフィンは駆け寄ることができなかった。気を散らしていてはガラエルの容赦ない攻撃を避けることができなかった。
二人は戦いに集中するしかなかったが、できなかった。剣を交えている間にもオーリスの血は止まらずに流れ出ている。
そこに小さな影が走り寄ってきた。
「……お父様!」
ライザだった。ライザは怪我した肩を庇いながら、体を引きずるように向かっていた。
しかし視界に移った突然の惨劇に、堪らず痛みを忘れて駆け出していた。彼女の姿を見てグレンデルが「来るな」と叫ぶが、止まらない。
ライザはオーリスの横に倒れるように跪いた。胸の穴から血が流れていた。
「お父様」
「……ライザ」
もう助からない。間もなく事切れるのは誰もが見て取れた。それでもライザはオーリスの体に被さり、胸の傷に両手を被せた。
「いや……止まって、お願い」
治癒の魔力を灯す。しかし、淡い光は力を発さないまま空しく消えていく。ライザの指の間から生温かい血が溢れてくる。血に塗れ、震える小さな手をオーリスがそっと握った。
ライザは大声を上げて泣き出した。
「お父様……お父様」
「泣くな、ライザ。まだ終わってはいない。絶望するな」
オーリスは力を振り絞り、優しく微笑んで愛娘を見つめた。
「お父様のいない未来など、明るくはありません」
「何を言うんだ。私はいずれお前より先に逝くと決まっている。それが少し早まっただけのこと。お前にはまだやることがたくさんあるだろう。もっと魔法の勉強をして、愛する人と結婚して、子を産み、育てる……」
「でも、でも……彼は……」
「疑うなど、お前が信じてあげなくてどうする。忙しいのはこれからだ。お前には辛い思いをさせてしまうかもしれないが、私がいなくなったらこれからの魔法界はお前たちが担っていかなければいけないのだから」
「いなくなるなんて言わないでください。私にはそんな力はありません。お父様、どうか私を一人にしないでください」
「一人ではない。一人だなんて言ってはいけない。いいか、必ず幸せになりなさい。お前が泣いていては、私は安心して眠れないではないか」
別れの言葉など聞きたくない、しかし聞かなければいけない。ライザは激しく葛藤しながらオーリスの声に耳を傾けていた。
「ライザ、使命を果たせ。お前は私の自慢の娘だ。お前をこの世に送り出したことが、私の一番の誇りだ」
「お父様……私も、あなたの娘でよかったと……心から思っています」
オーリスは何よりも嬉しい言葉を聞いて、体の力を抜いた。
「……愛しているよ」
オーリスの指が垂れた。ライザはもう声をかけなかった。
返事がないことを確認したくなかった。嗚咽が止まらない。冷たくなった父の手を握り締め、体を震わせた。
グレンデルとダラフィンも悲しみに捕らわれた。今までメイの三大頭として、ずっと一緒に国を守ってきたのだ。三人の信頼は厚く、絆も強かった。国の平安は均衡の取れた三人によって成り立っていたのだ。
その一角が失われた。グレンデルとダラフィンは今すぐ彼の傍で泣き崩れてしまいたかった。
ライザが顔を上げる。そこには父の死を受け入れようと努力している強い瞳があった。
涙は止まらない。それでも、先ほどまでの取り乱していた彼女とは別人だった。
泣いてる場合ではない、と自分にいい聞かせる。まだ終わっていない。まだ悲しみに暮れていい時間ではない。
ライザは震える手でそっとオーリスの首から翡翠のネックレスを外した。それを自分にかける。優しく、緑の光が灯った。体に力を入れようとするが、言うことを聞かない。
「……立って」
ライザは自分の足に声をかける。もう一度、と歯を食いしばる。その時、ライザは三人の戦士が剣を交えている光景に目を奪われた。凄まじかった。剣豪と言われた王とダラフィンが押されている。しかも、見間違いではない。王の右腕が、ない。また体が震えだす。今度は恐怖だった。なぜ自分がここにいるのか分からなかった。自分に一体何ができる? なぜ父は私に望みを託したのだ。こんなにも小さい自分に。ライザは無意識にネックレスを掴んでいた。心の中で、もう答えない父になぜと何度も問うていた。
ライザはゆっくり目を閉じた。
(怖い……ここから逃げ出したい。でも……どこにも逃げる場所なんてない)
力を抜くと歯がカチカチなる。すぐに噛み締めてそれを止める。必死で自分を落ち着かせる。そして考える。
自分の持つ力を頭の中に並べ、この状況で何が使えるかを想像する。考える。
(だめ……やっぱり、私はここでは何も役に立たない。下手に手を出しても二人の足を引っ張ってしまうだけ)
ライザは頭を振る。
(でも、もう誰も傷ついて欲しくない……お父様、お願い、力を貸してください)
ネックレスを握り、祈った。ライザの体が光に包まれた。三人と、ギメルもそれに気づいた。
(私は……祈ることしかできない。ならば命が尽きるまででも、出来る限り祈り続けます。祈りが神に届くが早いか、私の命が果てるのが先か分からないけど……)
ライザを包む光は緑を濃くしていく。グレンデルとダラフィンはオーリスの気配を感じた。
ライザは無意識に魔法を起こしていた。イサ(停止)の魔力が発動する。目を開く。そこには恐れはなかった。戦うグレンデルとダラフィンに向かって大きな声を出す。
「王よ!」ライザは力強く。「魔道の星はまだ堕ちてなどおりませぬ!」
5
グレンデルとダラフィンは驚いた。そんな勇ましい彼女を見たことがなかったのだ。
「あなたの弓手に剣あらば、私はあなたの馬手になりましょう」
二人はすぐに同じことを思った。オーリスだ。彼がそこにいる。肉体から離脱した彼は最後に奇跡を起こそうとしていたのだ。
「!」
ガラエルの体が一瞬止まった。二人はその隙を逃さない。
グレンデルとガラエルの剣が前後からガラエルの胸を貫く。ガラエルはもがいた。しかし二人は決して離さない。そこにライザが続けてガラエルの魔力を封じる呪文を唱えた。あまり長くはもたないだろう。
ギメルは目の前の戦闘が自分の思い通りになっていないのが気に入らなかった。我慢するという概念はなかった。冷静でいられない。
「おのれ!」ギメルは怒り狂った。「女、邪魔だ!」
ギメルは土の上を滑るようにライザに向かっていった。彼の背中から、マントを突き破って、長く巨大な泥の手が二本飛び出してきた。
ライザの体がその手に掴まれる。そしてギメルは彼女を自分の頭上まで持ち上げる。
ライザは物凄い力で締め付けられ、血を吐く。ライザの封印が解け、ガラエルは溜めた魔力を一気に放出する。グレンデルとダラフィンは弾き飛ばされた。手が滑り、ガラエルの体に剣を残してきてしまった。
武器は奪われた。二人は蒼白する。
ギメルは更にライザを締め付け、高らかに笑った。
「女如きが、戦場にくるものではない。場違いだ。お前は死んだ者の墓でも拝んでればよかったんだ」
ライザはギメルを睨む。もうオーリスの気配はなかった。そこには耐え忍ぶ、一人の女性だけがいた。
「あなたに慈悲はない」ライザは苦痛を堪えて、微笑む。「生まれてくるべきではなかった。私はあなたを哀れみます。死に場所も選べない、卑しき生き物よ」
ギメルは舌を出して笑っていた。
「生きも死にもしない。あなたはどこにもいなかった。そう、最初からどこにもいなかったのです。あなたは何も選べない。だから、私が与えます」
ギメルはその言葉の意味も理解しようとはせずに、更にライザを締め付けた。圧死させるつもりだった。
「ライザ!」
グレンデルとダラフィンが体を起こしながら見守る中、ライザは顔を歪ませる。内臓を圧迫され、また血を吐く。
オーリスに続いて、彼女まで……それだけは、と二人は武器も持たずに駆け寄ろうとした。その時。
急に悲鳴を上げたのは、ギメルだった。甲高く、濁ったそれは耳を劈く不快音のようだった。
ライザを掴んだ大きな土の手がぼろりと崩れた。続いて雪崩のように砂となった土がギメルに降り注ぐ。ギメルは震えていた。その体から、じわりと煙が立ち上った。
「そんな……」
崩れる土と共にライザも地面に落ちる。這うようにしてギメルから離れた。
ギメルは佇んで目を見開いていた。マントの裾から本来の両手を見せた。それはやせ細り、骨が浮き出ていた。
「なせだ……」焼けるように煙を出す自分の手を見つめた。「煙の出る水が……儂の体を溶かしていく。そんな、嫌だ……」
クライセンから受け取った魔薬はグレンデルからオーリスへ預けられていた。そしてオーリスは咄嗟の思いつきで、ここに来る前に王室の扉でライザに渡していたのだ。
理由は分からなかった。オーリスは彼女に駆け寄って声をかけた僅かな時間で、最後の希望を娘に託していたのだ。それはグレンデルにも伝えられていなかった。ライザは受け取ったものを魔法兵の制服の内ポケットに潜ませておいた。そしてギメルに体を締め付けられて、中で瓶が割れてしまったのだ。
ギメルは自ら死を導いていた。ただの思いつきで魔薬はオーリスからライザの手に渡り、それを黙ってポケットに忍ばせていただけで──その幕は閉じることとなった。
ギメルの体が乾いていく。皮膚にヒビが入り、剥げ落ちていく。ギメルの筋が、骨が露になっていく。むき出しになった骨も粉になり、さらさらと静かに地面に還っていった。
それを見届けないうちにガラエルが倒れた。それはただの屍だった。あっという間だった。
ガラエルの体は鎧ごと土になり、二本の剣を残して地面に吸い込まれていった。
国中のゾンビと巨人も同じように消えていっていた。人々にはなにが起こったのか、すぐには理解できなかった。大陸が静寂に包まれる。
雲が割れ、隙間から太陽の光が差した。今まで地面を見つめていた人々は、誘われるように空を仰いだ。