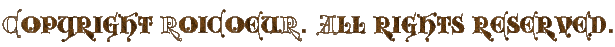第17章 傷痕





1
あれから一年の時が過ぎていた。
天界、魔界、人間界のすべてを揺るがすほどの出来事は「魔薬戦争」として歴史に刻まれることになった。
その中心になっていた四代目魔法王は世界を救った英雄として人々の間で語り継がれていた。
彼の勇姿を世に広めたのはティオ・メイの王子、トレシオールだった。彼は途中からクライセンのノーラ討伐の旅に参加し、彼のその姿、魔法使いとしての偉大さを実際その目で見てきたことを人々に伝えた。クライセンの性格など、個人的ことについては一切触れなかった。共に戦った若い魔法使いや海賊たちのことも含め、ただ数人の仲間がいたとだけ、それ以上は何も言わなかった。
なぜならトールはクライセンが世界を救った勇者であると、それだけを伝えれば十分だと思ったからだった。そして、魔法王は疲れて眠っている、どうか騒がすそっとしておいてやってくれと念を押した。
人々はそれを不満に思った。ぜひ彼の姿を見たい、声が聞きたいと切望したが、トールはそれを軽く躱す。
「探しても無駄だ。彼は世界一の魔法使い。魔法でその姿を隠してしまえば誰も見つけることはできないだろう」
そうして時が経つにつれ、人々は彼を探すことを諦めた。
戦争によって失ったもの、壊れたものの修復に勤しんだのもあり、魔法王が奇跡を起こしたという事実が人々の心を支えていた。
*****
ウェンドーラの屋敷の居間ではマルシオが一人で本を読んでいた。
それを棚の上から見つめている丸い二つの目があった。それは悪戯な色を灯し、無防備な彼の手の中の本めがけて飛び降りてきた。
「わっ!」
マルシオは大きな声を上げ、本を落とす。
「こらっ、ジン!」
それは一匹の猫だった。以前にマルシオたちが虐められていた彼とは全く違う。もう百年以上生きている普通の猫ではなかったが、その大きさは人の腕の中に納まる程度で、四つ足で地を歩く。決して二足歩行でもなければ人語を喋るわけでもなかった。
その性格は気性が荒く、暇さえあれば何かとマルシオにちょっかいを出してくる。ジンにあのときの記憶があるのかは分からないが、唯一サンディルにだけは従順だった。その様子で、マルシオは自分がなめられているんだと気づいていた。むかつくが、ここにきたのは自分の方が後なのだ。猫と本気で喧嘩しても仕方ないが懐かせようという気は更々なかった。
ジンはマルシオに怒鳴られて、つんとして窓から出て行った。それを見送って、マルシオは本を拾ってソファに座りなおす。そこに奥からサンディルが現れた。
「またジンが悪戯したのか」
サンディルはマルシオの向かいのソファに腰を降ろした。マルシオはため息をつく。
「まったく。飼い主に似て……」
性格が悪い、と言いたかったが、さすがにその父親の前では控える。気まずそうに再び本を開く。サンディルは全く気にせずににこにこしていた。
マルシオは目線を落として、本の文字をなぞった。内容は理解していない。上の空だった。サンディルは構わずに声をかける。
「本が逆さだぞ」
マルシオは我に返って恥ずかしそうに本を置いた。
数秒、間があった。ごく自然に、サンディルが呟く。
「――あれから一年か」
マルシオは特に反応しない。いつものことだった。マルシオにはサンディルが何を言わんとしているのか分かっていた。
当然だった。この一年間、二人の間での一番の心配事だったのだから。気にかけて当たり前のことだった。
サンディルは自分の息子がいつ帰ってきてもいいようにこの屋敷で静かに待っていた。
ギメルの襲撃のときもここでじっと息を潜めていた。
ギメルの死後のしばらくの沈黙、そして突然起こった不気味な地震。その間、何が起こっているのか想像できた。身が張り裂けそうだった。だがサンディルは何もしなかった。ただただ、彼の帰りを待ち続けた。
その脅威は突然この世から消え去った。目には見えなかったが、サンディルには感じて取れた。
希望と絶望が交差した。静寂と平穏が訪れてもサンディルは落ち着かなかった。
さらに一週間という時が過ぎた。その夜、玄関の扉がノックされた。
サンディルはそれが何者であろうと迎え入れるつもりで扉を開けた。
そこには、疲れ果てたマルシオがたった一人、青い石の入った箱を胸に抱いて立っていた。
マルシオは俯き、目は空ろだった。サンディルは今にも消え入りそうな少年に優しく声をかけた。
「……おかえり」
マルシオはその声を聞いて銀の目を動かした。少年は何も言わずにサンディルを見つめた。その目は震え、マルシオは小さな子供のように声を上げて泣き出した。
今ここに一緒にいない友を思い、寂しくて寂しくて……それだけが彼を包んでいた。
サンディルはマルシオを抱きしめた。何も言わずに泣きじゃくる少年を包み込み、サンディルも涙を流した。悲しみが溢れて止まらなかった。
長い時間泣き続けた後、マルシオは気を失うように眠りについた。その寝顔はまるで死んでいるように儚く、美しく見えた。
二日経ってもマルシオは目を覚まさなかった。サンディルは深く心配した。彼がこのまま二度と目を覚まさないのではないのだろうかと。
天使もまた、あまりにも辛い悲しみに捕らわれてしまうと石になってしまうことを知っていた。それでなくても彼は心身共に疲れきっていた。
サンディルはできる限り彼の傍にいた。時々声をかけたり髪を撫でたりし、そしてマルシオの枕元においてあるリヴィオラに祈りを捧げ続けていた。
サンディルは五千年の時を経て舞い戻ってきた天使が、また悲しみで消えてしまうなんて、それだけはさせたくないと強く願っていた。リヴィオラは時折、そんな切な思いを受け入れるように青い光を灯したように見えた。それが光の加減で揺らめいているだけなのか、サンディルには分からなかった。
そしてその願いが神に届いたかのように、三日目の夜にマルシオは目を覚ました。
「……青い光が俺を呼んだんだ」マルシオは独り言のように呟いた。「俺はこのまま眠っていたかった。でも、その光が許してくれなかった」
サンディルはよかった、よかったと繰り返しながらマルシオを再び抱きしめた。
マルシオは目を覚ましてからもしばらくの間、ベッドの上で呆然としていた。そこに「にゃあ」と猫の声が聞こえた。振り向くマルシオを待たずに一匹の茶色の猫はベッドに飛び乗ってきた。前足を揃えて、首を傾げてマルシオを眺めている。マルシオもその黄色い目を見つめ返した。
「……ジン?」
猫の代わりにサンディルが答える。
「ここで飼っている猫じゃ」サンディルもジンを見つめて。「君も以前に会ったことがあるじゃろう」
マルシオはあの時のことを、この猫に怒鳴られていた毎日を思い出した。
そして今ここにいない、いつも一緒にいたはずでこれからもずっと一緒にいると思っていた二人の姿が脳裏に描かれた。漏らすように呟く。
「……クライセンは?」マルシオは目を細めた。「ティシラは?」
サンディルに向き合い。
「なあ、あいつらはどこに行ったんだ。まだ帰ってこないのか」
マルシオは身を乗り出して興奮し出した。
「どうして俺だけ置いていかれたんだよ。どうして俺は一人なんだ」
「落ち着きなさい」
サンディルはマルシオの肩を掴む。だがマルシオは再びボロボロと涙を流した。ジンは驚いて、ひらりとベッドから降りて早足で室を出ていった。
「なんでこんなことになるんだよ。なんであいつらがいないんだよ。俺は天上界から追放されてどこにも行くところがないんだ。いや、行くところなんていらない。ただ、あいつらさえいればそれでよかった。こんなふうに、こんなに早く別れがくるなんて考えたこともなかった。みんな命を懸けてた。いつどこで誰が死んでもおかしくない状況だったけど、まさか本当にこんなことになるなんて信じられない。なのに、なんでだよ。なんで俺だけ生かされてしまったんだ。こんなの嫌だ。あいつは、クライセンは人間だけど世界一の魔法使いで最強で不死身で……死ぬなんてあり得ないよ。あいつは完璧なんだ。なあ、そうだろう? ティシラもそうだ。あいつはどうしようもないバカだ。バカが死ぬわけないよ。世界を救うために好きな男と心中なんて、そんな感動的な最期なんて似合わない。あいつがバカだから俺は安心できたんだ。あいつがいたから、なんか自分が天使だとかどうでもよくなってきて、すごく楽だったんだ。あいつがいなきゃ意味がないんだ。なあ、あいつらはどこにいってしまったんだ」
必死で訴えかけるマルシオをサンディルは見つめた。マルシオの肩を掴む手に力が入った。
そして、その辛い質問を口に出した。
「……彼らは、死んでしまったのか?」
マルシオはまた泣き出した。頭を横に振ると、滴がひとつ散った。
「……分からない」泣きながら続けた。「クライセンが修羅界に入っていって、気がついたらティシラもいなくなってて……しばらくしたら地震が起きたんだ」
2
それは立っていられないほどだった。
「皆、逃げるんだ!」
トールが叫んだ。身の危険を感じた一同は洞窟から抜け出すべく体を起こした。しかし、マルシオだけは振り向かない。
「マルシオ!」トールが彼の腕を掴む。「何をしているんだ」
「離せ!」マルシオは怒鳴り返した。「あいつらが戦っているのに、置いていけるか」
「僕たちがここにいても何もできない。洞窟が崩れたら潰されるだけだ。とにかくここを離れるんだ」
「嫌だ!」
トールが舌打ちすると、ほとんど同時にワイゾンがマルシオに駆け寄ってきた。
「引きずってでも連れていくぞ」
ワイゾンは嫌がるマルシオを無理やり抱えて走り出した。
ここにいても仕方ないことをどこかで分かっていたマルシオは、喚きながらも扉を見えなくなるまで見送った。
一同は急いで外に泊めてあったシャルノロエスに乗り込み、その場を離れた。地震は世界全体を揺らしていた。激しい波に襲われながら、マルシオは小さくなっていくパラ・オールから目を離さなかった。
その目に絶望が映った。パラ・オールは激しく揺れながら、それに耐えられなくなったように崩れ始めた。
遺跡はマルシオの視界の中で海に沈んでいく。一同はマルシオと共にそれを見届けた。
マルシオの視界がぼやけていく。彼はパラ・オールと同じくして頭を垂れ、その場に崩れ落ちていった。
地震はしばらくして収まった。海は何もなかったように静まり返った。その上をシャルノロエスはゆっくり流れ続けた。
四日ほどでフィレスアンの港に着いたが、その間、一同はほとんど会話をしなかった。
港にいた兵たちが、海賊船が来たと騒いだがすぐにトールがそれを収めた。
ワイゾンたちはマルシオとトールを降ろし、慌ただしく海に帰っていった。トールはすぐに通信を使ってティオ・メイに連絡を取った。グレンデルに今すぐ帰ってこいと言われ、馬を準備した。馬は二頭連れてこられた。トールは黙って俯いているマルシオに一頭を渡した。
「帰れるか?」
「……どこに帰ればいい?」
「それなら城についてこい。すぐに落ち着くことはできないだろうけど、君の居場所は用意できる」
マルシオは目を逸らし、頷かなかった。
「……いや、俺にはやることが一つだけ残っている」
「そうか」トールは時間を惜しむように馬に跨った。「必ず連絡をくれ。何があっても僕は君の味方だから」
トールは兵に見送られてその場を去っていった。
マルシオはしばらく立ち尽くした後、港を出ていった。結局馬は近くにいた兵に鞍を渡しておいてきた。
マルシオは急ぐでも足を止めるでもなく、のろのろと歩いた。
行き先はウェンドーラの屋敷だった。何を期待しているわけでもなかった。何も考えていなかった。ただ、突然一人になってしまった現実を受け入れる努力をしていた。
寂しかった。そこには、いちいち人を小馬鹿にして癪に障る彼も、我儘でマイペースで騒がしい彼女もいなかった。二人はどこにもいない。だが、きっとどこかにいるんだとも思った。その葛藤がマルシオを更に追い詰めた。
ふらふらと歩き続けた。どのくらい歩いていたのか自分では分からなかったが、見慣れた森が見えた。マルシオは迷い込むようにそこに入っていっていた。
「儂は」サンディルはマルシオの頭を撫でた。「君が戻ってきてくれたことを、本当に喜んでいるよ」
そこまでを途切れ途切れに話したマルシオは呼吸を整えようとする。しかし肩は大きく揺れ、体が言うことをきかない。
「マルシオ。君がここへ来てやるべきと思ったことは何かな」
マルシオは少し落ち着きを取り戻してきた。腫れた目を枕元の青い石に移す。
「これを」マルシオは菱形の箱に手をかけた。「返しに……」
マルシオは決して箱からそれを出さなかった。石には一度も、指一本触れなかった。直接手にすることは、今の自分には許されないと思っていたのだ。
「あいつは預かってくれと言ったんだ」マルシオは眉を顰めた。「必ず取りにくるって言ったんだよ」
ふっとサンディルは体の力を抜いた。僅かに顔の皺が下がった。
「そうか」そして、微笑む。「それを聞いて安心した」
マルシオはサンディルを見上げた。もう涙は止まっていた。
「奴はな」ゆっくりと話す。「約束はしない主義なんじゃ……だが、稀に交わしたそれは決して破らない」サンディルの目に涙が浮かんだ。「いくらか時間に遅れる、だらしないところもあるがな……」
それからマルシオは屋敷に居着いていた。
行くところがないのもあったが、何よりもクライセンとティシラがいつ帰ってきてもいいように、ここで待ちたかったのだった。
だが、一年が経っても、まだ二人の消息さえ噂にも聞かなかった。
マルシオは最悪の結果を想像しないように、目を閉じて頭を振る。気を紛らわそうとサンディルに声をかけた。
「そういえば」サンディルには聞きたいことがたくさんあった。「あなたと初めてここで会ったとき、あなたはティシラをからかっていましたよね。まるであいつのことを知っているかのように」
サンディルがとぼけた顔をする。
「ああ」思い出したように。「ジンから話は聞いていた。天使と魔族が居候しているとな。奴から他人の話をしてくるのは珍しいことじゃった。ここに一緒に住まわせるなんて儂は驚いたよ。そこを深く追求すると、あいつのことじゃ、意地を張って何をしでかすか分からんからな、儂は刺激しないように興味深く聞いていた」
「それで」マルシオは身を乗り出す。「あいつは俺たちのこと、なんて言ってましたか」
「それは聞かない方がいい」
「え? なぜ」
「愚痴と悪口ばかりじゃったからな」
「……なんだ」
マルシオは口を尖らす。まあ、そんなところだろうなと思いながら。
「だが、奴は君たちのことは好いておったようじゃ。でなければここにいさせはしなかっただろう。最初は兄弟ができたような感覚だったのかもしれないな。君たちがここにいる間に、きっと奴は『生きたい』という感情を初めて持ったんじゃと思う」
「どういうことですか」
「流れる時間の端々に、止まって感じる間があったんじゃ。あいつは時間に敏感じゃ。普通の人間が感じる一時間、一日という単位ではない。常に流れ行く、目に見えないものを体で感じ取る。好きでそんな体質になったわけではないのだろうが、果ての見えない螺旋に終わりがないことを知ってしまったら、人は生と死の境が薄くなってしまう。いつの間にか生まれ、いつの間にか死んでいく。そうやって遠くを見過ぎてしまうと、何もかもが無意味に感じてしまうんじゃ」
マルシオは、またサンディルの話が小難しくなってきたと思いながら、必死で耳を傾けた。
「例えば君は、抱える問題に答えがないことを知ってしまったら、どうする?」
「そ、そんなの」マルシオは突然の問いかけに戸惑いながら。「やってみなきゃ分からないよ」
「いや、ないのじゃよ。確実に。例えばじゃが、君は先にその答えを知ってしまうんじゃ」
「確実に……」そんなことを言われても、と思いつつ。「まあ、普通に……やめるだろうな」
「そう、普通はな。奴はそんな時間を何千年も過ごしてきた。天使や同胞と共にノートンディルで生きていればこれほど孤立せずに済まなかったかもしれぬ。もしかすると、つまらない話で笑い合えるような友達の一人や二人いたのかもしれぬ」
「想像できない」などと余計に混乱するマルシオの傍らで、サンディルはしみじみと語った。
「『持ち過ぎた力』が奴を捻じ曲げ、完璧という孤独へ追いやった。じゃが、その完璧だったはずの一本道を塞いだのが、君とティシラじゃ。その迷路には答えがなかった。そして今も、まだ見出せてはいないのじゃろうな」
マルシオは後半辺りから話の全部を理解できないでいた。しかし、自分にとって悪い話ではないことだけは分かる。
「……なぜ、あなたは」マルシオは呟くように。「彼をこの地に?」
サンディルは間を置いた。その目が弱々しくなる。
「……生きて欲しかったんじゃ」風のように答える。「クライセンは母親の死体を見ても泣かなかった。すべてを受け入れるかのように、黙ってそれを見つめていた。まだ一人で歩けないほど幼かった。なのに、まるでこの世を儚んでいるかのように、戦火の中で怯えもせずにじっとしていた。儂はランドールが滅ぶことを知っておった。同胞たちと同じ道を選び、共に果てるつもりでいた。しかし、できなかった。クライセンが哀れで仕方がなかった。教えてやりたかった。この世はそんなに悪くないことを、奴が死ぬために生まれてきたわけではないということを。儂はランドール人であることも賢者であることも忘れて、夢中でクライセンを抱いて走り出した。しかしパライアスは儂らにとって、とにかく住みにくい場所じゃった。生き延びたとはいえ、クライセンを笑わせるものはなにもなかった。それどころか奴の幼い目は憂いていた。なぜ自分がここにいるのか、なぜ生きているのかと言わんばかりに。儂は答えてやることができなかった。ただ待つことしかできなかった。奴の心を開いてくれる、何かが現れてくれることを」
マルシオは聞き入っていた。真剣な顔の彼にサンディルが目を移した。
「そして、五千年という時を経て……やっと来てくれた」
「…………」
「儂は自分のしたことを、今はまだ、後悔などしていないよ」
今は、まだ──マルシオも同じ気持ちだった。まだ答えは出ていない。答えなどないのかもしれないし、もしかすると答え以前に疑問すら明確ではないのかもしれない。
クライセンとティシラが帰ってこない限り何も分からない。
待とう。今、自分にできることをしながら。
ふと、居間の棚に常備してある水晶が光った。それに気づいて、マルシオが立ち上がる。寄りながら手を翳すと聞きなれた声が聞こえてきた。
『マルシオ』その主はトールだった。『元気にしてるか』
「何か用か」
『なんだよ。久しぶりなのにそんな挨拶はないだろう』
「久しぶりって、一週間前に話したばかりだろ。何かあったらこっちから連絡するから。そんなにせっつくなよ」
『分かってるけど気になるんだよ。今度そこに顔を出すよ』
「いいよ。忙しいんだろ」
『暇とは言わないけど、僕は別に魔法も使えないし、国の再建に王子って立場はあんまり役に立たないんだ。正直、居辛いよ』
「立場の問題じゃなくて、お前が頼りないだけだろ」
『うーん』トールは笑い出す。『まあね』
「相変わらずお気楽だな。来るのは勝手だけど、ちゃんと許可を取ってこいよ」
『何だよ、君まで。全くあれから周りの目が厳しくてね。監禁されているみたいで息苦しいよ』
「自業自得だ」
『でも、君たちと一緒にいた時が一番楽しかった。また旅に出たいといつも思う』
共感はできるが、マルシオは素直に頷けなかった。
『そう言えば、最近ワイゾンの名前を聞いたよ。あいつらすっかり復活したみたいで、極悪海賊としてメイに手配書が回ってきたんだ。組織も最大規模と言われ、百人近くの手下がいるらしい。まあ、頭が魔族となればなかなか敵う奴もいないだろうけどな』
「そうか。あいつらも元気なようだな」
『ここだけの話だが、実はワイゾンがメイに海賊の情報提供をすると交渉を持ちかけてきたらしい。陸を狙うような不穏な動きの海賊がいたら国に知らせ、必要があれば力も貸すと。その代わり、ワイゾンは国の情報機関を自由に利用できるように許可を求めたんだって』
「それで、国はどうしたんだ?」
『僕はこの話を成立した後から聞いたんだ。ワイゾンも、ここで僕の名前を出してくれれば早く話が進むのに、律儀な奴だよな。王子が海賊とお友達だなんて笑えないからね、きっと僕のことを考えてくれたんだと思う。それで国のことだが、ワイゾンは別に陸を行き来することで何かを企んでいるつもりはない、ただ魔力、魔物、魔界についての知識が欲しかったのと、何よりも戦争で行方不明になった者の消息を知りたいだけだと主張したんだ。たったそれだけのことで、そこまでの報酬を出してくる海賊を疑ったが、数日後に彼がクライセンに同行した一人だと分かって……おそらくダラフィンが口添えしたんだろうな。余計な詮索はなしで許可が下りたんだ。だからと言って仲良く手を組んだり、今更陸と海が共存できるわけがない。あくまで極秘で、お互いができる範囲での物々交換という契約が結ばれたんだ』
「……主人の身を案じるのは魔族の本能だからな。あいつ、魔族のことも何も知らないんだ。きっと辛い思いをしてると思う。傍にいるマイとキジも、どうしたらいいか分からないはずだ」
『そうだな。僕は彼らにいろんなことを教えてもらったんだ。彼らにも会いたいな』
「あいつらとはまともにお別れもできなかったからな」
『会いに行くときは僕も誘ってくれよ』
「一人で行けよ」
『連れないことを言わないでくれよ。君に会うっていう口実がなくちゃ、また家出しなきゃいけなくなるだろ』
「俺を利用するな。とにかく、その話はまた今度だ」
『僕も監視の目がきつい。そろそろ見回りが来る時間だ。また連絡するよ』
「ああ」
そこで通信は切れた。マルシオは「困った王子だ」と思いながらため息をついた。振り向くと、すっかり緊張の解けたマルシオに微笑むサンディルがいた。
「困った王子じゃな」
サンディルはソファに深く座り直しながらパイプを取り出した。それを口にくわえ、火を灯す。
3
トールはマルシオと別れてから、ほとんど休まずに馬を走らせた。それでも城に着くのに五日はかかった。
城門前にはダラフィン率いる兵の数十人が彼を出迎えた。一同は王子の帰還に深々と頭を下げた。
しかしトールは違和感を持った。何かが足りない。いつもダラフィンの隣にいるはずの彼が、オーリスがいなかった。
「オーリスは?」
ダラフィンは頭も上げず、答えもしない。
「彼はどこだ。怪我でもしたのか」
ダラフィンは頭を下げたまま、低く呟いた。
「国王陛下がお待ちです」
嫌な予感がした。トールは疲れた体に鞭を打ちながら、馬を下りて王室に走った。
すれ違う兵たちは彼の姿を見ると、作業の手を止めて頭を下げる。トールはそれに全く構わず走った。
勢いに任せて王室の扉を開ける。そこには喪に服したグレンデルがいた。
久しぶりに見る父はひどく老けて見えた。普段は着ない、真っ白のローブを身に纏っている。
室内は大量の白い花で飾られていた。その片隅には俯いたライザが佇んでいた。彼女もまた全身を白い衣装で包んでいる。
他の数人の兵も王子の姿に頭を下げるだけで暗い表情を変えなかった。
オーリスの姿がどこにもない。トールはゆっくりと歩を進める。グレンデルが振り向き、薄汚れている息子を悲しみの目で迎えた。
「よく無事で……もう、会えないかと思った」
二人は歩み寄った。トールは大きく息を吸い込み、聞かなければいけないことを聞いた。
「誰を……弔っているんでしょうか」
「……たくさんの人が死んだ。堕ちた国もある。だが皆、立派に戦った」
トールは震え出した。グレンデルの低い声は静かな室内に響く。
「オーリスもまた、この国の英雄として語り継がれるに相応しい……最期だった」
トールは言葉を失った。信じ難く、まだ、涙は出ない。
トールにとってオーリスはもう一人の父親のような存在だった。その優しい笑顔はトールだけでなく、人々の不安を癒してくれた。
厳格なグレンデルと豪快なダラフィンの隣で、オーリスは人々の相談役だった。偉大な魔法使いでありながら、暇さえあれば娘の自慢話ばかりで人を退屈させることもあった。そんな人間らしい一面も愛されていた。
トールはオーリスが好きだった。剣も持たない彼が戦争で死んでしまうなんて、受け入れたくない現実だった。
「父上、僕は……」
トールは震える手でグレンデルの肩を掴んだ。
が、異常な感触で咄嗟に手を離してしまった。固まり、青ざめる。まさか、と思う。
父の右腕が、なかった。
怖くて確認することはできなかったが、間違いなかった。グレンデルの右肩から下が無くなっていた。
トールはあまりにも深い戦争の傷痕を目の当たりにし、がくりと膝をついた。見開いた目から涙が流れる。追うようにグレンデルも膝を折った。
「僕は」トールは陰る父の顔に自分を恥じた。「何も出来ませんでした。僕は無力です。すべてを裏切って出た旅で得たものは、己の小ささを知ることだけでした」
「お前は私のたった一人の息子だ」グレンデルはトールを責めなかった。「生きて帰ってくれた。それだけで十分だ。離れていたからこそ、思った。やはりお前でなければいけないのだ。代わりなどどこにもいない」
「……父上」
グレンデルは、今は何も言わなくていいと思った。
今はただ疲れた体を休め、失ったものを悼むその時間だと、グレンデルは片手でトールを抱き寄せた。
もしトールの身にまで何かあっていたらと思う。もう自分は立ち直れなかっただろう。
だが息子は帰ってきた。片方を失ったこの手の中で泣いていた。少なくとも優しい心は失っていない。それだけでよかった。一人の父として、グレンデルは彼の帰りを心から喜んでいた。
トールは丸一日眠り続けた。
目が覚めると、そこにはライザがいた。ベッドの傍の窓際で静かに椅子に座っていた。きっと彼女が自分の看病をしてくれたんだと思う。目が合うと、ライザは微笑んだ。
「……おかえりなさいませ」
トールは気まずそうに目を伏せたまま体を起こした。最初に出た言葉は「ごめん」だった。
「謝ることなど……」
ライザの声は優しかったが、トールには怒っているのが分かった。
「心配をかけてしまって」
「あら」ライザは首を傾げる。「心配なんかしていません」
トールは面食らい、困ってしまう。ライザはつんとして目を逸らす。
「心配なんかしていませんわ」ライザは繰り返した。「全然、あなたのことなど考える暇もないほど忙しかったので」
嫌な空気が流れた。トールはどうしたらいいか分からない。
そんな彼を無視して、ライザは立ち上がった。
「食事の用意ができています」言いながら、扉に向かった。「王が一緒に食事をしたいとおっしゃっていました。正装で王室へいらしてください」
「ま、待ってくれ」
トールは堪らずベッドから這い出た。ライザは足を止める。だが背を向けたまま振り向かない。
「こっちを向いてくれないか」
ライザはゆっくり向き合った。そこには俯き、唇を噛み締める辛そうな表情があった。
トールは何から言うべきか迷った。だけどこのままでは駄目だと、とにかく何か話をしなければと、口を開く。
「本当に、ごめん。そんな言葉で済むとは思っていない。君が今、僕のことをどう思っているかは分からないけど……僕の気持ちは何も変わっていない。途中、迷ったことも疑ったこともなかった。僕の勝手かもしれないけど、それだけは分かって欲しいんだ。話を……聞いてくれないか」
ライザは俯いたまま、微かに微笑んだ。
「何も、お話など」
トールは戸惑った。ライザの気持ちがまだ分からない。怒っているのか、呆れているのか、恨んでいるのか、それとも……。何にしても受け入れるつもりでいた。ライザが動く。顔を隠すように、トールの胸にそれを埋めた。
小さな肩が震えている。トールはそっとそれに手を添えた。するとライザは体をぴくりと揺らす。ガラエルに刺された傷が疼いたのだ。ギメルに締め付けられた体のあちこちもまだ少し痛む。
トールはそれに気づく。撫でるように肩に触れると、彼女の服の下に抉れた酷い傷があることを知った。トールは深く息を吸って、目を閉じた。
言葉が出ない。ゆっくりと彼女の体に腕を回した。
「……あなたが」ライザの小さな声がトールの胸に響く。「何を得て、何を失ったかなど語る必要はありません。ただ、これからは傍にいてください。あなたがここにいてくれるだけでいい。やっぱり一緒にいたい。もう一人にしないでください。やっぱり、私はそんなに強くないんです」
トールは強く、しかし優しく腕に力を入れた。その中でライザは泣いていた。
ライザは今までを経て、複雑な思いや立場のすべてを捨てて素直な気持ちを伝えた。これが一人の女としての正直な言葉だった。我儘だと分かっていた。自分が好きになってしまったのは一国の王子なのだ。個人的な感情など交えてはいけないと分かっていたが、もう無理だった。
叶わなくても、伝えなければ後悔する。
トールは彼女の切実な思いを受け取っていた。嬉しかった。だが、それ以上にライザの痛みを肌で感じ、苦しめてしまった自分の不甲斐なさを噛み締める。
帰ってきた自分の城は、傷だらけだった。
「なぜだろうな」トールは呟いた。「こんな僕にも役目がある。それを皆が待っていてくれたなんて、まだピンとこないよ」
「あなたしかいないのです。あなたでなければいけないのです」
「うん。片腕を失った父上を支えられるのは、そして君の寂しさを埋められるのも僕しかいないって、分かるんだ。僕は王位を継ぐよ」
「……本当?」
「ああ。決めたんだ。今それに相応しいなんて思わない。だけど、王子としての役目を見つけたんだ」トールは遠くを見つめた。「僕はクライセンたちとすべてを見てきた。これを人々に伝えられることができるのは僕だけだ。彼らの伝説と、そして立場を守ってやらなければいけない。父上やダラフィン、そしてオーリス。彼らの他にも勇者がいた事実を彼らが望む形で残していきたい」
「望む形とは?」
「彼らは人に称えられたくて戦ったわけじゃない。本当に自分勝手な集団だった。僕もその一人だったんだけど。彼らは国を救ったにも関わらず、何も欲しがらなかった。おかしな連中だ。でも僕は彼らを掛買いのない友だと、仲間だと思っている。もしかしたら僕が生きているうちに二度と会えない者もいるかもしれない。ならば尚更、僕はそれを心に留めておくべきだと思う。僕だって彼らに感謝なんてされたいわけじゃない。僕がそうしたいだけなんだ。この国の王子だからこそ、王位継承者だからこそ。僕の役目はこれからなんだ」
「……妬けますね」ライザはトールの胸の中で微笑んだ。「私も一緒に行きたかった」
トールはそれを聞いて、ライザから体を離した。涙で濡れた彼女の顔を見つめて無邪気に笑う。
「今度は君も連れていくよ」
ライザは困ったように肩を竦めた。
「あなたは……また出て行くおつもりなのですか」
「あ、いや」
トールは目を泳がせる。戸惑う彼を見ながら、ライザはまた涙を流した。そしてそれを隠すようにまた彼の胸に顔を埋める。
「……ご無事で、本当によかった。怖かった。お父様が亡くなったとき、あなたの顔を思い出しました。ずっとそんなことはないと自分に言い聞かせていたけど、もしかしたらと疑ってしまいました。あなたは自分勝手な人だけど、私にとっては一番大切な方。怖かった。絶望に取り憑かれてしまったら、私は打ち勝てる自信がありませんでした。だけど、あなたは帰ってきた。どうかもう二度と私を一人にしないでください」
トールは改めて自分の罪深さを思い知った。
自分の勝手でどれだけの人を悲しませてしまっていたのかを痛感した。ごめん、という言葉を飲み込んだ。今は謝るときではない。今は彼女を抱きしめることが先決だと思った。
そして一年が過ぎた。パライアスの人々は王の言葉に従って、一つ一つ壊れたものの修復をしていった。簡単には元に戻らない。当然だった。建物などの崩壊よりも深く傷ついていたのは、何よりも人々のその心だったからだ。
それを支えたのが、他ならぬトールの言葉だった。本当は勝手に城を出て行って、勝手なことをしていただけのダメ王子だったのだが、人々はそんなことは知る由もなかった。
グレンデルはそれでいいと思った。トールは真実を見てきて、語る言葉に嘘はなかったのだから。
4
数ヶ月経ってトールは(やっと周りから許可を貰って)ウェンドーラの屋敷を訪れた。もちろんマルシオに会うためだった。結局ライザは同行できなかった。
オーリス亡き後、新たな魔道総監が急遽任命された。それはオーリスの信頼のおける一番弟子のサイネラだった。彼がオーリスの後を継ぐのに不満を持つ者はいなかった。
サイネラはダラフィンと行動を共にして国のあちこちを駆け回った。そしてライザはまだ就任したばかりのサイネラの補佐となっていた。もちろんライザ以上に経験のある優秀な魔法使いは他にいた。だがサイネラがオーリスの心を教えて欲しいと直接彼女に頼んだのだ。断る理由もなければ嫌とも言えなかった彼女は、傷は塞がったものの、その後を気遣う暇もないうちに忙しい日々を送ることとなった。
トールよりライザの方が城にいる時間が少なかった。気楽な毎日を送っていたトールは、彼女と顔を合わせる度に散々文句を言われていた。
ダラフィンはその様子を見て「もう尻にひかれている」と笑っていた。
それでもトールはめげずに、友との久しぶりの再会を心から喜んだ。
その日、偶然にもそこにはラムウェンドも訪れていた。トールは思いがけずアカデミーの話を聞くことができた。その日はサンディル、ラムウェンド、マルシオ、トールの四人のそれぞれの持ち寄った話で話題が尽きることはなかった。
アカデミーも戦争の被害は受けていた。
異常が起きてから、ラムウェンドは即急に寮にいる生徒たちを家に帰した。身寄りのない数人の者を残して。アカデミーは特殊な結界で守られてはいたが、魔薬の力には無効化されてしまっていた。その現実と、半壊した建物を目の当たりにしてラムウェンドは悩んでいた。
アカデミーをこのまま終わらせてしまおうかと。その相談のためにサンディルを訪ねてきたのだと言う。
「今や魔法だけがこの世の力ではありません。このままでは人々の視野が狭くなってしまい、死角が生まれ、また同じようなことが繰り返されてしまうのでないのでしょうか。私はそれを恐れています」
ラムウェンドの言葉に猛反対したのはマルシオと、意外にも魔法に疎いトールだった。偉大な魔法使いは必要だと捲くし立てる二人の隣で、サンディルは自分の出る幕はなさそうだと黙っていた。
「それだけじゃなくて」とマルシオ。「アカデミーは人の正しい心を養い、歴史を守る場所ではないですか」
「規模が小さくなったとしても」トールも口を挟む。「アカデミーは続けるべきだと思う。自らの手で滅ぼそうなんて、そんなのランドール人の奢りじゃないか」
「トール」マルシオが睨み付ける。「そんな言い方はないだろう」
「僕はランドール人の在り方は好きじゃない。きっと自分たちが最も優れた人種だと思い込んでいたんだ。だから劣ったアンミールに白旗を挙げるのが嫌で、大陸ごと破壊したんじゃないのか。屍は晒さないのが彼らの美徳だか何だか知らないが、なんで他の道を探そうとはしなかったんだ。どれだけ汚れてももっと足掻いてもよかったんじゃないのか」
「何も知らないくせに、偉そうなことを言うな」
「魔法戦争で何かが変わったように、今回ことでもきっと何かが変わる。アカデミーにもいつか変化は起きるだろう。だけどそれはいつ、どういうふうにかはまだ分からないじゃないか。少なくとも今は必要とされている。ここで勝手に形を変えることは逃げなんじゃないか。戦は終わったが、まだ戦いは終わっていない。これからが重要だ。何を創り、残していくか。それはきっと、この傷の上に生まれる新しいものが導いてくれるんじゃないだろうか。そして、その新しいものが正しく育つために僕たちはこの痛みを伝えて守っていかなくちゃいけない。それが生き残った者に科せられた努めだと、僕はそう思う」
トールは真剣に語るが、マルシオは素直には頷かない。
「そう言うお前は遊んでるじゃないか」
「うるさい」痛いところを突かれて。「そのうちやるよ」
サンディルは、この場にクライセンやティシラがいたら何と言うだろう、そんなことをふっと考えた。
脳裏に二人の姿が浮かんだ。その表情は、優しい笑顔だった。ここにいないのが不思議なほど鮮明だった。
だが二人の幻影は一同を見守ったまま、何も言葉を発さなかった。
次第にその姿は薄れていく。そして二人の言いそうなことをいくつか想像しようとするうちに、完全に消えていった。
改めてつくづく思う。あの二人の言動など、誰も予測できるものではないと。
「とにかく」トールはラムウェンドに。「あなたがやる気がないと言うのなら、アカデミーはティオ・メイの管轄下に置きます」
突然の申し出に面食らうラムウェンドの代わりに、隣でマルシオが呆れる。
「何を言っているんだ」
「あなたが引退したとしても、他の優秀な魔法使いを探してアカデミーは継続させます。建物の修復やこれからの運営に必要な資金も国に出させます」
「勝手なことを言うな」マルシオは黙って聞いていられない。「アカデミーはただの養成所じゃないんだ。いいからお前は口を出すな。大体、ダメ王子にそんな権限なんかないくせに」
「だから」トールは口を尖らせる。「僕が王になってからだ」
間を置いて、一同は笑い出す。トールは自分が「ダメ王子」だと自覚することにした。今はそれでいいと開き直っていたのだ。ラムウェンドはそんな彼に微笑んだ。
「そうですね」そして、目を伏せて。「トレシオール殿の言うとおりかもしれません。ランドール人は諦めが良過ぎたのかもしれませんね」
「ラムウェンド先生……」
すっと立ち上がるラムウェンドをマルシオは目で追った。
「分かりました」胸に手を当てて。「アカデミーは存続します。私の手で。もっと足掻いてみましょう」
マルシオとトールはほっとして顔を見合わせた。
「でも」ラムウェンドは付け加えた。「国の援助は遠慮いたします」
「そ、それは冗談だよ」トールは慌てて。「ちょっとそれっぽいことを言ってみたかっただけだよ」
一同に再び笑いが起こった。
ラムウェンドは暖炉の上にあった青い石を見つけ、それに目を奪われる。
リヴィオラは蓋の開いた銀の箱の中で沈黙していた。光の加減で揺らめく青い光に吸い込まれるような感覚に襲われた。ラムウェンドはしばらくその錯覚に身を任せた。魔法戦争のこと、ランドール人のこと、自分の受け継いだもの、自分のやるべきこと……リヴィオラがそれを改めて思い出させた。迷っていた自分を戒めるように。
それがなぜそこにあるのかは、ラムウェンドは聞かなかったし、誰も言わなかった。
それから数週間後、マルシオとトールはフィレスアンの港に出向いた。
そこにシャルノロエスがお忍びでくるとトールが知り、マルシオに連絡したのだ。彼らの滞在期間は一日だけだったので二人は急いだ。
三人は抱き合って喜んだ。港から少し離れた海上に、闇に紛れてシャルノロエスが浮いていた。
マルシオやトールが知ってるそれとは少し様子が違った。どうやら中にはたくさんの海賊、ワイゾンの手下たちが黙って潜んでいるようだ。それを警備する数人の限られた兵もそれを暗黙している。トールが声に出さずに兵に手を振ると、兵は戸惑うことなく目を伏せて頭を下げた。
マルシオとトールは一緒に船を下りてきたマイとキジを見て驚いた。
マイが昔とは違っていた。元からどこか妖艶な雰囲気は持っていたのだが、それがさらに色濃くなっていたのが見て取れた。
マルシオには一目で分かった。彼女はワイゾンの呪いを受け、彼と同じく魔族になっていたのだ。
ワイゾンが魔族になって、その生態が今までと確実に変わったことを日に日に思い知らされていった。傷はすぐに治るし、病気にもならない。食事の回数も寝る時間も減り、近くにいればいるほど時間の流れの違いを感じずにはいられなかった。
三人は何度も話し合った。二人は彼の存在が遠くなってしまっていることが怖くて仕方なかったのだ。
ワイゾンは「そんなことがあるもんか」と口では否定するが、彼も感じていた。きっといつまでも同じではいられないことを。
彼自身はそのままなのだろうと思う。しかし、周りが変わっていってしまう。きっと自分を残して老い、死んでいくのだろう。
ワイゾンはこれが人を捨てて魔族に魂を預けた試練だと、受け入れる努力をしていた。今はまだいい。数年後、数百年後、世界そのものが変わっていく。それをまるで部外者のように傍観しなければいけない。
どこまで自分の精神が耐えられるか、想像もできなかった。そう思えば思うほど、ワイゾンは孤独になりつつあった。
それを見守る二人もまた、どうすることもできずに苦悩していた。そしてマイが出した結論は、永遠に彼の傍にいることだった。
二人ならきっと寂しくない。そう言ってマイはワイゾンにすべてを委ねたのだ。
キジももちろん志願した。しかし、それを許さなかったのはワイゾンとマイだった。キジは精神的に幼い。きっと耐えられない。今より辛い思いをさせるに違いないと確信していた。
しかしどうしてもと言うキジを納得させる必要があった。そこで、二人は愛し合っているのだと説明した。ワイゾンはマイを永遠の伴侶として苦しみのすべてを分かち合う、だから邪魔をするなと言ってのけた。
それでも今までと変わらずお前は俺の弟分だとワイゾンに言われて、キジはやっと意志を曲げた。
マルシオとトールは、ワイゾンとマイがとうとう結ばれた、とは思わなかった。ワイゾンがマイによからぬ想いを寄せながら、あくまで海賊同士としての関係を守っていたことは聞かなくても分かっていた。
マイが彼をどう思っているのかは誰も知らなかったが、少なくともワイゾンと同じように感情を抑えているようには思えなかった。二人の微妙な関係は、船に居たときから誰もが暗黙で認識していたことだった。
それでもマイはワイゾンに魂を捧げた。明確な理由は分からない。きっと愛でも恋でもない、それ以上の思いが彼女の中にあったのだと思う。なぜなら、二人の信頼関係が確実に近くなっていたのを感じ取れたからだ。
恋人でも夫婦でもない、また違う形でお互いを必要とする関係を確立したのだと思った。
それはきっと、この二人だからこその望む形であり、他人には理解できないものなのだろう。
だからマルシオとトールはそこに口を挟む気にはなれなかった。キジも今はそう思っているのだろう。むしろ、やっと二人がくっついてくれたと、勘違いでも喜んでいるに違いない。
キジは決して頭はよくないが、子供のような優しい心を持っている。素直に祝福し、いつか自分が二人より先に死んでしまうことを悔やまずにいられると思っていた。
マルシオとトールはワイゾンからノートンディルの海のことを聞いた。パラ・オールが崩壊してから海にはもう毒はなくなってしまったと言う。
ワイゾンはティシラを探そうと、何か手掛かりだけでもないかと、パラ・オールのあった海底に何度か潜ったらしい。だがそこにはただ崩れた遺跡の残骸が眠るだけで何も見つからなかったと落胆していた。
未だ見ぬ魔界に、漠然と焦がれるときもあった。しかし主人を失った彼は魔界へ行く手段も知らないままだった。
「主人の許可がなければ勝手に魔界へ行き来することはできない」と、マルシオ。「どっちにしても勝手に迷い込みでもしたらどんな目に合うか分からない。魔界には凶暴な魔族がウジャウジャしてる。あっという間に食い殺されてしまうだろうな」
「そうか……」
それを聞いてワイゾンは肩を落とすが、皆に気を遣ってすぐに話を変えた。
「まあ、いいさ。今はとにかく海賊生活を満喫しているんだ。海賊界は今やほとんど俺の手の内にあると言っていい。しかし海賊なんてのはただの悪党の塊だからな、俺に爆弾でも落としてくる輩が現れてくれるのを待っているくらいだ。そうでなくちゃ俺も張り合いがない。負ける気はしないがそれだけが楽しみだ」
ワイゾンは豪快に笑った。
「海で何か異変が起きたらすぐに連絡するよ。今度、お前たちも船に遊びにこい。ずっととはいかないだろうが、苛酷な冒険に連れていってやるよ」
「本当か」トールが身を乗り出す。「それは楽しみだな」
「おい」それをマルシオが遮る。「ワイゾン、トールの前でそんな話はするな。こいつは断ることを知らないんだ」
「ああ、そうだったな」ワイゾンはまた笑って。「王子さま、あんたはだめだ。あんたの仕事の邪魔をしたなんて言いがかりをつけられたら面倒臭いからな」
「ええっ」
トールが眉を下げるが、それ以上は言わずにいじけた顔をする。そんな彼を見て笑いが起こる中、ワイゾンは話を続けた。
「前と違って、シャルの中は混雑して騒がしいぞ。また別の船を捜さないといけないかもしれないな」
「殺して、奪うんだろ」
マルシオがため息をつく。
「正確にはそういうことだ」
夜も更け、一同の酒盛りは頂点に達していた。
戦後、港の隅に新しく建設された二階建ての謎の小屋の明かりが消えることはなかった。
謎の、と言ってもティオ・メイが海賊との交流をするために新設したものだった。その計画にはワイゾンも参加していた。しようがするまいが酒盛りできる場所は確保しろと言い張ったらしい。設計者は嫌がり、話し合いは揉めに揉めた結果、お互いが提示した大きさの半分で妥協したのだった。
中はそれぞれが酔っ払い、収集のつかない会話が交わされている状態になっていた。気がつくと人数が増えている。巻き込まれた見張りの警備兵や、じっとしているのが嫌いな海賊の数人が紛れ込んでいたのだ。
騒げればそれでいいという、種族も身分もそっちのけの無礼講が繰り広げられていた。酒は海賊船にいくらでも積んであるらしく、歯止めとなるものは何もなかった。
5
熱気で息苦しくなったマルシオがふらりと外に出た。
顔を真っ赤にしているが正気は保っていた。外は少し冷たい風が吹いている。潮の香りが混ざっていた。心地よかった。
そのまま海の方へ歩く。しばらく風に当たって一休みでも、と思ってシャルノロエスが停泊している波止場とは逆の海沿いに向かった。ふと足を止める。
先客がいる。見慣れた後姿があった。遠目でもキジだとすぐに分かった。
彼が室内からいなくなっていたのも気づいていなかった。マルシオはもう少し近づいて様子を見る。
キジは頭を垂れて座り込んでいた。気分でも悪いのかと思ったが、どうやらそうではないらしい。その大きな背中が微かに揺れていた。
マルシオは放っておこうかと迷った末、声をかけることにした。背後から近づきながら。
「泣き上戸なのか」
キジは頭を上げるが、振り向かない。マルシオはそのまま彼の隣に腰を下ろす。
「やっぱり、寂しいんだろ」
キジは慌てて顔を拭う。
「さ、寂しくなんかない。俺だって海賊だ。自分の死に場所くらい自分で決める」
「そっか……俺は、寂しいよ」
マルシオは空を見上げた。
「俺はここが好きだし、友達もいる。毎日が楽しくないわけじゃない。だけど、何だろうな。足りないって言うか、いや、未だにどうしても納得いかないんだ」
「……俺も」キジは腫れた目を細めて海を眺めた。「そうかもかもしれない」
「置いてきぼりにされてしまったような……空しさが消えない。たぶんそうじゃないんだろうし、きっとあいつらの方が辛い思いをしてるに違いないんだろうって分かっているのに、酷いときは恨みさえ募るときがある。それでも俺は生きてる。死んだ方がマシなことなんて、本当にこの世にあるんだろうか。だけど待つことしかできない自分が腹立たしい。それでも、待つことしかできないんだよな」
キジは自分と同じ気持ちを持っている者がいると、初めて気がついた。少し楽になった。遠くを見つめながら自然と語り出していた。
「お頭が本当に、好き好んでマイさんを呪いにかけたと思うか?」
「いや」マルシオはキジに顔を向けた。「そうだな。ワイゾンがそんなことをするとは思えない。いくら好きだからって……好きだからこそ、彼女を傷つけることはできない。彼はそういう男だと思っていた」
「そうだよ。お頭は優しすぎるくらい優しい人だ。何よりも自分の荷物を人に持たせて楽しようとするようなずるい人じゃない。確かに行き当たりばったりな所もあるけど、仲間のことを一番に考える人なんだ」
「何があったんだ」
「お頭は絶対に頷かなかった。一人でどこかに行こうとしたときもあった。仕舞いには、納得がいかないなら殺せと言って俺たちに剣を投げつけた。斬っても刺しても簡単には死にはしないが、気の済むまでやれと俺たちを煽った。マイさんはそれを手にして……構えたんだ」
マルシオは嫌な予感がし、聞く前から眉を寄せていた。
「そして……その剣で、自分の喉を……掻っ切った」
予感は当たり、息を飲む。酔いは完全に覚めていた。
「躊躇いも手加減もなかった。深い傷からは息の音が漏れていた。普通なら助からない。普通なら……そんなことできやしないよ」
マルシオは寒気を感じた。相変わらず無茶苦茶だと思いながら。
「お前だったら、どうする? 目の前で好きな女が血塗れで死に掛けているんだ。冷静でいられるか?」
「……考えたことがない」
「最善の方法を用意する時間なんかなかった」再び、キジの目が潤んだ。「ただ、俺には真似することはできなかった。だからと言って、他に方法を思いつけるほど頭もよくない。俺は、弱い。お頭に命を預けると言いながら結局何もできないんだ」
キジは項垂れた。マルシオは未だに海賊の感覚についていけない。だが、命の重みは同じものだというのは分かる。
自分には、それがなかった。マルシオにとってはそのことの方が心を締め付けた。
人間は変わらないものを欲しがる。だが自分は限りあるものに憧れている。
どうして両方はどこにもないのだろう。ないものがあるから欲が出るのだ。自分は決して人間にはなれない。だけど、近づくことはできるはず。それが限界だと気づいていた。それでも一瞬一瞬を精一杯大切にすればいい。そう思っていた。
誇るのも後悔するのも、未来にあるのは自分の選んだ結果なのだ。
「真似する必要なんかないよ」潮風がマルシオの髪を揺らした。「マイはマイ、お前はお前だ。お前はお前の時間の中でできることをすればいい。俺はマイが正しいなんて思わない。間違っているとも言わないけど、きっとそれが彼女のできる精一杯だったんだ。だから、認めてやれよ」
いじけた様子のままのキジは唇を尖らせて返事をしなかった。
「それにしても」マルシオは薄く笑い。「マイはしっかりしているようで、意外と不幸体質なんだな」
キジが顔を上げる。涙は止まっていた。
「……そうなのか?」
「俺には女の気持ちなんてよく分からないけど」
「マイさんは不幸なのか?」
「ワイゾンもそうだ。悪魔に魂を売って幸せになんかなれないよ。マイは幸せになる権利を放棄したんだ。でも、たったひとつのものを手に入れるためにはそこまでの覚悟が必要なときがあるのかもしれないな」
「たったひとつって、お頭のことか」
「いや、たぶんそんな単純なことじゃないと思う」そこでマルシオは急にキジに顔を寄せる。「……あ、怒られそうだから本人には言うなよ」
声を潜めるマルシオにキジは黙って頷いた。自然と悲しみがなくなっていた。マルシオは歯を見せて笑った。キジもつられて頬が緩む。
「すっかり覚めたな」マルシオが腰を上げた。「俺は戻るよ。まあ、いなくなったことも誰も気づいていないんだろうけど。飲みなおしだ」
「お、俺も行くよ」
「無理するなよ。まだ泣き足りないんじゃないのか」マルシオが背を向けながら皮肉った。「俺はもう泣き飽きたんだ。これ以上泣き虫海賊に付き合っていたくない。ついてこないでくれ」
キジは体を捩ったまま、眉を寄せる。ゆっくり歩いていくマルシオの背中を見つめたまま、さっきまでの悲しみがじわじわと怒りに塗り替えられていく。
「何だと、このガキ!」立ち上がり、剣を抜く。「帰りの船の中で一番メソメソ泣いていたのはお前じゃないか」
「お、おい」マルシオはキジの剣幕に慌てる。「剣を抜くことないだろ」
「今の侮辱は万死に値する。死んで詫びろ」
しばらく二人は揉め合った後、べろべろになったトールに窓から呼ばれて室内に戻っていった。そこには笑顔しかなかった。悲しさ、寂しさなど入る隙は一切なかった。
一同は朝まで飲み明かした。日が昇るとほとんど同時にシャルノロエスは出航した。
マルシオとトールはそれを見送って、次の約束もせずにそれぞれに帰っていった。
*****
それからトールとライザが結婚するまで十年近くかかった。
トールが国が落ち着くまでと言い訳しながら、なかなか身を固めようとはしなかったのだ。だがいつまでもそうしているわけにはいかなかった。時を経てトールも少しずつ大人になっていった。
二人の結婚は国中に祝福された。
ただ、最も出席して欲しい二人がそこに姿を現さなかったのだけが唯一の心残りとなった。
ワイゾンたちにも声をかけたが、結局海賊の三人も祝いの手紙ひとつさえ送ってこなかった。後日、顔を合わせたときは「忘れていた」と笑って済まされる始末だった。改めて祝ってはくれたが、海賊にとって「結婚式」などはただの飾りにしか感じていなかったのだ。
一年後に一子が誕生してから、トールはやっと大人しくなった。
それを見て安心したのか、三年も経たないうちにグレンデルは安らかにこの世を去っていった。
そしてトールの王政が始まった。
トールはまず医学の知識のある者を集め、魔薬の研究をさせた。人々は驚いた。国を脅かした魔薬をなぜ復活させようと言うのか、最初は酷く反対された。しかしトールはこう言った。
「いずれは第二、第三のノーラが現れる。恐ろしいものから目を逸らしてはいけない。魔薬はきっと使い方次第で人々を守る力になる。本当に恐ろしいものは目に見えるものではない。人の奢りと心の欲、それに負けたときの弱さだ。魔薬が引き起こした戦争はその代表的なものに過ぎない。これから先、もっと恐ろしいものが生まれてくるかもしれない。だがそれから逃げていては、失うことを恐れていては何も変わらない。この国にあるもの、善も悪もすべては他ならぬ国の人間が、我々が生み出したものなんだ。二度と同じことが繰り返されないように、それを受け入れる必要がある」
さらにトールは続けた。
「ノーラは邪悪でたくさんの人を殺した。しかし彼も同じ人間だ。彼を恨まないで欲しい。ノーラは我々の中にある邪悪な心、醜い欲のすべてを背負って、それに相応しい罰を受けた。彼は我々に教えてくれたんだ。奇跡とは何もないところに与えられるものではない。苦しみの末、救いの光さえ遮られたときに自らが見出すものだと」
彼のその言葉は謎めいていた。だがそこに、人の数だけの解釈が生まれ、誰もがその答えを探しているうちに自然とトールを批判する者はいなくなっていた。
トールのような王は異例だったが、彼が人々から認められるまで、思ったより時間はかからなかった。