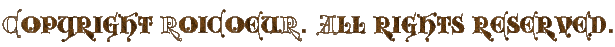第18章 約束





1
「ねえママ、魔法使いの話を聞かせて」
「また?」
「魔法使いって、困ってる人を助けてくれる優しい人なんでしょ」
「それは少し違うわ」
「どう違うの?」
「そうね、困ってる人を助けてくれるときもあるけど、それだけじゃないのよ」
「他に何ができるの?」
「何でもできるわ。でも、何でもしてくれるってわけじゃない。それじゃ誰も、自分で何もできなくなってしまうでしょ」
「そっか。そうだね。できることは自分でしなきゃいけないのよね。じゃあ、自分でできないことって何だろう」
「奇跡を起こすことよ。魔法使いは人に生きる希望を与えてくれるの」
「本当? 素敵。会ってみたいなあ。魔法使いは人間の世界にいるのよね。人間界へ行けば会える?」
「ええ、人間界にいるわ。でも会えるかどうかは、難しいかもね」
「どうして?」
「今でも魔法使いはいるわ。でも数が少なくなってしまっているの。何よりも、本物の魔法が使える人は……」
「本物って?」
「本物と言っても偽物があるわけじゃないのよ。そうね、本来あるべき魔力、魔法を生まれ持った人はもう……たった一人しかいないの」
「たった一人?」
「そうよ。昔はもっとたくさんいたんだけどね、もうたった一人になってしまったの」
「一人なんて……寂しくないのかしら」
「…………」
「ねえ、その人は寂しがってないかしら。それとも魔法使いって、魔法で寂しさも消してしまえるの?」
「……いいえ。それはきっと世界一の魔法使いでも使えない魔法よ」
「そんな……かわいそう」
「もちろん、他に修練して立派な魔法使いになった人も、これからなる人もたくさんいるのよ」
「じゃあ、私もなれるかな」
「ふふ、おかしな子。あなたは魔法使いになんかならなくてもいろんな力を持っているじゃない」
「やだ、そんなの。魔法が使えるわけじゃないもん。魔法使いがいい」
「そう。そうね、あなたならきっとなれるわ」
「そしたら、寂しさを消せる魔法を使えるようになれるかな」
「さあ……それはどうかしら」
「決めた。私、魔法使いになる」
「もう少し、大きくなってからね……」
*****
人間界では魔薬戦争から四十年という時が過ぎていた。
ここは魔界のヴィゼルグ。その頂点にあるアラモードの城ではささやかな宴が行われていた。
広い室にいるのは四人の魔族とそれを取り巻くピクシーが数匹だけだった。
煌びやかで、まるで美術館のような城だった。豪華な室はどこも天井が高い。少々不気味に感じるが、立派な絵画や彫刻などの美術品が訪れる者を迎え入れる。
立ち並ぶすべての柱には装飾が施され、ステンドグラスや天井画、壁画で包まれていた。埃一つ落ちていないエントランスには大きな階段がそびえ、その先にはいくつものリビングが続いている。
室の一つ一つが違う雰囲気であしらわれている。この城にいくつ室があるのかはここの主人ですら把握していない。
長い時間の間に、欲しいと思ったものを片っ端から増やし続けてきたのだ。管理や掃除は部屋の片隅に住まわせている小鬼たちに任せてある。王ならではの贅沢な生活だった。
リビングの先の、さらに広いリビングに明かりと人の気配がある。連なるテーブルの上には、量は少ないが質の高い食材を使った料理が数品と赤いワインが並んでいた。
それを囲む城の主、ブランケルが機嫌よさそうに笑っている。その隣にはアリエラが肘をついて座っていた。
そして二人の前には愛する一人娘、ティシラが微笑んでいた。
ティシラは落ち着いた雰囲気で派手過ぎない宝石とドレスで身を包んでいた。大きな声を出すこともなく、その仕草も上品だった。薄い化粧はまだ幼さの残る彼女の可愛らしい容姿を引き立てている。
ティシラの隣には彼女より少し大人っぽく見える若い青年が座っていた。長い黒髪を一つに纏め、紫のマントを礼儀正しく整えている。背もすらりと高く、顔立ちも美しい。
ブランケルは彼の赤い瞳と、笑ったときにちらりと見える二本の牙に親近感を持っていた。
彼の名はメディテラウス。愛称でメディスと呼ばれていた。
メディスは数ヶ月前にティシラの前に突然現れた。
それまでどこか元気のなかったティシラは、彼と出会って笑顔を見せるようになった。ブランケルはそれを何よりも喜び、ぜひ彼を紹介しろとティシラにしつこく迫ったのだ。
そして今日がメディスとの対面を兼ねた、ちょっとした宴の日だった。
メディスはヴァンパイアの血族だった。だが同族であるブランケルは彼の存在を知らなかった。
メディスはアラモードの遠い親戚にあたるかもしれないが、それを確かめる手段はないと言った。ヴィゼルグの片隅で生まれた彼は、意識を持ったとき、周りには誰もいなかったので自分が何者であるのかずっと分からないままでいた。成長し、魔力が養われるにつれて自分がヴァンパイアであると知ったと話した。
「しかし」ブランケルはグラスを口に運びながら。「こんな立派なヴァンパイアがいることを知らなかったなんてな」
メディスはにこりと笑う。
「同族であり、魔界の王であるあなたにそう言ってもらえるのは身に余る光栄です」
メディスの持つ魔力も類稀なるものだった。とてもブランケルに敵うとは言えなかったが、本気を出せば彼に次ぐかもしれないほどの力を秘めている。メディスは決してそれを試そうともひけらかそうともしなかった。
ブランケルを王として称え敬い、アリエラやティシラにも紳士に振舞う。そんな礼儀正しい彼をブランケルはすっかり気に入っていた。
「ところでメディス、率直だが君はティシラをどう思っているんだ」
「パパ、いきなり何なのよ」嫌な予感がしていたティシラが慌てて口を挟む。「メディスに失礼でしょ」
「一番大事なことだ。お前には後で質問する。今は彼と話をさせろ」
ブランケルはきっぱりと言い切った。ティシラは困ったようにメディスを見る。
メディスも横目でティシラを見た後、浅く頷いてブランケルに向き合う。
「彼女はとても高貴で美しい女性です。初めて出会ったときはとても儚く見えましたが、その取り巻く悲壮感が僕の心を捕らえて離してくれなかった。運命を感じました。僕は迷わず彼女に惹かれました。そして次第に彼女は笑顔を見せてくれました。僕は感動しました。やはり彼女には笑顔が似合うと確信しました。俯く彼女も美しいけど、何よりも笑ったときの輝きはどんな宝石の光にも適わない。できることなら僕はこの輝きを永遠に守りたいと思い、それを伝えるために今日、ここへ参りました」
照れもせずに語るメディスの代わりにティシラが顔を赤くする。
「一目惚れというやつか」
ブランケルが聞くと、メディスは即答する。
「はい」
しばらくブランケルはメディスの赤い目を睨むように見つめていた。彼の心を探っている。
メディスは目を逸らさずに堂々としていた。緊張した空気が流れた。
ブランケルは何かを確認したように、ワイングラスをテーブルに置いた。そして嬉しそうに口の端を上げた。
「よし、いいだろう。ティシラとの結婚を認めよう」
「!」
ティシラは咄嗟に立ち上がった。
「待ってよ! メディスとはそんな関係じゃないし、誰も結婚なんて言ってないじゃない。そんなつもりで連れてきたんじゃないのよ。勝手に決めないで」
「お前はメディスが嫌いなのか」
「……そうじゃなくて」
「好きなんだろう?」
ティシラは目を逸らす。力が抜けたように椅子に座り直す。
そんなティシラを無視してブランケルはメディスに続ける。
「メディス、君はどうなんだ」
メディスは全く取り乱していなかった。
「僕は彼女の幸せのためならこの命を懸けましょう」
「ティシラを愛しているんだな」
「はい」
ブランケルは深く頷いて、今度はティシラに質問する。
「で、ティシラ、お前はメディスのことをどう思っているんだ」
ティシラはゆっくり顔を上げた。口を尖らせている。
「私は」瞼を少し落として。「メディスのことは好き。でもまだ会ったばかりだし、結婚とかそんなの、相手が誰とかじゃなくて考えたことがないの」
「お前は魔界の姫。いずれはその器の男と結婚するんだ。それがいつであってもおかしくないだろう」
分かっているつもりだったが、実感があるわけではなかった。ブランケルは返事をしないティシラに続ける。
「メディスは私が認めた、お前に相応しい男だ。彼ならお前を幸せにしてくれる。そうでないときは私がメディスに制裁を与えるまでだ。私はお前の幸せだけを願っている。分かってくれるか」
「……それは分かってる」
「それとも」ブランケルは目を細めた。「他に誰か心に決めた男でもいるのか」
ブランケルのその質問でふっと緊張した空気が流れた。
ティシラはその中で一度目を閉じ、すぐに開く。
「いいえ」頭を横に振り。「そういうことじゃない。そんな人はいないわ」
ティシラのその言葉が両親を複雑な思いにさせたことは、本人は知る由もなかった。
「そうか。それを聞いて安心した」ブランケルは気を取り直して。「それならこうしよう。今すぐ結婚とは言わない。まずは婚約を交わして、お互いもっと知り合ってから正式に結婚と言うのはどうだ」
ティシラは顔を上げた。ブランケルは戸惑っている彼女に見つめられて眉を寄せた。
「パパ」ティシラは首を傾げられずにはいられなかった。「何をそんなに急いでいるの?」
ブランケルは息を飲んだ。そんな彼をアリエラが横目で見つめた。
「い、急いでなど」今度はブランケルが目を逸らす。「ただお前には早く幸せになってもらいたいだけだ。こうしてせっかくいい男が現れたんだ。先延ばしにする理由がどこにある」
ティシラは言い返せなかった。助けを求めるようにアリエラに質問する。
「ママはどう思う?」
今まで黙っていたアリエラがティシラを見つめた。しかし、ふっと目を伏せて。
「あなたが決めることよ」
ティシラは気づいていた。二人が何かを隠していることを。それが何なのかは分からなかった。
しかしティシラは両親の惜しみない愛情に応えるために二人に逆らおうとせず、常に安心させてあげようと努めていた。
メディスのこともその一環だった。まさかここまで話が進んでしまうとは思っていなかったが、心の拠り所が見つかったことを知らせてあげたいと思っていた。
予想通り二人は彼を歓迎してくれた。喜んでくれた。なのにここで迷ってしまったら、また二人は自分を心配するだろう。それを思うとティシラは心が重くなった。
結婚なんて、余りにも急だからまだ実感が沸かないだけだ、と思い直す。メディスは自分を好きだと言ってくれている。自分もメディスは嫌いじゃない。
これでいいのかもしれない、と自分に言い聞かせた。
「……分かりました」
一同はティシラに注目した。
「メディスと婚約します」
一瞬、沈黙があった。だがブランケルが素早くそれを壊した。
「そうか」嬉しそうに立ち上がって。「ならば善は急げだ。すぐに準備に取り掛かろう」
メディスは俯いているティシラに微笑んだ。ティシラはそれに気づき、申し訳なさそうな笑顔を返した。
はしゃぐブランケルを他所に、アリエラはそんな二人のやりとりを黙って見ていた。
2
その日の宴は終わりになり、ティシラはメディスを送って自分の部屋に戻った。
ブランケルとアリエラはピクシーたちが片付けたリビングに戻ってくる。
「私は反対よ」
一転して二人は険悪だった。背を向けるブランケルにアリエラはきつい口調で言った。
「確かにメディスは高等な魔族だわ。だからってティシラと結婚する理由にはならない」
「ティシラが選んだんだ」
「あなたが無理やり言いくるめたんじゃない。あんなの政略的よ」
「お前は何が気に入らないんだ」
「ティシラの言う通りよ。急いで何になるの」
「ティシラには早く幸せになって欲しいんだ」
「私だってそうよ。でも強引だわ。もっと時間がかかってもいいじゃない」
「これ以上ティシラの苦しむ姿を見ていたくないんだ」
「それはあなたの我儘よ。一番辛いのはあなたじゃない。ティシラ本人なのよ」
「じゃあどうしろと言うんだ!」
ブランケルは振り向き、つい怒鳴ってしまう。微かに怯えているアリエラの見開いた目に気づき、ブランケルはしまった、とすぐに目を逸らす。
「もうやめよう」ブランケルは頭を抱えた。「この話をするといつも喧嘩になる。ティシラのことだけでも胸が痛むと言うのに、お前まで苦しませてしまうなんて、これ以上は耐えられない」
アリエラも同じ気持ちだった。だけど、どうしても納得がいかない。長い時間、いくら考えても解決の方法なんか見つからなかったし、最善策さえ思いつかない。黙っていても、動いていても事は何もいい方にはいかない。それでも成り行きや時間に任せることができなかった。
「……これじゃ、ティシラが可哀想よ」アリエラは俯く。「きっと今でもティシラの気持ちは変わってないわ。でも割り切ろうとして必死で戦ってる。あなたも知ってるでしょう? 今でも時々あの子が意識を失って何かに怯えていることを」
「……ああ」
「あれは魔薬の後遺症だわ。嫌だ、怖いって言いながら震えて泣いているのに、目を覚ましたらそれを本人は何も覚えていない。きっと自分でもどうしたらいいのか分からないのよ」
「大体、なぜティシラが魔薬なんかを飲まなければいけなかったんだ。それがおかしいだろう」
「そんなことは今は問題じゃないでしょ。魔薬自体はもう体には残っていないわ。それによって伴った恐怖がティシラの心の奥底に刻み込まれているのよ。怖いもの知らずで向こう見ずだったあの子があんなに怯えるなんて、普通じゃないわ。でも原因が分からなければ私たちでもどうしてやることもできない。だからって、それを無理やり忘れさせようなんて、ティシラはもっと傷つくかもしれないのよ」
アリエラは言いたくないことを必死で搾り出した。
「もしかしたら……あの子を救えるものがたった一つ、あったのかもしれない。でも、それはもう……そうだとしたら……ティシラの傷は、永遠に消えないのかもしれない」
ブランケルは崩れるように近くの椅子に腰を降ろした。両手で顔を覆う。アリエラはその背中を見つめた。
「……なんで」ブランケルの声は震えていた。「なんであいつなんだよ……なんでティシラはあんな男を選んでしまったんだ。あんな目にあってもまだ奴が好きだなんて……私だって分かっているんだ。ティシラの中にはまだあの男がいる。決してその名を口にはしないが、心のずっと奥ではあの男のことだけを想っている。それがティシラの笑顔を奪ったんだ。畜生……あの男はどこまで私を苦しめれば気が済むんだ」
あのときの地震は魔界にも起きていた。修羅界に近いそこは空間を歪ませた。
ブランケルは異常を察知し、修羅界に素早く飛んで行った。そこには娘が、ティシラがいるのだ。一体何が起こったのかと気が気でいられなかった。
ブランケルがイン・クーラを通り抜け、修羅界の入り口に辿り着いたときには、もう地震は収まっていた。
そこは見渡す限りの、何もない荒野だった。
来た方向に背を向けてただひたすら真っ直ぐ歩き続けると、いつ間にか暗闇にぶつかる。そこが修羅界だった。
周辺には何も生息していない。だが今日は、その荒野に何かがあった。
ブランケルは目を奪われた。胸が潰れそうなほど痛んだ。声も出せず、脇目も振らずにそれに駆け寄った。
それは見たこともない奇妙な物体だった。生まれたての赤ん坊くらいの大きさで、人の形はしていない焦げた茶色の軟体だった。いくつかの細胞だけが膨張して、僅かに残っている魔力が中で行き場を探していた。目鼻口も手足も何もなかった。
きっと放っておいたら数時間で事切れていただろう。ブランケルはそれを迷わず掬い上げ、震える手で抱きしめた。
ブランケルにはすぐ分かった。
それはティシラの、禁断の魔薬を投じた魔族の成れの果ての姿だったのだ。
ブランケルは、なぜこんなことにと涙を流した。抱きしめたそれからは小さな鼓動が伝わってきた。感じて、泣いている場合ではないとブランケルは城に連れ帰った。
アリエラはそれを見て気を失いそうになった。だがそんな暇はなかった。
すぐに城の一番奥の地下室に運ばれて棺桶の中に入れられた。ブランケルは強制的に魔界中の魔力の強い貴族を集めた。そして休むことも許さずにティシラに魔力を注がせた。それは数ヶ月間続いた。ブランケルの命令に逆らえずに途中で尽きる者もいたが、ブランケルは全く気に留めなかった。自分も魔力を注ぎながら、ただティシラの復活だけを願い続けた。
その甲斐あって、ティシラは一命を取り留めた。しかし元の姿に戻るにはまだ長い時間が掛かりそうだった。
何年も、何十年もティシラは暗い棺桶の中で眠り続けた。
ブランケルとアリエラはその長い間、ティシラだけのことを思って過ごしていた。
特にアリエラはティシラの眠る地下室からほとんど出てこなかった。虚ろで、ブランケルの言葉にもあまり答えなかった。
次第に塊は人の形を作っていった。少しずつ、少しずつ二人の知る彼女の姿に近づいていっていた。アリエラは眠らずにそれを見守った。徐々に衰弱していくアリエラの体も限界を迎えようとした頃、やっとティシラは目を覚ました。ブランケルとアリエラは泣いて喜んだ。
だがティシラは、そんな二人が誰だかも判断できない状態だった。
記憶を失っていたのだ。いや、元の彼女がただ記憶をなくしただけではなかった。
ティシラはすべてを失っていた。辛うじて魂の欠片だけが現世に留まっていただけだったのだ。そこに膨大な魔力が注がれたことで、塊が在るべき形を成して肉体を造り、生を持った。
体は大人でも、脳は赤ん坊のもと同様だった。
声は出るが言葉すら話せない。家族のことも、友のことも、そしてただひたすらに愛した人の名も、何もかもを失くしてしまっていたのだ。
それでも五体満足に生きてさえいてくれればと、両親はティシラに付きっ切りで面倒を見た。
まずは言葉を教えた。知能はあった。ティシラは空っぽの頭と体にどんどん知識を入れていった。
数年もすれば彼女は何の不自由もないほどに回復していった。
しかし、ブランケルは人間界のこと、魔法のこと、特にクライセンのことだけは彼女に何も教えなかった。
これだけはとアリエラにも強く、何度も念を押した。
「これでいいんだ。お前にも分かるよな」
ブランケルはアリエラに言い聞かせた。
「……クライセンは死んでしまったの?」
「知らん。あいつはどこにもいなかった。気配もなかった。おそらく修羅界に飲み込まれてしまったんだろう」
「そんな……」
「ティシラが助かったんだ。それだけで十分じゃないか」
アリエラは悲しんだ。クライセンの死と、それに伴うティシラの心に刻まれた傷の痛みを思うと溢れ出す涙を抑え切れなかった。ブランケルはやり切れず、黙ってアリエラを抱きしめた。そうすることしかしてやれなかった。
「クライセン……私はお前を絶対に許さない。死んでも許すものか……!」
3
魔界の姫の婚約パーティは一週間後に控え、慌ただしくその準備が進められていた。
ブランケルは派手に盛り上げようと、片っ端から貴族に招待状を送った。
その中にもメディスの名前を知っている者はおらず、皆が「ブランケルの娘を娶るなんて、一体どこの貴族様だ」などと騒いだ。
そのことでアリエラは何度もブランケルに注意を促したが、彼は気にしなかった――気にしない振りをした。
せっかく見つけた娘の縁談を壊したくなかったのだ。
「本当にいいの? メディスは只者じゃないかもよ。寝首をかかれたらどうするの」
「ふん。そうだとしてもこの私があんな若造にやられるものか」
黙るアリエラにブランケルは戸惑った。
「……なんだよ」
アリエラは意地悪な表情を向けた。
「たった一度だけあなたを追い詰めた男も、見た目は若造だったわね」
ブランケルの脳裏に「彼」の姿が浮かびあがり、かっと胸に熱が篭った。
「ずっと気になっていたんだけど、メディスってどこか彼に似てるわ。接点があるとは思えないけど、雰囲気とか、何となくね。あなたはそう思ったこと、ない?」
ブランケルはぐっと息を詰まらせた。アリエラは構わずに続ける。
「まあ、ティシラの相手だから似ていてもおかしくはないのかもしれないけど……あなたがそれを気に入るなんて不自然じゃなくて?」
「ば、馬鹿なことを言うな。メディスは魔族だ。ヴァンパイアだぞ。だから私は安心しているんだ。人間なんかと一緒にするな。メディスが私に逆らえるものか」
「……ならいいけど」
アリエラは無神経にブランケルの不安を煽る。ブランケルはアリエラと顔を合わせない。アリエラもそんな彼の背中から目を逸らし。
「私ね……」独り言のように呟く。「あなたがティシラに無理やりメディスと結婚しろなんて言ったとき、あの子のことだから絶対に嫌だって反抗して、あなたと喧嘩するんじゃないかって……期待したの」
ブランケルの心が揺れた。
「あなたもそうだったんじゃないの?」
ブランケルは答えなかった。アリエラはそれ以上待たずに静かにその場を去っていく。ブランケルは眉を寄せ、立ち尽くしていた。
パーティの準備は予定通り進み、その日を明日に迎えた。
ティシラは城の中庭で佇んでいた。明日のパーティに備えてヴィゼルグの人々は早めに休んでいた。静かだった。
背後に人の気配を感じた。ティシラが振り向くと、そこには闇の中から姿を現すメディスがいた。彼はゆっくりティシラに近づいた。
「ティシラ、どうしたの」メディスは微笑んだ。「こんなところで。明日は僕たちの婚約パーティだ。今日はゆっくり休まないと」
ティシラも微笑み返す。しかしそれはどこか悲しげだった。
「それとも、緊張して眠れない?」
ティシラの気持ちを解そうと気を遣ってくれているのが伝わる。ティシラは改めてメディスが優しい人だと思った。
「そうじゃないんだけど、何だかまだ信じられなくて……」
「怖いの?」
「……うん、そうかも」
メディスは何が怖いのか聞かなかった。
しばらく沈黙が続いた。
ティシラの中にいろんな思いが流れ込んできた。それは靄がかっていて、はっきりとはしなかった。迷いだった。
自分が過去の記憶を失くしているのは自覚していた。おそらくそこに何か秘密があるのだろうと思う。
間違いなかったのは、ブランケルとアリエラが自分の幸せだけを願っていてくれていることだった。疑う余地はなかったし、今のティシラにとってそれだけが救いだった。だからティシラは二人を問い詰めることはしなかった。
たまに城に訪れる貴族や血縁者に、こんな話を聞いたことがあった。
「死に掛けていた君を助けるためにブランケルはかなりの無茶をした。魔界中の貴族が巻き添えにされたが、彼は持つすべての魔力と権力を駆使して君を守ったんだ。あれほど必死になってる魔界の王なんてなかなか見られなかったよ」
と。また、ある貴族が「言うこともやることもとにかくデタラメで、すっかりやつれてしまっていた。その時だけは王の風格も威厳もなかった」と冗談交じりで口にしたときがあったが、その後ブランケルに半殺しにされていた。その光景は笑えるレベルではなかったが、父の取り乱す姿を見て、余程だったんだと事の大きさを思い知った。
だがそれが何なのかは分からない。きっと追求することは父を責めてしまうことになると気づいていた。
知りたいと言うのが本音だった。本当にこのままでいのだろうか、このまま何も知らずに親の懐で時を過ごすことが幸せなのだろうかと疑問を抱いていた。
メディスと出会う前まで、ティシラは何度か貴族の集まるパーティに出席したことがある。
知らない人だらけだった。なのにその知らない人は、自分よりも大人ばかりなのに機嫌を取って諂ってくる。自分を褒めちぎりながら、綺麗な男たちが周りを囲んだ。
それぞれに個性はあった。あの手この手で自分に近づいてこようとする。
そこには何でも揃っていた。持ってこいと言えばすぐに用意される。だがティシラはすべてが空虚に感じていた。
欲しいものは何もなかった。なのに、いらないものばかりだと思った。
そう思いつつ、ティシラは何かを探していた。無意識だった。
自分を欲しがる美しい男たちの顔を一人一人見ていった。何を探しているのか自分でも分からなかった。
結局、何もなかった。
それでもティシラは楽しむ努力をした。出来るだけ笑い、話し、誘われれば二人で会うこともした。毎日のように「どうだった」聞いてくるブランケルに「楽しかった」と嘘をつくしかなかった。
そんなときは自分を責める一人の時間が必要だった。いろんなことを試してみたが、どうやっても心の靄が消えることはなかった。
自分は死に掛けた。いや、一度死んで生まれ変わったのかもしれない。その前の自分がどんな人物で何をしてきたのか、してしまったのか。それはきっと想像しても及ばないほどの所業だったに違いない。でなければ自分が命に支障を来たし、父をここまで追い詰めてしまうことにはならないだろう。だがブランケルとアリエラはそれを許してくれている。それだけは受け入れなければいけないと思った。
二人が真実を教えてくれないことを不安に思ったが、一体何が足りない? 過去を知らなかったとしても今の自分に何か不自由があるだろうか。
自分を愛してくれている両親がいる。姫という地位も魔族としての高貴な力もある。十分に恵まれているではないか。
今、自分の知る限りのこの狭い世界の中では──。
そう、ティシラは「狭さ」を感じていたのだ。説明できない窮屈さがあった。
ここ以外を知らなければそんなことを思わないはずなのに、なぜだろう。過去の自分はここじゃないどこかの、ここにない何かを知っていたのではないだろうか。「狭さ」はそれを訴えているのではないだろうか。
体が何かを求めていた、そんな気がした。まるで見たこともない、記憶にない何かを必要としているかのように。
それがないと生きていけないほどに。
もしかしたらメディスと結婚することで、この苦悩から抜け出せるかもしれないと思った。
同時にそれが正しくない判断だということも分かっていた。メディスへの情はあったのだが、これは彼を利用することになるのだ。彼だけでなく、両親も何もかもを裏切ってしまうかもしれないのだから。
心では分かっていながらティシラは自分の中にある危険な衝動を否めなかった。いずれにせよメディスの出現はきっと何かのきっかけであり、変化の前触れであることだけは感じていた。
だからこそティシラは迷っていたのだった。
メディスはそんな彼女の心中を察しているかのように、急がせずに黙ってティシラの決断を待っていた。
その数分は長く感じられた。静寂だけが二人の間に流れた。
「……やっぱり」
とうとうティシラが口を開いた。その声は弱々しかったが、ある決心が導いたものだった。
「これ以上嘘はつけない」
ティシラは顔を上げてメディスを見つめた。メディスは何も驚かなかった。
「やっぱりあなたとは結婚できない」ティシラはまっすぐに本心を伝えた。「あなたのことは好き。でも何かが違うの。うまく言えないんだけど、恋人とか夫としてじゃない。ごめんなさい。あなたに何かが足りないとかじゃない。あなたには何も悪いところなんてない。でも、何かが違うの」
気まずい。婚約パーティの前日にこんな話など、非常識なのは百も承知だった。しかし今更訂正はできないし、したくない。
「ごめんなさい。あなたは怒って、私のことなんて嫌いになるかもしれない。それは辛いけど、仕方ないわ。あなたを傷つけて裏切ってしまうんだもの。それでもこのまま嘘をつき続けたら、きっともっと傷つけてしまうから……」
「……いいよ」
メディスは遮るように囁いた。ティシラは体を揺らし、息を飲んだ。メディスの顔から表情が消えていた。それがティシラの胸を貫く。
「建前はそのくらいで」
「――え?」
「僕を傷つけるとか、裏切るとか、そんなことは二の次なんだろう?」
「そんな……」
「本心は、真意は他のところにあるんじゃないのか?」
「……メディス?」
ティシラは戸惑った。最初は彼が怒っていると思って胸が痛んだ。しかし、そうではなかった。メディスは未だに無表情でじっと自分を見つめている。
いや、違う。微かに笑っている。そこにはまるで「すべてを知っている」ような威圧感があった。
同時に、不思議な透明感があった。ティシラはその目に引き込まれた。
そして初めて気づく。ティシラは彼のことを、何も知らない。
一体彼は何者なのだ。そして彼は一体何を知っているのだろう。
メディスは出会ってから今までの短い時間、常にティシラをリードしてきた。彼女のことを何でも分かっているかのように、ティシラの心理状態に合わせて丁度いい間や言葉を与えてくれた。だからティシラはメディスに心を許したのだ。一緒にいて楽だった。
だけど、これほど造られたような完璧な人がいるのだろうか。今になってそれに気づく。
ティシラは漏らすように、下から押し上げられるように呟いていた。
「……あなたは、誰?」
メディスはすぐには答えなかった。その沈黙はティシラにのしかかってくる。捕らわれてしまったように動けなかった。ティシラの中に恐れ、疑問、困惑などの感情が入り乱れる。だがそのどれよりも、何よりも「知りたい」という彼への興味が彼女の心を占めていた。
これ以上は待てない。メディスはそんな彼女のすべてを読み取ったかのように、ふっと目を細めた。その動きでティシラは我に返る。
「よかった」メディスは牙を見せて笑った。「僕も君とは結婚できないからね」
4
「僕も本当のことを言うよ」
戸惑うティシラに構わず、メディスは目を閉じた。
「僕の名はメディス──メディテラウス・ウェンドーラ。ヴァンパイアの血を引くライド(輪)の魔法使い……」
言い終わって、メディスは目を開いた。そこには青い光が灯っていた。
ティシラは言葉を失った。彼は間違いなくヴァンパイアだった。なのにその象徴である紅蓮の瞳が、深く揺らぐ青い色に変わってしまっていたのだ。
「ある人に頼まれてあなたを迎えに来たんだ」
ティシラは目を見開いて混乱していた。
「あなたは誰? 何……どういうこと?」
「最もな質問だ。でも今全部を説明してたらパーティが始まってしまう」
「だめよ。ちゃんと説明して。じゃないと人を呼ぶわよ」
「怖がらないで。大丈夫。僕はあなたの味方だから」
ティシラは片足を一歩引きつつ、膨らむメディスへの好奇心を止めることができない。
「あなたの失くした記憶は忘れてはいけないものなんだ。だけど無理に思い出す必要はない。あなたはそれで、そのままでいいんだ。あなたの好きなようにしていればその道に導かれる。僕という存在はあなたが辿る運命の樹の枝の一つに過ぎない。あなたもそれをどこかで感じているはずだ」
「……な、何を言っているの? 分からないわ」
「それもそうだね。じゃあ今から話すことを落ち着いて聞いてくれ」
メディスは警戒するティシラに失くした記憶の話をした。ティシラが人間界で魔法使いになったこと、そこで出会ったマルシオやたくさんの友人のこと。そして、クライセンのことも。
ティシラは眉を寄せて聞き入っていた。メディスは戦争の話も聞かせた。ティシラが修羅界に飛び込み、禁断の魔薬で死に掛けたこともすべてを。
ティシラはあまりに壮絶な話に気が遠くなりそうになった。まだ整理できないまま口を挟む。
「待ってよ。その話が本当だとしたら、どうしてあなたがそこまで知っているの。おかしいじゃない。修羅界に入ったのは私と、そのクライセンって人だけなんでしょ。私は記憶にないし、それともあなたがクライセンなの?」
メディスは頭を横に振った。
「彼は今も修羅界に閉じ込められている。だけど完全に死んだわけじゃない」
「あなたがクライセンに会いに修羅界に行ったとでも言うの?」
「あなたは修羅界に入って出てこられた、現在ではただ一人の魔族だ。だがそれは魔薬の力と、クライセンがかけた魔法に魂を守られたからなんだ。あなたは何も覚えていないけど、以前に彼に守護の魔法をかけられた。それが死にかけたあなたの魂の欠片を現世に留めたんだ。だけどクライセンはただの人間。抜け出す手段もなく闇に捕らわれてしまった。そもそも修羅界に入っても正確には死んでしまうわけじゃないんだよ。でもこの説明をしている時間はさすがにない。そのことはいずれ知ることになる。だから今は勘弁してくれないかな。とにかく、僕はクライセンに頼まれてここに来たってことだけを理解して欲しい」
「わ、分かったわ」それでもティシラは頭を抱える。「修羅界のことはいいわ。つまり、あなたは一体誰なの。そこをはっきりして」
メディスはにこにこ笑っている。まるで人を翻弄して楽しんでいるように見えた。
「僕はリヴィオラを受け継いだ、六代目聖魔法王――ただし、まだずっと、ずっと先のね」
ティシラはもう何から聞いていいのか分からなくなった。黙ってメディスの話を聞くことにする。
「まだ分からない?」
「……全然」
「僕はあなたとクライセンの子供だよ」
ティシラの頭の中が完全に真っ白になった。
「僕は時間を操ることができる特殊な魔法使いなんだ。この時代のあなたを魔界から連れてくるように、未来のクライセンに頼まれたんだ。さっきも言ったけどクライセンは、父はまだ修羅界で肉体を失ってしまい身動きが取れなくなっている。今はまだ意識すらないだろうね。父の魔力が戻って、人の姿を取り戻してそこから出てこれるようになるのはそう容易いことではない。何よりも、あなたを始めとする力と知識のある仲間の助けも不可欠となる。そこまでを繋ぐ道を僕も通らなければいけないことになっているんだ。僕はあなたをここから連れ出すという重要な役目を持っていると、それを父から知らされた。そしてあなたを救うために、未来の彼に力を貸して欲しいと頼まれたんだ」
ティシラはまだ理解できない。まずはメディスの話を信用する方向で考えた。
「……そうだとして、なんでその人は私を?」
「あなたと約束をしたんだ。父はいい加減で時間は守らない人だけど、決して約束は破らない」
「約束?」
「あなたとずっと一緒にいると、傍にいると約束を交わしたんだよ」
そこで、今まで真面目だったメディスが急に肩の力を抜いた。
「まあ、父はその時の流れでつい、不本意だけど仕方ないって言ってたけどね」
「……な、何よそれ」
「それに父があなたを一人の女性として認めるまで、再会してさらに数年かかるらしいんだけど」メディスはあははと笑った。「それまでにも相当揉めて、いろいろ大変だったらしいよ。そこは僕も詳しくは聞いてないけど。教育に悪いらしくってさ。しかもあなたたちの決定的な馴れ初めは、それは酷いものだったんだって。まあ、今の二人を見れば普通じゃないってことは誰でも分かるけどね」
言ってることは曖昧だが、馬鹿にしていることだけは伝わってくる。ティシラは意味も分からないまま不愉快になった。しかしそれを抑えて核心に迫る。
「信じられないわ。あなたの話が本当なら、あなたの行為は大罪のはずよ。過去を変えれば未来にも異常が起こる。そんなことが出来るはずないわ」
「いいや」メディスは不真面目な態度を改める。「未来は変わらないよ。だって、僕とあなたがここで出会わなければ僕は生まれなかった。僕が二人の間に時間を操る力を持って生まれることは決められていたことなんだ。僕がここに来ることは流れる時間の中であって然るべき事柄だった。でもこれはほんのきっかけに過ぎない。これ以上の僕の介入は危険が伴ってしまうからね、ここを出たら僕はいなくなるよ」
「で、でも、あなたが未来から来たなんて、それをどうやって信じろって言うのよ」
「確かに、今は無理だよね。でもそのうち分かるよ。その時間が来れば、僕は違う形であなたと再会するんだから」
「そうなら何であなたは私と会ってすぐにその話をしてくれなかったのよ。まさか私を騙そうとしたの?」
「そういうわけじゃないんだけど」メディスは困ったように肩を竦めた。「依頼主がね、ついでだから派手に引っ掻き回してこいって……本当なら明日のパーティまで引っ張って、ヴィゼルグ中の貴族の前でブランケル様に大恥をかかせてこいとまで言われたんだけど、それはさすがに良心が痛むよ」
「な、なんでそんなことをしなくちゃいけないのよ」
「父とブランケル様は救いようがないほど仲が悪いんだ。僕にとっては祖父に当たるって言うのに、酷いことをさせるんだから」
そう言いながら、ティシラにはメディスが楽しんでいるようにも見える。今までの「優しい彼」でないことは確かだった。頭の整理もできず、彼の変貌振りにさえついていけてないティシラに微笑んで、メディスは彼女の手を引いた。
「さあ、そろそろ行こうか」
「行こうって、どこに?」
「そうだね。あなたは父に会う前に他にもたくさんの人に姿を見せてあげないといけない。しばらくは忙しいよ」
「それって……」
「人間界だよ」
「人間界? そんな遠いところに?」
「遠くないよ」
「でも、私は何も覚えてないのよ」
「大丈夫」
「それにもう何十年も会ってないんでしょ。相手だって私のことなんか忘れているかもしれないじゃない」
「忘れないよ」メディスは素早く答えた。「忘れるものか。あなたに会った人は、あなたのことは絶対に忘れない」
途端、彼の言葉がティシラの胸に重くのしかかった。その重みに反応するように、脈が僅かに早まり出していた。
「みんな、待ってる。あなたのことを。あなたが死んだなんて思いたくなくてずっと長い間、寂しさと戦っているんだ。だけどあなたがここから脱出するには外部からの侵入がなければ無理だ。僕が今していることは奇跡だと、そう思って欲しい」
「奇跡……?」
「起こり得ない現実、だと言えば分かる?」
ティシラはメディスの真剣な眼差しに飲まれる。が、また腕を引かれて慌てて振り払う。
「……急にいなくなったら、パパとママが死ぬほど心配するじゃない」
メディスはため息をつく。
「それも大丈夫。あの二人は、あなたの親なんだよ?」
「ど、どういう意味よ」
ここでまたメディスは白々しい顔をする。
「別に」
ティシラは彼の失礼な態度にむっとする。メディスのペースに巻き込まれていることには気がつかない。
「あなたはいつまでも我儘でいればいいんだよ。そのうち二人は認めてくれるから。だから大丈夫」
「でも、せめて事情を説明しなくちゃ」
「あなたに真実を隠して騙そうとした罰だよ」
「それは私のことを思って……」
「好きでもない男と結婚するのがあなたの幸せ?」
うっと言葉を詰まらせるティシラを見るまでもなく、話を進める。
「よし、決まりだ」
言いながら、メディスは空を仰いで印を結んだ。
何やら呪文を唱える。最初はそよ風だった。周辺がざわりと揺れる。
ティシラは辺りを見回した。風は上下左右から流れ、次第にぶつかり合い、不協和音を起こすように大きくなっていく。彼を中心に竜巻が起こり、あっという間に嵐になる。
ティシラは初めて見る「魔法」に驚きながら、風に振り回される黒髪を押さえた。
そこに、城からブランケルとアリエラが血相を変えて飛び出してきた。すぐにティシラの姿を見つける。
「ティシラ!」
ティシラは慌てて顔を上げる。
「パパ、ママ!」
「ティシラ」ブランケルは眉を顰めた。「これは一体何事だ!」
メディスは振り向き、ブランケルに向けてその青い目を見開いた。
まるで見せ付けるように。さらに、挑発するようにちらりと舌を出す。
5
ブランケルはその姿に怒りや憎しみを灯した。
間違いない。アリエラの言う通りだ。そこに渦巻く魔力と魔法。忌々しい青い両の瞳。その上で揺れる黒髪──その姿はブランケルの最も憎む「あの男」を思い出させないではいられなかった。その横でアリエラが呟いた。
「……クライセン?」
ブランケルは確信し、怒り狂った。
「貴様!」
ブランケルの黒いマントが風に靡く。かと思うとそれは大きな蝙蝠の羽に姿を変える。
アリエラは危険を感じ、ブランケルから離れた。
「殺してやる!」
ブランケルは嵐をものともせずに宙に舞う。牙と爪を尖らせ、メディスに襲い掛かる。真っ赤な口の中には炎が宿っていた。
ぶつかり合ったメディスとブランケルの魔力は閃光を放った。その瞬間、辺りは黒い炎に包まれる。それは風に撒かれて螺旋を空に作った。
メディスは透かさず人差し指を立てて、それで魔法陣を宙に描いた。指先には紫の光が灯り、ペンで描くように不可思議な図形が浮かび上がる。
待たずにブランケルが炎を吹く。メディスはふわりと飛び上がってそれを躱した。代わりに彼の傍にいたティシラが地に伏せた。
「ティシラ!」
ブランケルは一瞬我に返った。その頭上には魔法陣を背負ったメディスが浮いている。
ブランケルは顔を上げるより早く、自分も飛び上がった。そんな彼を押さえつけるかのように空から大きな黒い光の柱が降ってくる。
ブランケルは交差させた腕でそれを受け止め、地面に叩きつけられる寸前に弾き飛ばした。黒い光は散り、ブランケルはその飛沫を浴びながら翼を揺らし、体勢を整える。一度片手を地につき、黒く分厚い翼を周囲に敷き詰める。その翼は飲み込まれるほど大きく、太い骨格や脈打つ血管が浮き出て見えた。
メディスは宙に浮いたまま身を屈め、早く正確に十三の印を結んでいく。ブランケルの怒り狂った顔とは対照的に、メディスは不敵に笑っていた。
メディスは印を結び終えて、力強く体を伸ばして仰け反った。するとその背中に大きな四枚の蝙蝠の羽が、弾けるように飛び出したのだ。その黒いものは空を覆った。
ブランケルは目を疑った。
蝙蝠の羽、鋭く伸びた牙と爪。まさにヴァンパイアの姿そのものではないか。
ただ目の色が青いというだけでブランケルの神経を逆撫でする。
こんなことがあり得るのだろうかという困惑が怒りと入り混じる。メディスは自分が知っている「彼」よりいくらか幼い。雰囲気はどこか似ているが顔立ちも同じではない。
彼は、本当にクライセンなのか、そうだともそうじゃないとも言い難い。
ブランケルが目を奪われている隙に、メディスは風のように飛び交いながらティシラを抱き抱えた。
「貴様! ティシラは渡さんぞ!」
ブランケルは戸惑いながらもメディスに牙を剥いた。再び彼に飛び掛ろうと翼に力を入れる。その背中にアリエラがしがみついてきた。
「……アリエラ!」
「ダメよ」アリエラは腕に力を入れる。「ティシラが選ぶの」
嵐の中、メディスに抱き抱えられたティシラが注目された。
未だに状況についていけないティシラはメディスと両親を交互に見つめた。
一同は短い時間、ティシラの答えを待った。ティシラはメディスの青い瞳に吸い込まれる。
ティシラは迷わず、この青い目の男についていくだろう。彼女がずっと望んでいた未来に向かって。誰もがそう思って疑わなかった。
ブランケルさえも漂う雰囲気に口出しできす、もう彼女を止めることはできないかもしれないと諦めかけていた。
ティシラはメディスに抱えられたまま唖然としていた。
自分が中心になっていることすら自覚できていない。だが、注目されていることだけは分かる。戸惑いながらも考える。まとまらない。頭が痛くなってくる。次第に、なんとなく、腹が立ってきた。
迅速に、我慢が限界に達してくる。
メディスはティシラを抱えた手に力を入れる。しかし翼が羽ばたこうとしたその気配を感じ、急にティシラは暴れ出した。
「いや!」
一同はティシラの意外な行動に目を丸くする。
「冗談じゃないわよ! 顔も知らない人と結婚なんかできるわけないでしょ」
ブランケルとアリエラは面食らう。メディスも慌てて宙で揺れた。
「ちょっと! なんでここで暴れるんだよ」
「何なのよ。皆して勝手なことばっかり。いい加減にして!」
「記憶を失っているとは言え、あなたが命を懸けて愛した人と結ばれるって言っているのに、一体何が気に入らないんだ」
「全部よ! 全部気に入らないわ。意味が全然分からない。あんた頭おかしいんじゃないの。何が未来よ、何が魔法使いよ。そんなの知らない。大体、この私が命を懸けてまで尽くす男なんかこの世にいるわけないじゃない。作り話も大概にしなさいよね。誰がそんなの信じるもんですか。あんたなんかに指図されなくても男なんか山ほどいるのよ。私を誰だと思っているのよ!」
「参ったな」メディスは困りながらもティシラを離さない。「あなたのデタラメぶりは相当だとは聞いていたけど……」
ここまでとは。何も覚えていないとは言え、何とも自分勝手な発言だった。言うのはいい、だが今でなくてもと思う。
とうとう本性を現したティシラは、堰が外れたように言いたい放題捲くし立てて一同を驚かせていた。
「離してよ。気安く触るんじゃないわよ。あんたなんか大っ嫌い!」
「嫌いで結構。僕だってあなたみたいな下品な女は好みじゃない」
「な、なんですって、このクソガキ!」
「どっちが」
そう言い合いながら宙で暴れている二人に呆気を取られてしまっていたブランケルが、はっと我に返る。
「見ろ」ブランケルはアリエラに。「あれはどう見ても喧嘩だぞ」
「……我が娘ながら」アリエラも困っていた。「こうも色気に縁遠いと不安になるわね」
そんな一同をさらにかき乱そうとする嵐は止まらない。
そんな中でメディスはティシラに鋭い目を突きつける。
「この際はっきり言うけど、あなたは死のうが生まれ変わろうが父から、クライセンから離れられない運命なんだ。例えここで僕を拒絶しようと未来は変わらない」
「あんたに何が分かるのよ。偉そうに」
「僕は何でも知っている。この先あなたがどうするのか。天上界、人間界、魔界がこれからどうなっていき、それに関わる偉大な人物のこともそのすべてをね。あなたはそれを自分の目で見てみたくはないか? あなたはそういう人だ。否定できるかい?」
「否定はしないわ。でも、私は……」
「なら」時間を惜しむように、素早く遮って。「あなたは一体どうしたい?」
ティシラはその青い目に貫かれる。しかし彼女も負けずに睨み返す。
二人は短い時間でお互いの魔力をぶつけ合った。その力の差は歴然で、ティシラは及ばないことを知る。だが、それに屈する気は全くなかった。
「私は誰の言いなりにもならない」
ブランケルとアリエラも嵐の中でティシラの本心を待った。
「あんたの言ってることなんか信じられない。でも」ティシラは一度深く目を閉じ、開く。「本当のことを、私は知りたい」
ティシラの言葉の意味をすぐに理解し、メディスは再び笑った。
(……そうだよ。おしとやかでいい子なんてあなたには似合わない……急がなくてもあなたはいずれ、母親にも劣らないほどの美い女になるんだから)
ブランケルが一歩前に出る。嵐がそれ以上近づけさせないかのように激しさを増した。
「パパ、ママ」ティシラは二人を見下ろして。「私は行かなくちゃいけないところがあるの」
「……ティシラ」
「ここじゃないの。私が本当に欲しいものはここにはないみたい。パパとママのことは大好きだけど、それ以外にも欲しいものがあるの。それを探しに行きたい」
「ティシラ!」
「ごめんね。でも私、嘘は嫌いみたい……」
最後まで待たずに、メディスは翼を大きく羽ばたかせ、さらに風を巻き起こした。その中でくるりと旋回する。メディスは再びブランケルに意地悪な笑みを見せた。
「ブランケル様! これはクライセンからの伝言だよ」
ブランケルはその憎き名に反応する。一瞬にして体中を嫌悪感が包んだ。
「悔しかったらいつでもかかってこい、だって!」
ブランケルは血が滲みそうなほど奥歯を噛み締めた。
「……貴様は私の手で、必ず殺してやる!」
メディスは竜巻に乗って空に昇っていく。
「伝えておきます」
嵐の中、メディスの笑い声が響いた。
風の余韻を残してメディスとティシラは姿を消した。
静まり返った空をブランケルとアリエラはしばらく見つめていた。
まるで夢のようだと思った。あまりにも突然で乱暴で、一瞬のような出来事だった。
呆然としながら、どこかで安堵していることは、まだ気がつかない。
見上げる空は遠く、深かった。まだ少し魔力の風が揺れていた。黒い炎で焼けた、朽ちた木々が黙って眠っている。
ブランケルの翼は力なく垂れ下がり、先ほどの迫力はすっかり消えてしまっていた。降りてきた静寂を邪魔するものは何もなかった。
ブランケルとアリエラは暗い空を見つめたまま、自然と体を寄せ合っていた。
二人は口にしなかったが、ティシラが「魔法使いになる」と言って家を飛び出していったときのことを、まるでついこないだのことのように思い出していた。
<了>