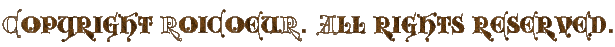第4章 満月




1
三日の日が過ぎた。ウェンドーラの森は満月の光で照らされ、木々や花の間を金の光の粉がふわふわと舞っている。
静かな夜で、すべての命が眠っているようだった。
だが、その静寂を乱す者がいた。それは森に忍び込み、こそこそと庭へ侵入する。そして屋敷の壁にまで走って行くと、ぴたりとそこに張り付く。
影は二つ──ティシラとマルシオだ。
「ティシラ、本当に大丈夫なのか」
「怖いなら帰りなさいよ」
二人は声を潜めている。周りを見回しながらじりじりと窓に近づく。例によって壊された玄関の扉は何もなかったように元に戻っていた。魔法で修繕されたのだろう。
「今度こそ殺されるかもしれないぞ」
「上等よ」ティシラは怯えるマルシオに凄んでみせた。「私は彼の死体を見るまで信じないと言ったでしょ。あんな石コロ、クソ食らえよ」
「でも」マルシオは窓に手をかけて身を乗り出そうとする彼女の腕を掴む。「これ以上ここで探って、何か意味はあるのか」
「あんたまだそんな事言ってるの。あの十日前の手紙、あれの差出人はきっとサンディルだったのよ」
「……だから?」
「サンディルは手紙で来訪を伝え、その一週間後に現れた。ジンはそれを知っていたけど思ったより早かったんだわ。きっと、最初からサンディルが訪れた時に私たちを追い出すつもりだったのよ」
「何のために?」
「おかしな事ばかりじゃない。あの手紙はもともとジンではなく、クライセン様宛だったし、一体サンディルは何の用で来たのか。少なくとも私たちを追い出さなければいけないほどの大事だったのよ」
「だからそれは一体何なんだよ」
「うるさいわね」ティシラはつい声が大きくなる。が、慌てて声を潜める。「分からないから調べるんでしょ」
「結局何も分からないんじゃないか」
「でもジンは私たちをうまく追い払ったと思って安心してるはずよ。ここで何かを行っているかもしれないわ。隙をつける」
「それは言えるかもしれないな」
「二手に分かれましょう」
マルシオは頷くと身を屈めて、庭を通って屋敷の反対側へこそこそと走っていった。
ティシラは再び体を起こして窓の中を覗き見る。人の気配はない。ぺたんと右手をガラスに当てる。するとガラスがたわみ、まるでビニールのように波打ったかと思うと枠だけ残してふっと消えてしまった。
ティシラは素早く中に入ってまた身を屈める。その背後のガラスはもう、既にもとのまま貼られていた。それを確認するようにティシラが振り向くと、そこには吸い込まれるようなまん丸の月が銀の粉を纏い、白い光を大地に注いでいた。
室内は静まり返り、空気が重かった。
そこはほとんど使われる事のない応接室だった。彼女たちは何度か掃除させられたことがある。部屋のあちこちにある、目を持つ形の置物のすべてが自分を見張っているようだった。
だがティシラはそれらをまったく恐れず、廊下へ続く戸を潜る。その部屋を出ても静寂が続いた。その暗い廊下は永遠に続いているようだった。
人の気配はないものの、等間隔に並んでいるロウソクには小さな火が灯っている。これは夕方になると勝手に発火し、朝を迎えると眠るように消えていく。
廊下はただひたすら真っ直ぐに続いており、その途中には窓もない。
ティシラは暗い方へと歩いていく。小さな足音が響き、まるで誰かにつけられているようだ。しばらく歩き続けると廊下の果てについた。
そこには大きく物々しい石の扉が構えている。扉には何やら文字が並んでいる。あまり見慣れない文字だったがティシラは気にもしない。
もちろんそれが、今は使われないランドールの言葉だとも知らないまま。
ここはジンに決して近づくなときつく言われていたところの一つだった。
実はティシラは前に中を覗いた事があった。そこは魔界を思い出させるような冷たく深い空気が漂っていた。中は真っ暗だったが高い天井の先は丸い窓になっていたため、星の光が薄く注ぎ込んでいた。その光の加減で部屋全体が紫の石で囲まれ、少々先の尖った円柱状の形をしているのが分かった。
逆に光の届かない足元には何があるのか、闇に強いティシラでさえ肉眼では確認する事はできなかった。しかし彼女はそれだけでもここが魔術の儀式が行われる所だと悟った。
その時は部屋に顔を突っ込んだ途端にジンに縛り上げられて連れ戻されてしまった。日を改め、再び足を運んで辿り着いた時には、扉には嫌味のような大きな錠がかけられていて、どんなに頑張っても外す事ができなかった。
しかし、今日はその錠がなかった。ティシラは「あたり」だと思った。
そっと扉を押す。鈍く、しかし静かに石の扉が動いた。途中で手を止め、中を覗く。前に見た時より中は明るかった。
それは天井の窓の中央に、見事に満月がぴたりと重なっていたからだ。
そうか、と思う。この部屋は満月の力で眠りを覚ますのだ。
今なら紫のヴェールに包まれたこの室の全部を見る事ができる。石の床には見た事のない複雑な魔法陣が描かれていた。圧巻だった。それは相当な魔法使いでなければ扱えない高等な魔術だった。その魔法陣は見ただけで、何年も何十年もかけて造り続けられたのが伝わってくる。その繊細な線は月の光を浴びてきらきらと細く輝いていた。
ティシラはその不可思議で奇妙な光景よりも、中央にあるものに目を奪われた。
黒い塊がある。それは光の柱の下で銀色の粉を纏っていた。粉はふわふわと浮いている。「それ」が静かに息をしているのだ。
ティシラの心臓がぎゅっと痛んだ。すると「それ」はピクリと動いた。
人間だった。禍々しい黒いマントで包まれ、まるで石のように身を縮め「眠って」いたのだ。だがこの完璧に整えられていたはずの魔力の空間に「何か」が侵入したのを体で感じ、目を覚まし、振り向いた。
しなやかな黒い頭髪が銀の粉を振り払う。異物であるティシラを青い光が貫いた。一瞬、リヴィオラかと見紛うそれは、魔力を秘めた「それ」の瞳だったのだ。
ティシラは吸い込まれるように「それ」に近づこうとした。が、その瞬間、凄まじい竜巻が空間を薙ぎ払い、ティシラは視界を遮られる。
頭上高くのガラスの割れる音で彼女は慌てて顔を上げた。満月を縁取る天窓からガラスの破片が降ってくる。風の余韻を残し「それ」は姿を消していた。窓を破って逃げ去っていたのだ。
ティシラは言葉を失い、慌てて部屋を後にした。
長い廊下を全速力で駆け抜ける。いくつかの扉を乱暴に開け放ちながら、もう周りの様子など気に留めもせずにバタバタと屋敷の外へ飛び出す。
そこで駆けつけたマルシオと鉢合わせる。
「ティシラ、何だ、今の音は! 逃げよう、もう見つかったかもしれない」
「それ所じゃないのよ!」
ティシラは息を切らして、絞り出すように大声を出した。
「……クライセン様よ!」
マルシオは息を飲む。
「彼がいたのよ」ティシラの目が潤んでいた。「やっぱり、死んでなんかなかった!」
2
ティオ・メイの砦の中では密かに会議が開かれていた。王室から少し離れたところにある会議室は、三十席ほどの椅子が縦長いテーブルの横に並べられているが、今は僅か三人の男だけが物静かに端の方に座っている。
警備は扉の向こうに鎧を纏った兵士が二人だけだった。もともと城の造りは複雑になっており、節々に警備兵が設置されていたため、王室とこの会議室には許された者しか辿り着けないような仕組みになっている。
三人の内、一人はティオ・メイの、実質パライアスを統治していると言っても過言ではない国王グレンデル。
その右に座るのが、魔法機関や魔法兵を取り仕切る魔道総監オーリス。
その向かい、王の左手にいるのが国の護衛全般を任せられ、その優秀な兵士の指揮を取る、総軍長ダラフィン。
そこにティオ・メイの三大頭と呼ばれる者が顔を揃えていた。しかし、その雰囲気は明るくはなかった。
「これは」グレンデルは思い悩んでいる。「ノートンディルの、いや、ザインの呪いかな」
「陛下」オーリスが宥めるように。「そのような事、決して人前では発言なさりませぬよう……」
「呪いでもなんでも」ダラフィンが力強く。「ティオ・メイは何者にも屈してはなりません」
三人は皆髭を生やしていた。恰幅のいいグレンデルとダラフィンとは対称的に、オーリスはひょろりとやせ細っている。グレンデルはその頭に国王の印である冠を被り、銀の刺繍の入った青いローブを身に纏っていた。
現在のこの大国パライアスに君臨し、ティオ・メイの名のもとに絶対的な力を誇り、その象徴として相応しい威厳と風格を持っていた。
だが今は、信頼のおける二人の部下の前でその顔を暗く陰らせていた。
オーリスは白髪の混じった、まだらな灰色の長い髪を一つに纏めている。
緑のマントには年季が入っており、それよりも少し淡い色の翡翠の数珠を首にかけていた。灰色の衣服にその緑が映えている。彼はアカデミー出身だったが、まだラムウェンドが幼く、今の職には就いていない頃の卒業者だった。
三人の面子の中では最年長者であり、その確固たる人格は誰もが認めるもので国王の補佐役としていつも傍に仕えていた。
ダラフィンは中でも特に体が大きかった。その巨体に兵士の象徴である青銅の鎧を装着している。
兜は外していたが剣は常に腰に据えられている。厳格で屈強な彼は剣を体の一部のように扱い、剣術、武術にずば抜けて長けていた。
だが決して魔力を蔑ろにしているわけではなかった。その力が剣や盾より効果的な使い方が在ることも、それを武器に宿せば強化される事も知っていた。
ただ、基本的には猪突猛進型であり、魔法のように頭を使い時間のかかるものを面倒くさい、自分には向いていないと自ら利用しようと言う気にはなれないのだった。
その三つの点を線で結べばきれいな三角形なり、国はいいバランスで保たれていた。人々の目には完璧に映り、弱点などないと思われていた。確かにそれは間違いではなかった──ただし、今までは。
「ノーラが蘇った」
グレンデルがとうとうそれを口に出す。ダラフィンが太い眉を寄せた。
「百年も前に死んだはずです」
「そう、百年前に奴はこの世から姿を消したはずだった。だが完全に死んだわけではなかったのだ」グレンデルは語りだした。「ノーラは致命傷を負い、いったんある場所へ身を潜めただけだった。そして百年もの間、奴は傷と力の回復と……新たなる脅威を作り上げていたのだ。それは魔法も剣も刃向かえぬ、パライアスの大地を砕くほどのものかもしれない。いや、天界、魔界をも巻き込みその秩序を脅かす可能性さえ秘めている」
「ならばなぜ」ダラフィンが拳を握る。「復活を待たずに討たれなかったのですか。そこまで知っておきながら、陛下は……」
オーリスが目でダラフィンを宥める。ダラフィンは口を噤んだ。そしてグレンデルの代わりにオーリスが話し出した。
「百年前とは、いくつかの不思議な出来事が重なった時期だ。ダラフィン殿も知っているだろう。まずは魔薬王の死。そして、パラ・オールの第二の地震」
「パラ・オール」ダラフィンが忘れかけていたその名を思い出す。「ノートンディルの遺跡か」
そして「まさか」と呟く。オーリスがゆっくり頷いた。
「そう。パラ・オールを震源とした二度目の大地震は、ノーラがそこに逃げ込んで起こったものだ」
「だが、あそこは毒ガスが充満していて誰も近づけないのでは」
「ノーラは魔薬王だ。すべての毒に精通する者。彼ならそこで息づいても不思議ではない」
「……確かなのか」
「あの地に赴ける者は他にいない。ただの推測ではあるが、ほぼ間違いないだろう。私はあの日起きた地震に何か不吉なものを感じ、魔を追う目で見たのだ。パラ・オールに一つの生命が感じられた」
「元を辿れば」ダラフィンが複雑な顔をする。「パラ・オールの毒が魔薬王を生んだと言える。それをきっかけに国の薬や医学が発達し、我々が喜んでいるうちに……ノーラも同じくして力をつけていたと言うのか」
「ノーラがパラ・オールの毒を盾にしては我々は太刀打ちできないのだ」
「しかし、食い止める方法はまったくなかったのか。あなた方はそれを知りながら、ただ黙ってノーラが蘇るのを、滅亡の予兆を傍観していたのですか」
ダラフィンは強い口調で二人を責める。グレンデルは黙って目を伏せている。
「ダラフィン殿」オーリスは動じずに。「まだ続きがあります」
ダラフィンは自分を落ち着かせて体の力を抜く。正直、苛立っていた。今すぐ国の全軍を率いてもノーラの討伐に向かいたかった。そんなことをしても無駄なのは分かっている。きっとノーラに剣を向ける所どころか、遺跡に近づいただけで軍は全滅するだろう。何もできない。だからこの二人は今までダラフィンには打ち明けなかったのだ。ダラフィンは最強だったはずのティオ・メイの力を無効化させる魔薬王を心から疎んじた。
「……お聞かせください」
オーリスはダラフィンが大人しく話を聞いてくれると確認し、続けた。
「その百年前、もう一つ不可解な事があったのをご存知か」
「……なんのことでしょう」
「なぜ、ノーラは負傷しパラ・オーラへ逃げこまなければいけなかったのか……」
遠まわしに語るオーリスの言葉に、ダラフィンは思ったより早く反応した。
「……クライセンか。魔法王、クライセンの失踪」
「そう、彼だよ。クライセンが異種の力と戦ったのだよ」
「クライセンは魔法王と言えど、あくまで人間の魔法使いだしかないはず。魔法で対抗できるなら、オーリス殿、あなたの力も有効なのでは?」
「彼はただの魔法使いではないよ。彼に会った事はなかったかね?」
「ありません。基準が違います。彼が消えたのは百年も前の事。私はその頃、まだ子供でした」
「そうでしたな」
「それに四代目クライセンは幻だと言われています。国に貢献しないのなら興味を持ちえません」
「興味など持たなくてよいのです。あなたは先ほど私たちに何もしなかったと言いましたが、できた事があったとすれば、現在も進行して彼の消息を追っている事です」
「まだ状況が読めないのですが……クライセンとは何者です。なぜノーラと戦ったのですか。戦って彼はどこへ行ったのです。そして彼は今から何をしようとしているのでしょう」
そこで、黙していたグレンデルが口を開いた。
「その答えは私たちにも分からないのだ」
「分からない?」ダラフィンは眉を顰める。「仮にも国がリヴィオラを与え、世界一を認めた者でしょう。そのような大事を陛下に説明もなく……そもそも彼が味方なのか敵なのかさえ、私には検討がつきません」
「ダラフィン殿の言う通りだ」
一国の王がこのような曖昧な答え。ダラフィンの苛立ちがまた募った。
「なぜ彼を自由にさせているのです。すべてを説明してもらう必要があるはずです。民を守るべき国家が、何も存ぜぬでは許されるはずがない」
「落ち着きたまえ」
ダラフィンはとうとう席を立った。
「クライセンを捕らえます」
オーリスも立ち上がり、ダラフィンに向かう。
「彼に剣は通じませぬぞ」
「そうだとしても、万全を尽くすまで」
「生きているかどうかも分からないのだ」
「ならば墓を暴き、魂に問いましょう」
ダラフィンはグレンデルに一礼して、素早く室を出て行く。追おうとするオーリスをグレンデルが止める。
「好きにさせろ」
「軍が動けば、民が恐れます」
「このままではいずれ恐怖は訪れる。私もクライセンと話がしたいのだ。オーリス殿も探索を続けてくれ」
「……御意に」
何も解決しないまま会議は終了した。オーリスも室を出て行った後、グレンデルはしばらく一人で思案していた。
3
それから数日後。
ティシラとマルシオはウェンドーラの森を出て、クルマリムとは反対の西方に向かい、ミングの山麓あるアムジーと言う小さな村を訪れていた。
しかし二人を歓迎してくれる村人は一人もいなかった。誰もいなかったのだ。すべての村人が苦しみながら息絶えていた。
あの後、二人は散々屋敷の周辺を走り回ったのだが、結局黒尽くめの男を捜し出すことができなかった。
仕方なくその場は諦めて、しばらくクルマリムの街で過ごしていた。
何かクライセンに関わる情報が得られないかと考えたのだ。お目当てのそれはなかったが、あるニュースが飛び込んできた。それは二人にとっても衝撃的で、パライアスの民のすべてを不安に陥れるものだった。
それがアムジー村の謎の大量死だった。
アムジー村は、クルマリムから馬で移動して五日ほどかかる場所にあった。ミングと言う横長の山の麓にある小さな村だが、農業が盛んで、剣や魔法などにはまったく無縁のごく平凡で平和な村だった。
その話を聞いて胸騒ぎがしたティシラとマルシオは魔法を使って高速で移動し、一日もかけずに村に着いていた。そのニュースと共にティオ・メイから「危険なので決して村には近づかないように」と厳しい注意があったのだが、二人はまったく気に留めなかった。
二人が急いだ理由は、村にメイの兵が到着してしまうと立ち入り禁止になってしまうだろうから、それより先に着く必要があったのだ。
その事件を調べたい理由は、特になかった。これ以上クライセンに関する有力な情報が得られずにイライラしていた二人は、とにかく事件が起きたらまめに足を運ぼうと思ったのだ。
ティシラとマルシオは言葉を失っていた。村の建物には一切破損はなかったのだが、道や庭、家の中にいるすべての人々が恐ろしい形相で死んでいたのだ。
子供も老人も、家畜も何一つ呼吸をしていない。花や木も萎れている。二人は注意深く村の中をゆっくり歩いた。
「これは……」ティシラが顔を顰めて。「毒だわ」
マルシオも微かに漂う嫌な匂いを感じていた。
「ああ。空気より重い、気体の毒ガスだな」
「私たちもあまり長くはいられないわ」
「そうだな。それに」マルシオは馬の蹄の音に気がつく。「ティオ・メイの衛兵がご到着だ」
村の向こうの平原を数十名の兵が馬に跨り、土煙を上げて走ってくるのが見えた。急いで二人は近くの建物に隠れ、そこから様子を伺った。
兵は村に近づくと少し歩を緩めたが、そのまま直進してくる。すると急に先頭にいた馬が嘶き出した。そして乗り手を振り落とし、狂ったように暴れだす。兵の進行は乱れ、悲鳴や叫び声が呻きに変わっていく。前方にいた数名の兵とその馬がばたばたと倒れた。後方にいた他の兵たちは慌てて後退する。
「止まれ! 引け! 村から離れろ!」
その声と共に、残った兵士たちは再びそこから離れて行った。
ティシラとマルシオはその一連を青ざめながら見ていた。おそらく倒れた兵士と馬は、死んでいる。一同が遠ざかったのを確認して、二人は急いで逆の山麓の方へ走っていった。
ミングの山道に差し掛かった所まで行くともう毒はなかった。二人は深呼吸をする。魔族や魔法使いだから毒が利かないわけではなかったが、普通の人間よりは抵抗力があり、アムジーの毒は時間が経って薄くなっていたため、二人は難を逃れていた。
しかしかなりの猛毒だったのは確かだった。あれ以上長くいたら二人も倒れていたかもしれない。今のたった数分でも急激に息苦しくなっていたのだから。
「マルシオ」呼吸を整えながらティシラは声をかける。「あんた、大丈夫なの」
マルシオは心配してくれる彼女から、なぜか目を逸らす。
「あ、ああ……お前こそ」
「私は魔界で育ったからあのくらいならなんとか平気だけど、あんたは……」
マルシオはぎくりと肩を揺らす。
「さぞかし綺麗な水と空気で育てられたお坊ちゃんなんでしょ? 行った事はないから、知らないけど」
マルシオは振り向いてティシラを凝視する。異常に驚いている彼にティシラは首を傾げる。
「な、何よ……」
「ティシラ、お前……」銀の目が見開かれていた。「まさか、知っているのか」
「な、何を?」
「俺の出生……」
ティシラはきょとんとしている。そしてやっとマルシオの質問の意味を理解した。
「隠してたの?」
「どうして知っているんだ」
「……見れば分かる」
マルシオはがっくりと肩を落とした。隠していたつもりだったのに、と拍子抜けしたのだ。
「ジンにも同じ事を言われたよ」
「私とジン以外は誰も知らないの?」
「ラムウェンド先生には話してある」
「何で隠すの? やましいわけじゃあるまいし」
「やましくはないけど、ただでは済まないだろ。それに俺は、親や同胞の反対を蹴って家出同然で出てきたんだ。本当の事を公表するわけにはいかないよ」
「ふうん」その会話はあっさりと終わらされた。「まあ、あんたの素性なんてどうでもいいんだけどね」
そう言ってティシラは緩やかな山道を眺めた。
マルシオは、人が真剣に気にしているのに、こうも無関心だと逆に腹が立ってくる。しかしここで食いつかれても面倒だとも思った。クライセンの事以外に興味を持たない彼女だからこそ、こうして付き合っていられるのかもしれない。そう思うことにした。
「さて、どうするか」
「……そうだな」
マルシオも気持ちを切り替える。しかしこれでティシラには今までより気を許せるようになった。彼女にもう秘密を持つ必要が無くなったからだ。もっとも、最初から隠す必要もなかったかと思うとなんだか切なく感じる。いやしかし、とマルシオはもう考えないことにした。そして再び村の方角に目を向けて。
「あれ、どう思う?」
「質の悪い猛毒。あれは魔薬よ」
「ああ。だがなんでアムジー村が襲われたんだ?」
「それに、誰が?」
「さあ……」
二人はしばらく沈黙した。考えても無駄だという事に、すぐ気がつく。
「あの様子だと、メイの兵がすぐ動くわね」
「魔薬は専門外だ」
「国の最高機関にお任せしましょう」
答えが出たところで、二人は結局なにしにきたのか分からなくなった。仕方ないのでまたクルマリムに戻るしかないのかと思うとうんざりする。すると、マルシオが何かに気づいた。
「ティシラ、何か臭わないか?」
「え? どこから?」
「微かだが……山の方から村と同じ魔薬の匂いがする」
普通の人間には分からないほどの微かな匂いだった。マルシオは山道を奥へ進んだ。ティシラも後ろから「本当だ」と言いながらついてくる。
そのまま僅かな匂いをもとに坂道を登っていると、山の中はどんどん険しくなり、歩きにくくなる。マルシオが「こっちだ」と急に道を逸れ、草むらの中に入っていく。ティシラも後に続いた。
「何で山の中から魔薬の匂いがするのかしら」
「出所が分かるかもしれないな」
「分かった所でどうするの」
「さあ。でもせっかく来たんだから調べてみてもいいじゃないか」
「暇人みたいな事言わないでよ。他にやる事があるでしょ」
「どうせ暇じゃないか。何ならお前、一人で帰っていいぞ」
「それは……嫌」
今のところ、確かに行く当てはなかった。ティシラはつまらなそうに背の高い草を掻き分けながらマルシオの後についていく。匂いが強くなってくる。魔薬というより、薬草の匂いに近づいているようだ。しばらく進んでいると、マルシオがふと足を止めた。
「どうしたの」
「見ろ」
マルシオが指したところに岩の塊が見えた。岩には苔や草花が生えていて、もうずっと前からそこにあるのが読めるほど根付いていた。その岩は人工的に積み上げられていたらしく、歪んだ丸い縁を描いている。その中は草木で覆われているが、確かに空洞になっているのが見える。
「洞窟だ」
「この匂いはあの中から?」
「そうみたいだ。行ってみよう」
マルシオはティシラの意見も聞かずに勝手に進んでいく。
「ちょっと!」
「魔力も感じる」無視して。「絶対何かあるぞ」
ティシラは文句を言う気がなくなった。かなり嫌な顔をしてついていく。二人は躊躇わずに中に入った。草木が覆っているのは入り口付近だけだった。奥に進むほど暗く冷たく、陰気な空気が漂っている。
決して楽しい気分にはなれなかった。足場も悪い。天井も低く、出張った石にたまに頭を擦る。
ティシラはこういう居心地の悪い環境には慣れてはいたが、男の無意味な好奇心に付き合うのがバカバカしくなってきた。
「もう、やっぱり嫌」ティシラはイラつきを隠さずに。「あんた一人で行ってきなさい。何かあったら呼んで。入り口で待っててあげるから」
ティシラはそういい終わらない内に、くるりと振り返った。
「分かったよ」
マルシオは全く気遣う様子もなく、振り向きもしないでポケットからビー玉くらいの小さな水晶を取り出す。それを掌に乗せ、何やら呪文を唱えた。すると水晶はふうっと光を灯した。大きさは小振りだが光は遠くまで広がり、しっかりと周辺を照らしだす。それを掲げながら辺りを見回していると、外に戻ったと思っていたティシラがまだ後ろを向いたままそこに立っていた。
「なんだよ、まだいたのか」
返事がない。
「?」
マルシオはティシラの正面に回る。水晶の光で彼女の顔を照らすと、青ざめて目を見開いている様子が伺えた。
「ど、どうしたんだよ」
ただ事でないのだけは分かる。ティシラは震えながら視線の先を指差した。
「……なんで」泣きそうな声で。「来た道がないのよ」
「……は?」
マルシオは慌ててティシラの指す、今来たばかりの道に水晶を向けた。
しかし、その先は壁になっていた。マルシオも動転して水晶を落とす。岩の壁に走り寄って手を当てる。今塞がれた感じでもなく、最初から行き止まりだったような状態だった。
叩いてみるが、何か細工されているわけでもないのが分かる。マルシオはしばらく壁を見つめ、ゆっくりと振り向く。その顔はティシラと同じく、蒼白していた。
「どうやら……」足元に転がった水晶が二人の顔を下から照らしている。「とんでもない洞窟に迷い込んだらしい」
ティシラは体中の力が抜け、ぺたんと座り込んだ。
4
アカデミーは現在休暇中で、生徒たちの大半が家に帰っていた。何人かは寮で過ごす者もいる。
ラムウェンドはアカデミーの外れにある自宅で、古い友と取り留めのない会話を楽しんでいた。
そこにはゆっくりとした空間があった。たまに流れる間も特に気にならない。魔法使いらしい珍しいものなどは見当たらないその部屋には、心地のいい太陽の光が差し込んでいる。
室内のあちこちにはいろんなデザインの椅子がバランスよく置かれている。そのうちの一つの大きめのチェアにはサンディルが深く腰掛けていた。
「そうですか」ラムウェンドは嬉しそうに笑う。「ティシラとマルシオに会いましたか」
「儂はもっとゆっくり話してみたかったんじゃが」サンディルも和んでいる。「あの根性悪の猫めが追い出してしまいおった」
ラムウェンドはサンディルの前にある小さなテーブルにお茶を運んでくる。そしてその向かいの、別の形をしたチェアに腰掛ける。大きな窓の外には木々が茂っている。
二人の間に数秒、沈黙があった。サンディルは木々の間を飛び交う小鳥たちを掛け替えのないもののように見つめた。
「ラムウェンドよ。儂の犯した罪はどれほどのものであろう」
すっと神妙になるサンディルに、ラムウェンドのその柔らかな表情は変わらない。
「それは誰にも分かりませんよ。かの王たちが成した事も私たちにとっては罪ではなかった。今こうして友と一緒に語らいながらお茶を飲める。何を恨みますか?」
「儂のせいでこの平和な時間が壊れてしまうのかもしれない……未来永劫に」
「進化とお考えください。あなたは分かっておられるはずです。ただ、それがご自身の身から出たものだから……辛くて仕方ないのでしょうね」
「許されない罪はない、か」
「私がまだ幼い頃、あなたが何度も言い聞かせてくださった言葉です」
「先祖の裏切りが許せない、自分はその業を背負って生まれた罪人なのだと、そなたはアカデミーを受け継ぐことを散々拒絶しておったな」
「あなたには心から感謝しています。そしてご子息、クライセン殿にも。私のような未熟者に偉大なる魔法王継承の場に立ち合わせてくださったのですから。イラバロスのあの安らかな顔……今でも思い出すと涙が出そうです。ただ……クライセン殿にはそれ以上の辛い思いをさせてしまいました。彼は表情ひとつ変えなかった。だから私が変わりにすべてを受け入れようと思ったのです。彼の代わりになどなれないし、その重荷を軽くしてあげられる力もありません。だけどせめて私は彼を裏切らない、何があっても味方でいようと心に誓っています」
「しかしあいつはそういうのを嫌がる。そんなことを言うからクライセンはあんたに会いたがらんのじゃよ」
「そうですね。でも、本心ですから」
昔を思い出して、サンディルはふっと微笑んだ。そして出されたお茶を口元に運ぶ。
その時、思いも寄らず室内にノックの音が響いた。二人はふっと目を合わせ、ラムウェンドは立ち上がってその意外な来客を出迎えた。
「これはこれは」ラムウェンドは大きな声を出す。「ようこそおいでくださいました」
迎え入れられたのはオーリスだった。サンディルも驚いている。
「メイの仙人殿」ラムウェンドは彼を招き入れながら。「今日はなんといい日でしょう。なかなか会いにくい方が二人も訪れられるとは」
「なんと」オーリスはサンディルを見て目を見開く。「賢者様。あなたに会えるなんて。全くの予想外でした。しかし丁度よかった」
「儂も」サンディルは微笑んでいた。「そなたの事は予想外じゃったよ」
ラムウェンドはいそいそと違うチェアを運んで来て、すぐにもう一杯のお茶を用意する。三人は意外な顔合わせに心から喜んでいた。オーリスは置かれたチェアにそっと座る。
「話したい事が山ほどありますな。だが……」オーリスの顔から笑みが消えた。「お二方のせっかくの休日を邪魔するのは心苦しいのだが、私には昔話をしている時間はないのです」
サンディルとラムウェンドは黙っている。オーリスがここに来た目的は悟っていた。
「今は……いや、もしかすると二度とその時間は訪れぬのかもしれない。お二方もご存知であろう。先日アムジーの村が一夜にして全滅しました。私たちティオ・メイは何もできなかった」
オーリスは気遣う事も出来ずに話し出す。ラムウェンドはオーリスの前にそっとお茶を出しながら、静かに腰を下ろした。
「パライアス最強の、完璧とまで言われた我々の力が全く及ばなかった。これはただの前兆。未知なる脅威がパライアスを侵食し始めた。王は……ザインの呪いとまでおっしゃった」
「ザインは恨んでなどいませんよ」ラムウェンドは落ち着いている。「彼は自分の死や敗北を悔やんでなどいません。彼は偉大なる男でした」
「分かっている……恐ろしいのだ」
そしてとうとう、片手で顔を覆ってその言葉を口にする。グレンデルには見せられない姿だった。彼の暗い顔とは裏腹に、窓の外はのどかだった。鳥の囀りが皮肉にさえ感じる。
「お気をしっかりお持ちください」ラムウェンドが優しい口調で。「あなたがしっかりしなければ、誰が国王の心を支えるのですか」
「分かっている」
オーリスは繰り返した。
「そなたの惜しむ時間とは」サンディルが口を開く。「儂らに泣き言を言うためのものではなかろう?」
オーリスはその言葉を受け止めた。辛い、が、それを振り払う。
「その通りです……あなた方に助言を頂きたいのだ。もっともサンディル殿、あなたがここにいるとは思いも寄りませんでしたが、これはいい兆候ではないでしょうか」
「そうか」
「分かっておいでのはずだ。あなたはいつも私の思うところにはいらっしゃらない。時間があればここを出た後にあなたを探そうと思っていたのです。その手間が省けた事は、私にとってとても有難い事なのです」
「で、このただの年寄りに何の用かな」
「ただの年寄りとは……私はこの世界であなた以上の年長者に会った事はない。そしてあなたほど物を見、知っておられる方もだ。それだけに価値がある。なのにその存在は猫のように気まぐれで、手を借りるには非常に難を被る……ご子息もその性格を受け継いでおられるのかな」
サンディルはすぐには答えず、参ったように笑みを浮かべた。ラムウェンドもオーリスの気持ちはよく分かると、言葉にはせずに深く頷いた。
「クライセン殿を探しているのだ」オーリスは本題に入った。「居所を教えてください」
オーリスの口調は厳しかった。だがサンディルは首を傾げる。
「さあ、儂も会いたいのじゃが……」
オーリスはサンディルの反応を予測していたかのように早口になった。
「国の、世界の一大事なのですよ。今はどんな言い訳も通用しませぬ」
「知らぬものは知らぬのだ。儂ももう百年は会ってない」
「なぜあなた方は我々に非協力的なのですか。あなたたちに恐怖はないのですか」
ラムウェンドが堪らず、声を大きくする。
「オーリス殿、落ち着いてください。サンディル様もお辛いのです。クライセン殿は彼のたった一人のご子息です。クライセン殿は百年前に死んだとまで言われています。その消息も不明のままです。なぜ父親の彼が心配せずにいられましょう。もちろん、国の大事もご存知です。ご子息がそれに関わっている事も。オーリス殿ほどの人格者がなぜそんな不安と寂しい思いを抱えるご老体を責め立てるのでしょうか。私には武器や魔薬などより、あなたの乱心の方がよっぽど恐ろしく思います」
オーリスは震えを抑えた。ラムウェンドの言葉が身に染み渡り、黙って自分を責めていた。
「言ったであろう」サンディルは動じずに。「儂はただの老人じゃと」
「……許してください。私は何もできないことが辛いのです」
「それぞれが役目を持って生きておる。そなたの成すべきことはここで文句を垂れて弱音を吐くことではない。時間が惜しいと思うなら早く王の元へ戻りなさい。それがそなたの役目であろう」
オーリスは嵐に打たれ、耐え忍んでいる細い柳のように踏みとどまっていた。もし彼が愚かな者だったなら、ここで心は折れ、逃げ出していただろう。しかし、そうではなかった。
「……そうだ」オーリスは絞り出すように呟き、立ち上がる「今はここに私の必要とするものはないようですね」
そして「失礼した」と一言残し、二人に背を向ける。ラムウェンドはその背中に優しく声をかける。
「私は力ある限り、このアカデミーを守ります。どうかあなたも全力をお尽くしください」
オーリスは振り向かずに軽く頭を下げた。室内には彼の重い足取りの音が響く。不安で一杯だった。
ラムウェンドはこのまま彼を帰していいものか少し悩んだ。だがここには自分を凌ぐ大賢者がいる。出しゃばるよりもサンディルに任せた方が賢明だと判断し、動かなかった。
サンディルもじっとしている。このまま見送ってしまうのか、と思った時、ふっと口を開いた。
「奴は──」その顔は無表情だったが、目に意地悪な笑みがあった。「難攻不落のメイの砦を持ってしても、その手には負えんぞ」
オーリスがぴたりと足を止める。
「運命が導けば出会えるかもしれんが……あれと関われば無傷では済まんじゃろう。噛み付かれるなとは言わん。問題は、噛み付かれ方じゃ」
サンディルは抜けぬけと言ってのけた。ラムウェンドが困ったようにため息をつく。
オーリスはしばらく固まっていたかと思うと、ゆっくりと肩越しにサンディルに顔を向けた。
「……あなたは年を経る毎に性格が悪くなりますな」オーリスも微笑んでいた。「あなたのご子息だ。一筋縄ではいきますまい」
オーリスはサンディルの意味深な挑発で闘志を蘇らせていた。
遠まわしで意地の悪い、励ましと希望の言葉だと受け取った。意味は自分なりに解釈する。
サンディルとの付き合いも短くはない。もう慣れた、とはとても言えないが、彼の言葉はいつもこうして休ませる事をさせない。
すっと姿勢を正し再び扉へ、王の元へ歩みを進めた。サンディルとラムウェンドはそんな彼の背中を見て、安心したように黙って見送った。