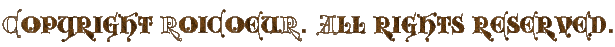第5章 儀式





1
今、ティシラとマルシオは世界で何が起こっているのか知る術を持たなかった。
無理もない。強力な魔術で、侵入した者を確実に迷わす洞窟に閉じ込められていたのだから。
「マルシオ、あんたもう絶対に許さない!」
ティシラがヒステリックにマルシオを殴りつけている。
「いい加減にしてよね! あの猫の虐めには巻き込むは、どうしようもない洞窟に連れ込むは、間抜けも大概にしなさいよ!」
マルシオは頭を抱えて、必死でティシラの暴行から逃げ回っていた。
「勝手についてきたのはお前だろ! 俺は帰っていいって言ったじゃないか」
「あんたとこんな穴蔵で心中するくらいなら一人で死んだ方がよっぽどマシよ。今ここで殺してやる!」
「落ち着けよ。死ぬと決まったわけじゃないだろ」
「クズでも魔法使いなら分かるでしょ。この空気、匂い、気配! 単純な目眩ましなんかじゃない。この空間から絶対に出られないようになっているのよ」
「そ、それは分かるけど……とにかく無駄な体力を浪費するな。できる限りで脱出の方法を探るんだ」
「無駄なのはありもしない出口を探す体力よ。私に殺されたくなかったら今すぐここから出してよ。今すぐクライセン様を連れてきなさいよ」
「入り口があるんだから出口もあるって」
今はクライセンの事は何の関係もないだろうと思いつつ、とにかくマルシオは彼女の理不尽な要求から逃れるために洞窟を走り回った。
どうせ迷うのだから今更道を慎重に選ぶ必要もないだろうと、複雑に入り組んだ穴道を右に左に曲がり、必要があれば横穴にも潜りこむ。
奥に行けば行くほど中は薄明るくなっていき、もう水晶の明かりは必要なくなっていた。
周りはくすんだ白い岩に囲まれており、その成分に光る粉が混じっているらしく辺りを薄く照らし出していた。地面は硬い土で覆われていたが、あちこちに雑草が生えている。その様子で土の中に水分が含まれていると考えられた。
簡単に餓死する事はないだろうが、ここで一生を過ごすくらいなら死んだ方がマシだろうと思う。
問題は精神状態だ。
ティシラが異常に怒っているのは彼女が我儘だからとか短気だからとか、それだけではなかった。彼女は敏感に感じ取っていたのだ。この空間が太刀打ちできないほど邪悪で強力な魔力に覆われている事を。
その正体はまったく、想像もできなかったが。
急に視界が開けた。狭い道を抜けたそこは大きな空洞になっていた。
光の粉を含む岩の壁がお互いを反射し、まるでライトが点いているように白く仄めいていた。
天井はずっと高いところにある。足元は人一人が通れる道を残して沈没したようにぽっかり穴があいていた。その穴の上にはまるで、巨大な蜘蛛の巣が蓋をしているかのように細い道が貼り廻っている。継ぎ目は見当たらない。
人工的に造られたものでないとしても、これが自然に出来たものなら異常だとしか思えなかった。どんな環境がどれだけの時間を経ればこんなものが出来ると言うのだろう。
穴の中には光がなく、暗くて底が見えない。だがそこに何かが息づいているのが感じられる。襲ってはこないが、きっと恐ろしいものだろう。
マルシオが足を止めると、後ろから追いかけてきたティシラが背中にぶつかる。
「何よ、急に……」
ティシラも一瞬で怒りを忘れて、その光景に目を奪われた。天井を仰いだ後、網の目のような地面の隙間から穴の底を探すが、彼女の目にも捉える事はできなかった。
2
マルシオが警戒しながら穴の上まで進んでみる。
その足場は岩でできていた。その下の奥底に潜む何かが発するものによって、時間をかけて成分を溶かされて不揃いな穴を開けられたのだろう。
乗っても落ちない。見た目よりしっかりしている。この強度なら数人が乗って走ってもビクともしないだろう。いや、敢えて壊そうとしても簡単には壊れないかもしれない。
その岩も普通ではなかった。マルシオは、もしかしたら誰かが自然の力を使って造り出したものではないのかと考えた。
つまり、魔法に限りなく近い現象だった。だが少し違和感がある。誰が何のためにこんなものを造ったのか、想像がつかない。善でも悪でもない、異様な狂気を感じて寒気が走った。
マルシオはこれ以上考えない事にした。今は目の前のものを知る必要がある。複雑に編みこまれたような細い道の上を進み、体を屈めて穴の中を覗いた。暗くて視界が悪いが、何かが見えた。
「マルシオ」ティシラはさっきまでの怒りをコロッと忘れ。「何か見える?」
「底に植物が生えている。いろんな種類が混合しているみたいだ」
「どんな?」
「分からない。見たことないものばかりだ」
ティシラも隣に屈んで中を覗いた。
「本当だ。それに……なんだか荒れてるみたい」
ティシラは人間には感じられない自然の感情を読み取っていた。
「荒れてる?」
「理由はわからないけど、緊張してるみたい」
「なんで……」
「マルシオ!」
ティシラは何かに勘付き、マルシオの服を掴んで移動した。そしてすぐまた地面に張り付く。
「ここ、燃えた後みたい」
マルシオも中を覗く。相変わらず底までは見えなかったが、そこだけ植物が生えていない。植物たちの緊張はそこを中心に発せられているようだ。ざわついている。二人は体を起こしてしばらく考えた。
「もしかしたら、アムジーを襲った毒ガスって、ここから流れたんじゃないかしら」
「だとしたらこれ、魔薬の草なのか」
「そうかも。でも誰が? こんな湿っぽいところで自然に発火するなんて考えられない」
「誰が……って言うか、誰かいるのか。こんなところに……」
その時、大きな声が洞窟に響き渡った。
「誰だ! お前ら!」
二人は体を揺らして驚いた。何事かとその声の主に注目すると、そこには体格のいい男が剣を片手に威嚇していた。胸の肌蹴た白いシャツと茶色のズボンは薄汚れていた。髪や髭もボサボサで品のかけらもない。突き出した剣も刃が毀れている。吊り上げた目は勇ましかったが、そこには恐怖が宿っていた。
ティシラとマルシオはきょとんとしてその男に首を傾げる。
「あんたこそ誰よ」
男は全く脅えようともしない二人に再び大声を上げる。
「俺様はノートンディルの海を制する海賊頭、ワイゾン様だ!」
二人はどう反応していいか分からなかった。威勢はいいが、何となく頼りないその男、ワイゾンがただの人間だと分かれば何も問題なかった。ティシラは一人で興奮している大の男の姿が鬱陶しくなる。
「海賊が何で穴蔵にいるのよ」
「そ、それは……」
鋭いが、当然の質問にワイゾンは後ずさる。
「まさか!」マルシオが急に怒鳴る。「アムジーに毒を撒いたのはお前なのか!」
マルシオは剣などまったくものともせず、ワイゾンに近寄る。その銀の目に睨まれてワイゾンは冷や汗を流す。すると彼の背後の横穴から緊張感のない二つの人影が姿を現した。
「ちょっと、何大きな声出してるのよ」
一人は女性だった。
「お頭、誰かいたんですか」
もう一人は背が低く、太った男だった。
「お、お前ら」ワイゾンは慌てている。「来るな、奥に隠れていろ」
ワイゾンの様子は二人の身を案じていると言うより、何だか調子悪そうな感じだった。
二人の手下らしき者たちは言う事を聞かずに横穴から出てきて、ティシラとマルシオを訝しげに眺めた。そして女性の方がため息をつきながら。
「やだ、まだ子供じゃない。そんなの相手に粋がってどうするのよ」
「だ、黙れ、マイ」
マイと呼ばれた女性はあまり上品ではなかったが、黒いタイトな服を身に纏い、そこにはしなやかな色気と美しさがあった。シンプルな服の開いた胸元からはモノクロの薔薇の刺青が入っていた。棘のある蔦は首元まで伸びている。
「お頭……いいから食料を探しましょうよ」
「キジ、お前も引っ込んでろ」
キジと呼ばれた男はワイゾンと似たような格好をしている。太った体を揺らしながら情けない顔をしている。全員が剣やナイフなどをそれぞれに装備しているようだし、腰元には機能的なベルトや用途に分けた皮の袋などをぶら下げている。確かに、三人纏めて見ると海賊に見えなくもなかった。
ワイゾンは気の抜けた二人に再び向き直る。
「てめえら、何者だ。大人しく俺に従え。逆らったらこの剣の錆にしてやるぞ」
二人はため息をつく。闘争心の欠片もないくせに、何を脅そうとしているんだと思いながら冷たい目線を送る。
「どうやって?」
マルシオは小馬鹿にしたように言い捨てる。ワイゾンはむっとして剣を振り上げる。
「なめやがって。まず見せしめにお前から……!」
だが彼が振り上げたのは、剣ではなかった。一本の木の枝だった。
「あれっ!」
その間抜けな姿にティシラとマルシオ、なぜかマイとキジまで笑っている。ワイゾンは顔を真っ赤にして奮えている。
「剣がなきゃ、錆にもなれないな」
マルシオにからかわれて、ワイゾンは変身した木の枝を投げ捨てる。枝は地に叩きつけられると同時に剣に戻った。背後ではマイが指を刺して喜んでいる。
「すっごい、それ魔法?」
マルシオが答えるより早く、眉を寄せて立ち尽くしていたワイゾンが物凄い速さで彼に駆け寄ってくる。
「お前、魔法使いか!」
ワイゾンの剣幕にマルシオは面食らう。
「頼む、ここから出してくれ!」
ティシラとマルシオは唖然とした。
3
ワイゾンは頭を垂れ、恥を忍んで話し出した。
「俺たちは本当に海賊なんだよ。ある日パライアスに船を停泊して陸に上がった。そこで久しぶりに狩をしようという事になったんだ。ある村を見つけた。それがアムジーだ。そこを標的にしようと思ったが、まだ日が高かったから近くの山に身を潜め、夜になったら襲うつもりだった。そこでこの洞窟を見つけたんだ。身を隠すのに丁度よかったし、何か宝でも見つかればラッキーだと、軽く考えた。だが……この通り、俺たちはここに閉じ込められてしまったんだ」
ティシラが率直な感想を述べた。
「すごい間抜けね」
ワイゾンはむっとするが、堪える。
「……なぜ迷ってしまったのか、まったく分からなかった。磁石も狂い、はぐれた仲間には二度と会えなかった。死体になっている仲間なら何度か見た。哀れな姿だった。まだそんなに時間も経ってないはずなのに、死体には植物や茸が生え、ぐちゃぐちゃに食い荒らされていた。俺たちの食料は蓄えと、ここに生えている植物で食いつなげた。だがそれも毒を含むものが多く、苦しみながら死んでいった者も何人もいた。トラップもあった。数は少ないが、それは特殊で強力な魔術の技らしく、ときどき襲い掛かるそれを見破る事ができなかった。目の前でミンチになった奴もいたよ……」
ティシラはさすがに気の毒に思い、かける言葉はなかった。
「俺たちの敵は『恐怖』だった。腕や体力には自信がある。頭の切れる奴も、トラップの専門家も船医だっていた。相手が見えるものなら尽きるまで叩き潰してやったさ。それで死ぬならまだいい。だが武器も戦略も何も無意味だった。強靭な精神力も次々と潰され自害する者もいた。結局、五十人ほどいた俺の仲間はたったこれだけになってしまったんだ……」
ワイゾンは肩を震わせる。悔しさと涙を堪えている。
「どれだけここを彷徨っているの?」
そうティシラが尋ねた。
「日が昇らないからな……もうはっきりは分からないが一、二ヶ月は経つかもしれない」
隣で話を聞いていたキジがめそめそと泣き出す。
「お頭、俺たち、いつになったらここから出られるんでしょう」
「馬鹿、泣くなキジ。ここまで生き残ったんだ。俺たちだけでも絶対海に帰るんだ」
「どうやって?」
マイが水を差してくる。
「だから」無神経なマイの質問にかっとなる。「何の因果か、ここで二人の魔法使いに会えたんじゃないか」
と、ティシラとマルシオを勢いよく指差した。ぎょっとしてしている二人にワイゾンが縋り付いてくる。
「頼む! ここから俺たちを出してくれ。礼はする。外に出られれば海岸には船がある。そこにはたくさんの宝があるんだ。いや、もしかしたら船は他の賊か軍に捕られているかもしれないが……そうだとしても、また俺たちは海に出て新たな宝を探す。それで何年かけてもあんたたちに礼をする。約束だ」
二人は目を合わせ、汗を流した。
「頼むよ。これでも俺は海では名を馳せた大海賊なんだ。この俺が頭を下げるなんて、一生に一度だ。せめて俺たちだけでも生き残らないと、死んだ仲間に、俺を信頼して付いてきてくれた仲間に申し訳が立たないんだ。なあ、分かるだろ?」
マルシオがぽつりと呟く。
「そう言われても……」
「なんでだよ! あんたたち魔法使いなんだろ。なんでもできるんだろ。さっきみたいに、剣を変身させたように」
「これだから」ティシラが困って口を開く。「素人は」
「どういう意味だよ」
「魔法使いは何でも屋じゃないのよ。そんなに誰もがやりたい放題ならこの世に苦労はないわ。魔法ってのはその人の持つ魔力、それを制御する力、それに魔道や魔術の知識と、道具や印、呪文、魔法陣。それらのすべてが揃ったものしか使えないの。私たちは万能じゃないんだから」
「つまり……?」
まだピンとこないワイゾンの代わりに、マイが無情に言い切る。
「未熟って事ね」
ティシラはむっとするが、その通りで言い返せなかった。
「……そんな」
ワイゾンが絶望して、がっくりと肩を落とした。単に迷子が増えただけだということを悟る。ティシラとマルシオは、こんなに落ち込んだ大人の男を見たことはないと、哀れに思った。
そんなワイゾンを置いて、ティシラは話を進める。
「とにかく、私たちもここで野垂れ死ぬつもりはないわ」
「あんたたちと目的は同じなんだ」
「出るまで、若しくは死ぬまで協力しましょう」
「……結局振り出しかぁ」
四人が話し合っている傍らで、ワイゾンが急に雄叫びをあげた。
そして体を起こし、腰に下げていた小さな皮の袋から何かを取り出す。
「お、お頭! どうしたんですか」
キジが慌てて駆け寄るが、ワイゾンに突き飛ばされる。
「ちょっと、ワイゾン! だめよ!」
マイも大きな声を出したが、ワイゾンは正気を失っていた。
「うるせえ! もう我慢できねえ! こんな穴蔵、吹っ飛ばしてやる!」
ワイゾンの手には小型だが、強力な爆弾が握られていた。ライターに火を点け、導火線に近づける。
「落ち着け!」
マルシオが止めようとするが、ワイゾンの目はまともではなかった。もう限界だった。ティシラたちが最後の希望だと信じていた。それを裏切られたことで張り詰め続けた緊張の糸が切れてしまったのだ。自分だけが死ぬならまだよかった。だがたくさんの仲間の惨い死に様が晒され、それなりに自信のあった腕や戦術が奪われ、自分の培ってきたすべてを姿さえ見えない何かに打ち壊される恐怖に耐えられなくなったのだ。
「────!」
すると、ティシラがそれとは違う殺気に胸を貫かれた。ざわりと総毛立つ。
「火を消しなさい!」ティシラの咄嗟の怒鳴り声で空気が揺れた。「植物たちが騒いでる! 火を恐れている! そして、怒ってる!」
「そんなもの、全部粉々にしてやる!」
「だめです、お頭」キジは震えながら大声を出した。「前にも爆弾を落として……恐ろしい毒ガスで死にそうになったじゃないですか!」
「何だと?」マルシオが眉を顰める。「やっぱり、お前たちが……」
「マルシオ、とにかく止めなきゃ!」
騒ぎが一転して、沈黙に変わる。
──間に合わなかった。一瞬の出来事だった。足元の穴からしゅるるっと一本の触手が伸び、素早く、目に見えないほどの勢いでワイゾンの心臓を貫いた。ワイゾンは抵抗する間もなく、どさりと倒れる。辺りには血が飛び散り、彼の胸も真っ赤に染まっている。一同は立ち尽くした。血に塗れた触手はうねりながら再び穴に戻り、暗闇に身を潜めた。
「お、お……」キジが蒼白して声を絞り出す。「お頭……!」
マイも震えながらゆっくりとワイゾンに近づく。まだ息はある。しかし今にも絶えそうだった。ティシラとマルシオはかける言葉が見つからなかった。毒の薬草とはいえ、自然の怒りに触れてしまったのだ。
「お頭ぁ!」
キジが大声を上げて泣き出した。マイはただショックを受けて、隣に膝を折り、彼の顔に震える指を這わせた。
「マイ、キジ……」ワイゾンは途切れた声で。「すまない……俺が不甲斐ないばっかりに。お前たちまでこんな事に……」
「い、嫌です。死なないでください。お頭がいなくなったら俺たちはどうすればいいんですか」
「俺だって死にたくない」ワイゾンは喉に詰まる血を吐きながら。「お前らをこんなところに残して……」
「ねえ」マイがティシラとマルシオに訴えるように。「彼を助けて。なんでもいい。傷くらい治せないの?」
「そ、そんなにひどい傷、簡単には治せないよ」
口籠りながらもマルシオはワイゾンに近づき、傷を見る。
「それに、凄い速さで猛毒が回ってる。これじゃあ、下手に魔法を使えば、最悪彼は人の形さえなくしてしまうかもしれない」
「見殺しにするって言うの!」
「見殺しなんて! さっきも言っただろう。魔法使いは万能でもなければ神でもない。今の俺の力じゃ……無理なんだよ!」
プライドの高い、自分を過大評価したがるマルシオが「無理」と認めた。認めるしかなかった。魔法使いになって初めて人に助けを請われたというのに、それが魔薬の被害者だなんて。悔しい。自分が未熟なだけなのか、運が悪いのか、どちらにしてもただ現実を受け入れるしかなかった。マイはマルシオの辛そうな表情から心情を察し、何も言えなくなった。
「マイ……こいつらを責めるな」ワイゾンはマイの手に触れる。「俺が悪いんだ。許してくれ。どうかお前たちだけでも生き残って……」
「あんたがいなきゃ意味がないでしょ!」
マイは内から突き上げるように怒鳴りつけた。
「うう……畜生」ワイゾンの体が冷たくなり始める。「死にたくねえ。この世に神がいねえんなら、悪魔でも何でもいい。助けてくれ。俺はどうなってもいい。こいつらを置いて逝きたくねえ……」
三人は諦め切れなかった。しかしただ彼の死を待つ事しか出来なかった。
すると、今まで黙って俯いていたティシラが、厳しい表情でワイゾンに向かう。
「それ、本当?」
「……え?」
「仲間を守るために命、懸けれる?」
ワイゾンは質問の意図が分からず、戸惑いながらも必死で腹から声を出した。
「あ、当たり前だ。それが海賊だ」
「きれい事は聞きたくないわ。どうせ死ぬのよ。本音で話しなさい。彼らのために死より辛い苦しみを味わえる?」
「ティシラ、お前」マルシオは嫌な予感がした。「何を……」
「その時間が」ティシラは構わず続ける。「永遠に続いても?」
ワイゾンは一瞬、迷う。だが自分の死がすぐそこまで来ている。考えている時間はなかった。
「何でもいい。この際、悪魔に魂を売っても構わねえ。こんなところで死ぬよりマシだ!」
「悪魔は」ティシラは赤い瞳でワイゾンを見据える。「あんたの魂なんか欲しがらないわ。でも──」
ワイゾンはティシラの目に飲み込まれ、ぞっとする。
「取引は可能かも」
ティシラはワイゾンの体を引き起こす。その目には邪悪な炎が灯っていた。
「ちょっとあんた、何を……」
素早くマルシオがマイとキジを止める。マルシオはティシラが何をしようとしているのか、彼女を取り巻く魔力で悟った。やっぱり、と思う。だが今は何が正しくて悪いのかなんて誰も決められない。
「あんたたちのボスが決めた事だ。邪魔するな」
ティシラの形相が変わる。空気が揺れるのを体で感じる。彼女は虫の息のワイゾンを見つめ、獲物を捕らえた獣のように微笑する。その真っ赤な口から鋭い牙が覗いている。マルシオは目を逸らした。
4
ティシラは頭を振り、大きく口を開く。
上下の八重歯が生き物のように、不気味に漫ろ伸びる。そしてワイゾンの青ざめた首筋にその牙を食い込ませた。
一同は絶句した。ワイゾンの悲鳴が轟く。彼は体から血が吸い取られていくのを感じ、痙攣を起こした。
そしてとうとう白目を剥いて完全に抵抗する力を失った。牙を抜くと、そこから血が溢れ出てくる。
ティシラは乱暴にワイゾンの体を放り出す。その口元から血が滴り落ちている。それを拭って、白くなったワイゾンの体に手をかざす。
深紅の目を開いたまま呪文を唱える。その声は地の底から響いているようだった。
呪文は魔界の言葉で、一同には何を言っているのか分からない。
ティシラは短い言葉を何度も繰り返しながら、鋭く尖った爪で自分の手首を切り、魔族の血をワイゾンの口元に滴らせる。白目を剥いたままのワイゾンはそれで唇で湿らせ、自らティシラの腕を掴み、引き寄せる。ワイゾンは自分の意思とは関係なく、まるで渇望した体がそれを欲するようにティシラの血を飲み込んでいた。
それを見つめながら、ティシラは白い息を深く吐いた。そしてワイゾンを振りほどき、言い聞かせるかのように低く呟いた。
『下等な弱き人間よ。神に与えられしその魂を捨てよ。我がしもべとなり、永遠に地を這う事を誓え。光を、祝福を冒涜せよ。闇を称え邪悪を崇めよ──』
ワイゾンが再び震えだす。
『お前の魂は闇の底に繋がれた。祈りも徳もすべてが奪われた。我に忠義を、永遠を捧げよ。さすれば栄光を。我を欺く事あらば相応しき苦痛と屈辱を与えよう……』
ティシラの言葉は声として聞くのではなく、ワイゾンの体中に染み込んでいっているようだった。響くそれは女でも男のものでもなかった。
「うう……」
『選べ。浅ましく地を這うか、それともその血肉を獣に食われるか』
ティシラは最後の選択を与えた。
ワイゾンの体は泥に塗れ、まるで悍ましい死体が死に切れずにもがいているようだった。呪いの言葉を囁くティシラも、まるで現実のものとは思えない形相で異様な空気を醸し出していた。そこには異空間があった。誰も近寄れなかった。
すると、ワイゾンは息を吹き返し、人間離れしていた顔に血の色が戻り始めた。
「寒い、寒い……恐ろしい……」
ワイゾンは言葉にせずに、突きつけられた残酷な選択の答えを出したのだ。
儀式は終了した。
ティシラは大きく息を吸い込んだ。目を閉じ、開く。すると、ふっといつもの顔に戻る。そこにはやり切れない悲しみがあった。
「後は……彼の精神力次第よ」
マイとキジがマルシオを押しのけ、ワイゾンに駆け寄って体を起こす。
「お頭、大丈夫ですか」
ワイゾンは青い顔で震えている。だがその顔から死相は消えていた。眼球には虹彩が戻っている。
ティシラは泣きそうな顔で座り込んだ。複雑な面持ちでマルシオが近づくが、かける言葉がみつからない。その様子を背中で感じながら、ティシラは呟く。
「……私を、軽蔑する? でも、私だって好きでやったんじゃない。こうするしかなかった。できなかった。せっかく魔法使いになったのに、結局私は自分の生まれ持った邪悪な魔力しか使えなかった。悔しいよ……」
マルシオは彼女を責める気にはなれなかった。それどころか、同情さえ感じる。何もできずに傍観していた自分のほうがよっぽど非力だ。
だがこの血の儀式が正しいかどうかは分からない。本当にワイゾンがこうまでして生き延びたかったのか、後悔はないのだろうか。それは、彼が決める事である。
だからマルシオは、否定も肯定もしなかった。
「いや……俺は目を閉じていたから、何も見なかった」
そのうちにワイゾンの意識がはっきりしてくる。奮えも少しずつ収まり、マイとキジの顔を交互に確認する。
「俺は一体……」ワイゾンは深く呼吸をしながら。「どうしちまったんだ」
「お頭!」
「生き返ったわ」
ワイゾンは体を起こし、手を見つめ自分の体を触った。生きてる。だが何かが違う。服に血はついたままだったが、胸や首筋の傷は消えている。だが一体何が変わったのかは、具体的には自分でも説明できない。混乱しているワイゾンにティシラは重い口調で声をかける。
「あなたは、魔族になったのよ」
「……魔族?」
「正確には一度『死んだ』のよ。そして魔族として蘇った。その体は魔力を帯び、人間より強く寿命も長い。ただし……」
「……ただし?」
「私の、ヴァンパイアとしてのしもべとしてか生きられない……そして主人だけでなく、あなたより強い魔族には決して逆らえない。魔界や魔族の性質や秩序も含め、いずれその体で思い知り理解せざるを得なくなるわ。今まで人間だったあなたには相当過酷なものになると思う」
ワイゾンはまだ理解できなかった。
「……魔族? 魔道のマの字も知らない俺が?」
三人は顔を見合わせる。すぐに飲み込めるものではないと、ティシラはそれ以上口を開かなかった。ため息をついて、なんでこんなことを、と改めて落ち込む。いろいろ考えているうちに、そもそもマルシオが巻き込んだのが始まりだったと思い出すが、怒鳴る元気はなかった。ティシラがそんな葛藤をしていると、思いがけず、歓喜の声が上がった。
「俺、魔族になったんだってよ!」
「お頭、凄いですね!」
二人は拳を握って喜んでいる。ティシラまったく予想もしていなかった反応に度肝を抜かれた。
「凄いぞ、心臓を刺されたのに、傷も治ってる!」
その隣でマイだけは気が抜けたようにため息をついていた。
ティシラはがっくりと肩を落とす。人がどんな思いと覚悟だったか知りもしないでと、その精神的負担は相当なものだった。マルシオはそんな彼女の心理を察した。
「よかったじゃないか。相手がバカで」
だがいつまでもこんなことをしている場合じゃない。ここから出る方法を考えなくてはいけない。海賊の命を助けたところで外に出られなければ意味はないのだ。まずはそれから、と気持ちを切り替えようとした。
その時だった。
上方の横穴から人影が現れた。
「……やっと終わったようだね」
一同は一斉にそれに注目した。そこには黒いマントに身を包んだ一人の青年が立っていた。
「それにしても、騒がしい」男は無表情だった。「暴れまわるは、爆弾は落とすわ、君たちの勝手だけど私の邪魔はしないで欲しいな」
男は気だるそうに、長身の体を折り、ふわりと舞い降りてくる。軽く着地しながら。
「まあ、でも」その青い瞳は、微笑んだ。「こんなところでヴァンパイアの血の儀式が見れるとは思わなかったよ」
男の態度は何となく失礼だったが、敵意は感じられない。姿勢を正しながら一同にゆっくり近づいてくる。
見た目は特に変わったところもないのに、なぜか緊張する。根拠はなかったが彼がただの人間ではない事が伝わる。
肩にかかる程度の黒い髪は無造作で不揃いだが光沢がある。長めの前髪やピンと立ったマントの襟で隠れ気味のその顔は少し冷たさを含んだ美しいものだった。
誰もが魅入られてしまうほど、完璧だった。
だが、完璧過ぎる。近寄り難い威圧感がある。
何よりも、前髪の間で見え隠れするその青い瞳は尋常ではなかった。ただの青ではない。深く、遠くで輝く空がそこにあるかのようだった。
いや、きっと色は問題ではないのだろう。例えそれが何色でも同じ光を灯していたのだろうと思える。なぜなら瞳そのものではなく、彼の内側から放たれる存在感こそが一同を圧倒していたのだから。
マルシオが、誰もが思っている事を代表して聞いた。
「……あんたは?」
男はやる気のなさそうな目をマルシオに向けた。
「魔法使いだ」
答えはそれだけだった。またしんとなる。理由も分からずに皆は戸惑っていた。海賊の三人は順に顔を見合わせている。
ティシラは頭の中が真っ白になっていた。必死で考える。
心の中でまさか、まさかと繰り返している。だが、確信していた。間違いなかった。彼はティシラが満月の夜、ウェンドーラの屋敷で見た者だった。
つまり、彼女が会いたいと切望して止まなかった「彼」だったのだ。
今度こそ、「本物」だと思った。無意識に声を漏らす。それしか言葉は出てこなかった。
「……クライセン……様?」
マルシオが眉を寄せる。彼も、もしかしてとは思っていた。
「クライセン?」ワイゾンが口を挟む。「聞いた事があるぞ。四代目魔法王だ。そんな奴がこんなところにいるわけないじゃないか」
ワイゾンは無理して笑う。男と目が合うと、彼もにっこりと微笑み返す。
「居ちゃ悪いかな?」
また一同は沈黙する。マルシオも彼が「本物」だと、その確信が足元からじわりと寒気として昇ってくる。
「そんな……」
声が震える。そんな彼らの反応は当然だったのだが、クライセンはまったく構わずに落ち着いて話し出す。
「とりあえず、ここで君たちと遊んでる暇はないんだ。私は用が済んだからここから出ようと思ってね。ついでだから案内してあげるよ。よかったら着いておいで」
「本当か!」
ワイゾンが身を乗り出す。
「ただし」クライセンは目を細めた。「ここを出るまで私語は禁止する。君たちはただ私の後を歩くだけだ。それ以外、何もしちゃいけない」
「わ、分かった! 本当に出られるんだな。だったら何でもする」
海賊はまたはしゃぎだした。だがティシラとマルシオは突っ立ったまま返事をしない。クライセンはそんな二人を見て。
「君たちはどうする?」
マルシオは彼の青い目に射抜かれてびくっと体を揺らす。
「あの……」
「早くしないと、置いていくよ」
クライセンはそう言うと背を向けた。マルシオは慌てるが、なぜか素直に体が動かない。戸惑っているマルシオの横で、ティシラが顔を上げる。
「あなたは」そこには迷いがあった。「本当にクライセン様ですか」
一同は黙った。ただならぬ緊張感は無視できず、注目された。
「そうだよ」
「さっきの……見てたんですか」
「うん」
クライセンは淡々と答える。そこに情はなかった。
ティシラはこみ上げる衝動を必死で抑えた。彼の冷たい態度がそうさせているのではなかった。今までの自分の想いや、ここで人間に呪いをかけた自分への罪悪感など別問題だった。ティシラはその感情を後回しにする事ができなかった。
「どうして助けてくれなかったんですか!」
突然のティシラの高い声に、一同は固まった。
「あなたならできたはずです。なのに……なんで黙って見ていたんですか」
ティシラはずっと想いを寄せていた彼に出会えた事を喜んでなどいなかった。その問いかけには怒りさえ感じる。
クライセンは表情を変えずに彼女に向き直る。
「そんな義理はない」
その冷酷な答えに空気がざわついた。
「目の前で傷と毒を負って苦しんでいる人を救わないなら、あなたは、魔法王は一体何をするんですか」
「それを説明するには時間がかかる」
マルシオも我慢できなくなる。
「そうだ。助ける義理がないと言うのなら、なんで出口に案内するんだ。それにあなたは一体ここで何をしていたんだ。いや、ここは一体どこなんだ」
「質問が多いな」
クライセンは軽く流す。そんな軽率な彼の態度に苛立ちを覚えた。
「クライセンは百年前から行方不明になってる。あんたのペットは死んだと言っていたんだ。だがせっかく会えたのに、分からない事が多すぎる。俺にはあんたを信じて、黙ってついていく理由がない」
「嫌ならこなくていいよ」
「行かなかったら、俺はここで一生彷徨って死んでしまうんだろうな」
「そうかもね」
「助けられるものも助けないのか」
「無理強いはできない」
険悪なムードが漂う。海賊たちは傍らではらはらしている。だが口出しできなかった。しばらく三人の魔法使いは睨み合うように黙っていた。そこには目に見えない三種の魔力が交差していた。空気が揺れる。足元の植物たちがざわざわと囁き合っている。
長いようで短かった時間は途切れる。折れたのはクライセンだった。
「分かったよ」ため息をつきながら。「簡単に説明するよ。手短にね。まず、ここはノーラの洞窟だ」
「ノーラ!」堪らずワイゾンが声を上げる。「海賊界でも知られる悪党、魔薬王?」
「そう、ノーラの薬草栽培所だ。私はここでしか採れない薬草を探しにきてたんだ。ちなみにノーラはここにはいない。で、私とノーラは敵対している。百年前に彼と戦った。そして引き分けた。私は負傷し魔力を失い、ある所に身を潜めて力の回復と対ノーラの再戦に向けて準備をしていた。私は百年という月日をかけ、満月の力を借りて復活を成し遂げた。まだ数日前の事だ。そしてここを訪れた。で、なぜ義理もないのに君たちを助けるか。さっきも言ったが、ついでだからだ。ここは特殊な迷路になっている。魔力の大きさは関係ない。決められた道筋に正確に沿っていけば簡単に外に出られる。ここはその通り道なんだ。たまたまそこに君たちがいたから声をかけてみた。それだけ。そしてなぜ困っている人を助けないか。私は便利屋じゃないからだ。ここに踏み込んだのも、それがたまたまノーラの洞窟だったとしても、それはその人の運命だ。この程度のドジをいちいち救済しているほど私は寛大じゃない。もし君たちが私に世界中の怪我や病気を治して回れと言うのなら、残念ながら、これ以上君たちと話す事はない」
クライセンは淡々と語った。そして「他に質問は?」と付け加える。
「ノーラと敵対って、あんた……」ワイゾンは信じられなかった。「あんなのと戦ったってのか。引き分け? 再戦? どういう事だよ。あんた何者なんだよ。何をするつもりなんだ」
「私はノーラを倒す。それだけだ」
しかしまだ二人の魔法使いは納得していない。
「なぜ」マルシオが問う。「ノーラを倒すと?」
「さっき言っただろう。彼は私の宿敵だと」
「それだけ?」
「他に理由がいるかな?」
「ノーラは世界中の恐怖だ。太刀打ちできる者はいないと言われている。だけどあんたなら、魔法王なら可能かもしれないと思う人々の期待をどう思っている」
「興味ない。これはただの私用だ」
「あんたは……!」
「ちょっと待ってくれ!」
かっとなって飛び出そうとするマルシオを待たずに、ワイゾンが大声を出す。
「取り込み中に悪いが、まずはここから出ないか?」顔色を伺いながら。「出られるんだろ? 積もる話もあるんだろうが、ここがノーラの洞窟ならまず身の安全を確保しようじゃないか」
「確かに」クライセンがあっさり同意する。「その後に君たちがどこで何をしようが、私をどう思い、嫌おうが憎もうが好きにしてくれ」
そう言ってさっさと歩き出す。海賊たちは嬉しそうに後についていくが、マルシオは当然納得いかない。
「待てよ。まだ話は終わって……」
すると、クライセンは流れるように振り向き、魔力を宿した目でマルシオを制する。
「黙れ」
マルシオは息を飲む。
「後で、機会と時間があればゆっくり説明してやるから」
そう言うとまた背を向け、問答無用で歩き出す。マルシオは戸惑った。彼の迫力もさながら、なんだか妙な感覚に襲われていた。まるで、無意識に身を守るための本能が働いたような、それが記憶のどこかから引き出されたような奇妙なものだった。今は彼に従うしかなかった。黙って俯いているティシラに声をかける。
「ティシラ、行こう。今は我慢するんだ」
マルシオはティシラの手を引き、その重い足を無理やり進ませた。
5
一同は入り組んだ岩間から這い出て、入った所とは違う場所に出た。
それはアムジー村とは逆の、ミングの山の反対側だった。海賊たちは久しぶりの太陽の光、外の風を感じて大喜びしていた。
そこは緩やかな斜面で、人も動物も通る事はなく、背の高い草木がびっしりと茂っていた。その隙間からは遠くまで広がる平原が見えた。さらに向こうには、海賊たちが焦がれていた海が細い線を描いている。
海賊たちは半泣き状態で駆け出す、が、ワイゾンはそうはしなかった。マイとキジは足を止めて首を傾げる。
「どうしたんですか、お頭」
「いや……なんだか体の調子が悪くて……」
「せっかく出られたのに、ノリが悪いわね」
ワイゾンは今までより太陽の光が眩しく感じられた。それは体を刺されるようで、今すくどこか影に隠れたい衝動に駆られた。ずっと穴蔵にいたせいだと思おうとするが、それをマルシオに否定される。
「魔族に、ヴァンパイアの体になったばかりなんだ。努力すればそのうち慣れるよ」
「……どういう事だ」
「魔族に限らず、魔に属する者は本来夜行性なんだ。月の満ち欠けや蝕に影響を受ける。太陽の光はそれを中和する力がある。太陽に抵抗を感じるのは体に魔力が宿ってる証拠だよ。だがそれだけじゃない。視・聴・嗅・味・触覚のすべてが変化し、今までの生活は送れないだろうな」
ワイゾンは理解できず、唖然としていた。
「……海には戻れないのか?」
「さあ、あんた次第だろ」
そう話しながら、一同は斜面を下り、平原についた。
「さて」クライセンは足を止めず、そのまま進みだす。「私はここで失礼するよ」
「ちょっと待て!」マルシオが慌てて彼のマントを掴む。「まだ話は終わってないだろ」
「忙しいんだ」
「後でゆっくりって言ったじゃないか」
「機会と時間があったらって言ったじゃないか」
「それはいつなんだよ」
「少なくとも私の用が終わってからだな」
「あんたの用って、ノーラを倒した後って事か」
「そう」
「冗談じゃない。いつの話だ。それに本当にノーラを倒せる確信があるのか」
「さあ」
「ふざけるな!」
飽きもせずに揉める一同を殺気が襲う。
一斉に緊張する。辺りを見回すと、先ほど降りてきたばかりの斜面の草木の間から数十人の衛兵が弓に矢を番えていた。弓矢の軋む音が微かに聞こえた。その標的は魔法使いと海賊の一行に向いている。
何事かと、状況を理解しようとする前に、さらに山際の左右から馬に跨った兵がぞろぞろと姿を現し、クライセンたちを威嚇するようにその周囲を隙間なく囲む。兵は青銅の鎧と兜を装着していた。
「お前たち、海賊だな」兵の軍帥らしき大きな男が問う。「三ヶ月前から岸に停泊している海賊船はすでに取り調べてある。ミングの山に潜み、アムジーを襲ったのはお前たちか」
ワイゾンが青ざめた。
「ち、違う」マルシオが慌てて男に弁解する。「俺たちは魔法使いだ。アカデミーの卒業証明書もあるんだ」
「ならばここで何をしている。この周辺は今立ち入り禁止だ」
「それは、山に洞窟があって……アムジーが襲われる前に迷いこんでしまっていたんだ」
マルシオは咄嗟に嘘をついてしまった。ティシラは未だ黙り込み、クライセンは迷惑そうな顔をしてそっぽを向いている。ワイゾンたちは縮こまって縋るような目でマルシオを見つめていた。
何なんだ、皆して自分ひとりに押し付けて、とマルシオは混乱する。特にクライセンには何か発言してくれと心の中で訴えるが、彼は目も合わせずに知らん顔をしている。
軍帥がそんな事で納得してくれるわけもなく、部下たちに片手を挙げて「捕らえろ」と合図をする。
「ちょ、ちょっと……」
「話は後で聞く」軍帥は馬を翻しながら。「じっくりとな」
マルシオはぞっとした。下手したら拷問にかけられるかもしれない。その時は、この海賊たちを迷わず差し出してやろうと強く思いながら。
そうして、怪しい一行はティオ・メイの軍に捕らえられてしまった。