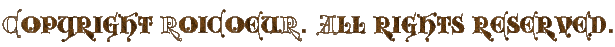第7章 反逆





1
ティオ・メイの城は相変わらず騒がしかった。しかし、それも一部の間で不穏な兆しが囁かれているだけで、周りを取り囲む国の民にまでは届いていなかった。
「クライセン殿」
王室を出て、中庭を真っ直ぐ歩いていたクライセンをオーリスが追いかけてきた。クライセンは足を止める。その後ろにはティシラとマルシオがいる。広間にはまだ魔法陣が描かれたままだったが、大掛かりな魔法に駆り出された魔法使いたちはそれぞれの役目に戻っており、もうそこから姿を消していた。
「まだ何か用?」
クライセンは足を止めてオーリスと向かい合う。
「全く、あなたは」オーリスはため息をつく。「まあよくも最後の最後まで……なぜもっと普通に話ができないのですか」
「何か問題があった?」
「時間が惜しいとおっしゃるのなら、あれは利口ではありませんぞ」
「なんで」
「お分かりでしょう。あの方は国王なのです。あなたがいくら魔法王であろうと、この世界は規律、法律の上に成り立っております。それを取り仕切る王に無礼を働いたとなったら、下手すれば罪人として罰せられますぞ」
「へえ」クライセンはあまり話を聞いていない。足元を眺めながら。「なあオーリス。せっかく魔法陣を造ったんだ。もう一回ミングまで送ってくれないか」
「クライセン殿!」オーリスは怒鳴る。「聞いていらっしゃるのですか。私はあなたを捕らえたくなんてないのです。どうか……」
オーリスは息を飲む。クライセンがじっと自分を見つめていた。その青い目に恐怖を感じた。
「オーリス」口元は笑っている。「私を捕らえたければ捕らえればいい」
できるものなら、とは言わなかった。オーリスが目を逸らす。
「それがお前や王の決断ならね」
オーリスは口を閉ざし、立ち尽くした。クライセンは再び振り返り、門の外へ向う。ティシラとマルシオも、まさに金魚の糞の如く早足で追いかけていった。
門の外に続く階段を下りながら、マルシオがクライセンに声をかける。
「ちょ、ちょっと待ってくれよ」
クライセンは足を止めない。
「何?」
「これからどこに行くんだ」
「さっき言っただろう」
「……俺たちはどうすればいいんだよ」
「好きにすれば?」
「な、なんだよ。それ」
「大体、何しに来たの?」
マルシオはむっとする。足を速めてクライセンの隣に並ぶ。
「あんたが連れてきたんだろ」
「私の弟子だとか言い出したのは君の方だ」
「そうだけど……あんたも認めたじゃないか」
「言ったかもね。まさか鵜呑みにするとは思わなかった。後腐れがあっても面倒だから、ここで破門する」
マルシオは黙る。過去に同じようなことを、どこかで誰かにも言われたような気がする。だが思い出せない。
二人に遅れを取らないように黙ってついていくティシラも同じような感覚を持っていた。何を発言すればいいか未だに分からず、複雑な顔をしていた。
三人はそのまま言葉を交わさずに早足で階段を下りきり、周りには目もくれずに城門に向かった。広く、石の壁に囲まれた長い道はずっと緩やかなカーブになっており、直線になったところはない。所々に見張り台や開け放たれた門構えがある。
その都度に数人の警備兵がちらほら立っているが、一見奇妙な三人の魔法使いに声をかける者はいなかった。先に依送魔法を使い、王の客が訪れることは報告されていた。それが彼らかは確信できないが、少なくとも上から降りてくるということは王の許可のある者だと判断できる。
だが、少し珍しいものを見る目で眺める警備兵が多かった。そんな視線を感じながら、クライセンが足を止めずに口を開く。
「どこまでついてくる」
「一本道なんだから仕方ないだろ」
「なら少し離れて歩いてくれないか。君たち、害はないが目立つんだよ」
「人のことが言えるのか」
「外見の話だ。悪いとは言わないが、派手なんだよね」
自覚はないが、反論もできない。マルシオの類稀な白い髪と瞳。まだ少し幼い雰囲気の中には、高潔な血が流れているだと思わせる立ち振る舞いを自然に身につけていた。
そしてティシラに至っては、黒髪がさらに深みを増させ、白い肌が際立たせている赤い瞳。しかも本人は美意識が強く、緩やかな長い髪とフリルのついたスカートには敢えてボリュームを持たせている。黙って大人しくしていれば、まるで女の子が憧れる人形のようだったのだ。
それでも「こいつに言われたくない」とマルシオは思いつつ、ここで外見について語り合うつもりはなかった。
「それより、あんた歩いていくつもりなのか」
「今考えてる」
2
その頃、ダラフィンはまだミングにいた。とてもティオ・メイに戻れる状態ではなかった。そこは戦場になっていたのだ。ダラフィン率いる三十名ほどの衛兵が突然の襲撃に緊張していた。
敵は、アムジーの村人だった。
先日、無残にも全滅してしまったはずの村人たちが起き上がり、ミングの砦に向かって押し寄せていたのだ。
兵たちはその恐ろしい光景に蒼白していた。決して味方の顔つきではない。村人のすべての皮膚は腐敗し、あちこちが剥げ落ちている。目つきは虚ろで動きも異常だった。足を引きずり、歩みは決して速くは無い。だがそれらは確実に兵たちに向かって進んできている。
兵たちは条件反射のように剣を構え、臨戦態勢を取る。全員が目を凝らして「敵」を見据えた。間違いない。誰も口にはしなかったが、確かに村人たちは死んでいたのだ。
兵のすべてが戸惑い、驚愕していた。声を押し殺している。ここで誰か一人でも大声を上げてしまったらそれに釣られて混乱が起きるだろう。基本的な訓練で教え込まれている。誰も逃げようとはしない。ダラフィンが剣を掲げて皆の先頭に立つ。
「皆の者、恐れるな!」その大きな声は全員の耳に届いた。「怯まず、戦え。奴らは国の守るべき民ではない。あの顔をよく見ろ。怨念に満ち溢れている。敵だ。躊躇せずに殲滅せよ」
兵たちの心は決まった。未知なる敵への恐怖はあったが、剣を持つ手に力が入る。ダラフィンの咆哮と共に一斉に走り出す。敵はざっと百体。その数がまさにアムジーの人口に値するということは、誰も口に出さなかった。
なぜ、とダラフィンは勇ましさとは裏腹、心の中で苦痛を感じていた。
なぜ我々は国の民を斬り殺さねばならぬのだろう。彼らはいつものように平穏な生活を送っていただけに違いない。なのに、突然意味も分からぬまま、苦しみながら命を奪われた。
それだけでも哀れなのに、と思う。なぜ死んでまでこうして切り刻まれねばならないのか。きっと彼らの魂は悲しんでいるだろう。その思いは誰にも届かない。
国を守るはずの我々が、なぜその悲しい思いまでを切り捨てているのだろう……だが、今は考えないことにした。ただ振るう剣から伝わる敵の骨肉の感触に嫌悪を感じながら、それを噛み締めていた。
敵は武器も持たず、ただ兵に掴みかかり、自分の体の腐った肉が剥げるほどに引っ掻いたり噛み付いてきたりするだけだった。力を入れればその腕や足ごともげ落ちるが首でも落とさない限り、いつまでも立ち上がってくる。彼らには痛みも感情もなかった。もう死んでいるのだから当然である。
そんな地獄のような状況の中、兵は傷を負いながらも倒れる者はいなかった。勝てる、という確信が募るにつれ、さらに闘志は漲ってくる。
そんな戦闘が地上で行われている頃、砦の地下牢では例の海賊たちが騒いでいた。
「なんだ、一体なにが起こっているんだ」
地下牢にもその戦慄は伝わってきていた。ワイゾンは鉄格子から鼻を突き出してキョロキョロしている。
「戦争かしら」
「せ、戦争? なんでこんな時に」キジは震え出す。「俺たちには関係ないのに」
「冗談じゃない。巻き添えなんて御免だ」ワイゾンは鉄格子に体当たりし始める。「お前らも手伝え」
キジも一緒にその巨体を鉄格子に叩きつける。マイは邪魔にならないように端に避けてそれを見ていた。二人がぶつかる音や振動が地下に響くが、誰も気に留める者はいなかった。
まず、地下牢には見張りもいなかったし、それ以上に地上での騒ぎでその音は掻き消されてしまっていたのだ。
次第に格子を止めていた釘が緩み始める。もともとそんなに頑丈にはできていなかった。ワイゾンとキジは息を合わせて最後の一発をかます。すると格子はガシャンと音を立て、ワイゾンとキジを巻き込んで倒れた。
「やった!」
二人は急いで体を起こして走り出す。マイもすぐについていく。三人は牢の木戸をそっと開け、地上に続く狭い階段を上る。
さらにさっきと同じ造りの戸を慎重に開けて外の様子を伺う。近くに人はいない。上半身を乗り出して声のする方を見ると、砦から離れた平野で兵たちが何者かと戦っていた。ワイゾンはその戦闘には興味はなかった。辺りを見回し、今なら逃げ出せることを確認する。
「今だ」
ワイゾンが二人に声をかけ、戦闘とは逆の方向に素早く駆け出した。
「やった!」キジが興奮して大声を出す。「やりましたね、お頭。これでやっと自由だ。海へ帰りましょう」
「でも船がないわ」
「そうだな。確かに。いや──」ワイゾンは走りながら妙な感覚に襲われた。「その前にご主人様を探そう」
「……は?」
ワイゾンの言葉に二人は眉を寄せた。だがワイゾンはその感情を抑えることができない。
「ご主人様、どこですか!」
その意味不明な叫び声は、ミングの平野に虚しく轟いた。
3
クライセン一行は城を出て、城下の町に来ていた。ティオ・メイの町はパライアス一大きな所だった。人々はこの大都市で毎日忙しく生活している。道はきれいに石畳で舗装され、左右には所狭しと煉瓦や木造の建物が立ち並んでいる。その間にはいくつもの横道が複雑に伸びており、よそ者は道案内がないと大抵は迷ってしまうだろう。
クライセンたちはその一角の宿屋に来ていた。目的は宿泊ではない。一階の広間にある大衆食堂で一息ついていたのだ。
今は食事時でもなく席はすんなり見つかったものの、店内は混雑している。クライセンは隅の席に腰を降ろしてのんびりお茶を飲んでいる。その向かいにティシラとマルシオも腰掛ける。
マルシオが周りを見回しながらクライセンに声をかけた。
「おい、こんな人の多いところで、何がしたいんだ」
「別に」クライセンはカップを口に運びながら。「喉が渇いただけだよ」
クライセンが何を考えているのか、未だに分からない。何も考えてないようにも見える。
こうしているとまるでごく普通の人間で、世界一の威厳も何も感じられない。先ほどの王との会話で見せた迫力はすっかり無くなっていた。
きっと彼は幻だと言われながら今までもこうして人に紛れ、すぐ近くで時間を過ごしてきたんだとマルシオは思う。根を張らず、誰とも深く関わらなければ空気のような存在にしかならない。これだけ長身で美形なら目立ちそうな気もするが、意識的にその存在感までも操作しているのだろう。
彼を現すに適切な言葉は思いつかない。ただ、考えるのを止めたとき、マルシオの頭の中には「変な奴」と言う一言が過ぎった。
そんな事を思いながら会話を探すが、見つからない。マルシオは痺れを切らしたように、上の空でクライセンを見つめているティシラを小突く。
「ティシラ、いつまで間抜け面してるつもりだ」
「えっ」ティシラが我に返る。「な、何が?」
「何がじゃないだろ。脳にバイ菌でも入ったのか。正常なら普通に機能しろよ」
「ああ……」ティシラは肩を竦めながら。「あ、あの……」
クライセンはちらりとティシラに目線を移す。それは一見優しそうで、冷たさも含んでいた。
「あなたは」ティシラはそれでも目を逸らさない。「本当にクライセン様ですか」
隣で、まだそんな事をと思いながら、マルシオは取り敢えず傍観する。
「初めて会った気がしないんです」
それはマルシオも同感だった。クライセンの反応を待つ。
「君とは」クライセンは微笑んで。「満月の夜に会ったね」
「そうだけど……そうじゃなくて」
「君は魔族だ。人より感覚が鋭い」
ティシラは俯く。が、すぐに顔を上げる。
「魔族だなんて言わないでください」
「なぜ? 故に魔力も強い。何を恥じる? 堂々とその力を活用すればいいじゃないか」
「……あなたは」ティシラは眉を寄せて。「何を知っているんですか」
「何でも」
「じゃあ、私が魔族だって言われるのを嫌がっているのも?」
「知ってる。でも何を嫌がっているのかは理解できない」
「あなたも魔法王と言われて、それを押し付けられるのは嫌だと言ってたじゃないですか。それと似ています」
「迷惑だが仕方ない。リヴィオラを持っていることは事実なのだから。人より多く持つ者はその分リスクを背負わなければいけないんだ」
「私は、自分が恵まれているなんて思ってません。たまたま魔族に生まれただけです。それとも魔族は魔法使いにはなってはいけないのですか。私は事実、アカデミーを卒業しました。それを魔族だからと言われてしまうんでしょうか。私は努力をしていないと見做されてしまうんですか」
「持つ者とは生まれついて持ったものだけでなく、努力して手に入れたものもある。反対に才能があってもそれをものにできるとは限らない。それは分かる?」
「……はい」
「君は生まれ持った力や才能を活かし、努力の末に欲しいものを手に入れた。それを否定する?」
「それは……否定できません」
「なら」クライセンは言い聞かせるように。「自信を持てばいい」
その包むような笑顔がティシラの心を鷲掴みにする。顔を赤くして、蚊の鳴くような声で「はい」と呟く。マルシオは照れる彼女を横目で睨む。やっと会話したかと思えばどうでもいい事を、と気分を悪くする。
その時、クライセンの背後にふっと人が近づいた。それは小柄な人物で焦げ茶のマントを羽織り、フードを深く被って顔は見えない。室内の喧騒に紛れて三人以外は誰もその存在を気にかけていない。
「クライセン・ウェンドーラ様ですね」
そのひっそりとした声は女性のものだった。
「そうだけど」
クライセンが無防備に答えると、謎の女性はフードの中から続けた。
「今すぐここから離れてください」
その一言でティシラとマルシオが顔を見合わせる。そして再び女性に注目する。クライセンの顔からも笑みは消えていた。
「メイの兵があなたを捕らえにやってきます。あなたは檻の中に留まるべきお方ではありません。行くべきところへお行きください」
焦りを隠しながらも何事かと不安になる二人を余所に、クライセンは黙って立ち上がる。女性は見下ろされる形になり、すっと背を向ける。
「こちらへ」女性は静かに人混みの中を歩き出す。「町の外への道を案内します」
ティシラとマルシオも立ち上がってついていく。クライセンはそんな二人を見て。
「まだついてくるのか」
「あんたの弟子だからな」
「破門と言ったろう」
「国王は俺たちの顔も知ってるし、弟子だと思ってる」
「君たちの事は一切眼中になかったと思うけどね」
「うるさいな。とにかく俺だってもうこんなところに用はないんだ」
そう小声で交わしながら、一行は宿屋を後にした。
「こちらです」
と、女性は早足で小道に入っていく。
「あの」ティシラがついてきながら声をかける。「あなたは?」
「私はライザ……」女性の声は穏やかだった。「この世の何よりも柔らかく、形に捕らわれない清か水の守り手。ラグの守護者です」
「魔法使いなのね」
「オーリスの娘です」
ライザの声は、フードの中で微笑んでいるのが伝わる。彼女がオーリスの娘だと言うだけでクライセンはすべてを悟った。
王はクライセンを、魔法王を我が戦力として傍に置き、共に戦うべきだと判断したのだろう。オーリスは国王に従うことを心に決め、クライセンの捕獲の命を兵に下した。
だがきっと、グレンデルに迷いがあったことをオーリスは敏感に感じ取ったのだ。それに救いを与えるのが彼の仕事だった。そして友であるクライセンへの情と、遠まわしな罪滅ぼしのすべてを込めて、娘であるライザに今の状況を打ち明けたのだろう。
決して「クライセンを助けろ」と言ったのではない。オーリスは娘に自分の本意を託したのだ。それがオーリスの賢明な決断だった。ライザが賢く、心優しいことを誰よりもよく知っている。そしてライザは父の心の伝言を受け取り、黙って行動を起こした。魔法王がここにいるべきではないと判断し迷わずに、迅速に彼のもとへやってきたのだ。
一行は目立たないように、ライザについて小道を細かく折り進んだ。まるで迷路にいるようだった。ライザは極力狭い道狭い道、人のいない方いない方を選んでいた。
その頃、町の中心にある広場に人だかりができていた。国の衛兵である象徴の青銅の鎧を身に纏った男が数人立ち並び、町の人々がそれらを囲むように集まっていた。
「お尋ね者は」兵の一人が大きな声を出す。「長身で黒髪、黒いマントを羽織っている。特徴は青い目だ。そしておそらく銀髪の少年と赤目の少女もいるはずだ。見つけた者は速やかに衛兵に知らせるように。彼らを見つけても決して騒がず、関わらないように」
町人の一人が恐る恐る前に出る。
「その人は、極悪人か何かでしょうか」
「いや、そのような報告はない。だが国王に無礼を働いた無頼者との事だ」
周囲がざわつく。王に逆らった者などここ何年も聞いた事がない。そこでまた一人、一人と前に出る。
「さっき宿屋の食堂で見かけない三人がいました」
「それならついさっき、そこの路地ですれ違いました。四人組でしたが」
「確かか」
兵はそう言うと、情報の宿屋と路地にそれぞれ数名の兵を向かわせる。兵はそうして、四方八方からじわじわとクライセンたちに近づいていた。
「やはり」ライザの声に不安が募っている。「何事も無くここから出るのは難しいかもしれません」
その緊張が伝わり、マルシオの顔に汗が垂れた。
「追い詰められているのか」
「ええ」
「後どれくらいで外に出られる?」
「まだ近くではありません。それに見つかってしまえば、出られても逃げ切れるかどうか……」
「そんな」ティシラは別の不安を感じた。「ライザさん、そしたらあなたも危険だわ。もういいからあなたは逃げて」
「いいえ。私は私の意志を貫きたいのです」
「どうして。私たちなら何とかするから。これ以上あなたに迷惑かけられない」
「いいえ」ライザは繰り返す。「国が滅べば私の大切な人もいなくなってしまうのです。王は決して愚かな人ではありません。ですが私には私の役目があります。故に悲しみが訪れようと、それも運命。私は私の善を信じて行っているのです」
「ライザさん……」
まだ顔すら見えない彼女の言葉には強く、そして切な思いが込められていた。そこにどんな決心があるのかは分からないが、何を言っても無駄だと感じられる。
「いたぞ!」
その時、路地の奥から兵の声が轟いた。
ティシラとマルシオは飛び上がらんばかりに驚く。ライザは慌てて方向転換して細道に潜り込む。皆もついてくるがその先にも兵の姿があり、もう逃げ道が塞がれるのも時間の問題だった。
息を切らしながら今度は壁を越える。だが次から次へと、あちこちで兵の掛け声が飛び交っている。一同は足場の悪い道を走りながら、半分諦めかけていた。ただ、大人しく捕まろうと思っているのではなかった。
こうして逃げていても駄目だ、ならば──と、次の手段を考えようとしていたのだ。
「捕らえた!」
しかし、思いがけず壁の影に隠れていた兵が目の前に飛び出し、ライザの腕が掴まれた。
ライザは咄嗟に魔法を使い、兵を弾き飛ばしてしまった。兵はその巨体を数メートル吹っ飛ばされ、派手に石の壁に叩きつけられる。
その勢いで、今まで深く被っていたフードが剥がれた。長く美しいブロンドの髪が宙に揺れ、その下の端麗な容姿が露になる。落ち着いた雰囲気があったが、その表情には寂しさと悲しさが宿っていた。
だがそんな彼女の儚げな美しさに見とれている暇はなかった。倒れた兵が力を振り絞って大きな声を上げる。
「反逆だ!」
一同は戸惑う。その声は合図となり、町中の兵士たちが次々と剣を抜く。人々は寄り集まる殺気に怯えながらそれぞれに散っていき、ばたばたと建物の中に身を潜めた。
ライザは震えていた。取り返しのつかないことをしてしまった、結局自分のせいで彼らを危険に晒すことになってしまったと。そしてこの事が明らかになれば父の立場も悪くなる。
危険は覚悟していたはずなのに、と思う。ライザはぎゅっと唇を噛み締めた。
ふっと視界が陰った。今まで冷静な顔で黙ってついてきていたクライセンが、彼女の背後から剥がれたフードを被せたのだ。ライザは涙目でクライセンを見上げる。彼は微笑んでいた。
「初めからこうしていればよかったんだよ」
狭い路地に兵たちが剣を構え、続々と集まってくる。警戒している。兵の一人がクライセンに怒鳴る。
「抵抗するな。もう逃げられないんだ」
クライセンは相変わらず落ち着いている。そしてその警告を無視して、隣で震えているティシラとマルシオの肩に手を乗せた。二人は目を丸くして彼に注目する。
「君たち」緩い笑顔で。「あいつらをやっつけてくれ」
すぐにはその言葉の意味が理解できない。頭が真っ白になる。次に顔が青ざめてくる。だがじっと固まっているわけにはいかない。マルシオが手を振り払い、大声を上げる。
「じょ、冗談じゃない!」
「できないの?」
「そういう問題じゃない! 俺たちを罪人にするつもりか」
「そうじゃないけど、仕方ないじゃないか。あの人たち話通じそうにないし、鬱陶しいし」
「確かにそうだけど……」
「このままじゃ捕まってしまうよ?」
「…………」
「殺さなくていいから」
「あ、当たり前だ!」
「大丈夫だから。ね」
「何を根拠に! 大丈夫なら自分でやればいいだろ」
するとクライセンは肩を竦めてため息をつく。諦めてくれたのかと、マルシオが息を整えようとした、その瞬間だった。クライセンの顔色、表情、その口調と態度のすべてが一転する。
「ごちゃごちゃうるさい! 命令だ!」
それはまるで、地震と雷に同時に襲われたような衝撃だった。今までの彼から想像もできないほどの大声で二人は怒鳴りつけられた。
4
「ごめんなさい!」
二人は同時に縮み上がり、条件反射のように土下座してしまった。そして、額を地面に擦り付けて、はっと我に返る。
言葉や頭ではなく、体が嫌でも反応する。ティシラとマルシオは真っ青な顔を見合わせる。そして、ガバッと飛び上がり。
「まさか!」
「ジン!」
その奇妙なやり取りをライザと、兵たちは怪訝に見つめていた。
だが兵は緊張しながらもじりじりと迫り寄ってきている。ティシラとマルシオはそんなものには意識がいってなかった。
縮こまる二人の前には、先ほどまでの気楽なクライセンはいなかった。鬼のような形相で睨み付ける恐怖そのもののような彼が、何倍も大きく見えていた。
「生意気に口答えするな! 私の言うことが聞けないなら、トカゲにして干上がらせるぞ!」
その迫力は本物だった。なんで、と思いつつ、抵抗することができない。長い間、毎日毎日この声に怯えて暮らしていた二人には、軍の剣より何よりもそれが恐ろしいものとして刷り込まれてしまっていたのだ。ティシラとマルシオは慌てて兵に向き合う。それを見て兵が一瞬たじろぐが、敵意と見なして剣先を向ける。
「あくまで逆らう気だな」
先頭にいた兵が威嚇する。だが二人の意識は別のところにいっていた。小声で何かブツブツ呟いている。
「どうせ魔法使うなら、逃げちゃ駄目かしら」
「無理だろ。ジンの遠隔魔法がどれだけのものか知ってるだろ。お前、逃げれたことあるか?」
「ないわ。何度小動物に変身させられたことか」
「俺もだ。ちくしょう……」マルシオは腹を括って大声を出す。「ジン、ちゃんと責任取れよ!」
それと同時に辺りが光に包まれ、魔法使い一同を中心に激しい爆風が巻き起こる。兵の数人が吹き飛ばされる。立っている者は怯まずに向かってくる。ティシラとマルシオは左右に分かれ、ひらりと近くの建物の屋根にまで飛び上がる。その隙にクライセンとライザも近くの壁に飛び上がった。
「あの」ライザが心配そうに。「大丈夫なんでしょうか」
「あの子たちは見た目より優秀だよ」クライセンは元の様子に戻っていた。「諦めの悪さと根性だけは半端じゃない」
ライザは彼の言葉を疑わなかった。
「では、あなたは私が守ります」
そう言って両手を広げ、不意に飛んできた弓矢を光の壁で弾き飛ばす。さらに高い位置に飛び上がり「こっちです」とクライセンを促した。それを見ていたティシラが慌てて。
「ちょっと」炎の塊を投げ捨てながら。「置いていかないで!」
足元で炎が上がるが、気にせずにクライセンの後を追いかける。
マルシオも屋根伝いに移動しながら、魔法で作り出した、光で模られた弓に雷の矢を番えて応戦していた。狙われたすべてが命中している。と言っても決して死に至ることはない。貫かれた者は強めの電撃に打たれ、痺れて身動きとれなくなるか気絶する。
ティシラは追い詰められると大きく息を吸い込み、口から炎を撒き散らす。それは一時的な幻覚で、しばらく経つと一面の火の海は消えてなくなる。ダメージは無いが足止めや撹乱には効果的だった。
その様子を見ていたライザは力強く微笑んだ。そして姿勢を正し、呪文を唱えると辺りの地面からいくつもの噴水が沸きあがった。兵たちはそれに足元を掬われ混乱し、収まったかと思うとマルシオの電撃の矢が一斉に走り抜ける。
水浸しの中でもティシラの炎は衰えなかった。両手の中に火の玉を宿し、地面に叩きつける。すると消えるどころか、油が注がれたかのように水の上を踊りながら回転する。
兵たちは戸惑っていた。こういった特殊能力と掛け合わせた魔法には不慣れだったのだ。どう考えても自然の法則に反している。目の前で、当たり前にように常識が覆される。手に負えない。兵の数人が「オーリス総監を」と伝達する。ライザはそれに気づくが、ふっと表情を消す。
オーリスはここへはこないだろう。それに、彼は敵ではない。今はダラフィンもその直属の兵も出払っている。希望が見えてきた。雰囲気が変わった彼女の周りを水飛沫が、生き物のように囲んだ。それは捩れながら尖った針に形を変えていく。動きが止まったかと思うと、兵にその針の雨を注がせた。
兵の一人が援軍を呼びに城へ向かって走りだした。それに気づいたマルシオが矢で狙うが、クライセンがそれを止める。
「ほっときなよ。どうせ間に合わない」
それもそうだなとマルシオは素直に狙いを変える。その時、ふと遠くを見渡すと、町の果てが見えた。もうすぐだ、と思う。が、その後のことまで考える余裕はなかった。
その頃、グレンデルの元には二つの凶報が届いていた。一つはクライセンたちの反逆。それによる民の混乱と軍の劣勢だった。
もう一つは、ミングでの恐ろしい出来事だった。
通信を使ってミングの砦から報告があったのだ。ミングから一番近い別の砦から援軍が向かったらしいが、その頃にはもう戦闘は終わっていたと伝えられた。兵のほとんどは無事だったとの事だが、問題はその襲ってきた「敵」だった。
アムジーで毒殺された民の死体が動いたというではないか。普通なら信じられない話だった。グレンデルは頭を抱えた。
「今ダラフィン殿がこちらに向かっているそうです」オーリスもその横で苦悩している。「急いでも二日はかかるそうですが」
王は応えない。ついでにクライセンと一緒にいた海賊が戦闘のどさくさに逃げ出したという報告もあったが、それはさして問題にされなかった。
クライセンを追っていた兵が恐縮しながら発言をする。
「反逆者の捕獲はいかがいたしましょう」
グレンデルは跪いている兵にちらりと目を配る。今となってはそれどころではないのだが、放っておくわけにはいかない。
「必要な援軍を好きなだけ連れていけ」
「は……」
兵は国王の弱気な答えに戸惑うが、これ以上ここにいても仕方ないと判断して立ち上がる。一礼して立ち去ろうとした彼にグレンデルは付け加えた。
「もし、取り逃がしたら」
兵は再び姿勢を正し、王の言葉を待った。だが、何とも気弱な声しか聞くことはできなかった。
「深追いせず、捨て置くのだ」
ティオ・メイの町は騒然としていた。クライセン一行は屋根から降り、もう小道をこそこそする必要もないと、大通りを駆け抜けていた。
ライザを先頭にクライセンが続き、その後ろをティシラとマルシオが守りながら進んでいる。接近戦だけは許さなかった。さすがに剣で斬りかかれたらお互い無事では済まない。
追ってくる兵は二十名ほどに減っていた。この調子ならもうほとんど心配はないと思われたが、援軍がきたらまた面倒なことになる。一行は急いだ。もう少しで町から出られる。
その記しである煉瓦造りのアーチが見えた。
「出口です」
ライザが叫ぶ。ティシラとマルシオも攻撃をやめ、足を速めた。
アーチが近づく。一直線にそれを目指し、潜り抜けた。ティシラはその直前でくるりと振り向いて最後に一発、強烈な炎弾を兵に食らわした。兵は完全にそれに拡散させられた。
すると、既にアーチを潜ったクライセンも足を止め、振り返る。その横をティシラがすり抜ける。
「よくやった」
そう言いながら、素早く宙で印を切り、指先に息をかけるように呪文を呟いた。
クライセンの髪やマントが微かに揺れたかと思うと、彼の足元から何かが沸きあがってくる。夢でも見ているようだった。地面から出てきたそれは、獅子頭を持った上半身裸の巨人だった。
だがその姿は薄く透けていて、空気のようだった。獅子の大きな目鼻口には迫力があるが、表情はない。その全貌は宙に浮き、太い両腕はまだ土の中にある。
獅子はそれを力強く引き出す。すると持ち上げられるようにアーチの下から硬く大きな土の壁が迫り出した。さらにその壁は波のように左右に広がっていく。
軽く人の身長を越える土の壁はそのまま両側に五十メートルほど連なった。兵たちは愕然としていて、動くことができなかった。土埃が舞う中、獅子は煙のように消え去った。完全に出口は封鎖された。
「これでしばらくはもつ」
一同は魔法王の術を初めて目の当たりにし、息を飲んだ。
「なんだよ」マルシオはふて腐れたように。「魔法使えるんじゃないか」
「使えないなんて言ってないし、今のは魔法じゃない。召還術だ。元々父の使い魔なんだが、言う事を聞いてくれてよかった」
「どっちでもいいよ」
そう言いながらマルシオは光の弓から手を離す。すると弓は砂のように散り、緩い風に巻かれて空気の中に消えていった。
ライザはフードを取りながら周囲を見回した。
「もう兵は追ってこないようです」
「そうだね」クライセンは町とは反対の広く長い道を眺めて。「近くにエンタナの森があるな」
「はい。そこを抜ければフィレスアンの港があります」
「たぶんそこにも兵がいるだろうが、行ってみよう」
クライセンとライザが歩きだす。その後をティシラとマルシオがついてくるが、マルシオは歩きながら大声を出した。
「ちょっと待てよ。そう言えばお前、さっきの何だよ」
「さっきのって?」
「ジンだよ」
あっとティシラも思い出す。クライセンは振り向かずに冷静に話し出した。
「ジンは私の家で飼ってた猫だよ。正確には父が拾ってきてそのまま居ついてただけなんだけど。いつの間にか魔力を帯びてもう百年以上生きてる」
「じゃあ」ティシラが口を挟む。「彼の口真似をしただけなんですか?」
「まあね。前に話した通り、私はノーラとの戦いで致命傷を受け、治療、回復に長年を要することになった。そのためには一度肉体と魂を切り離し、魂を何かに移し、その体で本体を治療、保管しながら魔力の回復を待たなければいけなかった。それで私は一番波長の合うジンに魂を入れてその体を借りていたんだ。最初はただの猫だったんだが、次第に二足歩行が可能になり、身長も伸び出した。五十年も経てば生活共に、術を使うのも何も不自由はなくなった」
「でも、なんで正体を隠す必要があったんだよ」
「隠していたわけではないよ。あれは私でもあるが、ジンでもある。ジンは元々気性の荒い猫でね、私を主人と認めながらすべてを侵食されるのが嫌だったんだ。だから私も体を借りている手前、私生活での主導権は彼に譲っていたんだ」
謎は解けた。しかし何とも歯切れが悪い。姿が猫だっただけに魔法王と言う名前を重ねることができず、真実が見え難くなっていたのだ。大体、クライセンのノーラとの因縁も何も知らなかったのだ。想像にも限界がある。それにクライセンは分かっていながら今まで自分たちをからかっていたのかと思うと腹が立つ。
「それにしても、あの性格の悪さは何なんだ」
「ジンは猫としては最強の魔法使いだったかもしれないが、さすがに私の魔力にはついていけなかった。百年という約束の時が近づくにつれ、私の魔力がほとんど回復し始めた頃には、溢れ出す魔力で心身に異常を来たし始めていた。それをコントロールするためにジンはさらに荒々しくなり、大声を出したり暴れたりすることでストレスを解消していたんだ。中で私は哀れに思ったが、それでも彼は私に主導権を譲ろうとはしなかった」
「……まさか、それで俺を軟禁したんじゃないだろうな。八つ当たりする為に」
「それは私の意志じゃないよ」
どっちにしても、そうらしい。マルシオはもう呆れるような悲しいようなで、文句の言葉も出てこない。だが靄はまだ晴れない。
「ジンはあんたが死んだと言っていたぞ」
「あの状態じゃ死んだも同然だったからね。肉体を持たない魂は、所謂幽霊のようなものだ。復活したところで待っているのはノーラとの報復戦。復活と同時にノーラに勝る力を得なければ、どうせ死ぬ。それは今も変わらない」
その言葉でマルシオは俯いた。
「……で、その力は得たのか?」
「さあ。使ってみないと分からない」
それが何か聞きたかった。だが、聞けなかった。
「とにかく」マルシオは顔を上げて。「あんたとジンは同一人物だったんだな」
「そういう事」
そこで、背後からその会話を聞いていたティシラが足を止める。
「……じゃあ、じゃあ」
その顔は真っ赤で震えていた。何事かと思うが、マルシオだけはまたティシラの下らない発言が飛び出ることを予測していた。目を細める。
「……私は、何も知らないで本人に告白していたの……?」
ティシラはジンに「クライセンの花嫁になる」のだと連呼していたことを思い出す。恥ずかしくて逃げ出しそうだった。両手で顔を覆って、ああ、と嘆く。
そんなティシラに、クライセンは足も止めずに一言。
「気にしてないよ」
ティシラには残酷な言葉だった。長い時間をかけて培われてきた、深く遠い想いが、あっさりと振られてしまったようなものだったのだ。底抜けに前向きなティシラでさえどう受け止めていいのか迷っている内に、マルシオが嫌な顔をしてその話を終わらせる。
「そんなことより、俺はあんたのした事は許せないからな」
呆然としているティシラは置いていかれる。ライザは彼女の様子を気にしながら、先に歩いていく二人についていく。
「何の事?」
「あんた、俺にリヴィオラを投げつけたじゃないか。ふざけるにも程があるだろ」
「あれは本心だよ」
意外な言葉に、マルシオは胸が痛んだ。
「君ならあの石を持ってもいいと思ったんだ」
「……俺は、故郷を捨ててきたんだ」
「そんなことは私には関係ない。君は受け取らなかった。それまでだ」
マルシオはクライセンの冷たい目を睨み付ける。
そんな二人の様子を見ていたティシラは顔を上げ、恥ずかしさとは別の感情が込み上げてきていた。
それは嫉妬だった。ティシラの目には喧嘩しているはずの二人が妙に親しそうに見えたのだ。
少し考えてみる。今までティシラがクライセンに感じていた違和感は、彼がジンだったことが分かって解決している。何よりもクライセンに抱く恋心が彼女の言動を制御していた。それももう本人にばれている。今更隠すことも何もないではないか。
過ぎてしまえばティシラにとってはどうでもいいことだった。考えることを止める。すると急に黙っていられなくなり、いつもの元気を取り戻して二人に走り寄って間に割って入った。
「ちょっと! あんた、なんでそんなにクライセン様と込み入った話してんのよ」
「何だよ、お前。何が『クライセン様』だ。こんな奴、ジンより性格悪い」
「なんてこと言うのよ。それ以上クライセン様を虐めたら私が許さないわよ」
「どんな角度から見たらそんな解釈ができるんだ。この低脳魔女。立ち直りが早過ぎるんだよ。たまには三日くらい落ち込んでみろ」
「人の勝手でしょ。そりゃ最初はいろいろ驚いたけど、一緒にいて分かったのよ。やっぱりクライセン様は世界一の魔法使いで、世界一かっこいいのよ」
「お前、ほんとに馬鹿だな」
「あんたこそ、何を粋がって魔法王に楯突いてるのよ。そのうち四肢を引き裂かれるわよ」
「グロい例えを出すな。大体お前、あいつはジンだぞ。今まで散々酷い目に合わされてきたのに、何とも思わないのか」
「ちゃんと話聞いてたの? 事情があったんじゃない」
「話を聞いてないのはお前だよ。虐めや虐待に正当な理由があってたまるか」
「あんた、心が狭いわよ」
ティシラはマルシオを押しのけて、クライセンに体を寄せる。
「クライセン様」無邪気な笑顔を向けて。「私、役に立ちました?」
「うん。よくやってくれたよ」
クライセンは心無く応える。それだけでティシラの機嫌はすっかりよくなった。今までそのやり取りを微笑ましく見ていたライザと目が合う。
「そうだ、ライザさん。あなたは大丈夫なんですか。こんなところまでついてきて……」
ティシラは自分たちを手引きしてここまで来てしまった彼女の身を案じた。ライザは不安を隠し切れないが、取り敢えず微笑む。
「ええ、落ち着いたら城へ帰ります。それよりまずはあなた方を安全な場所までお送りいたします」
不揃いな魔法使いたちの視界の遠く向こうに、エンタナの森が広がっていた。一同は歩みを止めずにそこへ向かっていった。
5
ティオ・メイでは壊れた町のあちこちの修復で慌ただしかった。
兵たちは、オーリスの指示でお尋ね者は捕獲したと嘘の情報を町中に流し、人々を安心させた。何者だったのかなど当然の質問もあったが、それは一切極秘であり、だがこれ以上は危険はないと説得された。国王を信頼している人々はそれを信じ、すぐに落ち着いていつもの生活を取り戻していた。兵たちも修復を手伝っているが、口数は少なかった。
お尋ね者を取り逃がしたこと、それを見逃がせとの命令を王が下したこと。そしてその事実を民に隠して嘘をついたことで肩身が狭かったのもあるが、何よりも国に迫る得体の知れない恐怖を感じ取っていたからだった。
もちろんそのことは誰も口にしなかった。兵たちのほとんどにも真実は明かされていない。今はまだ騒がずに待てとだけ言われている。混乱を防ぐためのその配慮がさらに不安を募らせる。
城内の王室では、グレンデルとオーリスが二人きりになっていた。
「どう思う」
グレンデルが漠然と問いかける。オーリスにはその意味が分かる。
「前兆でしょう」
二人は口にするのも恐ろしいと思っていた。まるで夢──と言っても、悪夢だが──のような出来事が確実に現実になろうとしていたのだ。
敵が襲ってくれば全力で戦えばいい。しかし、それに太刀打ちできないうちに、いつの間にかこの世が滅んでしまうのかもしれない。この世の生きる者のすべてが平和と幸せを望んでいる。なのに、なぜ苦しみながら殺されなければいけないのだろう。
グレンデルは答えの出ない疑問を考えられずにはいられなかった。オーリスも気休めの言葉すら出てこない。
「とにかく」オーリスは冷静を装い。「ダラフィン殿の帰りを待ちましょう」
「そうだな」グレンデルは言いつつ、心はここになかった。「クライセンはどこに行ってしまったのだろう」
「彼は道に従って行きました」
「奴の道とは何なのだ。私を愚弄し、背いてまで貫くに値するものなのか」
「それは私には分かりません。しかし彼の道は彼自身が選ぶでしょう。王よ、あなたもそれを悟られたから彼を見逃したのでしょう?」
「さあ、自分でもよく分からないのが正直な気持ちだ。しかし事はもう動き出している。もう運命に身を委ねるしかないのだな」
「生き延びるも滅びるも、それが我らの道です」
「だが足掻くことはできる。例えどんな醜態を晒したとしても、私は死ぬまで足掻くぞ」
「ええ、私もお供いたします。そして国の民の心も、同じくして常にあなたと共にあります」
二人の強張っていた顔が少し緩んだ。グレンデルはしばらく沈黙していたが、思い出したように顔を上げた。
「そうだ。私の息子は、トレシオールはどこだ」
「王子は……」オーリスは困ったように。「まだお帰りでは……」
「そうか」グレンデルはため息をつく。「私のたった一人息子、たった一人の跡継ぎなのに……いや、奴は私の後など継がぬのかもしれぬな」
「王子はとても賢い方です。きっと賢明なお答えを出されることでしょう」
「だといいが」グレンデルはちらりとオーリスに目をやって。「ところで、そなたの娘はどうした」
オーリスは肩を揺らす。それを見逃さずに、グレンデルは意地悪く続けた。
「ライザは、そなたの一人娘。いずれはそなたの後に続き、国に貢献するであろう有能な魔法使い。そして、我が息子の婚約者でもある。それだけ大切な娘は、一体どこで何をされているのだ」
「ライザは……」オーリスは俯いたまま。「あれもまた、自分の道は自分で選ぶでしょう。強制はできません。しかし私は娘の幸せを心から願っています」
「私も彼女には幸せになってもらいたいと思っている」
「有難き、お言葉……」
「だが……反逆者の手引きをしていては、遠い道かもしれぬぞ」
オーリスの心臓が縮み上がった。
「そ、そのようなこと……!」
「報告によれば、反逆者は四人だったそうだ。クライセンと赤と白の魔法使い。そして、ブロンドの水使いが加わっていたと。私の知るところでは、思い当たるのは一人しかおらんのだが……」
オーリスは胸を痛めた。これ以上問い詰められたら言い逃れられない。
自分の立場など問題ではなかった。何よりも娘の、せっかく手に入れた大切なものが剥奪されてしまうかもしれない。
ライザはまだ若い。自分の尻拭いで彼女の一生を傷つけてしまうかもしれない。それでも娘は決して誰も責めずに黙ってそれを受け入れるのだろう。
それがオーリスをさらに辛くさせた。軽率だった。すべて自分のミスだ、と目を閉じた。
そんな彼の背中を見ながら、グレンデルが口の端を上げる。
「いや……まさかな。そなたの娘が……考えられぬ」
オーリスが顔を上げた。グレンデルは王座に深く座り直した。
「早くトレシオールとそなたの娘が結婚して、孫の顔でも見せて欲しいものだな……未来へ続く新しい命をこの腕に抱ける。そんな時間は、果たしていつ訪れるのだろう」
オーリスは黙っていた。その言葉は彼の心を貫いた。
グレンデルはすべてを悟り、良心で覆い隠してくれると伝えていたのだ。オーリスにとって何よりも嬉しく、そして辛いものだった。
今はただ、クライセンに望みを託すしかなかった。そのためには自分たちも命をかけて大切なものを守らなければいけない。そう自分に言い聞かせていた。