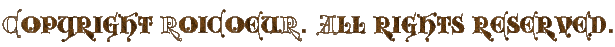第8章 精霊の森





1
クライセン一行はエンタナの森を歩いていた。
とても古い森で人の手はついておらず、何百年もかけて自然に育った大きな森だった。
特に何の変哲もないが、森は横長に広がっており、最短で抜けるにも休まず歩いて一日はかかる。方向を見失うと迷って出られなくなり、そのまま行方不明になる者も居ると言う噂があり、人々は必要がなければ中に入ることはなかった。
木々はのびのびと育ち背が高い。昼間は木漏れ日が差し込み、美しいほど輝いている。だが、夜になると光という光は失われて闇に閉ざされる。
いつの日か、この森をモデルに「森の精霊コルテ」という寓話が作られた。
エンタナの森の一番深いところにそれは大きな大きな古い木があり、そこにはコルテという子供の姿をした精霊が住んでいる。
コルテはとても寂しがり屋で、人々を迷わせては訪れた者を虜にし、そこに繋ぎ止めて一生遊んで暮らすのだという話だった。
その話の出所は何年も昔の、ある村の子供にあった。その子供は生まれついて持病を持っており、大人になれないうちに死んでしまう運命を背負っていた。子供が自分で本を読めるようになった頃には既に床に伏していた。
哀れに思った母親が危篤の子供を抱え、この森に入って二度と帰ってこなかったと言う。
人々は行方不明になった母子の霊が今も森を彷徨い、子供の遊び相手を求めているのだと噂した。
だが決して悪い霊だとは言われていなかった。きっとコルテは今も母親と一緒に、森の中で幸せに暮らしているのだと信じられていたからだ。
時が経つにつれてそこには楽園があるのだと言われ始めた。今でも不幸を抱えた子供や親など、この世を儚んだ者が密かに楽園を求めてここを訪れる。コルテはやり場のない寂しさを救ってくれる精霊として描かれ始めた。
ただし、少々悪戯好きだと付け加えられて。
まだ日は高かった。一行はできるだけ昼間のうちに先に進もうと、休まずに歩き続けていた。
「クライセン様」ティシラが辺りを見回しながら。「『精霊コルテ』は本当にいるんでしょうか」
「なんだい、それは」
クライセンは興味なさそうに答える。
「寂しがり屋の子供の霊ですよ」
ティシラはコルテの話を語りだした。クライセンは聞いているのかいないのか分からない態度で終わるのを待っていた。そして、すっかり話し終えてから、間を置かずに一言。
「知ってる」
一同は沈黙する。知ってるなら早く言えばいいのに、と全員が思った。
「そんなものはいないよ」
そう続けるクライセンの態度は、悪意は感じられないが取り付く島もない。さすがのティシラも困っている。間が持たず、ライザが口を挟む。
「確かに、いると言う証拠は出ていませんが、夢のある話ですよね」
「大切な人を失った者の楽園か」ティシラが気を取り直して。「人間はそうまでして何かに縋らなくちゃいけないのかしら」
「悲しいけど、きっとそれで救われた人はいると思いますよ」
「見えないからこそ縋るのよ。私には理解できない。コルテのモデルになった子供はもう土に還っているのよ」
「それでも、彼が生きた証しはこうしてここに残っています。母親の愛があったからこそです。生きるとはそういうことなのではないでしょうか」
「人間は寿命を持って生まれてくる。それをただの理想だけであやふやにするべきではないと思うわ。時間が限られているからこそ得られるものがあると思うの。生きてる者は死んだ者に自分の罪を擦り付けようとしたがる。でも本来は死んだ者の残したものを生まれた者が受け継ぐべきだと思うの。人は弱いから、つい辛いことを何かのせいにしたくなる。その標的を死者に向けるなんて、魂が安らかに眠れるわけがないわ」
「ティシラさん……」
ライザは初めて聞く意見に驚いていた。ティシラは人間と視点が違う。ライザはまだそれを知らずに、彼女の話を掘り下げようと口を開こうとする。が、そんな雰囲気を平気で壊す者がぼそりと呟く。
「ただの作り話じゃないか」
マルシオがつまらなそうに水を差した。ティシラは素早く反応する。
「あんたってなんでそんなに夢がないのよ」
「ありもしない話で盛り上がって何が楽しいんだ」クライセンのときとはえらい違いだなと思いつつ。「お前はいつもお気楽で、どこだろうと楽園気分じゃないか。理想郷なんて必要ないだろ」
「ありもしないなんて、死者への冒涜よ。今に罰が当たるわよ」
「何が、死者への冒涜だ。魔族のくせに」
「なんですって……!」
すると、そこでライザが大きな声を上げる。
「魔族? ティシラさん、あなた魔族なんですか!」
「ええ、まあ」ティシラは言いにくそうに。「生まれはね……そうだけど」
「どうりで。あなたの持つ神秘的な雰囲気といい、特殊な力といい、それで納得がいきます」
ライザは決してティシラを偏見の目では見なかった。それどころか、初めて出会う魔族に感激して目を輝かせている。嫌な気持ちはしないがティシラは複雑な心情になり、黙ってしまった。
そんな空気を読んで、マルシオはやばい、と少し足を速める。ライザが自分にもなにか聞いてくることを逸らそうとしたのだ。
察しの通りライザはマルシオに声をかけようとした。だが、彼の「構わないで欲しい」という態度を受け取り、不思議そうな顔をしてその話を終わらせた。
魔法使いは何かと謎や秘密が多い。ティシラとマルシオのそれは少し違う感じもしたが、魔法界で生まれ育ったライザは余計な詮索はしないように教育されている。理解はあった。
何となく空気が重くなってしまったが、ライザは構わずに周囲の木や花を見ながら、緩やかに話題を変える。森の生態や薬草や自然界の理力についてなど。それぞれの込み入った事情に関することはお互いに聞かなかった。どんな縁があって出会った一行なのかはまだ分からない。野暮なことはなし、と心地いい距離を保っていた。
クライセンは三人のやりとりには一切興味を示さず、黙って辺りの妙な匂いに集中していた。目の前は艶のある緑が覆い茂り、それが太陽の光を反射して輝いている。その隙間を縫って優しい風が流れており、汚れなどどこにも見えない。
なのに、彼だけが不吉な何かを感じ取っていた。
(昼間はいい。だが……)嫌な匂いがする。(夜は危険だ)
2
森の深いところで日は暮れた。
夜が明けるまで一休みすることになった。一行は木々の間にできるだけ広い場所を探して、そこに腰を降ろした。クライセンの指示で薪を集めて火を熾す。朝まで火を絶やさないように順番で見張りを立てることにした。
最初はマルシオだった。だが、クライセンは寝る様子もなく、静かに暗闇の中に歩いていく。
「どこ行くんだよ」
マルシオがそれに気づいて声をかける。
「偵察」
「何か気になることでもあるのか」
「別に」
「ちゃんと休めよ」
「余計なお世話だ」
マルシオは愛想のない彼の態度にむっとする。しかし、確かに自分が心配する必要もないだろうと、闇の中に消えていくクライセンを黙って見送った。すると離れた木の根元に寄りかかっていたティシラが体を起こす。
「マルシオ、クライセン様は?」
「知るか。どこかに行ったよ」
「そんな。まさか私たちをおいて行ってしまうんじゃ……」
マルシオもまさかと思う。そう言えばクライセンは自分たちを連れとして認めたわけじゃない。
このままはぐれてしまっても誰も文句なんか言える立場ではなかった。しかし、だからと言って彼に縄をつけて四六時中見張るなんてこともできるはずがない。冷静に考えると、そんな理由もなかった。
「私、探してくる」
「よせよ。もうこれ以上無理してくっついていても……」
「駄目よ。あんたはよくても私は彼の恋人なのよ。離れるわけにはいかないわ」
「ふざけてる場合か」
「私は真面目よ」
ティシラは聞く耳を持たずに闇の中に歩き出す。
「よせって。迷うぞ。それに、今のうちに休んでおけよ」
「うるさい。私はもともと夜行性なの。夜も闇も怖くないわよ」
そうだったな、とマルシオはため息をつきながら、何の為に見張りを立てたのかよく分からなくなった。マントに包まり、横になっていたライザも心配して起き上がる。
「大丈夫なんでしょうか」
「ああ……気にしないでください。あいつらは普通じゃないから。俺はここにいますし、何かあったら起こします」
「ええ」ライザは不安そうな顔をしながら。「お願いします」
そう言ってライザは再びマントに顔を埋めた。
辺りはしんとなる。火の燃える音だけが響き、森の中へ消えていった二人の足音さえ聞こえない。
まるで死んでいるようだった。風さえ靡かないし何の気配もない。マルシオはじっと、吸い込まれるように炎を見つめていた。
ここには何かがいる、と思った。呼吸をしないものだった。ここに迷い込んだ人々の霊が今も彷徨っているのか。それともコルテが遊び相手を渇望して探し回っているのか。
そんな事を考えている内に、マルシオは闇に捕らわれそうになった。意味もなく孤独が満ち溢れてきた。マルシオは今まで一度も寂しいなんて思ったことはなかった。誰かに何かを求めたことも。
そうだ、いつも一人だった。そんなことを思う。そして楽園と言う言葉を思い出す。そこには一体何があるのだろう。そこに行けば本当にすべての苦しみから解放されるのだろうか。
だが苦しみとは、一体何なのだろう。そして、幸せとは? 人がたくさんいて、いつも笑っているのだろうか。おいしい食べ物が尽きることなく溢れ、色とりどりの果実に囲まれているのだろうか。人間の求める幸せなんてそんなものなのだろうか。
それは映像として頭に浮かぶが、まるで不完全さを表すように白くぼやけている。答えは出なかった。出ないことを分かっていても考えずにはいられなかった。
どれくらいの時間が経っただろう。
マルシオはまるで今まで寝ていたかのように我に返った。まだ火は消えてはいないが、だいぶ薪の量が減っている。
まさか居眠りをしてしまったのかと周囲を見渡すが、そんなはずはなかった。自覚はしている。まるで長い間、幻を見ていたような気分だった。
意識をはっきりとさせると闇はさらに深くなっている。マルシオはその暗い空間に目を捕らわれた。何も見えない。が、何かが居る。マルシオは立ち上がり、ライザに近寄る。彼女はすぐに目を覚ました。
「どうしたんですか」
マルシオは何も言わなかったが、ライザも彼の捕らわれている目線の先の暗闇に何かの気配を感じた。ゆっくり体を起こしながら息を潜める。
「お二人は」ライザは小声で。「まだ戻られてないんですか」
「さあ」マルシオはこの期に及んで皮肉る。「楽園でも見つけて子供と遊んでいるんじゃないか」
何かが蠢いている。その不気味な音は四方から近づいてきていた。
どうやら囲まれているようだ。邪悪なものだということだけは分かる。闇の中を目を凝らして探るが何も見えなかった。
マルシオはこんな時にこそ夜目の利くティシラがいればいいのにと思う。いや、それよりティシラとクライセンはどこに行ったんだろう。あの二人が簡単にどうなるとも思わないが、無事だろうか。
キキキ、と奇妙な声が聞こえた。人ではないらしい。
火を警戒しているように感じられる。いや、火ではなく、明かりが嫌いようのだ。
マルシオはライザから少し離れて、手の中に光の玉を作り出す。そしてそれを暗闇に向かって放った。
白い光が弾け、辺りが照らし出される。二人は絶句する。そこには、今までみたことのないものが光に驚きながら体をくねらせていた。
それは腐った人間、つまり「死体」だった。
ほとんど原型を留めていない。肉は剥げ落ち、あちこちから変色した骨が覗いている。その体には土がこびりついていた。死体がキキ、と声とも軋みとも判別ができない奇怪な音を出している。その横でぼこぼこと足元の地面が盛り上がった。そこからまた別の死体が迫り出していた。
「……ゾンビ」
マルシオが漏らすように呟く。震えている。恐怖からではなかった。
こみ上げてくる憎しみや怒りがそうさせていた。ライザも息を潜め、目を細める。恐れというより、哀れみを感じていた。
「許せない」マルシオが唸る。「一体誰がこんなことを!」
その時、二人の背後で木の葉の揺れる音が聞こえた。二人が振り向くと、木の上からクライセンが舞い降りてきた。マルシオが大声を上げる。
「これはどういう事だ」
クライセンは姿勢を正しながら、早口で答える。
「この森で彷徨い、朽ち果てた者たちの死体だ。罪はないがもう死んでる。全部叩き潰すんだ」
「何だと」
「でなければ私たちが食い殺される。死者を敬いながらこの夜を凌げると思うか?」
「それより」ライザが警戒しながら。「ティシラさんは?」
「会ってない。その辺にいるだろう」
「そんな悠長な……」
ライザの心配を余所に、森の奥で大きな爆発が起こった。「彼女だ」と全員が悟った。
「あいつ、派手にやってるな」
「怯えているんですよ。私たちも戦いましょう」
とにかく、今は状況をゆっくり検討して作戦を練っている暇はなかった。クライセンが簡単な指示を出す。
「分散しよう。ティシラは南方にいるらしい。マルシオは北、ライザは東へ。私は西方へ行く。敵は多勢だが強くは無い。一通り片付けたらここに戻ってくるんだ」
マルシオは素直には頷かなかった。
「本当に戻ってくるのか」
「一応、状況の把握と、皆が無事かどうかを確認しておきたい」
マルシオは、クライセンが思ったより人間らしいことを言ったので、黙って言う事をきくことにした。ライザに目で合図をして、闇の中へ駆け出した。ライザがふっと振り返ると、クライセンの姿も気配も煙のように消えていた。
3
ティシラは一人でゾンビと戦っていた。結局、まったく見当違いの場所で迷ってしまっていたのだ。
「気持ち悪い! 近づかないで」
青ざめながらも遠慮なく死体を蹴散らしている。攻撃するたびに飛び散る肉片は嫌な匂いを漂わせながら散乱している。それは悍ましい光景だった。いくら倒しても次から次へと襲ってくる。
先は暗く、この行列がどこまで続いているのか想像つかない。
「これじゃキリがないわ」
ティシラは近くの木に背をつけて、手の中に熱を集める。
森が火事にならない程度の温度を保たなければと、集中する。いつもより慎重に長く溜め、火の玉は眩しくなっていく。ティシラが両手を広げると、高熱の光は弧を描いて波紋となった。
それに触れたゾンビは煙を出してぼろぼろと崩れ落ちていく。周りの木々は少々焦げるが、それ以上の損傷は負わない。視界はすっきりしたが、それも一時の場凌ぎだった。
敵は恐れることなく、また体を引きずって寄ってきている。ティシラは今の隙に取り敢えずその場を離れる。
「皆は無事なのかしら」
そう思いながら走っていると、どこかで魔力を感じた。それで皆も戦っているのだと悟った。確かに、こんな死体ごときでどうこうなる面子ではなかった。
だが一つの心配は拭いきれない。マルシオだ。彼のことをよく知るティシラは、彼が感情的になってはいないかと気になった。
このゾンビの襲撃は自然現象なんかではない。ここで迷い、死んでいった者がいるのは確かだが、彼らはただ朽ち果て、静かに眠っていただけなのだ。問題はそれを呼び起こして操っている者がいることだった。
その者の気配は近くには感じられない。遠隔魔術を使っているのだ。それだけでかなり力を持った術師だと分かる。
きっとマルシオは怒り、闘志に迷いを持っているに違いない。何もなければいいけど、とティシラはゾンビを蹴散らしながら思った。
ティシラの心配通り、マルシオは苦戦していた。及ばないわけではない。だが死体を切り刻むことに強い嫌悪感を募らせていた。誰だっていい気持ちはしないだろうが、マルシオはそこにない魂に懸念があったのだ。
「俺はこんなことをするために魔法使いになったわけじゃない」
マルシオの言葉は誰にも届かない。そう思った。
「ちくしょう」ここにいない、何者かを心から憎み。「出て来い! こんなことをして許されるものか」
その苛立ちは募るばかりだった。マルシオは全身から眩しいほどの光を放ち、ゾンビを溶かしていく。
その光は聖なるものだったのだが、彼らは浮かばれているわけではないのだ。それがマルシオをさらに困惑させた。なんて無力なんだと、悔しさを噛み締める。
(俺は……一人では何もできないのか)
マルシオはさらに強い光を放つ。それは森の一部が真っ白に掻き消されるほどのものだった。
力が制御できないでいた。焦れば焦るほど憎しみが増し、冷静さを欠いていく。目を吊り上げながら大股で歩を進める。
すっと光が収まる。マルシオは足を止めた。
「これは……」
急に目の前が開けた。まるで、今そこに現れたかのように。
マルシオは今までに見たことはおろか、想像したことすらない大木に目を奪われた。古い、古い木だった。それは静寂に包まれていた。
さっきまでの死体に囲まれていた悍ましい光景とは別世界だった。マルシオは怒りを忘れ、辺りを見回す。周囲にはゾンビの姿も、その気配もなかった。ここだけ結界のようなものに守られている。
再び大木を見上げる。ゆっくりとそれに近づきながら、無意識に呟いた。
「……コルテ」
あの話は本当だったんだろうか。いや、まさか。ただ条件が重なっただけだ。そう思おうとした。
しかし、それはあっさり裏切られる。
誰かがいる。大木の足元に。死体ではない。だが、生きている者でもなかった。小さな子供だった。密かに立っているその少年は悲しい目でマルシオを見つめた。マルシオはそれに魅入られた。間違いない、と思う。
「コルテ? 君は森の精霊か」
マルシオはゆっくり少年に近づく。少年は寂しく微笑んだ。
(みんなには、そう呼ばれている)
その声はマルシオの心の中に響いてきた。少年は今にも消えてしまいそうなほど朧げだった。
「そうか。君は昔、母親に連れてこられた子供だね。どうして今でもここにいるんだ。ここが楽園だと言うのか。まさかゾンビは君の仕業じゃないだろうね」
(違うよ。ここは楽園なんかじゃないし、みんなが思うような綺麗なところじゃない)
「……君もここで迷っているんだね」
(うん。みんな迷ってしまうんだ。僕にはどうすることもできない。あなたのような人を待っていた。どうか、助けてください)
「……俺を待ってた? なぜ」
少年は俯いて涙を流した。
すると少年とマルシオの間の地面がぼこりと盛り上がった。マルシオは体を引いた。
土の中から死体がゆらりと立ち上がる。そのほとんどの肉は腐れ落ち、削がれた骨がむき出しになっている。もちろん眼球など残っているはずもないが、その窪みの奥には恐ろしい怨念の光が灯っていた。
今までの、ただ操られていたゾンビとはわけが違った。死体は黙ってマルシオに向き合う。全身から発せられる凄まじい怨恨の念に、マルシオはぞっとする。
「あなたは」マルシオは恐る恐る、答えもしない死体に話かける。「この子の母親……だね」
(そうです)代わりに少年が答える。(お母さんはずっと僕の傍にいてくれました。僕のことだけを思って……たくさんの友達を連れてきてくれました)
少年は泣いている。マルシオは少しずつ、体の内側から何かが湧き上がってきた。微かに手が震えている。それを抑えるように拳を握った。
(だけど……お母さんが連れてきた友達は誰も話してくれないし、笑ってもくれませんでした)
「母親が……ここに迷い込んだ人を殺していたのか」
(お母さんは僕を愛してるし、僕もお母さんが大好きです。だから……)
少年は顔を上げて、微笑んだ。
(殺してください)
「……な」
(もう僕のために人が死ぬのを見たくありません。お母さんにもこれ以上罪を重ねさせたくないんです。お母さんがいくら友達を連れてきても僕の寂しさは埋められなかったし、そんな僕を見てお母さんはさらに悲しみました。もうこんなことを続けて何十年も経ちます。次第にお母さんに僕の声は聞こえなくなりました。僕は本当に一人ぼっちになってしまいました。僕はお母さんだけでもいてくれれば十分だったのに……お母さんは遠くへいってしまったんです。もうここにいるのは、心のないただの殺戮者です)
マルシオは乱れそうになる呼吸を整えた。話の意味は分かるが、まだ頭では理解できない。
「……君たちは、何をしたか分かっているのか」
少年は答えない。ただ、泣いているだけだった。
「ここで罪のない人々の命を無作為に奪い、結果、その死体が邪悪な術師によっていいように操られているんだぞ。そして、始末に負えないから、殺してくれだと?」
マルシオはどんどん声が大きくなる。
「君たちは死んだんだ。生きた人間の命を勝手に奪って、捨てて、さらに自分を苦しめて……そんなことをして本当に楽園なんかあると思っていたのか。なぜ寿命をまっとうできない。肉体を失ったお前たちが罪を犯せば、それを贖う方法なんてないんだぞ。今更殺してくれなんて、それで楽になんかなれやしないんだ」
(……分かっています)
「お前たちの魂はここでないどこか、もっと暗くて寒いところに、永遠に閉じ込められることになる。それがどれだけ辛く苦しいか、分かっているというのか」
(当然の報いです。だけどこれだけは分かってください。僕たちは寂しかったんです)
「もっと寂しい思いをするんだぞ」
(はい。でももうこれ以上ここにはいられません。どうか僕たちを消し去り、人々にはここが楽園だと言わせてください)
「何も、なかったように?」
(それがせめてもの救いです。僕たちはこれからもずっと語り継がれるのです)
「そんなこと……」
(勝手なのは分かっています。でも……あなたならできるはずです)
「俺なら……?」
(お願いします……聖なる光の守護者様)
マルシオは唇を噛み締めた。自分にならできる──マルシオの本意はこの母子を救うことだった。ここで母親を滅ぼしてしまえば二人の魂は永遠の責め苦を受けるのだろう。
当然の報いかもしれない。だけど、と思う。罰を与えることが自分にできること、為すべきことなんだろうか。
違う。これから人々がこの母子をなんと言おうと、今目の前にいるこの哀れな魂を救うべきなのではないだろうか。
どうしてこの母子はここまで来てしまったのだろう。この二人もまた、道に迷っただけではないのか。
だからといって、許されるかと問われれば頷けない。しかし、ここにある彼らの罪とは永遠に許されないほど蓄積されてしまっているのか。罰を与えることで、一体誰が救われるのだろうか。
4
母親の死体がマルシオに飛び掛ってきた。マルシオは不意を突かれ首を掴まれるが、慌てて振り払う。
(殺してください……)
少年は泣き崩れた。母親はぐちゃぐちゃと嫌な音を立てながら再び襲いかかってくる。
マルシオはその腐った手に捕まり、首を絞められる。凄い力だった。抜け出す方法はいくらでもあった。しかしその手から母親の恐ろしい怨念がマルシオの心の中に流れ込み、それに捕らえられてしまったのだ。力が入らない。
(やめて、やめて、お母さん)
少年が呼びかけるが、全く届かない。手遅れだった。
母親に少年の声が聞こえるほどの理性が残っているのならこんなことにはなっていなかったのだから。
マルシオの力が抜け、意識が遠のく。崩れるように膝をつく。母親が被さり、止めを刺すように圧し掛かってくきた。
少年は動かずに、泣きながら「やめて」と繰り返している。マルシオにはその声も遠のいていった。
朦朧とした意識の中で「やはり、殺すべきだったのだろうか」と掠めた。だがもう遅い。
マルシオは死を覚悟した。自分の判断が今後、どう影響していくのか、短い時間にいろんなことを考えた。そして、ふっとこんなことを思う。
(……俺が死んだら、誰か悲しんでくれるかな)
その時、マルシオは強い衝撃で弾き飛ばされ、無防備なまま地面に転がった。
苦しみから解放され、地に伏せたまま咳き込む。
ゆっくり目を開くと、そこにはクライセンが立っていた。
母親は離れたところでもがきながら興奮している。片手が千切れ、肉が飛び散っている。クライセンの投げた石が彼女の手ごと打ち払ったのだ。母親は落ちた片手など気にもせず体勢を整えるが、落ち着かない様子で肩を揺らしている。
怯えていたのだ。突如現れた魔法王の、その圧倒的な魔力に。ギイギイと音が漏れている。喉を鳴らして威嚇しているのだ。
「無駄だよ」クライセンは低い声で。「私はそこの軟弱魔法使いと違って、殺戮人形への情なんて欠片も持ち合わせていないんだ」
クライセンはマルシオの横を通り過ぎ、母親に向き合う。
母親が怯えないはずがなかった。マルシオは彼の放つ冷たく、重い空気に寒気を感じた。いつもの意地悪なそれでも、ジンの真似をして怒鳴ったときの迫力とも、どれとも違う。
怖い。マルシオはそう、心の底から思った。
母親の怨念の光がさらに強くなった。感情のないはずの彼女が警戒している。
クライセンのその瞳には、ぞっとするほどの強い魔力が灯っていた。目に見えるものではなかったが、彼女の積年の呪いよりも、クライセンが持つものはそれ以上に遠く、深いものだった。
クライセンはその目をマルシオに向ける。マルシオは体を揺らした。
「何をしている」そこに情はなかった。「君はこんな腐った死体に殺されるためにここへきたのか」
クライセンは冷たい目線を少年に移す。
「こんな小賢しい結界なんかで身を隠していたとは。君の仕業だね。この期に及んで救われようなんて……茶番はもう終わりだよ」
少年も怯えている。しかし、必死で訴えかけた。
(僕たちはもう眠りたいんです)
「エリオール」
クライセンのその一言に、少年は目を見開いた。
「忘れたか? 君の名前だ」
(エリオール……)
「君はここに長く居過ぎた。自分の名前さえ忘れてしまうほどに。もう君がここにいる理由はないはずだ」
(……殺してください)
「もう君はエリオールではない。ここに、この聖なる大木の元にいていいのは森の精霊だけだ。エリオールの魂など意味はない」
少年はまた泣き出した。マルシオが立ち上がり、ふらつきながらクライセンに近寄る。
「……どいてくれ」
「君に何ができる」クライセンは冷たく放つ。「黙って寝てろ」
「その子は俺に頼んでいるんだ。あんたこそ引っ込んでろよ」
「断る」
「何だと」
「君にも、そこにいる子供にも私に指図する資格などない」
「偉そうに。あんたは殺すしか脳がないのか」
クライセンに表情はなかったのだが、勢いでついて出た憎まれ口のせいか、突き刺さりそうなほど鋭く睨まれているように感じた。しかし、マルシオは更に反発する。
「悔しかったら救ってみろよ。ええ? 偉大な魔法使い様よ」
険悪な空気が流れた。黙って自分を見下ろすクライセンの目に飲み込まれ、気を失いそうだった。だが、逸らすものか、とマルシオは彼を睨み返す。
「ふうん」クライセンは、にっと笑う。「なら、譲ろう。どうぞ、心優しい魔法使い君」
そう言いながらクライセンは体を捻り、マルシオに道を開けた。マルシオは戸惑いながら、足を一歩前に出す。
少年と母親を交互に見る。少し息苦しい。それは先ほど、母親に首を絞められたからだけではなかった。極度の緊張からきているものでもあった。
マルシオは心を決める。失敗すれば、死ぬ。
だが魔法王に大口を叩いた以上、中途半端なことはできない。なぜそうまでして口出ししたかったのか自分でも分からない。自分より遥かに力を持った魔法使いがここにいるのに、彼に任せればきっと間違ったことだけはしないだろう。
クライセンが母子に何をするつもりでいたのかは、もう知ることはできない。何のヒントももらえないまま役目は自分が背負うことになった。
怖かった。きっとクライセンはこの母子の魂をどこかに、何らかの方法で消し去っていたのだろう。それでよかったのかもしれない。
だがマルシオは納得いかなかった。だから、止めたのだ。
何のためにここにきて、魔法使いになったのか。その答えを今すぐ出す必要はない。いや、出るとも思えない。何も分からない。
理由はひとつ。自分がまだ幼く、未熟だから。経験も知識もないからだ。
悔しい。それでも後悔だけはしたくなかった。その思いだけがマルシオを突き動かしていた。
マルシオは姿勢を正し、胸の前で手を組む。そして目を閉じ、祈った。マルシオの体がぼんやりと光に包まれる。それは次第に強くなっていき、まるで波紋を描くように広がっていく。それはどこまでも止まらない。どこまでも、どこまでも。風もないのに木々がザワザワと歌いだした。
その光は森のすべてを包みこんだ。違う場所でティシラとライザは足を止めてその光景を見つめていた。光に包まれたゾンビたちは次々と砂のように崩れていく。
不思議と、それは安らかに見えた。
だがティシラはそれを快く思わなかった。どうやら嫌な予感が的中したようだ。
「あのバカ……! 一体何やってるのよ。たかだかゾンビ如きに」
ティシラは光の発信源を探して走り出した。
マルシオはじっと祈り続けていた。
持つすべての魔力を、少しずつ放出していたのだ。呼吸が乱れ、額に汗が流れる。体が震え出すがそれを必死で抑えている。今にも倒れそうだった。
そして、苦しみか悔しさからか、自分の死を覚悟してからか、涙が頬を伝った。力を振り絞り潤む目を開ける。少年は未だ泣き続け、母親は奮えながら唸っている。
「エリオール……」マルシオは少年に語りかけた。「君は『コルテ』だ」
少年は顔を上げた。
「エリオールの名を忘れてしまったのなら俺が新しいものを与えてやる。光の恩寵を受け、精霊になるんだ。物語のように森の守り手となれ。それが、君にできる罪滅ぼしだ。母親を救えるのは君だけなんだ。俺が力を貸すから……寂しさと戦ってくれ」
少年はマルシオの言葉を聞いているが、涙は止まらない。母親が恐ろしい悲鳴を上げる。
(お母さん!)
「コルテ! もう泣くな。もう苦しまなくていい」
(苦しまなくていい?)
「そうだ、もう十分だろう」マルシオの涙も止まらない。「君はもう長い間、たくさん苦しんだ。もう終わりにしよう。一人じゃない、俺が見てるから、勇気を出すんだ」
母親は更に奇声を上げ、マルシオに向かって飛び掛ってきた。
(お母さん! やめて)
今まで立ち尽くして、ただ泣いていただけの少年が咄嗟に母親に抱きついた。母親はマルシオに辿り着く前に体勢を崩し、子供を巻き込んで倒れた。ギイギイと暴れるが、少年は離さない。
(やめて。もういいんだよ。お願い……)
母親はさらにもがき苦しみ出す。その姿はマルシオの目に絶望に映った。
母親の魂はそこになかったのだ。いくら実の子が説得しても、聞くその耳を失ってしまっていたのだった。
やはり滅ぼしてしまうしかないのか。万が一、子供は救えたとしても母親は無理かもしれない。いや、母親が救えなければ子供はこのまま森で泣き続け、きっと今度は彼が同じことを繰り返すだろう。それでは意味がないのだ。
マルシオは眉を寄せた。諦めない、と心に誓う。もう少し、もう少しと自分の心に呼びかける。
もう少し力を。そして光は強まり、母子を白く包んだ。もう限界を超えていた。立っているのが不思議だった。今、張り詰めた糸を自ら解いてしまえば倒れて、二度と起き上がれないだろう。だがそれは、もう少し後に延ばそう。
あと少しだけ──その意思は遠くなった。気持ちに反してマルシオの瞼が下がる。持ち上げる力が出ない。結んだ指も、するりと解ける。
(……なんだよ)マルシオの声は出なかった。(もう、終わりか)
これまで、と思ったその時だった。すうっ、と魔力が体の中に流れ込んできた。
マルシオは持ち上げられるように顔を上げる。なぜ、と考えている暇はなかった。マルシオはすぐに踏みとどまり、両手にしっかり力を入れて再び魔力を放出した。母子が白い光に包まれ、その姿を隠した。
(お母さん、お母さん……)
耳を澄ますと、少年の声と重なって遠くから別の声が聞こえた。
(……エリオール)
マルシオが虚ろなまま空を仰ぐ。何も見えない。だがその声は次第にはっきりとしてくる。
(エリオール)
(お母さん……)
光に包まれた母子の姿が再び姿を現した。少年の腕の中で、母親はだらりと脱力している。
よく見ると、そのただの死体は光の粉になって、少しずつ空に昇っていた。少年はそれを泣きながら見つめた。
(エリオール)その声は優しい女性のものだった。(そこにいたの)
(お母さん……)
(ずっと探していたの。ごめんね、寂しかったでしょう……)
少年は腕の中の死体を見つめた。動かない。自分がずっと愛しく思っていたのは、ただの腐った肉塊だったと理解し始めていた。
涙が溢れ、震えだす。少年は今まで自分が何をしていたのか、それにやっと気がついて、辛くて悲しくて唇を噛み締めた。
なぜこんなにも寂しくて仕方なかったのか、やっと分かった。ここには母親も、誰もいなかったのだ。自分だけが運命を受け入れられずにここに執着していただけだった。その為に犠牲になった人は、いっそ恨んでくれればよかったのに、と思う。許してくれている。だから余計に寂しかったんだ。
少年の体に熱が篭る。肉体などないのに、魂が実体化し始めた。
ゆっくりと腕の中の死体を地に置く。そうしてしまう前に、死体は溶けるように空に昇っていった。完全に消滅する。マルシオはそれを黙って見つめていた。
少年は顔を上げる。
(お母さん)そこには涙で濡れた、笑顔があった。(エリオールは、もう死んでしまったんだよ。もう、どこを探してもいないんだ)
(エリオール……)
その声に悲しみが灯った。少年は顔を歪めるが、ぐっと我慢して再び笑う。
(でもね、大丈夫だよ。僕が守るから)
(あなたが……あなたは誰?)
(僕は『コルテ』。この森を守る精霊だよ。死んだ者の魂を鎮める精霊……)
声はしばらく沈黙した。だが少年はそれを慰めるように続けた。
(エリオールはもう寂しがってなんかいないよ。だから、安心して)
(……本当に?)
(うん。でもあなたがいつまでも彼を呼び続けていたら、エリオールも往くべき所へ往けなくなってしまうんだ)
(私はエリオールを愛しているの)
(もうエリオールはいないんだ。その言葉は僕が受け取ります)
(エリオールに会わせて)
少年は言葉を飲んだ。本当はここにいると言いたくて仕方なかった。だが、それを我慢する。
口を結んだままクライセンとマルシオに目を移すが、二人は離れたところで黙って見守っているだけだった。何も答えてくれそうにない。
少年はすぐに目を空に戻す。そして、自分の中で一番辛いと思う答えを選んだ。
(……それはできないよ)
(なぜ? どうしてあの子と私を引き離そうとするの?)
(そうじゃない。だめだよ。エリオールはここにはいない。彼は逃げないことを選んだんだ。ここは、いや、この世に楽園はありません。だからあなたも逃げないで往くべきところへ往ってください)
(………エリオールはどこへ行ってしまったと言うの?)
(彼は、あなたを愛しています。そしてあなたの気持ちに感謝しています。短い間でも、生まれてきてよかったと心から思っているんです。だから強くなれるんです。だから、どうか見守ってあげてください)
しばらく間をおいて、ふっと空気が緩んだ。注ぐ光が柔らかくなる。少年はそれを体で感じ、同時に何かが軽くなったような気がした。
女性の声は二度と聞こえなかった。その気配も遠くなり、暗い空に完全に消えていったのを感じ取れた。それを確認してから、少年は大きな声を上げて泣き出した。
マルシオが崩れるように膝をつく。すべてが終わったかのように森を包んでいた光が消えていった。マルシオは肩を落とし、意識が朦朧としている。もう少しだけ倒れるのを我慢して、背後に立っているクライセンにぼそりとぼやく。
「……なんで手を貸した?」
あの時、マルシオに魔力を流し込んだのが彼の仕業だとは分かっていた。考える必要もない。そんなこと、他に誰ができるだろう。クライセンは背後からマルシオを見下ろしたまま答える。
「あのままじゃ母子は助からなかっただろ。その上、君にまで無念の死を遂げられたら」肩を竦めて。「縁起が悪い」
「……で、結局どうなったんだ。お節介ついでに説明してくれ」
「母親は森で迷い、訪れた子供の死を受け入れられないまま衰弱し、事切れても尚いなくなった子供を捜し続けていたんだ。時間が経つにつれて母親の魂は薄れていき、もうほとんど消えかけていた。だが君が放った光に導かれてここへ戻ってきたんだ。そして子供の方はこの森で母親の死をずっと悼んで、ここから動けなくなってしまっていた。そこから生まれた執着心が人を迷わせて死に至らせる怨念となった。その怨念こそがコルテだったんだ」
「母親はもともとここにいなかったのか」
「ああ」
「母親は救われたのか」
「子供が無事だと知って、安心したらしい」
「子供は?」
「エリオールは母親に別れを告げることで精霊になった。まだ泣き止むまで時間がかかりそうだけどな」
「なんで泣いてる?」
「一緒に母親と行くこともできたのを、そうじゃない道を選んだからだろう」
「そうじゃない道?」
「精霊になってここに留まり、罪を償うことだ」
「どうして?」
「生まれたことを、命を後悔したくなかったんだろうな」
「コルテは実在し、ずっとここにいるってことか」
「そうだ」
「あれは、本当に母親だったのか?」
「……さあ、どうだろうね」
淡々と答えるクライセンにマルシオは遠慮なく質問を続ける。
「俺は、無力……だよな」
「と言うか、無能だ」
「……どういう意味だよ」
「力がないとは言わないが、その使い方を分かっていない。自分を守れない者が他人を守れると思うか。なんにでも首を突っ込んでいたら碌な死に方できないよ」
「俺は、死ぬのか?」
「いや、今回は運がよかった。私が君を救ってやった。生き残ったついでに尊敬してもらわないとな」
「尊敬するかどうかは、後で考えるから……目、閉じていいか?」
「どうぞ、ご自由に」
マルシオはその言葉を聞き届けて、糸が切れたように崩れ落ちた。
5
マルシオは深い闇の中にいた。まるで宙に浮いているようだった。
上下左右の感覚がない。ただゆっくり揺られているのだけ感じる。水の中の落ち葉のように蕩んでいる。
ふっと声が聞こえた。どこからかは分からない。
(……お兄ちゃん)
誰だろう。でも返事をしたくない。今はそのまま眠っていたかった。
(お兄ちゃん)
しかし再び呼ばれ、目を開けてしまう。やはり、そこはぼやけた黒の空間だった。
「誰だ」
(僕だよ。コルテだよ)
「コルテ? あれは作り話だ」
(違うよ。僕がコルテとなって生まれ変わったんだ。コルテはエンタナの森に棲む精霊だ。これから森で誰も迷わないように守っていくって決めたんだ)
「……そう。でも俺には関係ないよ」
(お兄ちゃんには感謝してるんだ)
「どうして。俺は何もしていない」
(僕はお兄ちゃんに助けられたんだ)
「違う、俺は……一人では何もできない。俺は非力だ。クライセンの言う通りだった。あいつが助けてくれなかったら、君たちだけじゃない、俺もそのまま死んでしまって、きっと迷える魂の仲間入りをしていたんだ。そんなの、誰も望んでいない……間抜けな結末だよ」
マルシオは改めて、情けないと思った。
(ごめんね。僕が我儘を言ってしまったから……でもそれでいいんだ。意味がないなんて、そんな事ないよ。一人じゃ駄目なら、手を貸してもらえばいいじゃない。友達に、仲間に。君が誇るべきは力じゃない。君を慈しむ仲間だよ)
「……俺たちはそんな感動的な関係じゃないよ。クライセンはただの気分屋で、人をこき使いたいだけなんだ。ライザは、会ったばかりだ。よく知らない。ティシラは問題外だ。いい加減だしうるさいし、自分の事しか考えてない。故郷の皆だって俺の事なんか忘れてるよ。誰も俺を気にかけてなんかいないんだ」
コルテはくすりと笑った。
(そのままで、いいんだよ……僕はコルテ。この森で迷える者を救い出す森の精霊……)
声が薄れる。頭上にふと小さな光りが灯った。それはマルシオにゆっくり近づいてくる。自分が浮上しているような錯覚を感じた。光が自分に寄ってきているのか、マルシオには判別できなかった。ただ、闇に身を任せる。
(さあ、往って)
声に見送られて、マルシオは再び目を閉じた。
(僕はこの森で迷える者を救い出す森の精霊……)
「!」
マルシオは背中に激痛を感じ、目を覚まさずにはいられなかった。
眩しい。体を起こすと、そこは森の中だった。
夜は明け、昨夜のことが夢のように思われるほど清々しい空気が流れている。傍にはライザが心配そうに屈みこんでいた。マルシオを挟んだその向かいでティシラが仁王立ちしている。
「いつまで寝てるのよ、このバカ!」
まだ頭がすっきりしないし体も重い。そして背中が痛い。これはどうやらティシラに蹴飛ばされたと言うことだけ分かる。
「何を勝手に死に掛けてるわけ? 人に迷惑かけるのも大概にしなさいよ」
怒鳴りつけるティシラを無視してマルシオは辺りを見回す。少し離れたところでクライセンが木の根に腰を降ろしている。目を閉じているが寝ているわけではなさそうだ。
「マルシオさん、気分はどうですか」
ライザに声をかけられて、マルシオは我に返る。
「あ、ああ」背中の痛みに眉を寄せて。「背中が痛い」
「それは……」
ライザが困っていると、またティシラが突っ掛かってくる。
「天罰よ。死に掛けてたあんたをクライセン様が抱えてきてくれたのよ。それにライザが一晩中付きっ切りで看病してくれたんだから。一体何様のつもりよ。いっそ死ねばよかったのよ」
「ティシラさん」ライザが止めに入る。「もうそのくらいで……無事だったんだからいいじゃないですか」
「だめよ。優しくしたらすぐ付け上がるんだから。バカみたい。ゾンビ如きに何で命張ってんのよ。かっこいいとでも思ってるの?」
「……お前」さすがにマルシオはむっとする。「いい加減にしろよ。大体、誰も助けてくれなんて言ってないんだよ」
「なんですって。この恩知らず。そんなに死にたいなら今すぐ私が殺してやるわよ。頭下げて殺してくださいと請うがいいわ」
「お前が何でそんなに偉そうなんだよ。お前は何もしてないんだろ」
「ほんっと、心が狭い! 誰が何をしたかで格付けするわけ? それって最低よ」
「うるさいな。お前みたいな魔女に罵られても悔しくないね。大体な、俺が死のうがどうしようがお前には関係ないだろ。そんなに死んで欲しいならさっさと殺せばいいだろ。もうお前の金切り声はうんざりなんだよ」
「マルシオさん」ライザが堪らず遮る。「ティシラさんは……あなたが一命を取り留めるまで、治療の間ずっと傍で泣いていたんですよ」
「ライザ!」ティシラが慌てて大声を出す。「言っていい嘘と悪い嘘があるわよ!」
マルシオは俯いた。ティシラはそんな彼を見て余計に声を大きくする。
「バ、バカじゃないの! 何信じてるのよ」
効果絶大だと、ライザは微笑んだ。そしてマルシオに顔を寄せて。
「これも嘘ですけど」声を潜める。「ティシラさんは、魔族だから自分に治癒の力がないことをとても悔やんでいました。あなたは人間界でできた唯一の友達だと、死なないで欲しいと。慰めるのに大変だったんですよ」
マルシオの心にまたあの声が蘇った。
『そのままでいいんだよ』
漠然と、そうかもしれないと思った。今までの事が思い出される。アカデミーのこと、ティシラと喧嘩していたこと、クライセンにバカにされたこと。その時は気に入らないことが多くて思い通りにいかない現実にイラついていたのだが、思い出してみると何一つ無駄なものはなかったし、気分も悪くない。このままでいいのかもしれない。マルシオは心の中で繰り返した。
ふっと口元は緩む。それを隠して、ティシラに意地悪な目を向ける。
「バーカ! 信じてないよ。信じられるか。お前みたいな邪悪な魔女に人の痛みが分かるわけないだろ」
「な……」
ティシラが面食らう。
「だったら今ここで泣いてみせろ! 血も涙もないくせに、お前にそんな上等な感情があるもんか」
「さ、最低」ティシラは牙を剥きだす。「あんたみたいな捻くれ者、ほんとに死ねばよかったのよ」
ライザにはとても止められない勢いだった。おろおろしながら、諦めて肩を竦める。そして、困った笑顔を浮かべた。
離れたところで黙っていたクライセンも、それを見てため息をつく。
森は見た目には変化はなかったが、確実に邪気は清められていた。ここで死んでいった者の魂は一つ残らず浄化されていたのだ。そして精霊が誕生し、これからは彼が迷える者を救ってくれるだろう。
しかし、魔法使いの一行には大した問題ではなかった。この平和な森では、ティシラとマルシオの喧騒が響き渡っていた。