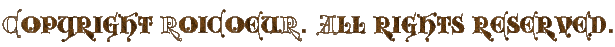第9章 星の揺篭





1
一行はマルシオの体調の様子を見て、少し休ませてから出発した。
まだ日は高くなっておらず、すこし涼しい。さらに数時間歩いていると太陽は一番高いところに昇った。
森の奥から微かに馬の蹄の音が聞こえてきた。一同は足を止めて周りを見渡す。間違いない。森の中に数十の馬の走る音が響いている。
まさか軍が追いかけてきたのではと思うが、その気配は城とは逆の方向から感じた。
どんどん近づいてくる。クライセンたちが森の奥を見ていると、次第にその姿が現われる。やはり馬上には青銅の鎧を纏った兵士たちが跨っていた。ライザは慌ててフードを被り、顔を隠す。逃げよう、と思ったがクライセンはじっと立ったまま動かなかった。
木々を避けながら兵たちは近づいてくる。そしてクライセンたちの姿を見て、ぞろぞろと速度を落としながら馬を止めた。クライセンの前に止まった兵士が兜を脱ぎながら大きな声で話しかけた。
「これはこれは」ダラフィンだった。「魔法使いの御一行ではないか」
「君か」
クライセンは冷静だった。ティシラとマルシオ、特にライザは気が気ではなかった。
ダラフィンは予想に反して友好的だった。
「いや、急いで城に向かっているのだが、この森は夜は危険だからな。かと言っていつものように迂回していく余裕もないし、仕方ないから森の外で朝になるのを待つことにしたんだ。そしたらまた不思議なことが起きてな、森が光に包まれて、それはまあ見事なものだった。あんた方の仕業だったか。それなら納得がいく」
機嫌良くそう説明した後、一息おいて本題に入る。
「で、一体ここで何をしていたのだ?」
クライセンも笑顔で答える。
「私たちも急いでここを抜けたいんだが、昨夜、怪奇現象に襲われてね。でももう問題ないよ」
「そうか」ダラフィンは馬から降りながら。「ところで、ミングの事は聞いてるか?」
「いや。何かあったのか」
「ゾンビだよ」
ダラフィンは小声になる。クライセンの表情は変わらないが、ティシラたちはその背後で顔を見合わせている。
「死体が襲ってきた」ダラフィンは神妙な顔になり。「しかもアムジーで死んだ者だった。たまたま村の毒殺の偵察を兼ねて俺たちがいたからその場で収めることができたが、それは惨い戦いだったよ。原因はまだ分からない。たぶん毒に何かが含まれれていたんじゃないかと言われているが……」
「そうじゃない」クライセンが遮る。「毒とは別だ。ある術師が魔術で死体を操っていたんだ。昨夜この森でもゾンビが出た」
「何だって」
「そいつは私を狙ってる。ミングでの魔道依送は予想外だったんだろうな。もしくはただの脅しだったのかもしれない。このパライアスは古い大陸だ。死体なんてそこら中に埋まってる。おそらくまた仕掛けてくるだろう」
「なぜ君を?」
「いろいろ訳有りでね」
「説明しろよ」
「君に理解してもらうには時間がかかる。ところで、急いでいるんだろ。早く行った方がいいんじゃないのか」
「そうはいくか。国に関わることだ。君もティオ・メイに来てくれ。陛下に説明して欲しい」
「生憎と王様とはさっき会ってきたばかりだ」
「じゃあ、陛下はちゃんと状況を把握していらっしゃるんだな」
「たぶん」
「だが、敵は君を狙っているんだろ。これからどこへ向かう気だ」
「さあ。でもできるだけ早くここを離れるよ」
「そうか……」
ダラフィンはしばらく黙った。クライセン以外の三人は、早く行ってくれと祈り続けていた。だが三人の願いは裏切られた。クライセンが少し首を傾げて。
「王様に何か言われているんじゃないのか」
一同が目を丸くした。なぜそんな余計なことを、と同時に思う。ダラフィンも息を飲む。そして厳つい顔にさらに力を入れる。
「芝居のつもりか」クライセンはそれに反して、さらに彼を煽る。「この状況であんたが何も知らないはずがないだろ。どうして中途半端に誤魔化そうとしてるんだ? できるなら、私にメイに来て欲しいと顔に書いてある。強制ではなく、とね」
ダラフィンは目を泳がせた。それを一度閉じ、すぐに開く。
「オーリスから通信で連絡があった」ダラフィンは重い口を開いた。「君を見つけたら連れてきて欲しいと言われた。そして、ライザ殿もな」
「!」
ライザは顔を上げた。ダラフィンはクライセンたちの背後に隠れていたライザに向き直る。
「姫、戯れはそのくらいで」
ライザはダラフィンの前に出る。
「戯れなどではありません」
「オーリスが死ぬほど心配している。それに誰も怒っていないから安心するんだ。もう十分だろう。城へ帰ろう」
俯くライザにダラフィンは諭すように続ける。
「じっとしていられないのは分かる。だがこのような形で城を出て、後の事は考えているのか? あなたが背徳を行っているとは思わない。だからこそ皆は許してくれる。それを分からない人ではないはずだ」
「私にも戦わせてください」
「あなたには力がある。奥に引っ込んでいろなんて、そんなことを言ってるんじゃない。ただ、あなたの戦場はここではないはず。あなたが守るべきものは『心』だと言ったではないか」
「では……ダラフィン殿。その守るべき『心』とは、どこにあると思われますか?」
ダラフィンは困った。それを答えてやれることも、その資格もなかった。
しかし今は彼女が何を言おうととにかく連れて帰るべきだと思っていた。縄で縛り付けていくわけにもいかない。かと言ってライザが納得いくまで説得している時間はなかった。
普段の彼女はこんなふうに駄々をこねて人を困らせることはしない。なぜ彼女がこうも冷静さを欠いてしまっているのか、ダラフィンにはその気持ちが理解できた。だからこそここに居させるわけにはいかなかった。こうなったら失礼を承知でも無理やり連れ戻そうかと、そんなことを思案していた。すると、クライセンが口を挟んだ。
「ライザ、城へ帰りなさい」
ライザはフードの中から泣きそうな顔をクライセンに向けた。僅かな間とは言え、共に戦い力になれたと思っていたのに。ライザはまるで厄介払いをされているような気持ちになった。
「オーリスは古い知り合いだ」クライセンは微笑んでいる。「彼の娘自慢の噂は聞いてる。これ以上心配させたら病気になってしまうよ」
ライザは黙って俯いた。確かに彼女は無計画でここまで来てしまったし、森を抜けたらそこで別れるつもりではいた。自分がついていっても仕方ないのは分かっていたが、ここで強制送還されるのが嫌だったのだ。出来れば自分の意志で動きたかった。
だがクライセンにまで帰れと言われては、これ以上はただの我儘だ。自分が正しいのか間違っているのか、今ここでは判断できない。
「分かりました」
ライザはそう呟いてフードを取り、ティシラとマルシオに寂しそうな微笑を送った。二人は何も言えなかった。
「クライセン」ダラフィンは彼女を気の毒に思いながらも話を続ける。「君はどうする」
「私は城へは行かないよ。だが王様に伝言がある、伝えてくれるか」
「伝言?」
「ゾンビ騒ぎはノーラではなく、ネクロマンサー(死霊使い)と黒魔術師の仕業だ」
「なんだって」マルシオが身を乗り出す。「まさか……」
「ギメルとハゼゴだ」クライセンは構わずに続ける。「ギメルの死霊呪術をハゼゴが遠隔魔法で操作していたんだ。昨夜の襲撃で間違いなく二人の力を感じた。手を組んでいるのは確かだが二人が仲良しだとは思えない。となると背後にノーラがいるとしか考えられない。近いうちにその姿を現すだろう」
「おいおい」ダラフィンが不満そうに。「俺は魔術だの魔法だの、その類の話には疎いんだ。正確に伝わるかどうか……」
「言えば分かる」
クライセンは一言で片付けた。ダラフィンは口をへの字に曲げて、仕方なさそうに了承する。
「それにしても」クライセンは目を細めて。「えらく聞き分けがいいんだな。あんたは相当な石頭だと思ったが。私としては助かるが、あんたがそんなに利口だとは思わなかったよ」
「そういう言われ方をされると参るな」ダラフィンはむっとしながら、体の力を抜く。「正直、自分がどうしたらいいか分からないんだ。そんな悠長な場合じゃないんだろうが、まずさっきも言ったが魔法については専門外だし、いざ戦いとなると相手は死体ときた。問題のノーラは名前だけが一人歩きしているようで全くその気配すらない。誰が敵なのか検討がつかないんだ。我々は誰に剣を向ければいい?」
「敵意を持って襲ってくる輩だよ」
「それが何なのか分からないんだ。ただ死体を斬り続けろと言うのか。それはいつを目途に勝利として目指せばいい?」
「ただの死体とも、死体だけとも限らない。敵がどこを、これからどういう形で襲撃してくるかは私にも分からない。終焉はノーラを滅ぼした時だ」
「ならば尚更、国と共に戦うべきではないのか」
「国中でノーラの毒ガス地獄に乗り込むというのか。やめた方がいいと思う」
「……ふむ。そうだな」
「それに、君たちは勝利だとか考えない方がいい。これは革命だ。起こる嵐をどう凌ぐかがこの先の時代を決める。悪もまた人の所業。ただ気に入らない奴を叩くだけではその芽までは摘めない」
「つまり?」
「そういう事だ」
クライセンは意地悪く笑って、そこで無理やり話を終わらせた。
ダラフィンはまるでバカにされたような気分になる。だが、クライセンはただからかったわけではなかった。
ダラフィンもまた、自分がすっかり彼の話にのめり込んでしまいそうになっていた事に気がついて、今は話し込んでいる時間はないのだと気を取り直す。つい縮めてしまっていた背を伸ばしながら。
「王の命令は絶対だが、それも王の為を思えばこそだ。君を捕らえることは、君の言うとおり賢明ではないような気がするんだ。果たしてそれに拘る必要があるんだろうか、とね。それにこの指示に限りオーリスの言葉に迷いを感じられた。もしかすると王も同じ思いなのかもしれない。こんなことは初めてだよ」
「あんたたちは王と言う人間を守るんじゃない。国を守るんだ。そこを履き違えたらとんでもないことになる」
「……なるほどね」ダラフィンはにやりと笑って。「それと、君を捕らえたくない訳は他にもある。性格には問題があるようだが、頭は悪くないと思うからだ」
「なんだそれは」
「褒めてるんだ」
「そうか」
「本来ならこんな個人的な感情は問題外なんだがな、今回ばかりはなぜか無視することができない。例えそれが結果的に間違っていたとしても、きっと後悔はしないんじゃないかと思えるんだ。全く、不思議だよ」
そこでダラフィンは再び兜を被って、鞍を引いた。
「さて、道草を食ってしまった。先を急がねば。ライザ殿、私の馬へ」
そう言いながらライザを促す。ライザはゆっくり近づいて、ふっとクライセンに向き合う。
「クライセン様」その目は切実だった。「どうか、生きてお帰りください。そして、どこかで私を知る者と出会われましたら……幸運を祈っていますとお伝えください」
クライセンは意味が分からなかったが、大して興味はなかった。返事の変わりに優しい微笑を送った。それを受け止めてライザは一礼して背を向ける。ダラフィンに抱えられて馬に跨る。
「姫には乗り心地がよろしくないだろうが、少々の間我慢してくれ。安全だけは保障する」
「ええ、平気です」
ダラフィンがその後ろに乗り、鞍を引く。兵たちも再発の準備をした。そこでマルシオがライザに声をかける。
「いろいろありがとう。気をつけて」
「あなた方も」
ティシラも前に出て。
「元気でね」
ライザはやっと微笑んだ。するとダラフィンがティシラを見るなり「ああ」と大声を出す。
「お譲ちゃん。忘れてたよ。あの海賊たち」
ティシラもすっかり忘れていた。あっと思い出し、途端に嫌な顔をする。
「戦闘のどさくさに逃げられてしまった。手配書を出せばすぐに見つかると思うが、その時には知らせるよ」
「いえ、いいんです」ティシラは慌てて体を引く。「どこかで適当にやっててくれればいいなあってくらいの仲なんで。お構いなく」
「そうか。承知した」
そしてダラフィンは馬を翻らせる。クライセンに短く別れを告げ、兵を引き連れて所狭しと木々の間を一斉に駆けていった。
「よい旅を。勇敢な魔法使いたち」
大男の腕の中でライザは小さく見えた。彼女は一行が見えなくなるまで肩越しに見つめていた。
2
さらに半日ほどクライセンたちは森を歩いた。
再び三人になった一行は、その間にもいろんなことを口論していた。
まず、クライセンが口にしたギメルとハゼゴについて、マルシオが文句を垂れていた。
「なんでそんな大事な事を言わなかったんだ」
「君に報告する義務なんかあったのか」
「ギメルと、特にハゼゴは俺が一番嫌いな人種だ」
「へえ」
「そいつらはどこにいるんだ」
「さあ」
「教えろよ。俺が倒してやるんだ」
「知らないものは教えられない。私が分かることは、今の君が束になっても奴らには適わないって事だけだ」
そこでティシラが笑い出す。
「確かにそうだわ。その二人は魔術界を追放された歴史上に名を刻む極悪人だもの。あんたみたいな軟弱魔法使いじゃ手も足もでないわよ」
「お前に言われたくない!」
ティシラは無視して目を逸らす。
「それにしても、まだ生きてたのね。エンタナでの魔術、相当なものだったわ。直接出てきたら大変なことになりそうね」
真面目な顔になるティシラを見て、マルシオも息を飲んだ。そしてまだ姿の見えない憎き相手に苛立ちを募らせながら一人の世界に入ろうとする。
だがそれをぶち壊しにするのが、またいつものティシラの浮かれた発言だった。
「でも、これで私たちはクライセン様の仲間として認められたのね」
「なんだよ、突然」
「だって、ライザは帰されたけど私たちは残ってるじゃない。ね、クライセン様」
ティシラは極悪な術師は眼中になかった。クライセンも彼女に笑顔を返しながら。
「ライザはついでだから帰ってもらっただけだよ」その言葉は容赦なかった。「知人の娘でもあるし、ダラフィンなら安心だろうと思ってね。しかし君たちまで押し付けるわけにはいかないだろう。迷惑も甚だしいし。それに君たちの家はとんでもなく遠いし。馬じゃ無理だろう?」
「ええっ、まだ私たちを追い払うつもりなんですか」
「うん」
「思ってても、口に出すか。普通」マルシオはふて腐れる。「あんたには気配りってものがないのか」
「誰に気を配れと?」
そう言うクライセンの表情は、やはり造られた笑顔だった。マルシオはため息をつく。彼の態度もだが、いつまでも状況を把握しないティシラにも腹が立っていた。
これほど纏まりがなくて何が仲間だと思う。だがエンタナの森での出来事を思い出すと何も言いえなくなるのだった。
マルシオはまだあれが夢だったのではないかと思うことがある。本当にコルテなんかいるんだろうか。だけどあの声は……「そのままでいいんだよ」という言葉。どうとでも受け取れる曖昧なものだった。いくら喧嘩しても悪態をつかれても、結局同じ道を歩いているのが現状なのだ。
そのままでいい、という言葉を繰り返していると力が抜けてくる。この旅は一体何なのだろう。何が目的なのか。クライセンはノーラを倒すとしか言わない。だが自分には何の関係があるのだろう。どうして彼についていっているのだろう。嫌なら離れてしまえばいい。きっと誰も止めないだろう。マルシオはそう思っていた。
そうしている内に森を抜ける。さらに平原が広がり、地平線には岩山の頭が見えた。それを越えればフィレスアンの港がある。さらにその先は、ノートンディルの海だけがあった。
次第に日は暮れ、夜中岩山まで真っ直ぐ歩き続けた。静かな時間が流れた。
ティシラとマルシオだけはどうでもいい話をやり取りしていた。ときどき絡まれては、クライセンが適当に躱すの繰り返しだった。
だれも休もうなどとは口にしなかった。特に何も変わったこともないまま、夜が明ける頃に山の麓についた。歩いて登れることを確認しながら、そのまま先に進む。
ふと、マルシオだけがティオ・メイを気にかけた。
「昨夜は何もなかったが、ティオ・メイは大丈夫だろうか」
ティシラは足も止めずに答える。
「気にしたって仕方ないでしょ」
「実際行ってみて思ったけど、確かにティオ・メイは国の要だ。あそこが落とされたらパライアスが滅びるのは時間の問題だろうな」
「最強の集う難攻不落の城と言われているのよ。そう簡単に落ちやしないわよ」
「お前は気楽でいいな」
「何よ、その言い方」
「よく考えろ。今は城に『最強』は不在だ」
確かに、と思う。今までは最強だったかもしれない。
だが今はどうだろう。最強は「魔法王」か「魔薬王」なのかもしれない。そのどちらか一人でも国を滅ぼそうと思えばできる力を持っている。
長い間守られ続けてきた古いものと、進化の中で生まれるべくして生まれた新しいもの。それがこの時代に存在を現し、ぶつかり合おうとしているのだ。
五千年もの間、頂点に君臨していた「軍神の砦」が取り乱すのも無理はない。この世界では一介の魔法使いでしかないティシラとマルシオはこの時をどう乗り越えるべきか、まだ道は見えていない。
だが、ティシラはそんな先の事など考えてはいなかった。
「大丈夫よ。クライセン様は世界一だし、他ならぬ私がついてるんだもの」
「どんな根拠だよ」
「愛は世界を救うのよ」
「……お前の能天気は救われそうにないけどな」
マルシオは話す気力を失った。
3
午後を過ぎたところで、一行は岩山の頂上についた。それほど高い山ではなかった。足場は悪いが、斜面は緩いので立って歩いていける。三人は一息ついて麓の先に広がる海を眺めた。
「あれがノートンディルの海。初めて見たわ」ティシラは感激していた。「あの海底にはかつての魔法大陸が眠っているのね」
マルシオは海よりも、その入り口であるフィレスアンの港に注目した。
「見ろよ」目を細めて。「メイの兵がうろうろしているし、船がほとんどない」
ここからでは中まではよく見えなかった。だがあの青銅の鎧が歩き回っていたり、立ち並んでいるのが分かる。貨物船、観光船、渡し舟などのいろんな船着場が設置されており、船員の住まいや造船上らしき建物も見えるが一般人の姿は見えない。
妙に閑散としている。何よりも近場を移動する旅人や商人が使う国内船であろう、小さく粗末な船以外見当たらない。これだけの港ならもっと立派な大型船があってもよさそうだが、と思う。
「例の事件で港は封鎖されてしまっているようだな」
クライセンが肩を竦める。
「どうするんだよ。船がないと海へはいけない。まさかあんたでも泳いでいくつもりはないんだろ」
「何とかなるだろう」
クライセンはそれだけ言うと山を下りだした。二人もそれについていく。
岩山を下り切った頃、すっかり日は暮れていた。クライセンたちにとってはその闇は好都合だった。港の入り口に近づき、門の見張りに見つからないように塀の影に身を潜めた。そこでマルシオがクライセンに小声で囁く。
「おい、なんでこそこそしてるんだよ。まさか密航するつもりなのか」
「この様子だと堂々といってもすんなり船に乗れるわけないだろう。様子を見てるんだよ」
「あんた本当に魔法使いか。泥棒みたいだぞ」
「文句があるなら君がなんとかしてくれ。まずあの見張りを眠らせろ」
「なんで俺が。大体俺たち、何も悪いことしてないだろ」
「じゃあ交渉してきてくれ」
マルシオは言いくるめられたのを承知で、のろのろと見張りの兵に近づいた。クライセンとティシラはそれを影から見守る。
夜の中でもマルシオの銀髪は目立つ。見張りはすぐにマルシオに気づいて声をかける。
「誰だ」
「あの」マルシオは言葉を選びながら。「船は出てないんですか」
「今は閉鎖中だ。それより君は誰だ」
「お、俺はただの魔法使いです。船に乗せて欲しいんですけど……何かあったんでしょうか」
「今は海に出ることはできない。危険なんだ。詳しく知りたいなら近くの町へ行って聞いて来い。最新の情報が国から伝わるようになっている。とにかくこの港には入れない」
「どうしても駄目ですか」
「船も船員も民間のものは出払っている。ここにいても無駄だ。私の口からも何も教えられない。帰るんだ」
「はあ……」
やっぱり駄目か、と俯く。取り敢えずクライセンたちのところに戻って話し合うしかないようだ。またバカにされるのは目に見えていたが、仕方ない。と、一歩引いたとき、兵が再び声をかける。
「いや、待て」
マルシオは顔を上げる。すると兵はなぜか剣に手をかけている。
「こんな時間に少年が一人で船に乗りたいだと? 怪しいな」
「えっ……」
マルシオは後ずさる。
「ちょっと来なさい。念のため、調べさせてもらう」
「いや、それは、あの……」
「不審なところがなければすぐに解放する。それとも何か都合が悪いことでもあるのか」
見張りはすらりと剣を抜いてマルシオに突きつける。マルシオは困ったが、この問答無用な兵の態度も気に入らない。剣の一本や二本、別に怖くはない。だが騒ぎを起こすわけにもいかない。
結局マルシオは見張りを魔法で眠らせてしまった。
「だから最初からこうしていればよかったんだ」
クライセンは気を失った兵を跨ぎながらぼやいた。
「そいつがおかしいんだ。何もしてないのにいきなり剣をつきつけるなんて」
「あんたって本当に素直じゃないのね」
ティシラはそう言いながら港の中を覗いた。ぽつぽつと明かりが灯っており、そこからは兵の姿は見当たらなかった。
「それより急がないと。見張りが倒れてるのがばれたら大騒ぎよ」
「そうだな」マルシオも気を取り直す。「とにかく中の様子を……」
すると、急に港の奥で騒ぎ声が聞こえてきた。まさかもう見つかってしまったのかと、一同が緊張した。
「違う」マルシオが言いながら中に入る。「何かあったみたいだ」
その内に剣の触れ合う音が響いてきた。戦闘だ。マルシオが走り出すと、クライセンとティシラも後に続く。
港の中心には乗船の登録所や簡易な休憩所を一つにした、大きな煉瓦造りの建物があった。戦闘はそこの裏で起こっているらしい。三人はそのまま裏に回って建物の影から覗いた。二十人ほどの兵が剣を手に何者かと戦っていた。
どうやらゾンビの類ではないようだ。この隙にどこかへ潜り込もうと思ったが、戦闘の様子を見ていたティシラが目を見開く。
つい大声を出しそうになったが、ぐっと堪える。さっさと身を引いてそこから立ち去ろうとしていたマルシオが固まっているティシラに気づく。
「どうした」
ティシラは答えない。マルシオがティシラの顔を覗き込むと、彼女は真っ青になって眉を寄せていた。
マルシオは再び兵の戦闘に目を移す。何かあるのか、と目を凝らしてよく見てみる。すると、マルシオもあっと固まってしまった。
兵が戦っている敵は、見たことのある海賊たちだったのだ。兵に囲まれてワイゾンを中心に、マイとキジも交戦している。
「あのバカ……」ティシラは舌打ちをする。「なにやってるのよ、こんなところで」
クライセンもそれを見ながら、黙って二人の後ろに立っていた。
海賊たちはそれぞれに剣を手にして、兵を蹴散らしている。多勢を相手に引けは取っていない。
「皆殺しだ!」ワイゾンが叫ぶ。「てめえら、俺の船に手を出すな」
それを聞いて、ティシラが身を乗り出す。
「船? 船があるの?」
「見ろ」マルシオが素早く反応した。「一層だけ大きな黒い船があるぞ」
マルシオが指を指した方に目を凝らすと、闇で紛れて確かに黒い船が見えた。停泊所の向こうの海の上に浮いている。岩山からはちょうど建物に隠れており、見落としていたようだ。
「盗むつもりなのかしら」
「どっちにしても」今まで黙っていたクライセンが口を開く。「丁度いい。あの船に乗せてもらおう」
「って」マルシオが慌てる。「なんであんたは既に盗む方向なんだよ」
「ついてるじゃないか。適当に兵を倒しても海賊の仕業で済むだろうし、船と船員も揃ってる」
「船員って、あいつらのことか」
「一応彼らは海賊だろう? 航海するには一番の専門家じゃないか」
不安だが一理ある。まさかここで彼らの手を借りることになろうとは。何とも不本意だったが、ティシラとマルシオは顔を見合わせる。結局クライセンの提案には逆らえない。今までもそうだった。彼のペースに乗せられているという自覚はまだないまま、同時に飛び出した。最終的な責任はクライセンに任せるつもりで。
ティシラとマルシオは高く飛び上がり、迷わずに戦闘の真ん中に舞い降りる。兵たちが驚いて注目した。瞬時にして新手の敵と見做すが、お互いに自己紹介している暇はなかった。
二人は同時に炎と雷を撒き散らす。数人の兵が倒れるが、怯まずにかかってくた。クライセンも後からかけてくるが、やはり戦闘に参加するつもりはないようだ。
「船へ急げ」
クライセンが大きな声を出すと、二人は同時に飛び上がり、ひらりと船の側壁の舷檣に着地する。手漉きになったワイゾンが歓喜の声を上げた。
「ご主人様!」それは雄叫びのようだった。「会えて嬉しいです」
「ワイゾン」ティシラは構わず。「早く船を出して」
「はいっ!」
ワイゾンとその手下の二人が船に向かい、ティシラが投げたロープを掴む。その横でマルシオが電撃を放ち援護する。クライセンはいつの間にか甲板に立ち、修羅場とは逆の闇の海を仰いでいた。
その背後でワイゾンが見た目の印象に反して、身軽に船に乗り込んでくる。その後にキジが続き、横でマイがロープを使わずに飛び乗ってきた。
「ご主人様……」
ワイゾンが涙目でティシラを見つめるが、ティシラは鬱陶しそうに厳しく言い放つ。
「いいから! 早く出して」
「は、はい」ワイゾンは慌てて身を翻す。「キジ、碇を上げろ。マイ、舵を取るんだ」
マイとキジは慣れた身のこなしで言われた通りに走り回る。
その間にもティシラとマルシオが魔法で兵を散らしていた。ワイゾンは力強く帆を張った。ゆっくりと船が動き出す。よし、と一同が思ったその時、兵もそう簡単には逃がさない。二本の鎖が蛇のようにティシラとマルシオに撒き付いた。
「!」
鎖には魔法がかけられていた。二人は動きを封じられた。立っている兵がその鎖に集まり、強く引き出した。船が止まってしまった。クライセンも振り返るが、心配する必要はなかった。
「ああ、もう」
「小賢しい!」
ティシラとマルシオは同時に踏ん張り、炎と電流を放流する。それは鎖を伝い、交差しながら容赦なく兵の間を駆け抜けていった。
鎖に触れていない者までもが気を失い、気絶する。鎖もぼろぼろと粉になって崩れ落ちていった。再び船が動き出す。
ワイゾンが、それは嬉しそうに咆哮した。
「出航だ!」
4
黒い船は闇に紛れるように浮かんでいた。波も風も穏やかで、陸はほとんど見えなくなっていた。
立派な船だった。新しくはなかったが、造りもしっかりしており、天災、人災共に難を潜り抜けてきた逞しさが感じられる。
船内には台所や寝室もあり、中身はすっかり押収されてしまい空になっている武器庫や冷蔵庫、地下には跡付けされたような大砲もその身を構えていた。
甲板に明かりを灯し、一同が一息ついていた。クライセンだけは一人で海を眺めている。
「じゃあ、この船は本当にあんたのだったの?」
「名はシャルノロエス。シャルと呼んでいます。俺の初めての獲物です」
「獲物?」
「俺が独立して初めて敵から奪った船です。あれから約十年、こいつは俺の故里のようなものです」
「シャルノロエス……」マルシオが船を見回しながら。「名の由来は?」
「さあ」ワイゾンが首を傾げる。「誰かの名前じゃないのか。最初からそう呼ばれていからな」
「シャル・ノーロ・アノエス」マルシオが呪文のように呟く。「『星の揺籠』。もう人間界では忘れられた天使の言葉だ」
「……そうなのか?」
「たぶん、ランドール人が天使に献上するために造ったものだろう。元は白かったんだろうな。魔力をなくし、海賊に奪われて海を漂っているうちに変色したんだろう。よく見てみろ。この黒い色は人の手によって染められたものじゃない」
「へえ」ワイゾンが感心しながら。「そう言えば、海賊船にしては妙な形をしていると思ったよ。船首から船尾までほとんど直線だし、ラットラインも必要以上に複雑だ。観光船だと笑う奴もいたよ」
「観光と言うより本来は観賞用に近い。まあ、今では立派な海賊船だろうけどな」
マルシオが少し皮肉をこめるが、ワイゾンは良いほうに受け取る。
「道理でな。一見頼りなさそうだが、嵐にも敵の砲弾にも耐え続けてきた。まさか天使の宝だったとは。いい話を聞いたよ」
ワイゾンは機嫌をよくしたかと思うと、急に拳を握った。
「それなのに、あいつら。勝手にフィレスアンに持っていって、解体しようとしてやがったんだ!」
軍が捕らえた海賊船は港に運ばれて、取調べの後、解体されて他の船の部品にされることがほとんどだった。ミングで捕獲されたこの船は、そこから一番近いフィレスアンに運ばれてもう少しでバラバラにされるところだったらしい。
ワイゾンたちは地下牢から抜け出して、フィレスアンに船があるかもしれないと思って急いでやってきたと話した。
彼らが着いたときはまだ港は閉鎖されておらず、民間人のふりをして中に潜り込んだ。調べてみるとやはりシャルノロエスがあり、三人は喜んだがそれも束の間。すでに中身は押収されており、数日後に解体されると知ったのだ。
のんびりはしていられない。何とか船を取り戻そうと思案したが、
仲間は僅か三人。ろくな武器もなく、もう捨て身で戦うしかないと決意した。そんな計画を立てている最中に急に港は閉鎖となり、民間人は追い出されて兵だらけになってしまった。
何が何でも、と三人は兵の目を盗んで身を隠した。それも見つかるのも時間の問題だと思っていたとき、ティオ・メイからダラフィンが何かのついでに適当に回したのであろう手配書が届き、彼らは見つかってしまったのだった。
もうやけくそになるしかなかった。後先考えずに暴れだしたところに、この魔法使いたちが現れたのだった。
「ご主人様のことをずっと気にかけていました」ワイゾンはティシラに寄り付く。「でも船は取り戻せたし、ご主人様にもこうして会えるし。死ぬほど嬉しいです。まるで洞窟に閉じ込められてたあの地獄が夢のようです」
ティシラは困って体を引く。そこに浮かべた笑顔は乾いていた。その横でマルシオが怒鳴りだす。
「何が夢のようだ」マルシオは頭を抱えて。「手配書が回ったってことは、俺たちも海賊の仲間だって思われるかもしれないんだぞ。それにクライセンに聞いたけど、ミングの毒はやっぱりお前たちの仕業だったそうじゃないか。お前たちは大量殺人を犯し、村を一つ滅ぼしたんだぞ」
「な、なんのことだよ」
マルシオは一連の状況を説明した。海賊たちは黙って聞いていたが、怪訝な顔をして肩を竦める。
「事故じゃないか。それに俺たちだって被害者なんだよ」
「開き直るなよ」
「どうしろと言うんだ」
「反省しろ。どれだけ村人が苦しんだか分かっているのか」
「分かるかよ」ワイゾンは口を尖らせる。「俺たちは海賊だ。元々犯罪者なんだよ」
その言い合いは止まりそうにない。そこでマルシオが横で目を逸らしているティシラに振る。
「ティシラ、お前こいつの主人だろ。何とか言ってやれよ」
「ご主人様には関係ないだろ」
ワイゾンが怒鳴る。ティシラは何も言わずに笑ってごまかしていた。
一時間ほどそんな会話が続いたが、それより大事な話があるんじゃないかと、マルシオがやっと気づく。
「所で、これはどこに向かっているんだ」
「とりあえず陸を背に沖に向かっているんだが、目的地があるのか?」
「さあ。俺らの大ボスはパラ・オールに行くとか行かないとか言ってたが……」
「パラ・オール?」ワイゾンが目を見開く。「あそこは毒ガスが充満していて誰も近づけないぞ」
「知ってるよ」
「お前らは一体何がしたいんだ」
「俺もよく分からない。でも海に出てしまっては船以外に足場はないんだ。敵がパラ・オールにいるんじゃ毒でも何でも行くしかないかもな」
ティシラが不安になって、未だに甲板の端でじっと海を眺めているクライセンの背中に目を移し、声をかける。
「あの……」
ティシラが言い終わる前に、クライセンはそのまま動かずに答える。
「向かって行こうが逃げようが、敵はやってくる。いずれ私はノーラと出会うだろう」
一同は黙って彼に注目した。少しずつだが、事の重大さがのしかかってくる。ふっとクライセンが振り向くと、緩やかな風が彼の髪やマントを後ろから押した。
「巻き込んでしまってすまないね」微笑んでいた。「少なくとも君たちを毒ガスなんかで死なせはしないから」
その声には魔力があり、綴られる言葉は一同の心に勇気を沸かせた。魔法王が命の保障をしてくれる、これ以上に心強いことはなかった。だが、それは少々勘違いだった。
「念のため、私が言ってるのはパラ・オールの毒のことだ。その前後の敵襲では各自で身を守るように」
一瞬にして、一同は複雑な顔になった。しかしすぐにワイゾンが笑い出す。
「そりゃ当然だ」立ち上がって。「俺たちは海賊だ。海の上で果てるなら本望だ。いいとも、乗るぜ。なあ」
とキジとマイに振る。二人も立ち上がりながら。
「俺はお頭に命預けてますから」
「ま、洞窟で死ぬより全然いいけどね」
「決まりだ。おい、魔法使いの旦那、この船のキャプテンは俺だが、今回はあんたに従うぜ。生憎と武器も財宝も食料も全部取り上げられちまったし、船員も俺たちだけで頼りないと思うかもしれねえがな。だが洞窟では非力だが、海の上じゃ最強の精鋭なんだ。よろしくな」
クライセンは何も言わずに優しく目を細めた。すると、やたら気をよくしてクライセンに馴れ馴れしくするワイゾンに引けを取らないように、ティシラとマルシオも立ち上がって身を乗り出す。
「俺もここまで来たんだ。最後までついていく」
「私はクライセン様に一生ついていくって決めてます」
「ティシラ、それは場違いだ」
「いちいちうるさいわね。あんたなんか存在が場違いなくせに」
「どういう意味だよ」
「いい加減に自分が邪魔者だったって気が付きなさいよ。あんたが居なきゃ私はクライセン様ともっと愛を深め合えたんだから」
「深める前に始まってもいないだろ」
相変わらずだった。そんな一同を見ながら、クライセンは微笑んでいた。しかし、その目には表情がなかった。
5
一致団結、かと思ったその時、一同の背中から人の気配を感じた。
一斉に振り向くと、そこには見慣れぬ青年が立っていた。シャツにコートを羽織り、長い金髪を無造作に一つにまとめている。一見しただけではごく普通の、どこにでもいる青年だった。
腰には立派な剣を差している。コートの隙間から見え隠れする柄には複雑な細工が絡み合い、単純に安いものではなさそうだと思える。それが彼を一般人だとは思わせなかった。
青年は一人一人の顔を眺めた後、とぼけた顔をする。
「君たち、誰?」
こっちの台詞だと全員が思った。黙っていると青年が勝手に喋りだす。
「中で昼寝をしていたんだけど、揺れに気づいて目が覚めたんだ。いつの間にか出航してるよ。どういう事だ」
「それより」マルシオが代表して。「あんた誰だよ」
「君たちこそ。これは捕獲された海賊船だろ。どうやら兵でもなさそうだし、なぜこれに乗って出航してるんだ」
「この船は」ワイゾンが口を挟む。「おれのものだ。持ち主が乗ってなにが悪い」
「じゃあ、海賊だな」
「だったらどうする」
「よせ」マルシオがワイゾンを止め、再び青年に。「俺たちは魔法使いだ。あんたと喧嘩する理由はあるのか」
「魔法使いが海賊の手下に成り下がったか。これは由々しき問題だな」
「なんだと」
青年は意地悪な笑みを浮かべる。一触即発だった。青年は微かに体に力を入れている。今にも剣を抜いて斬りかかりそうな気迫があった。この不利な条件の中でも全く物怖じしない。それだけ剣の腕には自信があるようだ。勝てる勝てないという問題ではなく、戦う理由がない。だが海賊たちは違う。理由なんか必要ない。ここで誰かが口火を切ってしまえば──マルシオが頭の中を整理していると、クライセンが緊張の糸を切った。
「からかうのはよせ」その目は冷ややかだった。「話は聞いていたんだろう。それ以上悪ふざけをするなら、私が相手になるよ」
一同の緊張は違うところに向いた。青年の剣よりクライセンの脅しのほうがよっぽど怖い。いつもと様子が違う。どうやらこの手の挨拶は嫌いのようだ。
青年は構えを解いて、クライセンを見つめる。もう闘志はなかった。そして再び笑い出す。
「すなまい。さすが四代目魔法王。すべてお見通しか」
「君が誰かも、名前すら知らない」
「失礼」青年は笑うのをやめ、胸に手を当ててクライセンに敬意を示した。「僕はトール。独学で剣を学んでいる。ここで昼寝をしていたのは本当だよ。目が覚めたのは港を出る前だ。あの喧騒でね。悪いけど状況を把握したくて君たちの会話は聞かせてもらった」
「それで?」
「どうやら君たちは魔法使いと海賊で、僕の敵ではないようだ」
「だが、今すぐここから君を放り出すことも簡単だよ」
「そのようだね。君に剣は通用しない」
「どうして閉鎖された港にいたのか、黙ってついてきたのか。訳は?」
青年、トールは黙った。今までの軽い笑みが消えた。困ったように目を伏せるが、すぐにクライセンに向き直る。
「参ったな。そんなに怖い顔をしないでくれ」どこか挑戦的な表情を残している。「結論から言うと、僕も連れていってほしいんだ」
誰も発言しなかった。クライセンの放つ迫力の前に誰もそんな勇気はなかった。クライセンは瞬きもせずにトールを睨みつけている。そして口だけを動かして。
「理由は?」
と繰り返す。何一つ誤魔化すことなどできない。トールはその空気を読み取って、根負けした。するしかなかった。
「僕の名前はトレシオール・インバリン。君の話はいろいろ聞いてる。港にいたのは海賊船が珍しかったのと、そこにいれば君に会えるかもしれないと思ったからだ。僕もノーラの討伐に参戦したい。もちろん単なる好奇心や遊びのつもりはない。僕は真剣だ。命を懸ける覚悟もある」
クライセンは黙ってトールを見据えていた。珍しく何か考えているようだ。一同が彼の答えを待った。
トールも目を離さずにじっとしている。妙な時間が流れた。
クライセンは注目される中、ぴくりとも動かなかったが、急に目を見開いてとぼけた声を出す。
「ああ、インバリン。王家の。って事は王様の血縁者?」
「そ、そうだ」トールは戸惑って。「息子だ」
「そうか。噂の放浪癖のあるダメ王子か。こんなところにいたのか。城は大変なことになっていると言うのに、何をやっているんだ」
どうやらクライセンはインバリンという名前をどこかで聞いたことがあると、思い出そうとしていたらしい。トールが名乗った後の話は聞いていなかった。
「僕は」トールは真剣な目になった。「王家に生まれただけで自動的に王位を継ぐつもりない。だがこの目で国を見て、剣の腕を磨き、それに値する男になれたら喜んで王になりたいと思っている。そのために旅をしているんだ。僕は父の飼い犬になんかなりたくないんだ」
「犬じゃなくて息子だろう?」
クライセンはすっかりいつもの調子に戻っていた。肩を落として腕を組みながら言い捨てる。
「息子が父親の後を継ぐのに何の問題がある。そんなに根性見せたいならここから泳いで帰ってみろ。皆驚くぞ」
トールはいつの間にか彼のペースに乗せられている。
「茶化さないでくれ。君とノーラの話を聞いたときに決めたんだ。この歴史の節目となる戦いに何かしらの形で貢献すると。それができなければ僕は王に、人の上に立つ者に相応しない。待つのは死のみだ」
「君の将来の夢なんかに興味はないし、関係もない。ここは不良のたまり場じゃないんだ。帰ってくれ」
そう言ってクライセンは疲れたように歩き出す。船内の入り口に向かい、トールの横をすり抜けて戸に手をかけた。ふっとその手が止まる。背後から剣先が突きつけられていた。クライセンは無表情で肩越しに振り向く。そこには殺意を込めたトールの目があった。
「僕と勝負しろ」勝てないのは分かっていた。「僕が勝てばつれていくと約束するんだ」
さすがの無謀さにマルシオが大きな声を出さずにはいられなかった。
「やめろよ。殺されるぞ」
「無謀は承知。戦わずして背を向けるのは僕の正義に反する。死んだ方がマシだ」
「相手が悪すぎるだろ」
「君だって男なら僕の気持ちは分かるはずだ」
「いや……」マルシオは少し引いて。「性別の問題じゃないぞ。お前がやってることは」
クライセンがため息をつく。トールの熱意には一切構わず戸に手をかけ、開ける。そのまま中に行ってしまおうとする彼にトールはかっとなる。
「逃げるな!」
勢いだけで剣を振り上げる。が、同時にその体もふっと浮き上がる。
「!」
一同が目を閉じた。その瞬間にどぼん、と海に何かが落ちる音が聞こえた。
すぐに顔をあげると、そこにはトールの剣だけが転がっていた。
海を覗く。波が揺れ、トールの姿はどこにもなかった。しばらくして彼が海面から顔を出した。無傷のようだが、どうやらクライセンに指一本使わずに海に放り投げられてしまったらしい。
船室への扉に目を移すと、既に彼は中に姿を消していた。