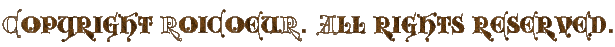第15章 魔薬





1
魔薬──それは魔法と医学を混合されたものである。
現在にその名は轟くものの、実際見る者、それに触れた者は多くはなかった。正しい知識を持ち、扱える者がただ一人だったからである。
それが「魔薬王」ノーラだった。
彼は一介の人間だった。魔法使いだと言う者もいたが、それは定かではない。確かなのは医学に通じ、若い頃から人間の体の仕組みなどに異常なまでの興味を示していたということだった。
彼は人との関わりを避けて、熱心に謎の研究を続けていた。最初は単なる好奇心から始まった。彼の探究心は止まることを知らず、まるで取り憑かれたように何かに没頭していた。
次第にノーラは夜中に外を徘徊するようになった。もう研究や勉学の範囲ではなかった。その足は墓地へ向かっていた。そして墓を荒らし、死体を解剖し始めるに至った。
そこから彼は道を踏み外したのだ。死体に触れるうちに、ノーラの興味は「魔力」へ向かった。
この世には三種類の世界がある。まずはここ、人間の住む世界。
もう一つは天上界。そこは天使以外赴くことのできない神聖な空間だった。
そして魔界。天上界とは逆の、暗闇を象徴する地の底の世界だった。
人間界はその狭間にある一番弱いと言われる世界だった。なぜなら天使と魔族は事故や故意で死なない限りはほぼ永遠に生きていられるからだ。
人間はそれを欲しいとは思わなかった。人間にとって天使や魔族の生態は自然の一部のように感じられたからだ。
魔力は魂を中心に宿っている。人間は肉体という入れ物の中に魂を入れて生を成り立たせているが、天使と魔族は魂と肉体そのものが魔力で形成されていた。その生態は人間と比べれば実に自然に近い存在だった。その光と闇の魔力に影響を受ける人間の寿命は様々だった。
事故や病気に見舞われずに普通に生活していれば百年前後生きられる肉体を持っていた。だが魔力を帯びて自然界との繋がりを持ってしまうと、その分時の流れが遅くなる。
さらにノーラは人間の種類の違いを調べ始めた。人間だけでいろいろな体を持つ者がいる。
魔力が乏しく平凡に生活し、寿命をまっとうする人間。
そして魔力を帯びた人間。そこでまた種類は別れる。まずは魔力を生まれ持った人間。そして環境に影響されて魔力を帯びた者。それが必ずしも魔法使いと呼ばれるわけではなかった。
魔力は人間の体に影響を与えるものの、それを扱って初めて「魔法」という形になり、その能力と知識を持つ者が「魔法使い」と呼ばれるのだ。
その他にも特殊な人間がいた。賢者と呼ばれる者だ。賢者はこの世の自然の理を熟知する者だった。魔力や魔法を使わずに自然を操ることができる。
何よりも人間が知ることの出来ない、知ってはならない真理に触れ、さらにそれに耐えることのできる強靭な精神力の持ち主だった。今までに賢者の数は少なかった。
ノーラは人間の体に大きな影響を与える魔力に惹かれていった。彼が持つ、医学の精神とどこか似てはいないだろうかと考えたのだ。医学の知識はいろんなことに繋がる。
まず怪我や病気を制御する。薬によっては精神を操ることもできる。毒や細菌の生態を知れば、それは見えない兵器にもなる。それに魔力を合成させれば一体そこから何が生まれるのだろう。
そして魔薬は作り出された。
それは名前の通り「魔力の薬」だった。特殊な薬草を特殊な方法で合成させ、それを肉体に与えると化学反応を起こす。そこに魔力が生まれる。
元々魔力を持たない者にも扱えるものだった。限界はないに等しかった。
しかしそれには多大な副作用が伴った。その肉体が、相応しくない魔力に耐えられなければ簡単に死に至る。それで済むなら楽なものだった。血液が逆流する、皮膚は破れ骨が曲がる、脳や内臓が腐るなどの無残な結果を招く。不治の病にかかり一生苦しむ者もいる。また、精神に異常を来たした者もそれは残酷な最期を迎える。
発狂する者、自我が崩壊する者、人でなくなる者。止める手段はなかった。檻の中に閉じ込めてしまうか、殺すしかなかった。
それで終わるのならば良い方だった。すべてを失い、人だった者はその姿を変え、今までに見たこともない獣に変形してしまうこともあった。そこには情も理性もなく、この世のものとは思えなかった。名前などなかった。それは未知の生物としてしか認識しようがなかった。
人は知らないものを理由もなく恐れる。誰もそれを救えなかった。何の情報も知識もなかったからだ。
世界はノーラを表の世界から追放した。魔薬は新しい呪いとして闇に潜んだ。
ノーラの研究は更に恐ろしい方向へ向かっていった。彼はそれが善だろうと悪だろうと関係なかった。彼にとっては「新しいものを生み出す」こと以上でも以下でもなかったからだ。
楽しくて仕方がなかった。ノーラは夢中になっていった。
そしてとうとう、彼は自分が求めているものが何なのか、その形の結末を微かに見出し始めていた。
そのヒントは意外なところにあった。
現在、唯一と言われる賢者サンディルがその答えを弾き出していたのだ。
サンディルは彼とは関係ないところである研究を進めていた。彼もまたノートンディルが発した毒について調べていたのだ。きっかけは、ただ暇だったからに過ぎないのだが。それはサンディルにとって恐ろしい結果となった。
これは決して世に出してはいけない。サンディルは黙って封印するつもりだった。
だが、すぐに処分することが出来なかった。一番身近で信頼できる息子にも、長い間隠してしまっていた。
しかしその存在はノーラに知られることとなった。
彼は魔薬王と呼ばれ始めて、世界の裏社会で魔薬の取引をしていた。そのほとんどは海賊だったのだが、ノーラは取引相手をただの実験材料にしか思っていなかった。
ノーラは悪人にもあまり好かれる人柄ではなかった。唯一魔薬を扱える者として特別視されていたものの、人を人と思わない冷酷さと、法外な金品を要求してくる彼を快く思う者はいなかった。故に魔薬は手に入りにくく、恐れられながら栄えることはなかった。
そんなノーラにも専属の情報屋がいた。ノーラは自分に利益のある者とはそれなりの付き合いをしていた。情報屋はノーラに懐き、確立していない情報を世間話として軽く口にするときがあった。
あるとき「賢者も魔薬の研究をしている」と適当な話をした。ノーラはそれを無視することができなかった。
ノーラは魔法使いだとかには興味はなかったのだが、賢者の持つ「人の知るべきではない心理」はいつか知りたいと思っていたのだ。いい機会だと、ノーラは動いた。
サンディルは神出鬼没でいつもどこにいるのか分かり難い存在だった。だが、サンディルも所詮は人間。ほとんどの人間は賢者を神のように扱うが、ノーラは違った。惑わされずによく目を凝らして見れば、必ずこの世のどこかにはいるのだ。
ノーラは慎重に、気取られないように彼に近づいた。少しずつ、その糸は解かれていった。
そしてサンディルは思わぬ形で「秘密」を暴かれた。
これだけはと、ノーラの魔の手から逃げ出した。
ノーラは喜んでいた。思った以上のものがそこにあったのだ。逃がすわけにはいかない。サンディルは誰にも相談もできずに、ただ追い詰められるのを感じながら逃げ回った。
それも長くは持たなかった。これ以上は無理だと、息子クライセンに助けを求めた。
それでもサンディルは本当のことが言えなかった。「ノートンディルの毒を中和する方法を見つけたが、魔薬王が邪魔をしている」と嘘をついてしまった。
話を聞いたクライセンは、その時点では理由はどうでもよかったし、魔薬にも興味なかった。ただ助けを求めてきた父親を見殺しにするわけにはいかない。敵なら倒すだけだと、ノーラと対立したのだ。
それが二人の出会いであり、魔薬戦争の始まりだった。
クライセンとノーラは相打ちとなり、その続きは百年後に持ち越された。
サンディルはクライセンが負傷し、休んでいる間も口を噤んで苦悩していた。クライセンは何かがおかしいと思いながらも、サンディルを問い詰めることはしなかった。
だが、ノーラは違った。パラ・オールに身を潜めながら、邪悪な手下を集めた。クライセンがまだ動けないその隙を狙って、サンディルの「秘密」を追わせた。
不意を突かれて、サンディルはとうとうそれを奪われてしまった。もう隠してはいられなかった。魂を猫の体に移しながら、会話ができるようになった息子にすべてを白状した。
クライセンはあまり驚かなかった。サンディルを怒鳴りつけるようなことはしなかったが、それから彼の陰湿ないびりが始まったのは言うまでもない。
クライセンは既に取り返しのつかないことになっているのをすぐに理解した。焦っても仕方ない。自分の魔力の回復を待つしかなかった。
その間にサンディルに、ノーラに盗まれたものと同じものを作って自分に渡すように言いつけた。それでノーラと対等だった。勝敗はそれから決まる。
何かを救うつもりはなかった。ただ、ノーラを倒す。それだけがクライセンの目的であり、価値だった。
2
クライセン一行はパラ・オールの奥に進んでいた。神殿の地下は何層にも階段で繋がっている。もういくつ階段を下りたのか分からない。どの室も階段以外は広かった。
そして古く、昔の輝きは完全に失われてしまっていた。
「なあ」マルシオが周囲を見回しながら。「ここって、もしかしてザインの城だったんじゃないか」
マルシオはクライセンに話しかけていたつもりだったが、彼は答えなかった。その代わりにワイゾンが声をあげる。
「海底にこんなところがあったなんてな。それにしても陰気で薄気味悪い」
「陸上にあった部分は遺跡以外崩壊してしまっているんだろう。ここは地下室だ。たぶん魔術や儀式を行うために建設されていたものだろうな」
確かにそこら中には海賊たちが見たことのない、何に使うのか分からない道具が転がっている。だがとても宝と言えるものはなかった。昔は光り輝いていたのかもしれないが、すべてが黒ずんでぼろぼろに壊れていた。
「ところで」今度はトールが。「辺りを取り巻いていたはずの毒はどうなったんだ。そんなものなかったじゃないか」
マルシオを助けるために、クライセンに黙ってついてきた一行は毒ガスのことなど聞いてる暇などなかった。気がついたら神殿の中に入ってきていたのだ。ないならないに越したことはないのだが、せめて状況を把握したいのは誰もが思っていることだった。トールが冗談を込めて続ける。
「海賊のガセじゃないのか」
「冗談じゃない」再びワイゾン。「あれで死んだ海賊は山ほどいる。俺も遠くから見たことはあった。それに陸の人間も確認してるんだろ」
「そんなに真面目になるなよ。分かってるよ、そんなこと」トールはクライセンに流す。「とにかく、毒ガスはどうなったんだよ。なあ」
クライセンは完全に無視していた。背を向けて黙々と歩いている。一同は黙ってしまった。また機嫌が悪くなっていると、やっと察した。しばらく沈黙が続いた。それを破ったのはマルシオだった。
「あのさ」恐る恐る彼の背中に声をかけた。「あんたの不機嫌な理由は……俺たちなんだろ」
するとクライセンはぴたりと足を止め、振り返った。一同は同時に固まった。
「そうだ」その目は冷たかった。「人が黙っていれば、一体どこまでついてくるつもりだ。毒は私が一時的に魔法で払っている。一時間は持つから今ならまだ間に合う。頼むから帰ってくれ」
「な、何でだよ。今更それはないだろ」
「今更も何もない。ここから先は君たちがついてきても死ぬだけだ。状況を考えろ。ここをどこだと思っている。君たちはここから先で一体何をしようと思っているんだ」
「何って」
「今まで何も役に立たなかったとは言わない。君たちの気持ちは有難く受け取るよ。しかし敵はもうノーラだけだ。ここから先は何もないんだ」
クライセンは今までになく苛立っていた。確かに彼の言ってることに間違いはなかった。何が出来るもの何も、何があるのかも分からない。
だが、帰れと言われて帰るなら最初からここにはいない。ならばなぜ自分たちはここにいるのか。そう思うとどうしても納得いかない。
「どうして、何も言ってくれないんですか」ティシラが小声で。「私たちは、何も分からない。それはあなたが教えてくれないからじゃないんですか。それが分かれば、自分でいくらかは判断できるはずです」
クライセンはティシラを睨み付ける。ティシラは目を逸らそうとしない。だが、内心怯えていた。
「じゃあ聞くが」クライセンは冷静に。「君たちは一体何が知りたい?」
「それは……」
ティシラはうっ、と言葉を飲む。そう言われると具体的な質問は思い浮かばない。
ティシラはマルシオに目線を移す。マルシオも体を揺らして目を逸らす。そうして一同はお互いに顔を見合わせた。
その動きが止まってしばらく重い空気が流れた後、クライセンがため息混じりに。
「どうやら」目を細める。「ただの好奇心って事のようだね」
再びティシラが大きな声を出す。
「それは違います」咄嗟だった。「どうしてそんなことが言えるんですか」
「うるさい」クライセンは遮った。「もうお仕舞いだよ」
クライセンが魔力を発した。それが一同に伝わる。空気がざわついた。彼の足元から目に見えない風が起こり、それが髪や服を揺らす。一同をここから消そうとしていた。本気だ。今度こそ強制的に追い払われてしまう。そう思った。
その時、クライセンの目に灯った青い光がふっと消えた。
「!」
風が掻き消えた。何が起きたのか、一同には分からなかった。
だが彼の魔力が完全に沈黙していたのだけは間違いない。
クライセンの様子がおかしい。自分の手を見つめ、額に汗が伝った。
(まさか、そんな)クライセンの目が泳ぐ。(まさか……どうして)
魔力が失われていた。信じられなかった。彼の脳裏に「魔薬」の言葉が過ぎった。
しかし、なぜ。いつ、どうやって?
混乱するクライセンの頭上から知った声が轟いた。クライセンは顔を上げる。
「やっと来たか」それは声だけで姿はどこにもなかった。「待っていたぞ」
クライセンにはその声が誰のものかすぐに分かった。その名を呟く。
「……ノーラ」
「この時をどれだけ待ち侘びたことか。しかし……どうも騒がしくて適わない。ここは子供の遊び場じゃない。じゃれ合いたいならよそでやってくれないか」
「そんなつもりはなかったんだが……」
「そうだろうな。俺の見間違いだよな。まさかお前がお友達と仲良く馴れ合っているなんて……悪い夢だ。吐き気がする」
ノーラは笑った。
「百年前、お前には俺と同じ匂いがしたんだ。だからお前を唯一の敵として認めた。まさか俺の期待を裏切るためにここに来たんじゃないよな」
「お前の期待が何なのかよく分からないが、同じ匂いと言うのは、どうも面白くない。一体何が言いたいんだ」
「しらばっくれるなよ。お前のその強さは孤独の上に培われたものだ。俺には分かる。いい加減に正体を現したらどうなんだ」
「正体? 何の事だ」
「目を見れば分かる。その氷のような冷たい目。お前は善人ではない。だが悪人でもない。どこにも属さない孤独を超越した者だ」
「私は私だ。お前にどうこう言われたくない」
「違う」その声は心を毒するものだった。「お前は何も欲しがらない。人間とは欲求こそを生きる糧とする。そして愛などという美学を唱えながら子孫を残す。なのに、お前にはそれがない。どういうことか分かるか?」
ノーラはわざとらしく間を置き。
「……分かっているんだろうが、はっきり言ってやる。お前は人間じゃない──化け物だ」
ノーラは嘲笑った。クライセンの不快感を煽る。
「でなければ、生きている意味がないだろう?」
クライセンは何も言い返さない。認める気はなかった。だが、否定もしない。もしそうだとしても、と思う。こんな外道の言うことに耳を貸すつもりはなかった。
「……何を言ってるのか分からないが、私の魔力を封じてどうするつもりだ。お前はこんな小細工で私をどうこうしたいわけじゃないだろう?」
「よく分かってるじゃないか。お前は俺の術中にはまった。ちょっと試してみただけだったんだがな、まさかこうもあっさりと堕ちてくれるとは思わなかったよ。なぜだか分かるよな?」
「…………」
「そうだよ、お前がそんなおまけと遊んでいるからだよ。そいつらがお前の気を散らした。邪魔したんだ。そうだろう?」
そうかもしれない、と口にはしない。
「だが、まだ希望はある。与えてやろう」
クライセンは眉を寄せた。先が読めた。
「そいつらを殺せ」
やはり、と思う。クライセンの顔色が変わった。
「できなければここでゲームオーバーだ。お前はここで死ぬ。人間らしく、血に塗れてな。それが嫌ならそのお友達をお前の手で殺すことだ。そうすれば先に進める。そこに俺はいる」
「……そう言われても魔力がないんじゃどうにもできない。この連中はこう見えても腕利きだ」
「安心しろ。ゲームにはルールがある。そいつらを本気で憎み、心底死んで欲しいと思えばいい。それでそいつらは死ぬ。簡単だろう? 単純な余興だ。待っているぞ。期待して、な」
「……待て!」
そこでふっと声は途切れる。完全に気配も消えた。クライセンは辺りを見回す。一歩下がる。そこには異様な空気が漂っていた。
先ほどまで緊張感の欠片もなかったティシラたちが無表情で立ち尽くしていた。目は開いているが意識がない。だが体は動く。トールが黙って剣を抜いた。マイとキジも少し遅れて剣を構える。瞬きもしない。息もしていない。ティシラとマルシオ、ワイゾンはじっとしていたが、その目の色は尋常ではなかった。
(だから帰れと……)
今更、と思う。そうだ今更だった。
帰そうと思えばいつでもできたはずだった。クライセンはそれをしなかった。できなかったことを後悔する。予想はできたはずなのに、最悪の状況を招いてしまっていた。
魔力がなければ逃げることもできない。どうする──クライセンは考えた。しかし考えても無駄だった。このままでは死ぬか殺すしか方法はない。即決はできない。
だが迷っている時間も、あまりなかった。
それ以上待たずにトールが先陣を切る。その勇ましさは今は鬱陶しいものに感じた。
クライセンはそれを避けた。が、避けきれなかった。腕の服が剥がれ、そこから血が溢れ出す。体勢を整える暇もなくマイとキジが続く。これも避けきれない。当然だ。この二人は百戦錬磨の手練れだ。即死を免れただけでも運がよかったと思うべきである。
クライセンの背中と足の肉が裂けた。片膝をつく。体に力が入らない。痛みはすぐにこずに後からゆっくり訪れてきた。呼吸するのも忘れるほど、体中が緊張する。
意識のない三人は勢い余ってその場に倒れた。それはまるで人形のようだった。
目を開いたまま動かない。クライセンは痛みを堪えてそれに意識を奪われる。
(まさか、死んで……?)
近寄ることはできなかったが、その様子を伺う。じっと見つめる。
倒れた三人はぴくりとも動かない。だが、生きている。確かに魂の呼吸が感じ取れた。
ほっとしている暇はなかった。傍らでは厄介な魔法使いとそのしもべが待ち構えている。
3
先に呪文を唱え始めたのはマルシオだった。瞬きもせずに印を結ぶ。
クライセンの血の気が引く。その印、呪文は……バカな、と息を飲む。
「マルシオ」クライセンは震えた。「お前、何をやっているのか分かっているのか」
その声は届かない。マルシオの周囲に禍々しい魔力が寄り集まってくる。その渦が彼の足元に魔法陣を描いた。
(ノーラ、お前はどこまで……)
クライセンが心底憎み、殺してやりたいと思ったのはノーラだった。だがこの状況を招いたのが自分の力不足なのも認めざるを得ない。そんな自分も恨めしいと思った。
マルシオの周りを黒い靄が包んだ。それは足元の魔法陣から沸き上がってきている。
悪魔召喚の黒魔術だった。天使が悪魔召喚など、あってはならないことだった。黒魔術の中でも最も高等で邪悪で、危険な術だったのだ。
止める方法がひとつだけあった。ノーラの呪いを利用して彼を殺すことだった。
クライセンは迷った。マルシオは操られているだけだ。しかし彼がやろうとしていることは魔法界、自然界でも許されない大罪だった。
殺しても止める価値はある。このままだと自分だけではなく、ここにいる全員が死ぬ。
いずれにせよクライセンが死ねばこの世はノーラに支配されて滅んでしまうのだ。ならばここで残酷な決断をするべきかもしれない。クライセンは考えた。
答えは、すぐに出た。
(……できない)
何度も心の中で繰り返した。理由は分からなかったが、それだけはできないと強く思った。
物理的に彼を殺すことは可能なのかもしれないが、今、自分にその力はない。殺したい、死んで欲しいなど、本気で思うことができなかった。
だが、どうする? このままマルシオに黒魔術を使わせてここで果てるのか。それをじっと待つことしかできないのか。
焦り、苛立つ。自分自身に。そうしている間にも邪悪なる者は奥深い闇の中から呼び出されている。
黒い靄は次第に形を成し始める。その形がはっきりするにつれ、クライセンの絶望はさらに募っていった。靄の中に二つの目が開く。クライセンはその名を呟いていた。
「……ジルヴォード」
それは二つの角を持つ獣の姿をしていた。
魔界のイン・クーラの中心で胡坐をかいている魔獣の総大将だったのだ。黒魔術でも邪神の象徴として崇められている。神殿でハゼゴの魔法陣に描かれていたのもジルヴォードの首だった。
現在は魔王の支配の下、それを呼び出せる術師もいずに長い間魔界に閉じ込められていた。
それが今、天使の魔術で蘇ったのだ。
寒気がした。声が出ない。ジルヴォードはそんな彼を両の目で睨み付けた。そして蹄の付いた前足を出す。
クライセンは待つしかなかった。戦う術も持たない。逃げ道もない。しかし死ぬことも殺すことも考えてなかった。
こんなことは初めてでどうしたらいいか分からなかったのだ。今までも危険に陥ることは何度かあった。死ぬか生きるかの窮地に立った経験もある。何よりもクライセンは死を恐れたことは一度もなかったのだ。
それでもこんなことは初めてだった。今までと一体何が違うのかが分からない、それが彼を恐れさせた。
マルシオも危険な状態だった。黒魔術を行った者は、成功、失敗に拘わらず術師に二倍の呪いが返ってくる。通常の方法としてはその呪いを代行して受ける、所謂「生贄」が必要だった。それもなく行ったときは代わりに術師の魂が削られる。それでも足りないときは、それは想像できないほどの恐ろしい呪いをかけられる。
マルシオは最悪の条件をすべて揃えていた。本来なら術師の持つ魔力と知識が伴わなければ術は成立しない。マルシオの今の力は魔法使いとしては未熟だったが、もともと天使なので秘める魔力は人並みはずれたものがあった。体も魂も削ってしまえば、確かに大魔術も不可能ではない。
問題は、それが本人の意志ではないことだ。このままではマルシオの魂は悪に蝕まれてしまう。
仮に命を取り留めたとしても邪悪に染まり、永遠に暗闇の中で救われることもないだろう。止めなければ──クライセンはそれだけを考えた。しかし手段は見つからない。いや、手段などどこにもなかったのだ。
考えても無駄だった。ただ待つことしかできなかった。
その時、棒立ちしていたティシラの目がキョロリと動いた。その視線の先は、形を成したジルヴォードに向いていた。クライセンはそれに気が付かなかった。
ジルヴォードはまずマルシオの魂を狙った。術師を食らってこの世界に完全に実体化しようと考えていたのだ。ジルヴォードは動物よりは高い知能を持っており、マルシオが未熟であることを素早く察知した。
本来、召還された者は術師の支配下にある。人間界との直接な繋がりのない遠い世界から、魔術によって決められた場所に呼び出される。
そこには契約が成立していた。邪悪な者はそれを破ろうとする。リスクが大きすぎる。だからこそ黒魔術は禁じられていたのだ。
ジルヴォードは次にクライセンを見下ろした。魔力を失い佇む彼を見て、まるで自分が思いも寄らない幸運に見舞われたかのような歓喜の表情を浮かべた。
人間界に召還された上、ここに高貴な魂が二つもあり、自分の思い通りになるのだ。ジルヴォードはどす黒い舌をちらりと出して見せた。その先は二つに割れている。
マルシオの顔が苦痛に歪んだ。ジルヴォードの呪いに侵食されている。ジルヴォードはその隣でみるみる魔力を増幅させていく。完全に実体化するのもそう先ではない。
クライセンは何もしなかった。しかし諦めていたわけではない。彼の中にそんな概念はなかった。何もせずに諦めるという答えは存在しなかった。
ただ、何もできないという現実を受け入れるしかなかった。
「マルシオ」クライセンは意識のない彼に話かける。「私のせいだな……すまない」
マルシオには聞こえていない。
「お前のことだ。口が利けるなら殺してくれと言うだろう。でも私にはそれも適えてやることが出来ない……今の私は何も出来ないんだ」
ジルヴォードがにやりと笑った。鋭い爪をマルシオに近づける。
しかし、それより早く、この重い空気の中でひらりと飛び上がる者がいた。
クライセンとジルヴォードは同時にそれに注目する。
ティシラだ。黒髪を靡かせて、クライセンを挟んでジルヴォードに向かい合う。華麗に着地したその動きは軽やかだった。上げた顔は邪悪に満ちていた。
目の赤さは深さを増しており、牙も爪も長く尖っている。クライセンはそれを見て、ぞっとする。まるで条件反射のように、無意識に。
ティシラの瞳は炎のように揺らめいていた。それを見開き、鋭い牙を剥き出して不適な笑みを浮かべていた。
いつもの彼女ではない。ティシラは胸を張り、低い声で笑い出した。彼女の中で一体何が起きているのか分からなかった。少なくともいい感じはしない。クライセンは何も考えずにティシラを見つめた。
ティシラもクライセンにじろりと赤い目を向けた。その目と合って、クライセンは眉を寄せた。
どこか腹立たしい。見下し嘲るような、いや、まるで勝ち誇ったようなその目。クライセンは今までいろんな悪党を見てきたが、これほど嫌悪を感じたことは初めてだった。
ティシラはそんな彼を無視してジルヴォードに目線を移した。顎を引き、その獣を威圧した。
「ジルヴォード」ティシラの低く出す声には魔力があった。「えらく機嫌がいいようだな」
クライセンはその様子を伺った。嫌な予感がした。
「気に入らん。浅ましい。みっともない。そんな子供の魂で私の支配下から逃れられるとでも思ったか」
ジルヴォードの毛がざわりと立つ。その顔には恐れの色があった。呻き、威嚇する。
「なんだ、その態度は」ティシラは腕を組んだ。「私が疎ましければかかってくればいい。私が怖ければ、今すぐここから消えろ」
ティシラの目に宿るそれで、ジルヴォードは容赦なく圧倒的な魔力の差を見せ付けられた。ジルヴォードはそれに押されて背を丸めてしまう。
クライセンもまた、二人の間で固まっていた。目を細めてティシラを見つめる。まさか、と緊張が頂点に達した。嫌な予感が当たっているとしか思えない。最悪だと思った。今こそこの場から走り去ってしまいたい衝動に駆られていた。
ティシラは腕を解き、じりっと前に出た。同時にジルヴォードが下がる。
「選べ。私に従うか、逆らうか」
じりじりとジルヴォードに歩を進める。ジルヴォードの瞳孔はすっかり細っていた。
「選べないなら」
ティシラは片手を上げて、すぐに振り下ろす。肩の高さで止め、ぴたりとジルヴォードを指差した。
「修羅界に叩き落してやる」
ジルヴォードは体を揺らした。すると別の唸り声が聞こえてきた。
ジルヴォードは混乱しながらその声のする方を振り向いた。そこにはワイゾンが牙を剥き出して震えていた。唸り声は彼の喉から漏れていたものだった。獣の形相だった。そこに彼の意志はなかった。ティシラの魔力に連動して魔物化していたのだ。
ジルヴォードが逃げる間もなくワイゾンが吼えた。そしてジルヴォードに飛び掛り首筋に牙を立てる。
ジルヴォードのそこから黒い血が飛び散った。ジルヴォードは一度体を丸めて、咆哮しながら仰け反った。クライセンは咄嗟に顔を顰めて耳を塞ぐ。
ジルヴォードは雄叫びを上げながら崩れ落ちた。ワイゾンは彼に振り落とされ、その場に倒れる。
次第にジルヴォードの縁がぼやける。再び彼の周りを黒い靄が包んだ。その体は黒い粉となって散り始める。ジルヴォードは口惜しみながらもティシラに屈したのだ。これも獣の本能だった。生き残るためには自分より強いものには逆らわない。ジルヴォードにプライドでもあれば、勝てないと分かっていても踏みとどまったかもしれない。だが所詮は獣。
彼に、魔界の王に逆らうほどの勇気はなかった。
ジルヴォードは傷を負い、靄と共に魔界に帰っていった。
完全にその姿が消えると、ワイゾンが、それに続いてマルシオが人形のように倒れた。まるで死体のように目を開いたまま沈黙した。しんとなった。
最悪の状態は回避された、はずだった。
4
しかしクライセンはそうではなかった。体が固まり、立ち上がる気力もない。
逃げられるなら逃げたかった。だがその道はない。冷や汗が流れる。
そんなクライセンの心中を読んで、ティシラがにやりと笑う。クライセンはそれを横で睨み付けた。
「いい様だな」ティシラは改めてクライセンに向き直る。「魔法王クライセン。それも魔力がなければただの無能な人間か。私は凄く気分がいい」
クライセンは斜めに構えた。
「……死に損ないが。まだ生きていたのか」
虚勢を張る彼をティシラはさらに笑う。
「なに、久しぶりに大掛かりな召還術が行われていたから何事かと思ってな、どこの大馬鹿者がこんな下らないことをしているのか顔を見てやろうとジルヴォードにくっついてきたんだ。そしたらなあ、まさかとは思ったが、やはりお前が絡んでいたか。しかしこんなに楽しいことになっているとは思わなかったぞ」
ティシラは大口を開けて笑った。
「いいね。絶景だ。今のお前をそのまま箱に押し込めて飾っておきたいよ」
クライセンはあからさまに嫌な顔をする。
「よほど暇なんだな……ブランケル」
今、ティシラの中にはブランケルの魂が入り込んでいた。
正確には、ティシラの体を通じて会話しているような状態だった。それでも確実に彼の魂はここにあった。完全にティシラの体が乗っ取られていたのだ。
「その通り」ティシラは牙を見せて。「幸せとは退屈なものだよ。お前みたいな捻くれ者には分からんだろうがな。どうせ未だに独身なんだろ? もてない男は可哀想だな。惨めなものだ」
「……脳が千年以上も前で立ち腐っているようだな。他に考えることはないのか」
「ああ、言っとくが」無視して。「私はお前を恩人だとか微塵も思っていないからな。別にお前なんかにその下らん魔法をひけらかされんでも私はあれで十分幸せだったんだ。お前は勝手にしたいことをしただけだ。そうだろう」
「まあね」
「相変わらず可愛げがない奴だ。私は礼なんか言わんぞ。決して」
「分かったから」クライセンは頭を抱える。「消えてくれ」
その時、ふっとティシラの表情が変わった。声が高くなる。クライセンは気配が変わったのを感じ取って顔を上げる。
「あら、久しぶり。クライセンじゃない。会いたかったわ」
奇妙な光景だった。まるでティシラが一人二役を演じているようだった。
「アリエラ」ティシラは大きな声を出す。「お前までついてくなんて。帰るんだ」
「どうしてよ。いいじゃない」
ブランケルに続いてアリエラもついてきていた。ティシラは何も知らずに親である二人に振り回されていた。
「だめだ」とブランケル。「私もすぐ戻るから先に帰っているんだ」
「さては、あなた」とアリエラ。「また妬きもちね。みっともない」
「そういう問題じゃない。こんな男と口を利くことは許さん」
「どんな男でも許さないでしょ。それにしても」ティシラはクライセンを眺めて。「相変わらずいい男ね。ティシラが好きになるのも分かるわ」
「アリエラ! なんて事を」
「やだ、あなたの方が素敵よ。クライセンはその次だから」
「こんな奴と比べるな。格が落ちる」
クライセンはため息をついて片手で顔を覆った。
「……そういうことは家でやってくれ」
「アリエラ、いいからお前は黙っていろ。私は」ティシラはクライセンを指差す。「こいつに話があるんだ」
ブランケルの剣幕とは対照的に、クライセンは冷たく言い捨てる。
「私はあんたと話すことはない」
「そうはいくか。貴様、この期に及んで私の可愛い娘を誑かしおって。許さんぞ!」
クライセンは肩を落とす。何をどうすればそんな解釈ができるのだろう。思うのは勝手だが逆恨みも甚だしい。そう思うが、いちいち反論する気も起きない。ブランケルは困憊し切った彼に構わず怒鳴りつける。
「しかもなんだ、この有様は! 貴様がどうなろうと知ったことではないが、ティシラを巻き込んでこんな危険な目に合わせるとは。今ここで貴様の首をへし折ってやりたいぞ」
「ふん」クライセンは目を伏せる。「あんたみたいなのをバカ親って言うんだよ」
「何だと!」
ブランケルはかっとなる、が、感情を抑えて黙った。クライセンからぽたりと血が垂れた。今になってトールたちに斬られた傷が痛む。普通ならこんな傷はすぐに治ってしまうのに。いや、普通ならこんな傷すら受けなかっただろう。
「で」ブランケルは落ち着いて。「どうするつもりだ」
「…………」
「間抜けが。魔薬なんぞにやられおって。それが一度でも私を追い詰めた男の姿か」
クライセンは何も言えなかった。
「この中の誰かを一人でも殺せば呪いは解けるようだな」
「……そうらしい」
「なぜ、そうしなかった? 私の知ってる魔法王ならできたはずだが」
「……そうだな」クライセンは顔を上げた。「ノーラの言う通り、こんな奴らに関わるんじゃなかった、いっそ皆殺しにしてやろうかと頭を掠めたよ」
「昔のお前なら手段を選ばなかっただろう。だからこそその強さと地位を手に入れたんだからな」
「ああ」クライセンはふっと微笑んだ。「私はどうやら神にでもなったつもりでいたらしい」
情けない、そう思った。
自分はただの人間だと思いつつ、そうではなかったのだ。
決して彼は「ただの人間」ではいられなかった。その自覚が足りなかったんだと思う。
だがどこかで気づいていた。同胞であるランドール人は故郷を失い、その血を持つ者はもうほとんどいない。希少な存在でありながら、さらにクライセンはその中でも優れた才能と力を持って生まれていた。普通でいられるはずがなかった。
本人はそれをどこかで否定していた。否定したかった。それが自らを孤独へ追いやってしまっていたのだ。
寂しいなどと思ったことはなかった。最初から、一人だったからだ。
大人になるにつれ、クライセンはこの世界に自分を受け入れてくれる場所はどこにもないと気が付いた。
どこにいても自分は「異種」だった。そんな彼が縋ったものは、結局持って生まれたその特異な力しかなかった。これがなければ自分の存在価値はなくなる。それを誇示することだけが彼の生きる目的となっていった。
その魔力がなくなった今、彼は完全に居場所を失った。そう思っていた。
「私も所詮はただの人間だった」クライセンは呟くように話した。「本当は五千年前の戦争で同胞と共に死ぬべきだった。だが生き永らえてしまった。ただそれだけで神だの伝説だの言われてどうすることもできなかった。私は欲しいものが何も見つからなかった。欲しいものなんてどこにもないと思った。それはイラバロスに会って、リヴィオラを受け渡されたときに確かなものになった」
それからクライセンの孤独は確立されてしまった。
そんな彼が初めて思い通りにならなかったのがアリエラだった。ブランケルは彼と等しい、若しくはそれ以上の魔力を持っていた。なのに、戦いを放棄してアリエラと共に石になることを選んだ。その姿を今でも鮮明に思い出す。
力があるのに、なぜ戦うことをやめてしまったのか。本当はずっと気になっていた。
ブランケルとの戦いは、本人の知らないところで傷になっていた。
その忘れていたはずの傷を抉ったのが、ティシラだった。
彼女の風貌と、アラモードという名前だけでクライセンを苦しめていた。ティシラは何も知らずに彼の傷を煽り続けていたのだ。
だが痛くはなかった。クライセンはその苦しみを悪いとは思わなかった。なぜだか分からなかった。初めての感覚だった。だから彼女を傍に置くことを許していたのだ。
ティシラとマルシオは、二人もまたこの世界では特異な存在だった。それぞれに複雑な立場や思いを抱えていた。そんな二人は神と呼ばれた自分に物怖じせずに馴れ馴れしく付きまとってきた。彼女らの存在が僅かな時間で彼を変えていった。クライセン自身が変わったというより、周りの自分を見る目が変わったと感じていた。
彼女たちがくっついて騒いでいるだけで、更に人が寄ってきたのだ。クライセンはいつの間にか、何があっても離れない二人がまるで体の一部のように思えていた。切り離してしまえばそこから見えない血が溢れ出し、もう二度と取り戻せないのだろう。
これが情だと気づくのに、時間はかからなかった。
「殺すことなんかできない」
クライセンは言った。ずっと言えずにいたことを、今ここで、なぜ幻である因縁の相手に言ってしまったのか分からなかった。
しかし、ふっと楽になったような気がした。
今まで誰にも心を開かず、気を張り続けてきた。休んだときはなかった。だけどこんなにも簡単で、こんなにも楽だったなんて。
こんなことも知らなかったなんて、世界一と呼ばれて長い間、一体何をしてきたんだろう。
「死ぬこともできない」虚ろなまま、続ける。「怖くはない。しかし、こいつらを悲しませてしまうんだ。下手をすれば後を追ってくるかもしれない。私がこいつらに何も与えていないからだ。こいつらが欲しいものを私が与えてやれるかどうかは分からないが、私はやっと本当の意味で生きる目的を見つけたような気がするんだ。なのに、できもしないくせに、こいつらを追い払おうとしていた。それが私の間違いだった」
ブランケルはじっと聞いていたが、肩を竦めて毒づいた。
「ふん」クライセンを睨み付けて。「何を言っているのか、私には全く意味が分からん。興味もなければ関係もないね」
クライセンはちらりとブランケルを、ティシラを見た。やっぱりこの男とは分かり合えるものは何もないんだろうなと思い、力を抜いた。それでいい。それが心地いいと思った。表情が緩む。
「私には分かるわよ」
アリエラが再び口を挟む。
「アリエラ、まだいたのか」
「残念だわ」アリエラはブランケルを無視して。「今のあなた、結構好きよ。もったいないことしたわ。考え直そうかしら」
「アリエラ!」今までの雰囲気をぶち壊す。「何て事を」
「冗談よ」
「クライセン!」見事な八つ当たりだった。「もうお前と話すことはない。話したくもない! 貴様や世界がどうなろうと知ったことではないが、ティシラに何かあっては困る。取り返しが付かなくなる前に娘は連れて帰るぞ。頼まれてもお前だけは助けてやらんがな!」
クライセンはすっと表情を消した。その変化に、二人は気づかない。
アリエラは帰ろうとせずにブランケルを煽る。
「ケチ。助けてあげなさいよ」
「ケチとは何だ」
「私たちがこうして幸せになれたのも、可愛い娘を授かったのも彼のお陰じゃない」
「私はそうは思わん。大体こいつはアリエラといい、ティシラといい、私に大切なものに悉くちょっかいを出そうとする。忌々しい。ティシラは魔界の姫なんだ。いつまでもこんな根性の曲がりまくった魔法使いなんかと一緒に居させてたまるか。何が『何も与えてない』だ。子種でも与えられたらたまったもんじゃない」
「ティシラが欲しいっていうなら別にいいじゃない」
「冗談じゃない! ティシラを不幸にしてたまるか」
「不幸になるって、あなたが決めることじゃないでしょ」
「ティシラの将来を思えばこそだ。いっそこんな奴、ここで殺してやりたいくらいだ。鬱陶しい。分かっているのか、クライセン。お前は今、魔力も持たないただの人間だ。私が捻り殺さないだけでも有難いと思え」
「そんなんだからバカ親って言われるのよ。ティシラだって女の子なのよ。恋の一つや二つ、できない方が私は心配だわ。だってこの子、いくらいい男を宛がっても全く興味を示さなかったじゃない。せっかく好きな人ができたのに、なんで見守ってあげられないの」
「ティシラに何かあったらどうする。男なんて他にいくらでもいるんだ。こいつだけは許さん」
「嫉妬でしょ」
「うるさい」
「嫌いになるわよ」
ブランケルは引きつる。アリエラのその言葉は彼にとって一番痛いものだった。これを言われるとブランケルは何も言えなくなる。
「……君たち」クライセンはさすがにうんざりしていた。「いいから帰ってくれ。頭が痛くなってきた」
「帰るとも!」ブランケルは気を取り直す。「私だってこれ以上お前の顔なんか見ていたくない。同じ空気を吸うのも反吐がでる。ここで一人でくたばれ。ティシラは連れて帰る。これでお前との腐れ縁もお仕舞いだ」
クライセンは何かを含んだ目でじっとティシラを見つめた。憤慨し、仁王立ちする彼女にすっと手を伸ばす。その手には流れた血がついていた。
ブランケルは眉を寄せる。クライセンの微かな笑みに寒気を感じた。
「嫌だね」クライセンは目を離さない。「ティシラは返さない」
「な、何を……」
ブランケルが歯を剥き出した。
が、その時、突然ティシラの体は雷に打たれたような衝撃を受けた。そして意志に反して体が固まり、自由が利かなくなる。バカな、と思う。クライセンは魔法が使えないはず。何が起こったのか、ブランケルはすぐに気が付く。
「貴様……」
「ティシラ」クライセンは意識のない彼女に語りかける。「こっちへおいで」
「純粋な少女の心を誑かす気か」
クライセンの笑みには自信が満ちていた。
「やめろ。この節操無しの変態魔法使い!」
「何とでも言え」
クライセンにはブランケルの罵倒など痛くも痒くもなかった。ブランケルは嫌だ、嫌だと心の中で繰り返す。しかしティシラの体は言うことを利かない。それどころか、次第にブランケルの意識を遠ざけようとさえしている。
ブランケルは踏ん張った。
「クライセン! 貴様はティシラをどうするつもりだ。ここで死んでしまうのかもしれないんだぞ」
「それは彼女の体だ。どうするかなんて本人に決めさせろ。ティシラはもう一人前の魔法使いだ。バカ親の言いなりになってたら、それこそダメになる」
「貴様……殺してやる」
ブランケルは容赦なく殺気を放ち、クライセンに浴びせる。しかし彼は全く動じない。いつもなら自分の一瞥だけで誰もが縮み上がるはずなのに。
額に汗が伝う。ティシラが無意識にブランケルを体から追い出そうとしている。
足が一歩前に出る。逆らえない。
ティシラはクライセンに呼ばれて、一歩一歩と重い足を進めた。クライセンの手にもうすぐで届く。そこでティシラは震えながら手を出し始めた。
それを見つめていたクライセンは、苦しみもがくブランケルに歯を見せた。
「殺せるものならやってみろ」
クライセンはティシラの手を掴む。ブランケルは反射的に叫んだ。
「触るな!」
クライセンはわざと意地悪な笑みを見せ付けた。
「さっさと消えないともっと触るぞ」
「やめろ」
とうとうブランケルの意識が剥がれかけた。そこに再びアリエラが出てくる。
「ブランケル、いい加減にしなさい」
そこでさすがのクライセンも一瞬固まった。
「クライセン」アリエラは微笑んだ。「あなたの噂はいろいろ聞いてるわ」
「な……噂だと?」
「あなたみたいないい男が五千年も生きてて浮いた話がないわけないでしょ」
「い、いい加減なことを言うな」クライセンは戸惑っていた。なぜか小声になる。「何の話か知らないが、私だってありもしない噂で迷惑したこともあるんだ。鵜呑みにしたければ勝手にしろ」
「大丈夫よ。全部が本当だとは思ってないし、ティシラには黙っててあげる……でも、この子を傷つけたら私が許さない」
アリエラの瞳が厳しく、冷たく尖った。
「……言っとくけど、私のお仕置きはブランケルより残酷だからね」
アリエラはティシラの体を借りて毒の微笑を浮かべる。姿は少女だがそこには、まだティシラにはないはずの大人の色気が漂っていた。クライセンは隙を付かれて思わず身震いする。ただでさえ魔力がないのに、卑怯な、と思いながら目を伏せる。それとほとんど同時にアリエラはティシラの体から離れていった。
「ティシラをよろしくね」
そう言い残し、ふっと二人の意識が消える。きっとブランケルはアリエラに無理やり連れて行かれたのだろう。喚きながらアリエラの言いなりになっているブランケルの姿が想像できる。
ティシラの体の力が抜け、崩れ落ちる。クライセンは彼女の体を受け止め、そっと手を離す。ティシラの体が死体のように重く感じた。
薄く開いたままの瞳に光はなかった。しかし生きていることを確認して安心する。
もう誰もいない。辺りを見回す。クライセンは深くため息をつく。なんて騒がしい親子なんだと、呆れに似た感想があった。あれならティシラの精神力が普通でないのが納得できる。
そんなことよりと、自分の体を確認した。血はほとんど止まったものの傷はまだ癒えていない。
魔力も、ない。
そこにあるのは静寂だけだった。クライセンは全身の力が抜け、体を屈めた。両手をついて俯く。目眩がした。考える気力もなくなる。
頭を垂れるとそのまま視界に地面が迫ってきた。どさりと倒れ、深い闇に陥った。
5
闇の中で何かが聞こえた。それは次第に近づいてくる。黒が薄れて白くなる。
目を開くと色のある世界に引き戻された。そこには体を屈めて心配そうに自分を見下ろしているティシラの姿があった。
クライセンは何が起きていたのか、把握するのに時間がかかりそうだと思った。
「クライセン様」ティシラが泣きそうな顔をしている。「大丈夫ですか」
「気がついたか」マルシオも身を乗り出してくる。「急に倒れるなんて、一体どうしたんだよ」
クライセンは眼球だけを動かして一同の顔をそれぞれに確認した。トール、ワイゾン、マイ、キジも自分の様子を伺っている。
クライセンは体を起こす。そういえば、と自分の腕を触った。あったはずの傷がなかった。
(……夢?)
そうだ。クライセンは自分の手を見つめた。集中する。一同はクライセンの不可解な行動に首を傾げていた。
彼は黙って指を動かす。そして拳を握る。再び開いたかと思うと、それに思いっきり力を入れる。
「!」
同時に、自分を囲んでいた一同が見えない力で弾き飛ばされた。
「な、何するんだよ!」
思いがけず体のあちこちを地面に打ち付けて顔を顰めている。クライセンは無表情でそれを見回す。
(魔力が……戻ってる)
クライセンはノーラの言葉を思い出した。
『お前は俺の術中にはまった──』
そうか、と思う。魔薬に毒されていたのは自分だけだったのだ。脳を侵蝕されて夢を見ていたのだ。
しかしただの夢ではなかった。そこには二重次元が生まれていた。クライセンが魔薬に支配されてしまっていたら、あの夢が現実になっていたのだ。
だが、なぜ──いや、愚問だった。あの世界でノーラが唯一予想できなかった出来事があったはずだ。
あの能天気な夫婦の介入だ。ブランケルが何だかんだ言いながら、去り際にクライセンから魔薬を取り除いていってくれていたのだ。
決して彼のためではない。それは我儘で手に負えない、愛する一人娘のためだろう。
重々承知していた。クライセンは微笑んだ。
(礼は言わない。これで貸し借りなしだ)
二度と会わない、会いたくないと思っていた。だが今は会えてよかったと心底思う。力を貸してくれたというだけでなく、話ができたことが嬉しかったのだ。
ずっと長い間、蓄積されてきた重いもののひとつが軽くなった気がしていた。縁とは不思議なものだと、つくづく思い知る。
一人で思い耽るクライセンを、一同は意味も分からないまま遠巻きに見つめていた。
どうやら元気そうだ、また何をされるか分からない、と、近づくのを躊躇っていた。するとクライセンが顔を上げた。
「みんな、すまないね。怪我はないか」
一同は戸惑う。まだ疑いは晴れない。その中でティシラだけが震えだした。
「クライセン様」今にも泣きそうな声で。「大丈夫なんですか。どこも痛くないですか」
隣でマルシオが不満をぶつける。
「痛い目にあったのは俺たちだよ」
ティシラはそれを無視して目を潤ませている。クライセンは相変わらずだと安堵した。深く息を吸う。
「心配かけたね」
その一言でティシラは涙を零した。夢中でクライセンに抱きつく。クライセンは驚く。が、再び微笑んだ。他の者も訳が分からないまま、安心だけはした。
(ノーラ……)クライセンの目には青い光が蘇っていた。(お前には何も奪わせない。何も与えない)
魔力を失い、再び取り戻した今、クライセンはその価値を噛み締めた。
そして、彼の中では確実に何かが変わっていた。