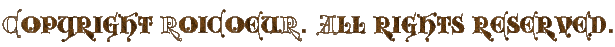第16章 扉





1
神殿の最下層でノーラが一人、壁の魔法陣を眺めていた。
もう彼の手下はすべて倒され、味方はいない。いや、最初からそんなものはいなかった。彼は誰も味方だとか仲間だとか思っていなかった。
ギメルとハゼゴも信頼していたわけではない。役に立ってくれれば彼らの望むものは与えてやるつもりだった。だがその後の保障は何もなかった。魔薬を使えばどうせまともではいられない。
それを分かっていて、ノーラは素知らぬ顔をしていたのだ。思ったよりは使えなかった。十分楽しませてくれたとも思う。どっちでもよかった。
結果は同じなのだ。ノーラの目的はすべてへの絶望。それもただ、自分の欲求が満たされさえすればそれだけでよかった。
ノーラは不適な笑みを浮かべた。
彼が来る。彼を倒すときが訪れる。そしてこの世は滅ぶ。この手によって──。
ノーラはクライセンが必ずここに来ると確信していた。
罠をかけたものの、逃げ道は用意してやった。きっと何らかの方法で回避するはずだ。ノーラは彼に期待していた。
クライセンは人々の希望だった。それを打ち壊すことがノーラの楽しみだった。
初めは彼の存在など気にも留めていなかった。魔法王などという弱い人間の幼稚な理想など、幻に等しいと思っていた。
しかしクライセンは存在した。彼は「本物」だったのだ。
ノーラはそれを認めた。クライセンが魔法使いだとかどうかということは関係なかった。彼の力を含め、持って生まれたもの、内に秘めたもののすべてがノーラを刺激した。
生まれて初めての障害だった。それをこの手で倒したい。この世を滅ぼす前に。
相打ちという結果はノーラを喜ばせていた。まだ時間はある。お互いが持つもののすべてを準備して、心置きなく戦える。そして今その時が訪れようとしていた。高揚せずにはいられなかった。
気配を感じる。海底の奥深いところに足音が近づいてきた。彼がやってきた。ただ自分に会うためだけに──そう思いたかった。
ノーラはゆっくり振り向いた。そして改めて挨拶する。
「会いたかったよ」
そこにはノーラが待ち焦がれていた宿敵がいた。クライセン・ウェンドーラ。
ノーラは彼を笑顔で歓迎する。しかしクライセンは笑みの欠片も持っていなかった。その青い目には冷酷な色だけを灯している。ノーラはそんな彼の態度を気にも留めない。
「とうとう俺の夢が叶う」ノーラは両手を広げた。「この時を百年待った」
クライセンは答えない。じっと彼を睨み付けている。
ふっとノーラの表情が消えた。そこにいるのは、彼だけではないと気づく。
クライセンの背後から彼の「仲間」が一人、一人と姿を現す。面子は誰一人欠けていない。なぜ──少し考え、目を細める。
「お前に俺の魔薬は効かなかったか」
代わりにクライセンが口の端を上げた。
「あれは効いたよ。さすがに驚いた」だが冷ややかな目は変わらない。「しかし普段の行いがいいんでね、奇跡を授かったんだ」
一同はクライセンの背後で彼の後半の台詞に疑問を感じたが、とりあえず今は口を開かない。
「なぜだ」ノーラは面白くなさそうに。「なぜそいつらをここへ連れてきた」
「連れてきてない。勝手についてきただけだ。気にしなくていい。私たちの力の前には何の支障も来たさない、ただの弱く小さい生き物だ」
一同はクライセンに視線を集めた。訝しげな顔をするが、ここにきてやっと本音が聞けると、黙って彼の言葉を待った。
「私はその弱く小さい生き物を守らなければいけない。そのために生き延びた。そのためだけにここにきた」
ノーラはクライセンの言ってる意味が分からなかった。
「何を言っている」ノーラの声が低くなる。「ここに来て笑い話か? それとも、もしそれが本音なら……お前がここにいる意味はない」
「私がどこにいようがお前にゴチャゴチャ言われたくない。それにここは私の故郷だ。去るとするならお前の方だ。まあ、ここがどこだろうと関係ない。私は用があってここに来たんだ。百年もかかった。門前払いはないだろう」
「理解できない。俺はこの時を楽しみにしていた。ここには俺とお前だけで十分だ。なぜ邪魔を入れる?」
「……うるさいな」クライセンは眉を寄せる。「少し喋り過ぎたんだ。今まで生きてきてこんなにたくさんの人間と喋っていた時間はなかった。慣れないことをして、少し疲れているんだ。だからお前なんかとこれ以上話していたくない。さっさと用を済ませよう」
クライセンは深く息を吸った。じわりと魔力が彼を包む。
「さあ、見せてみろ、魔薬王。お前の最期の力を」
歯を見せてノーラを挑発した。
その迫力に恐怖を感じたのは、彼の背中を見守るティシラたちだった。ぞっとした。今まで何に対してもいい加減で反応の薄かったクライセンが、自ら敵に立ち向かっている。
これまでも彼は非凡な能力を見せてきた。これから何が起こるのだろう。
一同はもう覚悟できていた。何が起きても驚かない、とは断言できなかったが、すべてを見届け受け入れる。そのつもりで来たのだ。そう心を据える。
ノーラは黙ってクライセンを見つめた。そして笑う。まるで見下したように。
「残念だ」ノーラは呟いた。「変わってしまったな、魔法王。いや、最初からそうだったのかもしれない。俺の目測誤りだったのか……それもいい。為すことは変わらない。この世界に訪れる結末もな。ただ俺の楽しみが減っただけだ。寂しいが、仕方ない。これが現実だ。この世に期待を抱いた俺が愚かだったよ。どうやら時間を無駄にしてしまったようだ……そうだな、もう終わりにしよう」
ノーラは懐に手を入れる。そこから何かを取り出した。掌サイズの小瓶だった。その中には液体が入っている。それを掲げて。
「これが何かは分かるよな」
クライセンは頷いた。
「もちろんだ」
そこにマルシオがクライセンに駆け寄る。
「おい」クライセンのマントを掴む。「何だよ、あれ」
「魔薬だろ」
「それくらい分かる。あいつ、何をするつもりなんだ」
「聞いてどうする」
マルシオはむっとする。どうせ聞いたところで何もできないだろうと聞こえた。否定はできなかったが、そんなもの、聞いてみないと分からないじゃないか。いつものこと、いつもは我慢してきた。だが今回はそうはいかない。我慢しない、したくなかった。
「……なんで」マルシオはクライセンのマントを激しく引っ張った。「あんたはそうなんだよ!」
怒鳴るマルシオを止めようとトールが肩を掴む。
「マルシオ、やめろ。こんなところまで来て喧嘩するな」
「うるさい!」マルシオはトールの手を振り払い。「こんなところまで来たから聞いてるんじゃないか。なんであんたはそうやっていつまでも人をバカにするんだよ。何の役にも立たないならなんでここまで連れてきた。なんで俺たちがここまでついてきたと思っているんだよ」
マルシオは必死に、まるで子供が駄々を捏ねるようにクライセンに掴みかかった。
「あんたが心配だからじゃないか! あんたは、俺たちなんかに心配されるほど弱くもないだろうし、俺たちなんかいてもいなくてもいいのかもしれないけど。俺たちはそうじゃない。あんたが魔法王だからじゃない。あんたに何かしてもらおうなんて思ってない。大体な、性格悪いし協調性はないし、はっきり言ってあんたなんかに今更何も期待なんかしてないんだよ。勘違いもいい加減にしろよ」
マルシオは捲くし立て、急に黙る。クライセンは予想以上に突っかかってくる彼に驚き、少々困った顔をしていた。
「それでも」マルシオは息を整え。「なんだかよく分からないけど……あんたに死んで欲しくないんだよ」
違う。そんなに難しいことじゃないと思う。マルシオは手を下ろし、言葉を変える。
「……一緒にいたい。この中の誰も、いなくなって欲しくないんだ」
マルシオは訴えるような目でクライセンを見つめた。
「なあ」そして、俯く。「クライセン、あんたはこれから……一人でどこに行くつもりなんだ」
マルシオの肩が揺れている。みんな同じ気持ちだった。
2
クライセンは一同の顔を一人一人見ていった。その表情は様々だった。目線をマルシオに戻す。
「マルシオ」クライセンは小声で。「これを」
言われて、マルシオは顔を上げた。そこにはあの銀の箱を差し出すクライセンがいた。
「預かっててくれないか」
マルシオは受け取った。それは前も手にしたことがある、あの青い石が入った菱形の小箱だった。一度は突き返したリヴィオラだ。今回は黙って握り締める。マルシオは中を確認しなかった。涙が零れ出した。
「必ず」クライセンは微笑んだ。「取りにくるから」
もう何も言えなかった。これ以上は無理だと思った。彼を止めることはできないと、みんなが理解した。
しかし、一人だけはそうは思っていない者がいた。だが彼女は今この場では何も言わずにその光景を傍観していた。
クライセンは再びノーラに向き合った。
「お別れは済んだか」ノーラは嘲笑った。「そんなに名残惜しいなら、みんな仲良く死ねばいいのに」
「死ぬのはお前だ」クライセンは間をおかず切り返す。「……これが何か分かるか?」
クライセンは懐から小瓶を取り出して見せた。ノーラは眉を寄せて、それに見入った。
「……それは」ノーラは次第に興奮し始める。「そうか。そうだ、それだ。それでいいんだ……やはりお前は俺の思った通りの男だった!」
ノーラは体の奮えを抑えた。顎を上げ、目を輝かせる。そして小瓶を、魔薬を持った手を掲げた。
「さあ、始めよう!」
ノーラは親指で蓋を開ける。そして中身を自らに落とした。口を大きく開き、その液体を流し込む。すべてを飲み干し、ノーラは大きく仰け反った。
ノーラの体からジワジワと煙が立つ。それを取り巻く空気が変わる。
一同は一歩引く。ノーラは次第に煙に包まれ、その姿を隠した。
背後の魔法陣が光り出す。目が眩むほど。
ぐらりと一度、大きな揺れがあった。それを合図に地震が起きる。ただの地震ではなかった。空間そのものが振動しているようだった。
魔法陣と煙の間の地面が割れる。そこから何かがゆっくりと迫り出してくる。一同は立っているのがやっとだった。
しかし気をしっかり持ってそれを見つめる。煙は起こる風に掻き消されていく。そこにノーラの姿はなかった。
代わりにそそり立っていたのは、大きな扉だった。
それは闇の色をしていた。そこにあるだけで何もかもを圧迫する。中に何があるのかも分からないのに、ただ恐怖だけが心の中に流れ込んできた。好んで近づく者はいないだろう。
なのに、なぜ「それ」は扉の形をしているのだろうか。誰も入れないなら扉など必要ないはずなのに。
しかし「それ」は何かを見つけたのだ。中に歓迎する何かを。もしくは、何かが「それ」に無理やり扉を作ったのかもしれない。
いずれにせよ「それ」は今、ここで生まれたのだ。
扉の中身が迎え入れたものは、かつてのノーラだった。もうノーラはノーラではなく、人間でもないのだろう。それはこの扉の向こうだけが知っていた。闇は彼を迎え入れたのだ。
ティシラが身震いした。その異常な空気は、自分が知っている、そして決してここにあってはいけないものだと感じた。慌ててクライセンに駆け寄る。
「クライセン様」その圧迫の中、大きな声を出す。「あれは……まさか!」
クライセンは扉を見つめていた。手は魔薬の瓶を握り締めている。
「そうだ」虚ろな目で呟く。「修羅界への入り口だ」
一同は驚愕した。
一度はその名を耳にしたことがある。だが本当に存在しているとは思っていなかった。彼らだけでなく、人間のほとんどはそれを認識していなかった。
ただ、一部の種族を除いては。それは魔族だった。
人間の間では、罪を犯した者が落とされる言われる架空の牢獄を「地獄」と呼んでいた。大抵が子供の頃にそんな脅しの寓話を聞かされる。実際そんなものは存在しなかったのだが、そのモデルとなったのが暗闇の世界とされる魔界だった。
そしていつの日か魔界にも、子供騙しで「地獄」という言葉が使われるようになった。
魔界で「地獄」と呼ばれるものこそが修羅界だったのだ。修羅界は魔界でも恐れられる神聖な空間だった。
修羅界は魔界の一角にある、魔界の王でさえ手出しできなかった空間だった。手出しできる者などこの世にいなかったし、する必要もなかった。あってないような、そんなあやふやな空間だったから。
そこには何も存在しない。無いところに在る。まさに虚無の塊だった。
サンディルが暇だからと調べ始めたのは修羅界の存在理由だった。
いつの間にかそこにあった無意味な空間に興味を示した。何も分かるはずがないと思いつつ、今まで誰もが無視してきたものに注目した。
サンディルは一人で没頭してしまった。それは興味深いものだった。修羅界は何も無いところに存在するものだった。
しかし、無いのではない。在る。その矛盾の世界もまた、自然の一部なのだと思った。
人間の無意識に似ている。意志はなく、制御できない。無いことに意味がある。
サンディルは気がついた。修羅界もまた、この世を支えるためになくてはならない存在なのだと。
それで満足すればよかった。そこで終わればよかったのだ。だがサンディルの興味は尽きなかった。その時はまだ弾き出される答えが何なのか分からなかった。彼自身が求めているものも何も。
ただ修羅界に誘われるように研究を続けてしまった。
修羅界には物質であるものは何もなかった。ただの魔力の塊だった。しかしその量は膨大なものだった。計る手段はなく、サンディルは「無限」と名づけた。その言葉が最も相応しいと思った。無限の魔力の塊。そこに介入できるものなどこの世にないと確信した。今の世には──まだ、いない。
ならばそれ以外のどこかにはいるのだろうか。若しくは、まだこの世にない新しい何かならばどうだろう。サンディルは考えることを止められなかった。
それが生まれるとするならば、きっとまだ先で、それもここではないどこかなのかもしれない。それは修羅界とも魔力とも呼ばれないかもしれない。言葉も違い、人の形をした者には発音できない名前かもしれない。それが何なのか、知りたかった。
待ってはいられなかった。サンディルはそれを探し求めた。魔力、魔法、魔術、そして魔薬。サンディルは自分の持つ知識のすべてを集結させた。結果、彼は恐ろしいものを手に入れた。
サンディルが辿り着いたのは、究極の魔術だった。自然ではなく、人の手によって新しい生命を生み出す「禁術」。その媒体が未だ誰の支配下にもない修羅界だとしたら、そこには何が生まれるのだろう。
彼の心は高ぶった。その時、やっとサンディルは我に返った。そして震え出した。一体自分が何を作り出してしまったのか、初めて気がついた。
それは決して踏み込んではならない神の領域だった。それは賢者である自分が一番よく知っているはずだった。
サンディルは混乱した。自分のしたことを償う方法が見つからず、隠すことしかできなかった。すべてを隠して墓の中に持っていってしまえばそれでいいと思った。
末梢することができなかった。そうすべきだったのに、サンディルはそれができなかった。自分の作り出したものを自らの手で殺してしまう勇気が出なかったのだ。
そして最悪の結果を導いた。
それは彼の息子、クライセンの手に託されることになった。サンディルはその時深く、深く自分を責めた。息子をこんな危険な目に合わせるくらいなら、それを抱いて死んでしまえばよかったと思った。
それを否としたのは、他ならぬクライセンだった。口では散々サンディルを罵ったが、それも生きているからできることである。クライセンは滅ぶことを踏み止まってくれた父を受け入れた。
その時、サンディルは改めて自分が愚かではなかったと思い直した。愛する息子を信じる。それだけが老いた賢者にできる最後の役目となった。
扉がゆっくり、ゆっくり開き始めた。中からノーラが招いていた。
空間はさらに揺れる。一同はそこに引き込まれる錯覚を起こした。それは錯覚でも現実でもなかった。
扉の向こうは無限。人間界に実体化した修羅界は、そこにあるすべてを吸収しようとしていた。自然の法則が、秩序が狂い始めていた。
「……何が起こるの」
ティシラは呟いた。その隣でクライセンは一歩前に出る。扉に招かれ、誘われるように。
「この世界はどうなるんですか!」
クライセンは足を止めた。扉の中から風が起こった。一同は巻き込まれそうになりながら身を屈める。クライセンは振り向かないまま話した。
「ノーラは人間であることを捨て、自らを修羅界に投じた」
「修羅界には何も存在できない。無理です」
「今まではそうだった。だがそうでない者が今、ここで生まれたんだ」
「それが魔薬の力だというんですか」
「魔薬が導いた力だ」
ふっとティシラはクライセンが持っていた瓶を思い出した。まさか、と思う。咄嗟にクライセンの腕にしがみついた。
「何をする!」
「こっちの台詞よ。何を考えているんですか」
一同も何かに気がついた。ノーラ自身が何をして、今どこにいるのかも理解できていない。しかしそれが取り返しのつかない恐ろしい所業であることだけは分かる。
たぶん、クライセンが持っているのはノーラが飲んだ魔薬と同じもの。だとしたら、彼はノーラと同じことをしようとしているのではないだろうか。そう思った。
扉が大きく開いた。激しく風が巻き起こる。立っていられずに地に伏せる。もう問答している時間はなかった。
「聞いてくれ」クライセンはティシラの手を掴み返した。「私は帰ってくる、必ず」
「……いや」
「時間は限られていた。いや、そんなものは言い訳にしかならない。これしかない。今この時代、この世界にはこれしかないんだ。最初はノーラを倒すためならどんな手段を使ってもと考えた。この世がどうなろうと関係なかった。脆弱な生き物など、強大な力の前に潰されるのは当然の成り行きだと思っていた。今更それを詫びる気はない。だが。これだけは言わせてほしい。今は違う。気が変わったんだ」
クライセンは微笑んだ。
「私は、四代目魔法王だ――奇跡を起こそう。この世の弱く、小さいもののすべてを、君たちを守るために」
「……そんなのいや。あなたは人間よ。修羅界なんかに入ったら出られない。それに修羅界が支配されたら魔界も滅ぶ。この世も全部失われる。そうなったら誰も生きていられない」
「滅ぼすものか」
「あなたがする必要なんてない。あなたは一人じゃない。あなたがいなくなったら悲しむ人がたくさんいるの。私はあなたがいない世界になんていたくない。この世に平和が訪れても、あなたがいなかったら何の意味もないの」
「一度でいい。私は魔法王として、生まれ持ったこの力で人々の希望になってみたい。英雄として称えられなくても構わない。もしかしたら私のすべてを持ってしても及ばないかもしれない。私自身も何が起こるか予測できないでいる。だけど、たった一度でいい。大切なものを守るために命を懸ける。その末に何があるのか、この目で見てみたいんだ」
そこでマイが体を起こす。
「ちょっと、あんた」眉を寄せて、大きな声を出す。「魔薬なんか使ったら、あんたもノーラと同じじゃない!」
「…………」
「最低よ。魔薬に溺れた者の結末を私たちは何度も見てきた。その悍ましさを誰よりも知ってる。あんなの、ただの化け物よ。いいえ、それ以下だわ。この世で一番弱くて、醜い生き物よ!」
寡黙なマイが口出しせずにはいられなかった。ワイゾンとキジが必死で訴える彼女を見つめた。そしてクライセンに目線を移す。彼は分かっている、とでも言いたげだった。
「君は」だがその優しい笑みは消えない。「強く美しい女性だ。そこの船長や船員は少々間抜けで頼りないが、ずっと傍にいてやってくれ。こいつらは君がいないとダメになる」
マイは俯いた。悔しそうに。それは自分の無力さを悔やんでいたのだ。歯を剥き出して、クライセンを睨み付ける。
「そんなこと、あんたなんかに言われなくてもそのつもりよ!」
それが精一杯だった。それが彼に言い返せる言葉の限界だった。本当はもっと酷いことを言いたかった。クライセンが怒るほど、酷いことを。でも、言えなかった。クライセンは浅く頷いた。安心したように。そして今度はトールに向く。
「トール」
トールは呼ばれても返事をしなかった。彼の言葉を待つ。
「言い忘れていたが、ライザから伝言があった。『幸運を祈っています』と。国はあんたがいなくても立派に戦ってくれたようだ。王位なんか気にせずに彼女の望みだけを叶えてやれ」
トールは俯いた。いろんな思いが駆け巡った。今はクライセンとの別れを惜しまずにはいられない。
「君は本当に」クライセンに皮肉な笑みを送る。「……嫌な男だ」
クライセンも同じ表情を送る。そしてほんの少し、間をおいて。
「……パライアスは素晴らしい国だ。守る価値がある」
それは「魔法王」としての言葉だった。
受け取って、トールの中に嬉しさがこみ上げた。同時に悲しみを止めることができなかった。
友だと思っていた男が突然、遠く見えたのだ。やはり、と思う。クライセンは紛れもない魔法王だ。
アンミールが滅ぼしたはずのランドールが五千年の時間をかけて許してくれた。いや、きっともうずっと前からランドールは恨んでなどなかったのだろう。
このたった一言が欲しくて足掻いてきた。このたった一言を待ち続けてきたのだ。今の一瞬という時間が尊くて、尊くて仕方なかった。
トールはその言葉を永遠に忘れないように、無意識に心に刻み込んでいた。
風はさらに強くなる。これ以上はもう待てない。クライセンは扉に向き直り、ティシラを突き放す。
「……クライセン様!」
クライセンは扉の中へ飛び込んでいった。すると扉は彼についていくようにその口を閉じた。
風は収まり、静寂の中、聳え立つ扉だけが口を閉ざして何も言わなかった。
誰もすぐには気がつかなかった。
扉が閉まる瞬間、ティシラも体を丸めてそこに潜り込んだことを──。
3
そこは闇に包まれていた。
黒一色の世界だった。いや、それは黒ではないのかもしれない。白にも見える。そこにまだ色は存在していなかった。色だけではない。何ひとつ名前を持っていなかった。
その中に一つの意識があった。まるで水の上に浮いているような感触だった。これが水でないなら、何と呼ぼう。
沈んでいっていた。たぶん、そんな感じだと思った。その体に何かがふっと当たった。手を触れる。地面だと思った。
それは、今生まれたのだ。意識はそれを見つめた。だがまだ何も見えない。もうすぐ色がつくだろう。若しくは自分がそれを認識できる触覚を持つべきなのかもしれない。
自分が後から来たのだから。それとも、これを造ったのは自分なのかもしれない。歩くために必要としてそこに造ってしまったのかもしれない。
それは虚ろだった目を大きく開いた。その目から「赤」が生まれた。体の感触がなかった。が、じんわりと流れるように手や足があることを確認できた。
立っているのか座っているのか分からない。左の耳と肩に何かが触れているのを感じ、自分が横になって倒れているのだと判断した。次第に感覚が戻るのを感じていた。それは戻っているのではなく、今生まれているのかもしない、ということまでは考えなかった。
他に気になることがあったからだ。意識は体を起こして座り直した。左右に首を動かす。
何かがおかしいことに気がつく。嫌な予感がする。俯いて、恐る恐る自分の手を見た。
視界に写ったそれは、茶色で毛むくじゃらの獣の手だった。その手で自分の体や顔を触る。全身が短く粗い毛で覆われていた。体型も今までの自分とはかけ離れている。
その生き物は、人間の世界で「ネズミ」と呼ばれるものに似ていた。同じではなかった。通常のネズミよりは何倍も大きい。大きいと言っても猫か小型犬程度である。
だが人間と同じ知能も記憶も持っており、言語を理解する。ネズミは記憶を辿り、状況を整理した。次第に震え出し、おろおろと辺りを見回して奇妙な行動を取る。そのネズミは憂鬱な気分で言葉を発した。
「……嘘」
その声はティシラだった。これが魔界の姫であり、高貴な姿と魔力に恵まれて生まれたはずの彼女の本体だったのだ。
ここがどこだとか一体何が起こったのかは後回しに、自分がこんな姿になってしまったショックで混乱していた。
魔族はどれだけ美しい姿をしていても、誰もがこうした醜く惨めな本体を持っている。その種類は様々だったが、それを知っている者は本人だけだった。それを晒すことも、暴くことも、唯一魔界で許されないことだった。それは王であるブランケルにも通じていた。
どれだけの残酷な行為で心や体を傷つけようと、本体にだけは触れてはいけないという暗黙の掟が遠い昔から確立していたのだ。それを破ったところで罰があるわけではなかった。簡単に言うと、魔族としてのプライドが許さなかったのだ。
そこに触れられてしまうと立ち直れないほどの苦痛を強いられる。それは魔族のすべてが持っているものである、共通の弱点だったのだ。だからないものとして扱うことが最善とされた。決して気遣いなどではなく、自分を守るための本能からくるものだった。
ティシラは今までにないくらい焦っていた。周りには誰もいないし、気配もない。それでも誰にも見られたくない、見られてはいけないという、恐怖に似た混乱が彼女を支配した。何もない空間で頭を低くし、地を這い回った。
ふっと指先に何かが当たり、体を大きく揺らす。体中の毛が逆立つ。
すぐにティシラの毛がふわりと下がった。今までの緊張が解け、手に触れたそれをもう一度掴む。どうやら布の端のようだ。
ティシラは警戒しながらそれをペタペタと触った。布の中に何かがある。人間の体だ。それは横になっていた。人が倒れている。
「……クライセン様」
ティシラは無意識に呟いていた。手や足、頭の形を確認する。それはぴくりと動き、ゆっくり体を起こした。
ティシラは慌てて彼の背中に回る。彼にだけは見られたくない姿だった。だがその場から逃げ出すこともできなかった。体を丸め、息を潜めて様子を伺う。
彼の意識と共に闇が溶け、その姿を現した。彼はティシラの見たことのない、しかし、間違いなく知っている人物だった。
彼はティシラが認識しているより一回り小さかった。今まで着ていた服が余っている。黒だったはずの髪の毛は真っ白になり、艶もない。見える肌は皺だらけで肉が下がり、色がくすんでいた。
そこにいたのは紛れもなく、今にも倒れてしまいそうな薄弱の老人だったのだ。唯一つ、瞳の青い光だけは失われていない。それだけが「彼」であると確信させられるものだった。
ティシラは何も考えられず、声も出なかった。
老人は顔を上げた。ゆっくりとその青いもので周囲を眺めている。ティシラはその背中で固まったまま動けないでいた。
老人はふと、背後で丸くなっているものに気づく。重そうに体を少し捻り、茶色のネズミに細い目を向ける。
目が合って、お互いにしばらく動かなかった。ティシラは地に伏せたままじっと彼を見つめていた。老人も吸い込まれるようにネズミの赤い瞳を見つめた後、少し首を傾げる。
「……ティシラ?」
その声は少々枯れていた。ティシラははっと我に返り、恥ずかしそうに俯く。
「い、いえっ」小さな声で。「違います」
そうだと言っているも同然だった。言った直後に、しまったと後悔する。もうだめだ。ティシラは落胆して目の前が真っ暗になったが、彼もまた今までとはかけ離れた姿だったせいか思ったよりショックは少なかった。
それでも惨めさはなくならないが開き直ることを決意する。顔を下げたまま、しぶしぶと体を起した。
「あ、ああ……あの、その……」言い難そうに。「これは……魔力をなくして、こんな姿になってしまって……どうやら修羅界に全部吸い取られてしまったみたいで……」
老人、クライセンはもう一度辺りを見回した。ここが修羅界だと認識する。再びティシラに目を移す。
「……どうして、ついてきた」
ティシラは上目でクライセンを見た。
「つい……咄嗟に」
クライセンはじっとティシラを見ていた。眉を寄せ、怒っているように見えた。
「だって」ティシラは肩を竦めて。「離れたくなかったんだもの。離れないって決めてたんだもの……」
そして頭を垂れる。クライセンはため息をついた。
「いいよ、もう戻れないんだ」俯くネズミの頭に優しく触れる。「それにしても、君の考えなしの行動には本当に驚かされるよ。魔界の貴族が本体を晒すなんて、何よりも最悪の屈辱だというじゃないか……ブランケルが知ったら、また私が恨まれるんだろうな」
ティシラは顔を上げた。クライセンは薄く微笑んでいたが、その表情は悲しげだった。
「だが、来ない方がよかっただろ。見ての通り、君が体を張ってついてきた男はただの老人だった。失望しただろう」
「そ、そんな……」
「私はこんな姿、見られたくなかった」クライセンは微笑んだ。「君の中では若い姿のままのいい思い出でいたかったよ」
「思い出なんて……私はそんなものいらないし、欲しいと思ったこともありません」
自然に出た言葉だった。ティシラは嘘をつかない。まだ出会ってあまり長くはないが、それだけは分かる。
やっぱり、と思う。真剣でまっすぐな目は母親によく似ている。
今はその姿は美女どころか人でありさえしないが。
ティシラは彼のそんな失礼な思いを知る由もなく声をかけた。
「でも、なんであなたまでそんな姿に?」
「人間は魔力の大きさでその強さと若さを保つことができる。私も君と同じく修羅界に魔力を全部吸い取られてしまった。つまりこれが、五千年以上生きた私の本当の姿だと言ってもいい。こうなるところまでは予想できていた。どうせ一人なんだ、誰も笑う者はいないと思っていたんだけどね……しかしまさか君がついてくるなんて、さすがの私も思いつかなかった。今は恥ずかしいという気持ちより、また君を裏切ってしまった自分が情けなくて、悲しいよ」
ティシラは戸惑った。こんなに弱気で自分を卑下するクライセンを初めて見たし、想像したこともなかったからだ。
ティシラにとってその容姿、仕草や声、魔法使いとしても異性としても完璧だった彼がすべてを失ってしまっていた。確かに今の彼にはどこを取っても、お世辞でも褒めてあげられるところはなかった。
それでもティシラは何も変わらなかった。彼が彼であることには間違いないのだから。
最初は勝手な思い込みで彼に憧れ、出会ってみると想像以上のいい男で、話すのも照れ臭かったと言うのに、今となっては例え彼がどんな醜い姿になろうとどんなに卑劣な行動を起こしたとしても、これから先は何があっても彼の隣で同じものを見ていたいという強い願望がティシラの中にあった。
以前は「クライセンのどこがいい」と聞かれれば、迷わずに「かっこいいから」と言えた。だが今は、同じ質問をされても同じ答えは出ない。
彼が魔力を失った老人だからではない。むしろ、クライセンがこうして心を翳らせているときこそ傍にいたいと思っている。クライセンという人を愛しいと思う自分が誇りにさえ感じる。
それが一体何なのかは、ティシラはまだ理解できない。だが彼女は物事の摂理や理由を明確にしたがる癖はなかった。今の気持ちをうまく伝える言葉が見つからずに困ってしまう。
「で、でも、私だって、ほら、こんな格好だし……」
ティシラは何とか慰めようとあたふたと動いた。クライセンは、彼女が一生懸命フォローしようとしているその気持ちは嬉しかった。が、その滑稽な動きを見て、つい吹き出してしまった。ティシラの目が一瞬、点になる。
「ひ、酷い!」ティシラは真っ赤になるが、毛で覆われていて見えない。「みっともないのはお互い様でしょ」
「確かにそうだ。ごめんよ」
クライセンは更に皺を寄せて笑いを堪えていた。ティシラはふて腐れていたが、ふっと肩の力を抜いた。
「あなたのそんな笑顔、初めて見た。いつもかっこつけてばっかりで、本当のことも何も言ってくれなくて……」
「……ああ」クライセンは肩の力を抜いた。「そうだったね。ずっとそうしてきた」
二人は見つめ合った。ティシラはその雰囲気に浸っていたのだが、クライセンはそうではなかった。
必死で我慢したのだが、あまりにも色気のないその光景に耐えられなくなってしまい、また、吹き出す。
「ちょっと!」
ティシラはかっと怒鳴る。クライセンは顔を覆い、腰を折って体を揺らした。
「ご、ごめん。君の顔を笑ったんじゃないよ。あり得ないだろ、こんなの。これはどう考えても笑うところだよ」
「信じられない。普通ならここで二人は抱き合ってキスの一つでもしたっておかしくない、感動的な場面でしょ」
「勘弁してくれ。せめて人間であってくれないと、キスしようにもどこにしたらいいか分からないよ」
「酷い! 自分だってミイラ寸前のジジイじゃない。贅沢よ」
クライセンは「確かに」と言いながら笑い続けた。ネズミのくせにリスのように頬を膨らませているティシラの姿が更におかしい。
「不思議だな」クライセンは笑いを抑えた。「君は魔界の姫で、誰もが羨む環境に恵まれて眩しいほどの生命力に満ち溢れていた。そして私は魔法王と呼ばれ、人々の理想そのものだとまで言われながら崇められていたと言うのに、今はお互いその見る影もない。なのに全然辛くない。おかしくて、腹が痛いほど笑えるなんて」
ティシラも微笑んだ。それもそうだと思いながら、体を乗り出した。
「ねえ、もしかしたら私たちってお似合いじゃないかしら」
「そうかもね」
「本当?」ティシラは目を輝かせる。「それって。もしかしてプロポーズ?」
順序を踏まずに話を飛躍するところは父親の影響だと思いつつ、クライセンは笑顔で誤魔化した。
そして話を逸らす。いや、本題に戻す。
4
「……見てみろ」
クライセンは闇の中に目線を移した。ティシラも同じ方向を見る。そこには小さな光があった。
「……あれは?」
それは微かに瞬きしていた。まるで星のように見えた。
次第に光は分裂するようにぽつぽつと増え始めた。綺麗に見えた。しかしそれだけではなかった。その数が増えれば増えるほど、何かが押し寄せてくるような気がした。増殖は止まらず、その速さも増してくる。
「さあ、何だろうね」
「さあって、そんな……」
「新しい、何かだ」
「修羅界に何かが存在するなんて、信じられない」
「ノーラは修羅界を支配するつもりだ。奴は魔術でその入り口を開き、自らに魔薬を投じてここの生き物になろうとしている。でなければ私たちがここで生きていることもできないだろう。今までだったら魔力を奪われ、こんな姿になるくらいでは済んでないはずだ。形も意識もすべてを失っていただろう。修羅界は本来そういうものだった。今は違う。この世界が物体化し、形を成そうとしている。そしてこの世界の法則に従って新しい命が生まれようとしているんだ」
「命って、人間?」
「いや」
「魔族?」
「いや。天使でも、そのどれでもない」
「じゃあ何なの」
「さあ。誰も知らない未知の新しい生物だろう。今まで修羅界に入れる者はいなかった。天使、悪魔。そのどちらでも、ましてや人間でもない新しい命だよ」
「……怖い」
「ああ」
「私たちの世界も始めはこうしてできたのかもしれない。でもこれはあってはいけない、許されない行為だと思う。この世界ができて命が生まれたとき、すべてのバランスが崩れる。よくわからないけど……これは、侵略……」
「……ああ」
ティシラに寒気が走る。言葉ではなく、本当の恐れが彼女を包む。浸っている場合なんかではないと、やっと体で感じた。
「どうしよう。私もクライセン様もこんな状態でノーラに適いっこない。今やあいつはこの世界の王であり、神よ。それに修羅界は無限の魔力の塊。それが形を成すなんて、一体どこまで侵蝕されてしまうの。魔界や人間界だけじゃない。天上界も、そして宇宙までも飲み込んでしまうのかもしれない。分からない。全然想像もできない」
「考えないほうがいいよ。すべての未来が壊れ、そこに別の次元が流れ込んで居座る。今、現世にあるものがなくなってしまうんだ。そこから先は私たちが介入することはできない」
「……だめ、目が回りそう」
くらくらするティシラの隣でクライセンは闇の中の星を見つめた。そして、まるで朗読するように、呟く。
「世界が創造されるとき、必ず神々の衝突があると言う。その戦いによって彼の地に或ることを許される者が決められる。今このときも例外ではない」
「……クライセン様?」
「そうだろう? ノーラ」
クライセンは遠くにある一つの光を見つめながら、ゆっくりと重い腰を上げた。ティシラはそれを見上げる。
「…………?」
クライセンは細った腕を懐に入れる。そこから魔薬の瓶を取り出し、その蓋に手をかける。
「!」
ティシラは素早く立ち上がった。痩せたクライセンに掴みかかって瓶を彼の手からもぎ取った。
「邪魔するな!」
「す、するわよ。当然でしょ」
「返すんだ」
「いや!」ティシラはその瓶を腕の中に隠した。「クライセン様、あなた、何をしているか分かっているの」
「悪いか。よく見ろ。それがなければ私はただの老人だ。だが、ここで無駄死にするつもりはない。私は失って惜しいと思うものを何も持たない。そんな環境を作ってきたのは自分自身なんだ。このためだけにここにきた。ここで逃げたら私の存在価値はなくなる」
「そんなことない。ううん、そんなのどうでもいいよ。存在価値とか、なんで人間ってそんなものに拘るの? 本当に死にたい人なんていやしないよ。いたとしても私には分からない。でも、もしそんな人がいたとしても、死にたい人が命なんか懸けるわけないじゃない。ねえ、あなたは生きたいんでしょ。本当のことを言って。お願いよ。もうかっこつける必要なんかないじゃない」
ティシラは小さな手に瓶を抱いて、必死で訴えかけた。
「怖いなら逃げればいいじゃない。もうどこにも逃げ場所なんかないかもしれないけど、できるところまで逃げようよ」
「……それができるなら、とっくにやってる」
「どうして? どうして逃げなかったの」
「……逃げられなかった。生かされてしまったんだ。だから逃げることを、やめた」
「その結果が、こんなことなの? そんなの寂しすぎる。あなたは生かされたんじゃない。生きる価値のある人よ」
クライセンは聞き分けのないティシラに苛立ちを覚える。今まで誰かと対等に口論などしたことがなかった。いつも自分は正しかった。自分の言葉に逆らう者はいなかった。ここにきて、思い通りにいかない目の前のものを打ち壊したくなる衝動に駆られる。
「君に何が分かる」クライセンの顔が怒りで歪む。「今まで自分勝手にやりたいことをやってきた温室育ちのお前なんかに分かるものか。私が五千年もの間、どんな思いをしてきたか……生きていたことが、生まれてきたことが苦痛で仕方なかった。それでもここまできた。意味なんかない。消えてなくなることができなかった。理由を探すことを止められなかったんだ。そしてやっと見つけたと思った。だからここまできたんだ。なのにその結果、何もしないまま……できないまま死んでいけと言うのか。お前に私の価値を奪う権利があると思うのか」
ティシラはクライセンに責め立てられ、泣きたくなった。温室育ちだと言われ、結局彼にもそんなふうに思われていたなんてと、深く傷つく。これは本心だ。目を見れば分かる。
だが今は涙を堪える。自分がなんと言われようと、ここは引くわけにはいかない。言葉を選んでいる時間もない。
本心には本心でぶつかるしかない。
「分からないよ!」ティシラは大声を出し、勢いに任せる。「私にはそんな昔のことなんか分からない。本当はどうでもよかった。魔法戦争とか、リヴィオラとか、パライアスもノートンディルも、本当はそんなものに興味はないの。アカデミーでの授業も退屈だった。その時は魔法使いになりたかったからいい子ぶってたけど、魔法使いになっても何も変わらなかった。私はこの世界が好きだった。楽しかったから、それだけで十分だった。でも今までのことがあったからこの世界があるんだって、そう思ったのは……あなたからパパとママの話を聞いたときだったのよ」
クライセンは色あせた瞳を揺らした。
「私、これでもね、いろいろ考えたの。あなたがパパとママの命を救ったことで私が生まれたんだって知って、最初はすごく複雑だった。でも、あなたはベルカナの魔法使い。その力で私に命を与えてくれた……そう思ったらいろんなことに気がついたの。なんで私が顔も知らないあなたに焦がれて、会ってもその気持ちは変わらなくて、こんな姿になっても命を捨てても傍にいたいと思うのか、やっと分かったのよ」
ティシラはクライセンに縋りつく。
「私が、あなたが見たいと言った『命を懸けた末に生まれたもの』の一つなのよ! パパとママが命を懸けて愛し合って、そしてあなたという力ある人の心を動かした。すべての偶然が重なって奇跡が起きたのよ。見えないものが形になって、あなたの前に現れた。私はそのために生まれてきたんだって思ったら、凄く嬉しかったの。お願い、私のことを好きになってくれなくてもいい。何もないなんて言わないで。こんな醜い獣に言われても嬉しくないかもしれないけど、あなたは生まれて、生きてきた中で何も間違ってなんかなかったのよ。今までのあなたがあったから、だから今、私がここにいるんじゃない。あなたは滅ぼす人なんかじゃない。生み出す力の持ち主なのよ」
ティシラがベルカナの魔法で生み出したもの──そんなふうに考えたことなんかなかった。
自分では、醜く女々しい嫉妬への罪滅ぼしのつもりでいた。そんなもので消せる過去だとは思っていなかった。だからティシラを切り離そうとした。だから傷つけようとした。
そうすることで自分の弱さを隠そうとしていたのだ。きっとどこかで彼女と離れてしまっていたら、自分が何者なのかも知らないまま死んでしまっていただろう。それでいいと思っていたはずの、一番惨めな死に方をしてしまっていたに違いない。
ずっと知りたいと思っていた答えがここにあった。こんなにも近くに、すぐ傍に。
守りたい。心からそう思った。しかし、今は──。
「…………」クライセンは拳を握った。「他に方法はないんだ」
その時、二人はふっと同じ方向に目を奪われた。
何かがいる。その周りにはいくつもの光が点滅している。二人には象られた形が何か分からない。見たことのないものだった。
頭がある。腕、足、胴……のようなものだろうか。少なくとも自分の知っているものとは違う。
知らないものだと思ったほうが正確かもしれない。理由は分からないが、不気味だ。
それに色がつき始める。そうすることで二人の目にはっきりとその姿が映し出される。全身が緑に見える。いや、紫だろうか。似ている気がするが、正しく表現できる言葉を知らない。
知らないのではない。存在しないのだ。
次に音が生まれた。もやもやと二人の頭の中に入り込んできた。たぶん、既存で言う「声」だろう。ノーラが音を出していた。体のどの部分から出ていて、何を言っているのかは理解できない。決して気持ちのいいものではなかった。
ティシラはクライセンの裾を握った。
「クライセン様」目の前の化け物を見つめながら。「あなたもこうなるのよ。本当にいいの? 私は、嫌。あなたがどこの何様で、その姿が猫だろうがお爺さんだろうが何でもいい。でもこんなのだけは、嫌」
「……私だって嫌だ。だが、これがこの世界の創造神なんだ。醜いとか怖いというのは私たちの感性に過ぎない」
「あなたは神じゃない。ならなくていいし、なって欲しくない」
「それは君の我儘だよ。ここには対抗する力がある。どちらがこの地を勝ち取るかは分からないし、仮に私が勝ったとしてもまともでいられる保障もない。だが、僅かでも可能性がある。それを君一人の我儘で潰すことはできないよ」
ティシラは口を噤んだ。返す言葉が見つからなかった。このまま何もしなかったら確実にノーラに、目の前の化け物にすべてを支配されてしまう。
それを止める手立てがあるとしたら、手の中にある魔薬だけなんだろう。
そしてクライセンだけがノーラに及ぶ可能性を持っている。だが、なぜとティシラは思った。自分のたった一人の愛する人が、なぜそんな使命を背負っていなければいけないのだろう。
自分の目の前で恐ろしい化け物になってしまう。そうすることで世界が、数多の人々が救われるかもしれない。逃れられない事実だった。
それでも、どうしても納得がいかない。自分はそれを傍観するためにここにきたのだろうか。
ここで自分は何をすればいいだろう。感動的な言葉を交わして、涙しながら彼に魔薬を手渡すべきか。何があってもあなたを信じています、とか何とか言って笑顔で見送ればいいのか。
そんなの、考えただけで鳥肌が立つ。
我儘? 違う、と否定する。
――いや、これは我儘だ。
ティシラは自問自答の末、答えを出した。これはただの我儘だ。だから何だと言うんだ。
嫌なものは嫌だと開き直る。文句があるなら止めてみろ。
ティシラは考えることを、理由を探すことを放棄した。
「そうよ。私は我儘なの。何でも思い通りにならないと気が済まないのよ」
「!」
遅かった。一瞬の出来事だった。
止める間もなく、ティシラは瓶の中の魔薬を一気に飲み干したのだ。
「ティシラ!」
クライセンは自分の目を疑った、疑いたかった。
ティシラは崩れるように体を折る。咳き込みながら奇声を発していた。クライセンは慌てて彼女の体を抱えた。そこには涙目で舌を出している、それは情けないネズミの姿があった。
「……何これ」ティシラは腹を抱えて。「まずいなんてものじゃないわ。臭いし苦いし痛いし……吐きそう」
ティシラの体から煙が出てくる。クライセンは奮えを抑え、もがくネズミを抱き締めた。
「……このバカ!」怒鳴りつけるその声は弱々しかった。「何てことを……」
それ以上は言葉が出てこなかった。ティシラは腕の中で痙攣している。
その体がぐにゃりと柔らかくなった。クライセンははっと顔を上げるとほとんど同時に、形の歪んだネズミに突き飛ばされる。
「……ティシラ!」
ティシラは煙に包まれた。白い靄の中で何かが蠢いていた。次第に違う形を造り出す。
クライセンは息を飲んで見つめた。ティシラがどれだけの恐ろしい姿になってしまうのか想像できなかった。絶望の色は変わっていった。
意外な答えが出た。煙が消えていくと共にそれは形になった。ティシラはゆっくり立ち上がる。
その顔は苦痛に歪んでいたが、決して醜いものではなかった。
長い黒髪が揺れ、細い手足が裾から伸びている。ティシラは持って生まれた赤い瞳を開いた。
そう、ティシラは元の姿を取り戻していたのだ。
その様子を見ていたノーラが空気を揺らした。それを感じてティシラが顔を上げ、彼を睨みつけた。
「何がおかしいのよ」
ティシラにはノーラが笑ったのが分かっていた。その意図も分かった。最後の秘薬はクライセンではなく、一介の小娘に奪われてしまったことで希望は完全に失われたと思っていたのだ。
クライセンは彼女が今までと同じではないことに気がついた。当然だった。姿は元の知ったそれだとしても、その目に映るもの、聞こえる音、感じる空気のすべてがこの世界のものになっているに違いない。ただ、ノーラと全く同じではないのだろう。
「ナメんじゃないわよ」ティシラは不適な笑みを浮かべた。「この私を誰だと思っているの」
ノーラは笑うのを止めた。
「私は魔物」ティシラの顔には自信が満ちていた。「もともと『化け物』なのよ」
ティシラからは今まで感じたことのない魔力が放たれていた。
「忘れたの、ノーラ。ここは修羅界と言えど魔界の一角に過ぎない。魔物である私が神になった以上、この世界の異物はあんたの方なのよ。私は修羅界の神であり、偉大なるカノン(炎)の魔法使い。この修羅界は魔力の塊。その絶大なる魔力は今、すべて私のもの」
ティシラは印を結ぶ。クライセンは戸惑いながら体を起こす。
「何をする気だ」
ティシラは彼を見向きもせずに素早く答えた。
「……この修羅界そのものを私の中に吸収する」
「何だって」
「私の中にどれだけの魔力が入るか分からないけど……それで、最大級の魔法を使って、あいつをやっつけてやる」
「やめろ。無茶だ」
クライセンはティシラに駆け寄り、結ばれた印を掴んだ。ティシラは今にも燃え上がらんばかりの赤い瞳を彼に向けた。
クライセンはその時初めて、彼女が内から溢れ出す魔力に体を突き破られそうになっていることを知った。
その瞳が微かに震えていた。ティシラの内側は魔薬によって侵蝕されていたのだ。きっとその痛み、苦しみは計り知れないものだろう。
自分の代わりにすべてを背負った彼女の姿にクライセンは言葉を失い、手を離した。ティシラは俯く彼に微笑んだ。
「クライセン様、お願い」
クライセンは顔を上げた。
「正直言って、凄く怖い。今すぐここから逃げ出したい。でもあなたがいるから、頑張れるの……だからお願い。傍にいてください」
ティシラは苦しみで歪む顔を隠すように、少し下を向いた。クライセンは迷わず答えた。
「……ああ」
ティシラはそれを聞いて顔を上げ、透かさず続けた。
「ずっと?」
そこには苦しさを隠しきれずにいる、無邪気な笑顔があった。
人々が想像する神などとは程遠い表情だった。
まったく、とクライセンは思う。この状況でも抜け目のないティシラに呆れながらも、もう根負けするしかなかった。誰が見ても無理やり口説いている場合ではないはずなのに、そんなことは後にしろと言いたいところだが──ある意味脅しだと思いながら、クライセンは答えた。
「ああ……分かったよ」
迷いも偽りもなかった。
もしここが人間界だったなら「こんな私でよければ」などというつまらない言葉を付け足していたかもしれない。だがここに余計なものは何一つ存在しなかった。
ティシラは心から喜んだ。素直に、素直にその言葉を受け取る。
5
「……ありがとう」
満足だった。
ティシラは目の前に聳えるノーラに向き直った。気合が入る。
正義感などはまったくなかった。彼女を突き動かすのは、後は負けず嫌いな根性だけだった。印を結ぶ手に力を込める。闇の中で点滅していた光がティシラに集まり出す。
「……この世のすべての生命よ」目を閉じて呪文を唱えた。「我が掌に集え。ティシラ・アラモードの名において命ずる──」
イン イン オルドラ セレドラ トー ヴェルノール デュレオ オラゴ リファイ エル グランデリオロス イン ヴァーレイ ディンヴェグナ……
クライセンは黙って聞いていた。
それは滅亡の呪文だった。術師自体も死に至る、破滅の魔法。
それだけではない。ティシラの唱える呪文には魔界の言葉が重ねられていた。そこの部分だけぼやけ、早口でクライセンには半分くらいしか理解できない。だが、大体は読めた。
『最も深い闇よ、手を差し伸べよ。我が瞳を、指を、心臓を捧げる。共にこの世の命を食い尽くせ。深い眠りを悪夢で支配せよ』
「深い闇」とは術師本人のことだった。これは自分の中の最も恐ろしい闇の部分を呼び起こし、ここにある命のすべてと共食いする意味を持っていた。
アカデミーで教えられる正当な「自滅」の魔法に、魔界でも禁じられている「道連れ」の魔術を加えたものだった。魔族であり、さらに禁断の魔薬の力を手に入れた今のティシラだからこそ可能な魔法だった。ティシラは持つものと得たもののすべてをそこに集結させようとしていた。
確実に死ぬ。ノーラも、ティシラも。もちろんクライセンも一緒に飲み込まれてしまう。
それでもいい。ティシラの傍にいる。例えそれが永遠の暗闇だったとしても、自分の選んだ道なのだ。
仮に生き延びても、一人でいるよりずっといいと思った。
(……そうか)クライセンは改めて思う。(ブランケルもこんな気持ちだったんだな)
ノーラが動いた。
予想外の魔法に戸惑っている。その色を目まぐるしく変えていた。
修羅界に生まれた命がティシラに集まる。ティシラは目を閉じたまま印を解き、片手を掲げた。それを中心に光が一つになっていく。
世界が揺れだした。ティシラは体に走る激痛に顔を歪めた。だが振り切って、かっと目を開く。
「私とクライセン様の仲を邪魔するこの腐れ外道が! 私が叩きのめしてあげる!」
今まで黙っていたクライセンが眉を寄せた。
「……は?」
「あんたって、本当にムカつく。変な薬は作るわ、魔界は乗っ取ろうとするわ、何よりも私の純愛を邪魔するなんて。許さないんだから」
「バカ!」クライセンは慌てて。「ちゃんと呪文を唱えろ。真面目にやれ」
そんな心配を他所に、ティシラの手中には生まれたばかりの生命と修羅界の魔力がとめどなく集まってくる。支えているだけで腕が震えるほど重い。ティシラは歯を食いしばって耐えた。
もう片方の手も上げて、押し上げる。集まった光が爆発する。同時にティシラの中にあった魔力のすべてが放出した。光はいくつもの線になり、流星のように修羅界を駆け巡った。
ティシラの苦痛が、ふっと消えた。
体は軽くなったが、何が起こったか分からない。目の前を何かが通過した。それが足元で嫌な音を立てる。
何が落ちたのか、ティシラは手の力を抜きながら目線を落とした。
そこには、見たことのある「手」が転がっていた。どう見ても、自分の肘から下の右手だった。
腕を見る。無い。まるで噛み千切られたような雑な傷口は骨や肉が露になっていた。
(……痛くない)
何で、と答えを出す前に、今度は鋭く尖ったものがティシラの腹部を貫通した。その反動で倒れそうになるが、やっぱり痛みはなかった。
腹に刺さったものがゆっくり引いていく。ノーラの体の一部分が変形し、ティシラを攻撃していたのだ。普通なら死んでいたかもしれない。
ノーラの牙が引き抜かれると、ティシラのそこから血が溢れ出す。痛みも苦しみも感じられないまま、ティシラは内から押し出されるように血を吐いた。充血した眼球が回った。自分が呼吸をしていないことに気がつく。
(……何、これ)ティシラの周りを光が舞っていた。(私、どうなっちゃったの)
目の前でノーラの牙が動きを止め、いくつかに枝分かれする。構えた、と思うと見えない速さで再びティシラの傷口を狙ってくる。
「ティシラ!」
咄嗟にクライセンが飛び出すが、その老体は思うように動かない。彼女に体当たりして自分が代わりにその牙を受けるのが精一杯だった。無数の牙が彼の体を刺す。
先に体勢を崩したティシラの上に、血に塗れたクライセンが倒れてくる。ティシラは慌てて受け止める。その衝撃で彼女の左の足の骨が折れたのが分かった。
どうやら内側で行き来する異形の魔力に、肉体が耐えられずに朽ち始めているようだ。
ティシラはそれを無視してクライセンに縋りつく。声が出なかった。泣きそうな目で彼の顔を覗き込んだ。
クライセンは薄く目を開ける。ティシラの中に再び光が吸収され始めた。二人は光に包まれた。
クライセンが口を動かしている。ティシラは必死で耳を傾けたが、何も聞こえない。
(……そうか、これが魔薬の呪い……魔薬を投じた罰)
ティシラから放たれる魔力がクライセンにも影響を与えた。
傷が塞がることはなかったが、クライセンは元の青年の姿に変化する。彼の体の時間の流れが狂いだしていた。クライセンはティシラの腕の中で青年から少年へ、そしてまた老人に変わっていく。それがゆっくりと繰り返されていた。
クライセンの一番強くてきれいな姿、知識も経験もない純粋な姿、力を失って終わりを待つだけの姿……ティシラはそのひとつひとつを目に焼き付けた。
長い間心に抱き続けてきた想いと、遠くて届きそうになかった愛しいもののすべてが腕の中にあった。
本当は何度も諦め、挫けそうになった。だけど今はこんなにも近くにある。お互いが手の届く距離ですべてを曝け出した。
何ひとつ汚れたものはなかった。なんて暖かく、柔らかいのだろう。
ずっとこうしていたい。いっそ溶けてひとつになってしまいたい。この世にはたくさんのものが溢れて、いらないものの方が圧倒的に多い。なのに、これほど愛しいものはたった一つしかないなんて。失ってしまっては生きていけそうもないのに、どうして別々に生まれてきてしまったのだろう。
最初からひとつだったら……どんなに楽だっただろう。
それを見つめるティシラの瞳から溢れたのは、赤い血だけだった。その雫がクライセンの頬に落ちる。
隣でノーラが更に牙を向けてくる。ティシラはそれを察知し、光の盾でそれを弾き返した。ノーラは戸惑いながら一度牙を引っ込める。
ティシラは再びクライセンを見つめた。まだ息はあるが意識を失いかけている。
もう時間はない。怖がっている場合ではない。
だめだ。ここじゃない。今ここでいくら待っても何も起こらない。
つまらない。全然、楽しくない。
ティシラは口を動かした。声は喉ではないところから出ていた。クライセンの心に語りかける。
『……帰ろう』
クライセンの目が動いた。
『みんな、待ってる』
その声を聞き届けて、クライセンは優しく微笑んだ。瞼を落とす。
ティシラは一度深く頭を垂れた後、すぐに顔を上げる。
そこには血に塗れても失われない狂気を帯びた美しさがあった。赤い瞳を燃やし、その光を容赦なくノーラにぶつけた。
ノーラの形が変形する。これが、最期。
空間を飛び交っていたすべての流星がティシラの体の中に消えていった。
一瞬、沈黙が落ちてきた。続いて、その上から潰されるような見えない圧力に襲われる。
『……ノーラ』
ノーラが膨れ上がる。先端が弾けたかと思うと、そこから虹色の液体が溢れ出した。それは辺りに満ち、すべてを埋め尽くそうとする。
ティシラはゆっくりとクライセンから離れ、足を引きずりながらノーラに歩み寄った。液体はティシラに触れると跳ね返されるように波打つ。
クライセンは僅かな意識の中で彼女の背中を見守った。
ティシラは足を止め、牙を見せて笑った。左手を掲げ、ノーラに向ける。その中心がきらりと光る。
『地獄に堕ちろ──!』
ノーラが吼えた。液体が暴れ出す。
ティシラを中心に、すべてを掻き消す波紋が広がった。
掌から一本の細い閃光が走った。空間が揺れた。ノーラはもがくように暴れ出し、大きな口を開いたままティシラに覆いかぶさってきた。
ティシラは抵抗もせずにそれに飲まれる。世界全体がとぐろを巻いた。
クライセンの体からも痛みが消えた。魔薬のせいではない。この世界から痛みや苦しみという感覚がなくなったのだ。
目を開き、体を起こすと胸元や腹部からグラスを倒したかのように血が零れた。本人はそれに気がつかない。
渦の中から細く小さな手が伸びた。指を揺らして自分を探している、呼んでいる。
クライセンはそれを掴もうと手を伸ばすが、届かない。かつて無い魔力に押し返される。巻き込まれ、体が歪みに溶け込んでいく。
もう何も考える必要はなかった。ただその渦に身を任せるしかなかった。
その中で一つだけ、クライセンはティシラの身を、それだけを案じた。
その意識も、渦に紛れて遠のいていった。